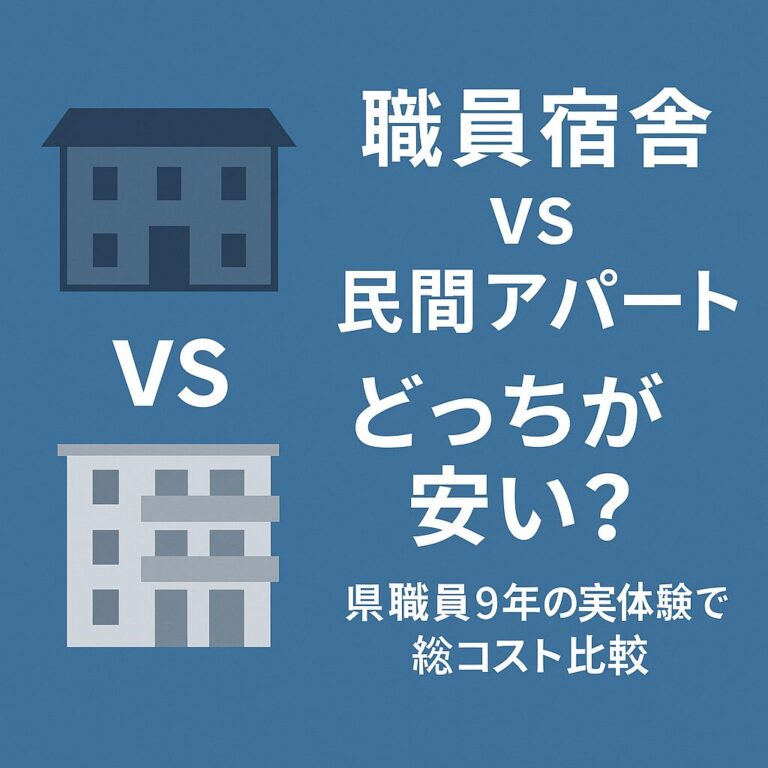県職員として働き始めたとき、最初に迷うのが「官舎(職員宿舎)に入るべきか、民間アパートを借りるべきか」という住宅の選択でした。
家賃だけを見れば官舎が安そう。
でも実際に住んでみると、築年数・設備・立地・通勤距離・光熱費など、見えないコストが地味に積み重なります。
逆に民間アパートは快適だけれど、敷金・礼金・更新料・駐車場代といった初期費用・固定費が重くのしかかります。
「結局、どっちが安いの?」「本当に官舎って得なの?」
──こんな疑問を抱える人は私だけではなかったはずです。
特にこれから採用される新人県職員や、異動が決まった方、家族持ちで住宅費を抑えたい人にとって、住まいの選択は家計に直結する重要テーマです。
私は県職員として9年間働き、その間に官舎・民間アパートの両方を経験しました。
出先機関での生活、住居手当の扱い、駐車場問題、通勤距離による燃料費……数字と現場感の両方を体感してきました。
この記事では、そのリアルな経験をもとに総コスト(家賃+初期費用+駐車場+光熱費+通勤費+更新料)まで含めて、わかりやすく比較します。
この記事を読むと
官舎(職員宿舎)と民間アパートのコスト差が“総額”で分かる
異動が多い県職員ならではの注意点が理解できる
家族構成や地域によって、どちらが得になるのか判断できる
住居手当を最大限活かすポイントが分かる
ようになります。
住宅費は家計の中でもっとも大きな固定費です。
だからこそ、正しい情報をもとに、自分に最適な選択をしてほしい
──そう思いながら書いています。
では、順に見ていきましょう。
県職員の住宅事情と比較の前提条件
県職員として働き始めたとき、多くの人が最初に迷うのが「官舎(職員宿舎)に住むか、それとも民間アパートを借りるか」という住まいの問題です。
家賃だけを見ると官舎が圧倒的に安く見えます。
しかし、住宅費は家賃だけでは決まりません。
住居手当、駐車場代、初期費用、光熱費、通勤費、更新料などを含めた「総コスト」で判断しないと、正しい比較にはなりません。
その中で強く感じたのは、「家賃の数字だけを見ても意味がない」ということです。
特に、官舎は住居手当が支給されないことが多いため、実質負担額が見えてこないケースが多いのです。
官舎(職員宿舎)の定義と特徴
官舎(職員宿舎)は、公務員向けに提供される住居で、名称は自治体によって「職員住宅」「宿舎」「官舎」と分かれています。
主な特徴は以下の通りです。
家賃が非常に安い(多くは月5,000〜20,000円台)
駐車場代が無料のことが多い
管理費も格安
- 敷金・礼金もなし
私が新人時代に住んだ官舎は家賃8,000円、駐車場無料でした。ただし住居手当は支給されませんでした。
「家賃は安いが住宅手当ゼロ」という構造になっているため、単純比較はできません。
民間アパートは住居手当を活用できる
民間アパートに住む場合、家賃は官舎より高いですが、多くの自治体で「住居手当」が支給されます。
【住居手当】
私の県では以下のように支給されていました。
| 家賃 | 支給額(月額) |
| 10,500円未満 | なし |
| 23,000円以下 | 家賃ー10,500円 |
| 23,000円以上 | (家賃ー23,000円)×1/2+12,500円 ※支給限度27,000円 |
総コストで比較すべき理由
住宅費は家賃だけでは成り立ちません。
本記事では、以下すべてを比較対象にします。
家賃
住居手当の支給額(官舎はゼロ)
駐車場代(民間は月5,000〜10,000円程度)
敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用
更新料(1〜2ヶ月分のケースも)
光熱費(官舎は築年数の古さから暖房費が高くなる傾向)
退去費用
これらを含めた「総額」で判断すると、官舎が必ずしも最安ではないことが見えてきます。
官舎(職員宿舎)のメリット・デメリットを実体験ベースで解説
官舎は「安い」「通勤が楽」「安心」といったイメージがあります。
しかし、実際に住んでみて分かるのは、メリットとデメリットの差が極端だということです。
ここでは、県職員として9年間暮らし、複数の官舎を経験した私の体感ベースで解説します。
官舎のメリット:家賃が圧倒的に安い
官舎の最大のメリットは、なんといっても家賃の安さです。
場所によりますが、家賃が月5,000~10,000円台で、駐車場代・共益費も無料というケースが多いです。
例えば、私が住んでいた官舎は
家賃8,000円
駐車場無料
共益費無料
という圧倒的低コスト。
民間アパートの半額以下どころか、1/3、1/5というレベルの差でした。
官舎のメリット:通勤が近い・時間が生まれる
官舎は、基本的に出先機関や勤務地の近くに設置されています。
そのため、通勤時間が短くなるというメリットがあります。
通勤10分(徒歩)
ガソリン代ほぼゼロ
冬の朝もすぐ職場に着く
この利点は生活の質に直結します。
特に民間アパートだと場所次第では片道15分以上車通勤に掛かる同僚もたくさんいて、その点では官舎はほんと近いというイメージです。
ただし、勤務地から遠く離れた官舎もあるのも事実です。
官舎のデメリット:築年数が古い・設備が弱い
官舎の弱点は、建物の古さです。
断熱性能が低い
暖房効率が悪い
給湯が弱い
隙間風や結露
私が住んでいた官舎は築30年以上で、冬になると室内温度が一気に下がり、布団から出るのが苦痛でした。
また、間取りが昔ながらだったり、ユニットバスになっていたり、壁や棚が傷だらけ、エアコンが付いておらず、床が畳の官舎に住んでいました。
寒さ対策で、灯油代・暖房費が民間アパートより高くなるケースがあり、「家賃が安くても光熱費が高い」場合もあります。
官舎のデメリット:住居手当が支給されない
官舎の最大の盲点は、住居手当が支給されないという点です。
家賃は安いですが、住居手当がゼロなので、実は民間アパートとそこまで家賃に大差がでません。
官舎の家賃8,000円が安く感じても、例えば住居手当30万円程度(年間)を受け取れないとなると、「実質負担」で見ると差は縮まります。
官舎のデメリット:自治体内の交流が固定化される
官舎は「同じ職場の人・同じ組織の人」が多く住んでいます。
そのため、プライベートでも職場関係が近すぎるという感覚が出ることがあります。
上司と階段で毎日顔を合わせる
休日でも職場の雰囲気が抜けない
生活音が筒抜けの古い建物も
特に若い職員にとっては、ストレスになりやすい部分です。
民間アパートのメリット・デメリット(県職員視点)
民間アパートは、官舎より家賃が高いというイメージが先行します。
しかし、住居手当の支給や設備の快適さ、生活導線の良さなど、官舎にはない大きなメリットもあります。
一方で、初期費用や更新料など「官舎にないコスト」が多いのも事実です。
ここでは、県職員としての実体験と制度上の仕組みを踏まえ、民間アパートを選ぶ際のポイントを整理します。
民間アパートのメリット:圧倒的に快適・設備が新しい
民間アパートの大きな利点は、設備の新しさ・快適性です。
断熱性能が高い(冬でも暖房効率が良い)
エアコン・給湯器・浴室乾燥など最新設備
結露や隙間風が少ない
- 間取りを自由に選べる
官舎では冬の寒さ・湿気・古い設備に苦しむ一方、民間アパートはそのストレスが大きく軽減されます。
私が民間アパートに移ったとき、まず驚いたのは「暖房費が全然違う」という点でした。
官舎時代は暖房費(灯油)が月1〜2万円だったのが、民間アパートではエアコン代だけで済み、約7,000円程度で落ち着きました。
家賃は高くても光熱費が下がるケースがあるのは、重要な比較ポイントです。
民間アパートのメリット:生活導線が整っている
民間アパートの立地は、生活のしやすさを重視した場所にあることが多いです。
スーパー・ドラッグストアが近い
病院や小児科が近く安心
大通り近くで照明が多い
コンビニやガソリンスタンドも周辺にあり便利
特に家族持ち、乳児のいる家庭では「生活導線の良さ」が生活の質に直結します。
民間アパートに引っ越してからは、徒歩圏で買い物が完結するようになり、ガソリン代が減りました。
民間アパートのデメリット:初期費用が高すぎる
民間アパート最大の欠点は初期費用の重さです。
敷金(家賃1〜2ヶ月)
礼金(家賃1〜2ヶ月)
仲介手数料(家賃1ヶ月)
火災保険(1〜2万円)
合計すると、家賃5万円のアパートでも初期費用20〜30万円が当たり前です。
さらに、引っ越し代も考慮しなくてはいけません。
基本的に異動に伴う引越しは「赴任旅費」が支給され、引っ越し代は負担にはなりませんが、自己都合の引越しの場合は全額自分で引っ越し代を負担しなくてはいけません。
民間アパートのデメリット:更新料・退去費用がかかる
民間アパートは、2年ごとの更新時に更新料が発生します。
更新料:家賃1ヶ月分
更新事務手数料:5,000〜15,000円程度
さらに退去時には、
クリーニング代
原状回復費
など、2〜10万円程度の支払いが発生する場合があります。
官舎は更新料がないため、この差は長期的に見ると大きいです。
民間アパートのデメリット:駐車場代が追加でかかる
地域や物件にもよりますが、民間アパートは駐車場代が有料です。
月3,000〜10,000円
都市部では1万円以上も
官舎は駐車場が無料のケースがほとんどなので、差が年間にすると数万円〜十数万円になります。
特に車2台持ちの家庭は、駐車場代だけで月1〜2万円の負担になります。
民間アパートのデメリット:住居手当が上限に達しやすい
民間アパートは住宅手当で実質家賃が下がりますが、上限に注意が必要です。
例:家賃60,000円の場合
住居手当上限27,000円→ 実質負担33,000円
家賃が高すぎると自己負担が大きくなります。
官舎と民間アパートの総コスト比較【1年目】(初期費用で明暗がわかれる)
「初年度」は、初期費用の有無で大きく差が生まれます。
官舎(職員宿舎)
家賃:8,000円
- 住宅手当:支給なし
- 初期費用:なし
駐車場:無料
光熱費:冬季の断熱性能の低さで暖房費が高い(例:灯油1万円/月)
民間アパート(家賃50,000円・手当26,000円の例)
家賃:50,000円
住居手当:26,000円
初期費用:20万〜30万円
駐車場:5,000円
光熱費:断熱性能が高く暖房費が少ない(例:7,000円程度)
1年目は、初期費用の差が圧倒的です。
官舎の勝ち:○
ただし、官舎と民間アパートで差は数十万円差がつきます。
家族構成・生活スタイル別の最適解
ここまで「官舎と民間アパートの総コスト」を数字で比較してきましたが、最終的な“最適解”は家族構成・生活スタイル・勤務場所によって大きく変わります。
同じ県職員でも、単身・夫婦・乳児家庭・車2台持ち・山間部勤務…など、条件が違えば答えも変わります。
この章では、あなたの状況に合わせて最適な選択ができるよう、パターン別に解説します。
単身の新人県職員の場合:官舎が最も合理的
単身の新人県職員は、官舎のメリットが最大限に活きます。
家賃が圧倒的に安い
通勤時間が短く、生活コストが低い
初期費用がほとんどかからない
住宅手当はなくても、実質負担は圧倒的に低い
新人のうちは給料も高くないため、固定費を抑えて貯金する期間と割り切るのが賢明です。
また、出先機関に配属されるケースが多いため、官舎は職場の真横、または徒歩圏内にあることが多いです。
この“通勤5分”の恩恵は計り知れません。
結論:単身者は官舎一択に近い。
夫婦・子どもあり家庭の場合:民間アパートの生活導線が強い
家族がいる場合、【生活導線=生活の質】が圧倒的に重要になります。
民間アパートは
スーパー・病院・ドラッグストアが近い
生活音・断熱性能が安定
子育てがしやすい
部屋数が多く、プライバシーが確保できる
- プライバシーが確保されている
など、家族で暮らすうえでの安心感が違います。
官舎は築年数が古く、防音性が低いため、子どもの泣き声が響きやすいケースもあります。
また、狭い2K・3Kが主流で、子育てには不便な構造が多いです。
さらに、民間アパートでは住居手当が支給されるため、実質負担が大きくはならないケースが多いです。
結論:家族持ちは民間アパートがストレス少なく長期的に安定。
ただし、とにかく家賃を下げ、どんどん貯金をしたい家庭は官舎が良いでしょう。
車2台持ちの家庭の場合:駐車場代で判断が分かれる
車社会の地方では、車2台持ちは珍しくありません。
この場合、駐車場代の差が年間で非常に大きくなります。
官舎
駐車場無料(2台分確保できる場合も)
民間アパート
1台5,000円、2台で毎月1万円
年間12万円の固定費
通勤距離や生活導線を考慮しても、駐車場代の差は無視できません。
ただし、官舎は2台停められない場合もあり、周辺の月極め駐車場を契約しなければならないこともあります。
その場合、民間アパートとの差が縮まるケースもあります。
結論:2台駐車が可能な官舎なら官舎優位。ただし要確認。
遠方出先機関の場合:官舎の利便性が勝つ
遠方出先機関の場合、民間アパートはそもそも近くに存在しないことが多く、官舎が唯一の実質選択肢です。
通勤距離が短い
災害時にも職場へすぐ駆けつけられる
夜間呼び出しがあっても安心
特に森林保全・林務部門・土木・農業系など、夜間対応や災害対応が発生しやすい部署では官舎が合理的です。
ただし、光熱費・生活導線の不便さは覚悟が必要です。
結論:山間部勤務は官舎で生活の安心を優先。
生活の質を重視する人:民間アパートのほうが満足度が高い
生活の質=QOL(Quality of Life)を最優先する人にとっては、民間アパートが圧倒的に快適です。
冬でも暖かい
防音性が高い
部屋が広い
設備が現代的
水回りが綺麗
官舎はどうしても“昭和感”があるため、ストレスにつながる人も多いです。
結論:生活の快適さを優先するなら民間が最適。
県職員の住居手当・赴任旅費の正しい活かし方
官舎と民間アパートで総コストが変わる最大の要因は、住居手当の支給有無と異動に伴う費用(赴任旅費)です。
県職員は市町村職員より広域異動が多く、生活拠点を移す頻度も高いため、この制度を正しく理解しておくことが家計に直結します。
ここでは、県職員として実際に9年間勤務した経験から、住居手当と赴任旅費をどう活かすべきかを整理します。
住居手当の仕組み(県と市町村で異なるケース)
住居手当は自治体によって細かく制度が異なりますが、共通するポイントは以下の通りです。
上限額が決まっている(例:1.5万円~3万円程度。上限例:東京都15,000円、長野県27,000円、国家公務員28,000円)
自己負担額に応じて支給される
同居人(配偶者・子ども)の有無で変動する場合もあり
官舎では支給されない
例として、家賃45,000円 → 自己負担額30,000円 → 住宅手当15,000円支給というケースでは、実質家賃が3万円になります。
一方、官舎に住む場合は、多くの自治体で住宅手当はゼロです。
県職員の住宅手当制度は「民間アパートの家計支援が目的」であるため、官舎利用者は対象外という形になっていることがほとんどです。
異動時に発生する実費を正しく把握する
県職員は、2〜3年スパンで異動することが一般的です。
そのたびに「引越費用」「家具買い替え」「敷金・礼金などのアパート初期費用」などが発生します。
【官舎利用の場合】
官舎から官舎への異動は初期費用なし
退去費用も基本なし(原状回復で請求されることもある)
【民間アパートの場合】
敷金・礼金が発生(家賃1〜2ヶ月分)
仲介手数料が発生
退去費用(2〜10万円)
民間アパート→民間アパートの異動は、年間30〜40万円の出費につながることがあります。
ここが官舎の圧倒的優位点です。
赴任旅費の仕組み(県職員の隠れた支援)
県職員の異動に伴って支給される「赴任旅費」は、引越し費用に関わる経費に対して「定額支給」か「実費支給」という形で補助されます。(自治体により違う)
ただし以下の注意点があります。
支給額には上限がある
荷物量が多いと持ち出しが発生
依頼業者によって費用差が大きい
家族帯同の場合はさらに生活用品の買い替えが必要になる
結論|官舎か民間アパートか?県職員9年の経験から言えること
ここまで、官舎(職員宿舎)と民間アパートを、家賃・住宅手当・初期費用・駐車場代・光熱費・通勤費・生活導線まで総合的に比較してきました。
県職員として9年間、官舎と民間アパートの両方を経験した立場から、最終的な結論を整理します。
総コストで比較した結果:ケースによって逆転する
単純な家賃だけで見れば、官舎は圧倒的に安いです。
しかし、住居手当の有無、光熱費、通勤費、生活コスト、暮らしやすさまで含めると「人によりどちらがいいかは変わる」というのが結論です。
【官舎が向いてる人】
単身の新人職員
- お金を貯めたい人
【民間アパートが向いてる人】
- プライバシーを第一に考える人
家族持ち(子育て家庭)
生活導線を優先したい人
車2台持ちで官舎に駐車場が足りない人
- 築浅のアパートで良い暮らしをしたい人
結論として、「官舎=安い」「民間=高い」ではなく、状況により逆転し得るということです。
生活の質(QOL)も判断材料にすべき
数字だけでは見えてこない「生活の質」「心の余裕」は、意外と住居の満足度に直結します。
民間アパートでは
暖かい
設備がしっかりしている
子育てしやすい
生活音対策が整っている
- 仕事とプライベートがはっきり分けられる
官舎では
職場が近い
通勤時間が短い
夜間呼び出しへの対応が楽
- 親しい同僚が一緒の官舎に住んでいれば楽しい
このように、それぞれの生活スタイルによって「得」の方向性が異なります。
数字+生活の質=最終判断材料
これが正解です。
自分がどのケースに当てはまるか見極めるポイント
官舎か民間アパートかを判断する際、以下のチェックポイントを整理しておくと迷いなく選べます。
- 家賃はいくらか?
住居手当はいくら支給されるか?
官舎と職場の距離は何分か?
官舎の設備・築年数はどうか?
民間アパートの生活導線はどうか?
家族構成は?子どもはいる?
車の台数は?駐車場代はいくらか?
防音は?
このあたりの項目をすべて考慮したうえで、自分のケースに近い方を選べば大きな失敗はありません。
私が9年間の経験やお金の勉強をしてたどり着いた結論
個人的な結論としては、貯金が最優先、投資もがっつりしたいという考えが強かったので、
「単身の時期も結婚後も官舎一択」
という選び方が最も合理的だと考えます。
「官舎で固定費を極限まで抑え、貯金をしつつ、投資を増やし、お金に余裕ができ、子供ができたら、極力安い中古住宅を一括で買う」
これが私の考える最適解です。
まとめ
ここまで、官舎(職員宿舎)と民間アパートを「総コスト」「住宅手当」「生活導線」「通勤距離」など、あらゆる角度から比較してきました。
最初に感じた「官舎の家賃の圧倒的安さ」は確かに魅力です。
一方、民間アパートも
住居手当の支給
快適な設備
生活導線の良さ
によって、家族持ちや子育て家庭には圧倒的なメリットがあります。
結論はシンプルです。
あなたの生活スタイル・家族構成・勤務地・通勤距離・光熱費・将来への貯金・投資などを踏まえて、「実質負担額」と「生活の質」のバランスで決めるのが正解です。
住まいの選択は、あなたの家計だけでなく、心の余裕・生活の質にも直結します。
焦らず、数字と現実のバランスを見ながら、最適な選択をしてください。
そして一歩だけ前に進むなら、まずは住宅手当の金額と、自分の実質家賃を紙に書き出すこと。
ここからすべてが始まります。
【関連記事】