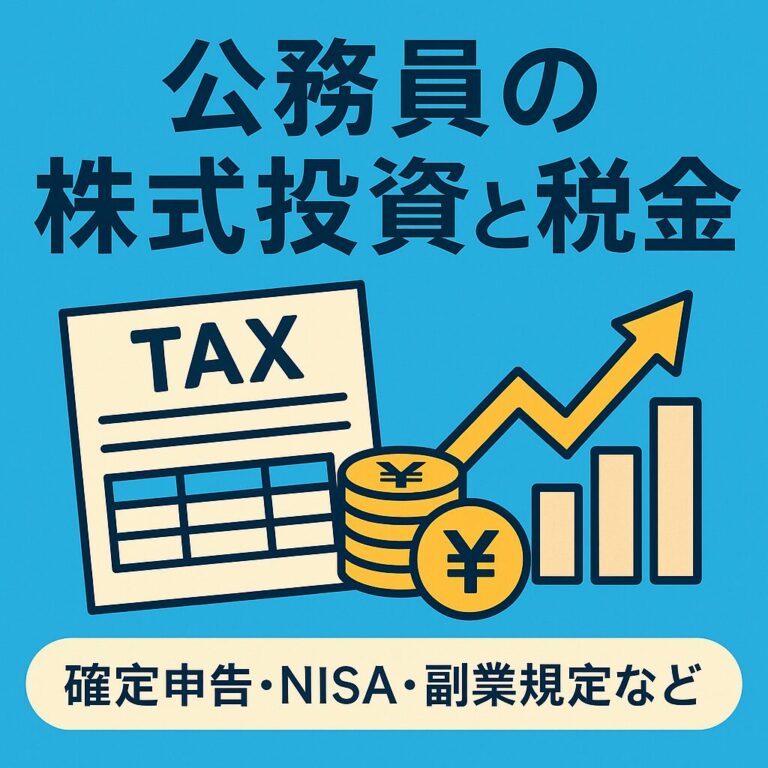株式投資を始めて「利益が出た!」と喜んだのも束の間、「あれ?公務員でも税金はどうなるの?」と不安になったことはありませんか?
実は、私自身も元公務員として、株式投資で利益が出たとき、税金や確定申告のことがまったく分からず戸惑った経験があります。
「NISAやiDeCoを使えば本当に税金がかからないの?」
「確定申告は必要?不要?」
「税務署や職場にバレるリスクは?」
そんな疑問や不安を抱える方はとても多いです。
とくに公務員の場合、民間と違って副業規定があり、税金の申告や住民税の納付方法ひとつで思わぬトラブルに巻き込まれるケースも――。
実際、私も確定申告の仕方や申告不要制度、NISA・iDeCoの活用方法、職場にバレない工夫など、試行錯誤を重ねてきました。
本記事では、
公務員の株式投資にかかる税金の仕組み
配当金・売却益・確定申告の流れ
NISAやiDeCoなど非課税制度の活用法
税務署や職場にバレるリスク・副業規定の注意点
私自身の体験談やリアルな失敗談
最新の法改正や公式情報へのリンク
など、「公務員だからこそ絶対に押さえておきたい“税金のすべて”」を元公務員FPの立場から、できるだけわかりやすく解説します。
数字データや図解・一次情報・Q&A・独自表も交えて、「この記事さえ読めばもう迷わない!」と言える決定版を目指しました。
読み終わる頃には、「知らないことで損した…」と後悔しないよう、今すぐ実践できる具体策までしっかりご案内します。
公務員と株式投資|「税金」の悩みはここで解決!
公務員として働きながら「資産運用を始めてみたい」「将来のためにお金を増やしたい」と思い、株式投資に興味を持つ方が近年増えています。
実際、低金利時代が続くなかで、預金だけでは将来が不安…と感じるのは当然のこと。
しかし、公務員ならではの「副業規定」や「コンプライアンス」に加え、“税金”に関しても民間とは異なる悩みや注意点があるのが実情です。
公務員の株式投資は「合法」でも税金ルールに注意
まず大前提として、公務員が「自分の資産運用目的で」株式投資をすること自体は法律上問題ありません。
実際、総務省や各自治体のガイドラインでも「財産運用の範囲であれば株式売買や投資信託の購入は可能」とされています。
ただし、ここで問題となるのが「利益が出た場合の税金」。公務員の副業規定は「継続的な事業・営利活動」を制限しているだけで、単発の株売買や長期保有で利益が出る場合は通常“副業”には該当しませんが、税金の申告・納税義務は当然発生します。
公務員の株式投資で多い悩み・疑問
利益が出た場合、確定申告は必要?
配当金にも税金がかかるの?
NISA・iDeCoを使えば本当に税金はゼロ?
職場や税務署にバレるリスクは?
副業禁止規定との関係は?
このような悩みは私自身も最初はまったく分からず、何度も税務署や証券会社に相談した経験があります。
実際、ネットには「公務員は株で副業禁止!」「バレたら処分される!」など不安をあおる情報もありますが、正しい知識を持てば心配ありません。
きちんと知っていれば損をしない
たとえば、株式投資の利益には「譲渡所得税」や「配当所得税」がかかります。
これらは証券会社で自動的に税金が引かれるケースがほとんどですが、一定のケースでは自分で確定申告が必要となる場合もあります。
また、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、うまく活用すれば利益に税金が一切かからない仕組みもあり、これを知らずに損をしている公務員も少なくありません。
これから本記事では、こうした「税金の仕組み」「申告の必要性」「副業規定とバレるリスク」「NISAやiDeCoの使い方」まで、FP資格を持つ元公務員の視点から、実体験をまじえて徹底解説します。
公務員が株式投資で知っておきたい税金の基本

株式投資で利益が出ると、どんな税金がかかるのか気になる方も多いのではないでしょうか?
ここでは、公務員が押さえておくべき「株式投資の税金の基本」を、なるべくわかりやすく解説します。
株の売却益にかかる税金(譲渡所得)
まず、「株式を売却して得た利益(=売却益)」には譲渡所得税がかかります。
たとえば、100万円で買った株を120万円で売った場合、20万円の利益が出ます。この20万円が「譲渡所得」と呼ばれる部分です。
日本では、譲渡所得に対する税率が「所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%」で、合計約20.315%が課税されます。
たとえば20万円の利益なら約4万円が税金として引かれる計算です。
配当金にかかる税金(配当所得)
次に、「株を保有しているときにもらえる配当金」にも税金(配当所得)がかかります。
こちらも基本的に「約20.315%」の税金がかかり、証券会社の口座に配当金が振り込まれるときに、自動的に引かれています。
【配当金の税金は2パターン】
特定口座(源泉徴収あり)で受け取る場合
→ 税金が自動で引かれる。ほとんどの人がこのパターン。源泉徴収なし口座や一般口座の場合
→ 配当金の受け取り方法によっては、自分で確定申告が必要になる場合がある。
税率と源泉徴収の仕組み
ここで、「源泉徴収」という言葉が出てきました。
これは「証券会社があらかじめ税金を差し引いてくれる仕組み」のことです。
多くの公務員の方が利用している「特定口座(源泉徴収あり)」の場合、売却益も配当金も、自動的に約20%の税金が引かれて手元に残るので「確定申告不要」で済むケースが多いです。
【注意ポイント】
年間の売却損益や配当の合計額によっては申告が必要になる場合もあります。
(例:複数証券会社の損益通算、配当控除の利用、医療費控除などを同時に申告したい場合)
税金計算の具体例
| 取引内容 | 利益・配当 | 税率 | 税金額 | 実際の手取り |
|---|---|---|---|---|
| 株の売却益 | 100,000円 | 20.315% | 20,315円 | 79,685円 |
| 配当金 | 10,000円 | 20.315% | 2,031円 | 7,969円 |
【体験談】
私がはじめて株式投資で値上がり益や配当金を受け取ったとき、「金額が想像より少ない…」と感じたことがありました。
あとで確認すると、ちゃんと税金が引かれていたからだったのです。
このように、手取りが思ったより少なくてびっくりする人も多いので、最初に仕組みを知っておくことが大切です。
NISA・iDeCoを使えば税金はどうなる?公務員が活用できる非課税制度

「株式投資で利益が出たら、やっぱり税金が心配…」
そう感じている方にぜひ知ってほしいのが、NISA(ニーサ)やiDeCo(イデコ)といった“非課税制度”です。これらは国が推進する「お得な投資の仕組み」で、条件を満たせば利益に税金が一切かからないという強力なメリットがあります。
NISAの基本と公務員の注意点
NISA(少額投資非課税制度)は、毎年一定額までの株式や投資信託の「売却益・配当金」が非課税になる仕組みです。
一般NISA(2023年まで)
→ 年間120万円まで・5年間非課税新NISA(2024年~)
→ 生涯投資枠1800万円・年間360万円まで・最長無期限非課税
→ つみたて投資枠(年間120万上限)と成長投資枠(年間240万円上限)が併用できる
【公務員が注意したいポイント】
「公務員はNISA口座を使えるの?」とよく聞かれますが、問題なく利用できます。
NISAで得た売却益・配当金は「確定申告不要」。税金ゼロでそのまま受け取れます。
副業所得とみなされることはないので、職場に申告したり報告する義務もありません。
iDeCoの税制メリットと注意点
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金を作りながら「掛金が全額所得控除」「運用益が非課税」「受取時にも税制優遇」と三重のメリットがある制度です。
掛金が全額所得控除
→ 年末調整・確定申告で所得税・住民税が減る運用益(売却益・配当)も非課税
60歳以降に一括・分割で受け取るときも一定の税控除あり
【公務員の注意点】
公務員は2017年からiDeCoに加入可能になりました。ただし、掛金の上限額(月2万円)が民間より少ないので注意。
「老後までお金を引き出せない」「転職・退職時の手続き」なども要チェックです。
ジュニアNISA・未成年口座の注意点
2023年で新規募集終了となったジュニアNISAですが、「未成年口座」を使った資産運用も一定の非課税メリットがあります。将来の教育資金づくりに活用する人も多いです。
NISA・iDeCoの非課税イメージ
NISAやiDeCo口座で得た利益(売却益・配当)は、「税金が0円!」
特定口座(通常課税)だと、20.315%の税金がかかる
(図:NISA/iDeCo vs 特定口座の課税比較フロー)
[株式投資で利益や配当が出る]
↓
[証券会社の口座区分によって分岐]
┌─────────────┬─────────────┐
│ 1. 特定口座(源泉徴収あり) │ 2. NISA・iDeCo口座 │
└─────────────┴─────────────┘
↓ ↓
税金約20.315%が自動で引かれる 税金ゼロ!(非課税)
↓ ↓
「手取り分」が口座に入金 全額そのまま口座に入金
↓ ↓
確定申告は原則不要 確定申告不要
【体験談】実際にNISAで税金ゼロを実感
私は公務員時代に「特定口座」と「NISA口座」の両方で株式投資を経験しました。
初めて20万円という大きな利益が出たときは特定口座だったので、利益が税金で20%減り手元には15万に、、、。
実際に5万円引かれた金額を見ると、やっぱり「税金20%はデカい」と感じました。
その後NISAで売却益が出たとき、半信半疑でしたが実際に全額そのまま入金されている画面を見て、嬉しかったことを覚えています。
NISA口座ならそのまま手元に入るので、資産を効率よく増やせると実感しました。
NISA・iDeCoは「公務員でも問題なく使える制度」なので、税金を抑えてお得に資産運用したい方は、必ずチェックしておきましょう。
公務員の株式投資と「副業規定」|税務署・職場へバレるリスクと対策
「公務員が株式投資で儲けると“副業”とみなされるのでは?」
「税金の申告で職場にバレてしまうリスクは?」
こういった不安の声は非常に多いです。ここでは、公務員の副業規定と株式投資の関係、そして“バレる”典型パターンやその対策について、実体験や公式情報も交えて解説します。
そもそも株式投資は「副業」になるのか?
結論から言うと、公務員が自身の資産運用目的で株式投資を行うことは「副業」に該当しません。
国家公務員法・地方公務員法では「営利企業への従事や報酬を得る副業」を原則禁止していますが、「資産運用としての株の売買」は合法とされています。
通常の個人投資家レベルならほとんど心配ありません。
ただし、「業務時間中の売買、インサイダー取引」は絶対NGです。
税金の申告で職場や税務署にバレる?住民税の落とし穴
多くの公務員が気にするのが「株で得た利益を申告したときに、職場にバレるのでは?」という点。
その最大の要因が「住民税」です。
通常、株の利益や配当金は証券会社が源泉徴収しており、「申告不要制度」を使えば住民税も自動的に処理されます。
しかし、「確定申告をして配当控除を受ける」「複数の証券会社の損益通算をする」などで住民税の申告方法を「自分で納付(普通徴収)」にしないと、職場に通知がいく可能性があります。
【具体例】
住民税の「特別徴収」…給与から天引き。住民税の通知が職場の事務担当者に渡ります。副収入があると事務担当者が「妙にこの人税金が高いな」と気づく場合もあります。
住民税の「普通徴収」…自宅に納付書が届き、個人で支払う。副収入の情報は職場には通知されにくい。
職場にバレないための「住民税の普通徴収」設定方法
確定申告の際、「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、原則として副収入分の住民税は自分で納付でき、職場に通知されにくくなります。
ただし、自治体によっては自動で特別徴収になるケースや、仕組みが異なる場合もあるので、確実にバレたくない場合は税務署や自治体窓口に直接確認するのがおすすめです。
【Q&A】公務員と株式投資の税金バレに関するよくある質問
Q. NISA口座なら絶対にバレない?
A. NISAの利益は申告不要・税金ゼロなので、住民税にも影響せず、バレるリスクはほぼありません。
Q. 配当や売却益でバレる可能性は?
A. 確定申告の方法や住民税の納付方式次第でリスクは変わりますが、正しい手順を踏めば基本的に問題ありません。
Q. 大きな利益が出たら調査される?
A. 数百万円以上の利益が短期間に出た場合や、繰り返し多額の利益がある場合は、税務署の調査対象になりやすいですが、違法でなければ心配ありません。
【体験談】実際に住民税を確認していた話
私自身、公務員の新人の頃に事務担当をしていたことがありますが、職員自身が「なんでこんなに住民税高いの?」と自ら相談してきたケースがありました。確かに同じくらいの年代の職員よりも税金が明らかに高かったので不思議になりました。「何か所得があれば高くはなるんですが。計算ミスかもしれないので上司に相談してみます。」といって、上司に投げたまま、その後上司とその職員が何か話して普通に帰って行ったので、どうなったかは知りません。私にお金の知識があれば、ズバリ「副業してます?」と確認していたでしょう。バレたくない場合は、住民税が高くても職場の事務担当に確認するのはやめておきましょう。
公務員が株式投資で絶対に守りたい税金・申告のポイントまとめ
株式投資は、正しい知識とルールを守って運用すれば、公務員でも安全に資産を増やせる手段です。ここでは、公務員が「損をしない」「バレない」「トラブルを防ぐ」ために守りたい税金・申告のポイントを具体的にまとめます。
申告が必要なケース
基本的に「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していれば、売却益や配当金の税金は自動的に引かれるため、多くの場合は確定申告不要です。ただし、以下の場合は必ず申告が必要となるので注意しましょう。
複数の証券会社を利用していて、「損益通算(利益と損失を相殺)」をしたいとき
配当控除を活用して税金を取り戻したいとき
一般口座や源泉徴収なし口座で取引をしたとき
年間の株式売却益や配当の合計が20万円を超える場合で、源泉徴収なしの場合
iDeCoの掛金や医療費控除など、ほかの所得控除と合わせて申告したい場合
【体験談】
私も株以外の所得の件で毎年確定申告をしています。
初めてのときは戸惑いましたが、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を使えば意外と簡単にでき、無事に税金を取り戻せた経験があります。
慣れればどうってことはありません。
申告不要なケース
以下の条件に当てはまる場合、確定申告は不要です。
証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」での取引のみ
NISA・iDeCo口座内での運用益や配当
年間20万円以下の売却益や配当で、かつ源泉徴収済みの場合
多くの公務員は、この範囲であれば「何もしなくてもOK」です。
確定申告の流れ・必要書類・実践アドバイス
確定申告が必要な場合は、以下の流れで進めましょう。
証券会社から「年間取引報告書」を受け取る
郵送またはWebでダウンロードできます。複数社使っている場合はそれぞれ入手を。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
初心者でもガイドに沿って入力できる便利な無料サイトです。入力後、プリントアウトor電子申告(e-Tax)で提出
必要に応じて、マイナンバー、本人確認書類なども準備。住民税の「普通徴収(自分で納付)」を選択
副収入分が職場に通知されるのを避けたい場合は、必ずこの項目を選びましょう。
【アドバイス】
書類は1年分まとめてファイリングしておくと、いざというときラクです。
わからないことは、税務署や証券会社のサポートに遠慮せず相談しましょう。
【チェックリスト】申告・納税で損しないために
□ NISA・iDeCoはフル活用できているか?
□ 「特定口座(源泉徴収あり)」を使っているか?
□ 複数口座の損益通算や配当控除が必要な場合、確定申告を忘れていないか?
□ 住民税の納付方法(普通徴収/特別徴収)をきちんと設定しているか?
□ 毎年の税制改正・新制度に目を通しているか?
口座別・税金比較一覧表
| 口座区分 | 税率 | 税金の引かれ方 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 約20.315% | 証券会社が自動で引く | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 約20.315% | 引かれない(自分で申告) | 必要 |
| 一般口座 | 約20.315% | 引かれない(自分で申告) | 必要 |
| NISA | 0% | 非課税 | 不要 |
| iDeCo | 0% | 非課税(運用益も) | 不要 |
よくある質問Q&A|公務員の株式投資と税金まるわかり

ここでは、公務員の方や家族、これから投資を始めたい方からよく寄せられる「株式投資と税金」に関する疑問に、FP資格を持つ立場からわかりやすく答えます。
Q1. 公務員でもNISA・iDeCoは絶対に使えるの?
A. はい、使えます。
NISA・iDeCoは公務員も利用可能です。
どちらも副業規定には抵触せず、税金面でも優遇されているため積極的に活用をおすすめします。
ただしiDeCoは掛金上限(月2万円)が民間より低いので注意。
Q2. 配当や売却益で20万円以下なら申告不要って本当?
A. 原則、特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要です。
年間の利益が20万円以下で源泉徴収ありの場合、追加の確定申告は基本的に不要。
ただし複数口座をまたぐ損益通算や、他の所得控除と合わせて申告したい場合は必要です。
Q3. 公務員が確定申告すると職場に副収入がバレる?
A. 住民税の「普通徴収」を選択すれば、原則バレません。
確定申告時に「住民税は自分で納付(普通徴収)」にすることで、副収入分が職場の給与課税と合算されるのを防げます。
ただし自治体の運用によっては自動的に特別徴収になる場合もあるため、念のため事前確認を。
Q4. 投資信託の分配金やETFの分配金も税金がかかる?
A. はい、課税されます(約20.315%)。
ただしNISAやiDeCo口座内で受け取れば非課税です。
Q5. 株で大きな利益が出ると副業扱いになる?
A. 通常の範囲であれば副業扱いにはなりません。
あくまで「自己資産の運用」であればOK。
ただしデイトレードなど“事業的”な取引を長期的・大規模に続ける場合は例外になるリスクもあるため注意しましょう。
Q6. NISAやiDeCoの運用益も申告しないといけない?
A. 申告不要、税金ゼロです。
NISAやiDeCoで発生した利益や配当は、申告も納税も一切不要。
確定申告の手間が省けるのも大きなメリットです。
Q7. 年度途中で公務員を退職した場合、税金や申告はどうなる?
A. 退職前後の所得をまとめて確定申告します。
年度途中で退職した場合は、給与と株式取引の損益など、すべてをまとめて翌年の確定申告で申告する必要があります。
証券会社の年間取引報告書を忘れずに用意しましょう。
Q8. 配当金や売却益はどうやって証券会社から連絡がくる?
A. 年に1度「年間取引報告書」として届きます。
証券会社のマイページや郵送で確認できるので、申告や記録のために必ず保管してください。
Q9. 税金が還付されることもあるの?
A. 損失が出た年に確定申告をすれば、翌年以降の利益と相殺(繰越控除)ができます。
これを活用して税金を取り戻せることも。
損益通算・繰越控除についても定期的に見直しましょう。
Q10. 税制改正のリスクは?最新情報の入手先は?
A. 制度変更は毎年のように起きているため、公式サイトや公的機関の最新情報を必ずチェックしましょう。
体験談|FP資格を持つ元公務員のリアルな税務アドバイス・失敗談
株式投資の税金に関して、私自身が公務員時代に体験したこと、FP資格を取得してから実感した注意点やリアルな“やらかし”も正直にお伝えします。
【実話1】「確定申告し忘れ」でヒヤリとした株仲間の話
私の株仲間の話です。
その人は株式投資を始めて2年目、複数の証券会社を使って取引していました。
この年は、A証券で利益、B証券で損失が出ていて、「損益通算すれば税金が安くなる」と知り、はじめて確定申告にチャレンジしました。
しかし、確定申告の期限が近づくにつれ、書類の準備や入力の多さに気が重くなり…結局、直前まで放置。
「あとでやろう」が積み重なり、ギリギリで提出したため不備が見つかり、税務署から「追加書類を出してください」と連絡がきたことも。
この経験から、「年間取引報告書や必要書類は早めにそろえること、わからなければすぐ相談することが大事」と強く実感したそうです。
税務署の窓口や電話相談は意外と親切で、初歩的な質問にも丁寧に対応してもらえたみたいなので、ありがたかったらしいです。
【実話2】NISA・iDeCoの「非課税」の威力を実感
NISA口座で初めて10万円以上の利益が出たとき、「税金が一切かからずそのまま手元に入る」ことに感動しました。
周りの公務員仲間にも勧めましたが、「NISAって難しそう」「手続きが面倒」と敬遠されがち。
しかし、実際は証券会社のWebサイトから簡単に申し込めるし、設定も迷わず進めます。
また、iDeCoに関しては、掛金が所得控除されることで年末調整後に税金が還付されるのも大きなメリットです。
FP資格を取ったあとで「どうせやるなら非課税制度を活用しないと絶対に損!」と心底思いました。
【実話3】住民税の普通徴収を忘れそうになった話
確定申告書を作成するとき、「住民税の納付方法」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選び忘れそうになったことが何度かあります。
もしここをうっかり「特別徴収」にしてしまうと、副収入分の住民税が職場に通知されてしまう可能性が。
幸い毎年申告前に念入りにチェックする癖がついてからは問題ありませんが、申告書類は最後まで丁寧に確認することが大切だと痛感しました。
【アドバイス】公務員は「慎重すぎる」くらいでちょうどいい
株式投資も税金の申告も、「大丈夫だろう」と油断せず、必ず最新の公式情報を確認することが何より重要です。
困ったときは税務署や証券会社のサポート、あるいはFPや税理士、さらには株仲間に相談することで、不安や失敗を最小限にできます。
まとめ|公務員が株式投資の税金で損しないためにできること
株式投資は、ただ「買って売って利益が出る」だけでは終わりません。
税金や申告、そして職場との関係まで考えてこそ、本当に安心して資産を増やすことができます。
ここまで、税金の仕組みや非課税制度、副業規定・住民税対策、体験談やQ&Aまで幅広く解説してきましたが、最後に「絶対に損しないためのポイント」をもう一度整理します。
税金で損しないための5つのポイント
NISA・iDeCoなど非課税制度を最大限活用する
→ 利益や配当に税金が一切かからず、申告の手間も省ける証券口座は「特定口座(源泉徴収あり)」が基本
→ 税金が自動で引かれ、ほとんどのケースで確定申告が不要確定申告が必要な場合は「住民税の普通徴収」を必ず選択
→ 職場バレやトラブルを未然に防げる制度改正や税率の変化、公式情報は毎年チェック
→ 知らない間に損をしないための自己防衛わからないことは早めに税務署やFP、証券会社サポートに相談
→ 独りで抱えず、専門家や株仲間の上級者に相談
今すぐできるアクション
まずは証券会社の口座区分をチェック
NISA・iDeCoを未開設なら「新NISA」「iDeCo」公式ページを見てみる
利益が出た年は「年間取引報告書」を必ず確認し、必要なら確定申告を早めに準備
住民税の納付方式も必ずチェック!
不安を解消して一歩踏み出そう
株式投資の税金や副業規定が不安で一歩踏み出せない方も、正しい知識があれば心配無用です。
公務員でも、ルールを守って投資を続けることで、将来の資産形成がしっかりできる時代になっています。
あなたも今日から「損しないための一歩」を踏み出してみませんか?
【関連記事】
【2025年最新】公務員のiDeCo完全ガイド|初心者向け始め方・メリット・デメリット・注意点を元公務員FPが解説