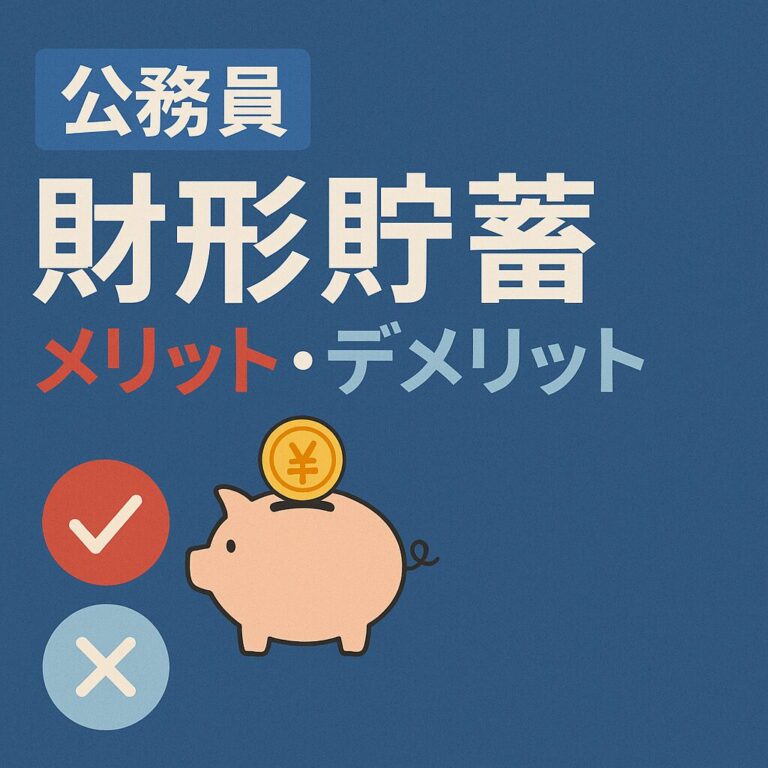公務員として働く中で、「財形貯蓄って本当にやったほうがいいの?」と悩んだことはありませんか?
財形貯蓄は、公務員の多くが一度は勧められる制度。給与から自動で天引きされるので、確実にお金が貯まる仕組みとして根強い人気があります。
一方で、最近は「利息がほとんどつかない」「iDeCoやNISAのほうがいいのでは?」という声も増えてきました。
私自身、県庁職員として9年間働き、実際に財形貯蓄を利用した経験があります。始めた理由も、途中で悩んだことも、今だからわかる「本当に知っておきたかったこと」もたくさんありました。
この記事では、元公務員&FPの視点から、公務員の財形貯蓄のメリット・デメリットを徹底解説します。リアルな体験談、実際の利用データ、最新の制度比較も盛り込みながら、
これから財形貯蓄を始めるか悩んでいる方
すでに利用中で見直しを検討している方
家族に公務員がいる方や公務員志望の方
こういった方が「結局どうすればいいのか?」までわかる内容に仕上げました。
難しい専門用語はやさしく解説し、初めての方でも安心して読める内容になっています。この記事を読めば、公務員の財形貯蓄で後悔しない選択ができるはずです。
それでは早速、財形貯蓄の基本から見ていきましょう。
公務員の財形貯蓄とは?基礎知識と仕組み

財形貯蓄制度の種類(一般・住宅・年金)
財形貯蓄(ざいけいちょちく)は、給与から毎月自動で一定額が天引きされる「勤労者向けの貯蓄制度」です。公務員も多く利用しており、社会人になって最初に案内される福利厚生の一つといえます。
この制度には、以下の3つの種類があります。
一般財形貯蓄
もっとも基本的なタイプで、使い道が自由。旅行や家電の購入、車の買い替えなど、まとまった資金が必要な時に引き出して使えます。財形住宅貯蓄
住宅の新築・購入・リフォームなど、「住まいに関する資金」専用の財形です。住宅取得目的で使う場合は、一定の税制優遇(利子が非課税)を受けられるのが大きな特徴です。財形年金貯蓄
将来の年金や老後資金のために積み立てるタイプ。こちらも、満60歳以降の受け取りで利子非課税となる優遇措置があります。
それぞれ、1人1契約ずつ持つことができ、同時に3種類すべて利用することも可能です(ただし、住宅・年金財形は合計元本550万円までが非課税の上限。一般財形には上限なし)。
公務員の財形貯蓄「種類と特徴」早見表
| 種類 | 主な目的 | 非課税メリット | 引き出しの自由度 | 利用者の主な層 |
|---|---|---|---|---|
| 一般財形貯蓄 | 使い道自由・目的問わず | なし | ○(比較的自由) | 若手・貯金初心者 |
| 財形住宅貯蓄 | 住宅取得・リフォーム等 | 利息非課税(550万円まで)※ | △(住宅目的のみ優遇) | マイホーム検討層 |
| 財形年金貯蓄 | 老後資金・年金積立 | 利息非課税(550万円まで)※ | ×(60歳まで引出制限) | 老後準備を早く始めたい層 |
※住宅・年金財形で合算で550万円まで
公務員の財形貯蓄が民間と違うポイント
公務員の財形貯蓄と民間企業の財形貯蓄は、基本的な仕組みは同じですが、いくつか特徴的な違いもあります。
制度の導入率が高い
公務員の場合、ほぼすべての自治体や官庁で財形貯蓄制度が用意されています。職場によっては、福利厚生の一環として推奨・サポートが強めに行われていることも。銀行・信託・労金など取扱先が幅広い
地方自治体では、地元の金融機関や労働金庫と提携していることが多いです。自分に合った条件の金融機関を選べるのも公務員ならでは。利子補給制度(上乗せ利息)や奨励金がつく場合も
一部の自治体や組織では、一定の条件を満たせば、積立額に応じた「奨励金」や「利子補給」が受けられることも。これは公務員ならではの特典と言えるでしょう(全員に必ずあるわけではありません)。天引きによる“強制力”が強い
毎月の給与から自動で引かれるため、気付いたらお金が貯まっている、という声が多いです。民間企業でも同様ですが、公務員の場合は「職場の同調圧力」もあって、つい始める人が多い傾向です。
※財形貯蓄は「将来のためにコツコツ貯める習慣」を身につけるにはとても有効な制度です。一方で、気軽に引き出しできない・金利が低いなどの特徴もあるため、次の章でメリット・デメリットを詳しく解説していきます。
財形貯蓄のメリット【公務員向け徹底解説】
給与天引きで強制力がある
財形貯蓄最大のメリットは、「給与天引き」という強制力です。
手取りをもらう前に自動で積み立てられるため、「今月は使いすぎて貯金できなかった…」といった失敗が起こりません。
公務員の場合、毎月決まった日に安定して給料が支給されるため、天引きの仕組みと非常に相性がいいです。
私自身「知らないうちに、気が付いたら30万円程度貯まっていた!」という経験もあります。
また、一度始めると途中で積立額を変更・停止するのに手続きが必要なため、「つい使ってしまう」誘惑から自分を守れるのも大きな強みです。
「なかなかお金が貯められない」という人ほど、財形貯蓄は味方になります。
利子補給・住宅財形の優遇措置
公務員の財形貯蓄では、「利子補給」や「奨励金」が用意されている場合があります。
これは、積み立てた金額に対して自治体や職場から上乗せ利息やボーナスが支給される制度で、
通常の銀行貯金にはない特典です。
特に、住宅財形を利用した場合、一定条件を満たすと利息が非課税になり、
金利自体は低くても「普通預金よりお得」な状態になります。
例えば、「年に100万円までの積み立てに対して、3%の奨励金が付く(100万円積み立てると3万円もらえる)」といった事例も。
この特典は職場ごとに異なるため、まずは人事や福利厚生担当に確認するのがおすすめです。
貯蓄習慣が身につく
財形貯蓄を利用すると、毎月決まった金額が自動的に貯蓄されるため、無理なく「貯めるクセ」が身につきます。
特に社会人なりたての頃や、将来のライフプランに不安がある方にはぴったりです。
私自身も、新人公務員時代に労働金庫の営業の人が職場に来て財形をおすすめしてきました。ただ、その当時は財形に関する知識が全くなかったため始めようか悩んでいたところ、実際に財形をやっている上司から「やっておいて損はないよ」と勧められて財形貯蓄を始めました。最初は3種類の財形合わせて月1万円程度からスタートしました。
「自然と積立残高が増えていく」体験は、自己肯定感も上がりやすく、将来への備えにもなります。
税制上の優遇(住宅・年金財形の場合)
財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄には、「利子非課税」という税制優遇があります。
これは、積み立てた元本550万円までの利息に対して税金がかからない、という仕組みです(通常は20.315%の税金がかかる)。
【例】住宅財形で毎月2万円を10年間積み立てると、合計240万円。
この間に発生した利息には税金がかからないため、同じ金額を普通預金に預けるより「お得」になります。
ただし、制度ごとに条件や上限があるため、「住宅購入」「老後資金」といった明確な目的がある人におすすめです。
まとめポイント
公務員の財形貯蓄は、給与天引きによる「強制力」や、場合によっては「利子補給」などの優遇があるのが最大の特徴です。特に「どうやって貯金したらいいか分からない…」という人ほど、まずは財形貯蓄を活用することで、将来への備えをスタートしやすくなります。
財形貯蓄のデメリット・注意点
金利の低さとインフレリスク
財形貯蓄は「お金を確実に貯められる仕組み」という安心感がある一方、金利の低さが最大のデメリットといえます。
現在の財形貯蓄の金利は、とても低い水準です。
例えば長野ろうきんの場合、5年積立で0.4%程度となっています。(参考:長野ろうきん「各種預金の金利情報」)
このため、インフレ(物価上昇)には非常に弱いという欠点があります。
例えば、毎月1万円を20年間積み立てても、利息による増加はごくわずか。
その間に物価が上がれば、「お金の実質的な価値」が目減りするリスクがあります。
せっかく貯めたお金が「将来使う時に思ったほど価値がない」という結果になりかねません。
「安全第一で、とにかく減らしたくない」という人には向いていますが、「お金を効率よく増やしたい」「インフレ対策も考えたい」という方は、他の運用も検討が必要です。
中途解約や引き出しの制限
財形貯蓄は「簡単に引き出せない」というデメリットがあります。
特に「財形住宅貯蓄」や「財形年金貯蓄」は、原則として目的外の引き出しや中途解約に制限がかかる場合があります。
たとえば、住宅財形を「住宅購入以外の目的」で解約した場合、利子の非課税メリットが受けられなくなり、過去の利息に対して遡って課税されるケースもあります。
また、緊急で現金が必要になっても「銀行の窓口で即時に引き出す」ということができません。
申請から着金までに数日~1週間かかる場合もあり、「流動性が低い(すぐ使えない)」という点は要注意です。
転職・退職時の扱いと不便さ
意外と見落としがちなのが、転職や退職時の手続きの煩雑さです。
財形貯蓄は「給与天引き」で成り立つ制度のため、職場を離れると自動的に積立が止まります。
その後は「個人名義口座に切り替え」「一括で解約」「他の金融機関に移管」など、自分で手続きをしなければならず、うっかり放置すると残高が「宙ぶらりん」になるケースも。
また、再就職先が財形貯蓄制度を導入していない場合、これまでの積立をそのまま継続できない場合もあります。
私自身も、県庁を退職した際、「どうやって手続きすればいいのか」「窓口がわかりづらい」「必要書類が多い」などでかなり手間取りました。
人生の節目でバタバタしがちな時期に、事務作業が増えるのは正直ストレスでした。
iDeCo・NISAなど他の資産形成との比較
近年、資産運用の選択肢は増えており、「iDeCo」(個人型確定拠出年金)や「NISA」(少額投資非課税制度)と比べる声が多くなっています。
iDeCo
節税効果が高く、運用次第では大きく増やせる。ただし60歳まで引き出し不可。NISA・新NISA
投資の利益が非課税。株・投資信託など運用商品が豊富。元本保証はないが、インフレ対策には向いている。
これらと比較すると、財形貯蓄は「安全性重視だが増えない」選択肢です。
将来のライフプラン・リスク許容度に応じて、どの制度をどのくらい使うか検討することが重要です。
【関連記事】
【公務員向け】iDeCoとNISAどっちがおすすめ?元公務員FPが失敗しない選び方を解説
注意点まとめ
財形貯蓄は「安心して貯められる」反面、金利が低く、流動性も高くありません。将来の物価上昇や転職リスク、他の資産形成制度とのバランスを考え、「貯める仕組みの一つ」として上手に使うことが大切です。
メリット・デメリット比較表
| 項目 | メリット例 | デメリット例 |
|---|---|---|
| 強制力 | 給与天引きで確実に貯まる | 簡単に解約・変更ができない |
| 安全性 | 元本保証で安心 | 金利が低くインフレに弱い |
| 優遇制度 | 利子補給・奨励金あり(職場による) | 利子優遇は限定的、職場によって差がある |
| 税制メリット | 住宅/年金財形なら利息非課税 | 一般財形は非課税なし |
| 引き出しやすさ | 一般財形は比較的自由 | 住宅・年金財形は制限多い・手続きが煩雑 |
| 他制度との比較 | NISA・iDeCoとの併用で幅が広がる | 投資リターンは狙えない |
公務員の財形貯蓄 実際の利用データ・利用率
財形貯蓄利用者の割合・平均残高
公務員の財形貯蓄制度は、全国的に広く導入されており、その利用率は比較的高い傾向があります。
具体的な統計データとして、全国の国家公務員・地方公務員のうち約3~4割の職員が何らかの財形貯蓄を利用しているという報告もあります(※各自治体の福利厚生報告、労働組合の調査など参照)。
また、財形貯蓄の平均残高はケースによって幅がありますが、
・月額1万円~3万円程度をコツコツ積み立てている人が多い
・10年続けると100万円~300万円ほどになる例が一般的
一方で、「積立を始めたものの数年で中断する」「ボーナス時だけ追加で積み立てる」といったパターンも見受けられます。
定年まで継続して財形貯蓄を利用している方は、500万円を超えるケースも少なくありません。
どんな人が活用しているか?属性・傾向
財形貯蓄を積極的に利用しているのは、
20代後半~40代前半の若手・中堅層
住宅購入を見据えた「住宅財形」を選ぶ人が多い
「貯蓄が苦手」「先取り貯金したい」と考えている人
「自動で強制的に貯まる制度」を重視する人
お子さんの進学やマイホーム資金を考える子育て世帯
こういった層が中心です。(私の県職員時代の上司・先輩・同期・後輩のデータ)
一方、資産運用に積極的な層(株式投資・NISA・iDeCo重視層)は、「財形よりリターンのある方法を選びたい」として、積極的に利用しない傾向もあります。
【実体験】
私も、30歳あたりにお金の勉強をし、リスクを取りもっとお金を増やしたいという気持ちが高まり「一般財形を解約し、NISAやiDeCoへ」とステップアップしました。
【体験談】私が実際に財形貯蓄を使って感じたメリット・後悔したこと
なぜ始めたのか/運用の流れ
私が財形貯蓄を始めたのは、公務員1年目の春でした。
配属直後にパンフレットをもらったり、労働金庫の営業の方が説明に来たり、上司や先輩、同期もみんなやっているので「なんとく始めた」のがきっかけです。
当時はお金の知識もなく、「とりあえず月1万円を財形で貯めてみよう」と軽い気持ちでスタートしました。
実際の運用はとてもシンプルでした。
給料から自動で天引きされるため、毎月の貯蓄をまったく意識せずに続けられました。
気が付くと3年で約40万円が貯まっていて、「これはすごいな」と感動したのを覚えています。
使ってみて良かった点・困った点
良かった点は、「勝手に貯まっていく安心感」と「強制力」です。
どんなに忙しくても、誘惑に負けて無駄遣いしてしまう月でも、必ず一定額が真っ先に積み立てられていくので、「気が付いたらまとまったお金になっていた」という体験ができました。
一方で、困った点・後悔した点もあります。
まず「金利が低く、思ったほど増えない」こと。
NISAやiDeCoなど他の制度について学び始めると、「もっと運用効率のいい方法を早く知っていれば…」と感じたのも事実です。
また、退職時の手続きは思ったより面倒でした。
庁内にあった労働金庫の窓口で「解約書類」の手続きが必要で、この手続きの流れや必要書類が分かりづらくて困惑。
結局、窓口を何度も往復することになりました。
【まとめ】
財形貯蓄は「貯める習慣が自然につく」「大きな安心感がある」という点で初心者・貯蓄が苦手な方にはとてもおすすめできます。
一方で、「お金を増やしたい」「柔軟に資産運用したい」人には物足りなさもあるので、ライフプランや目的に応じて使い分けるのがベストだと、体験から実感しました。
公務員が財形貯蓄を選ぶべき人・選ばないほうがいい人
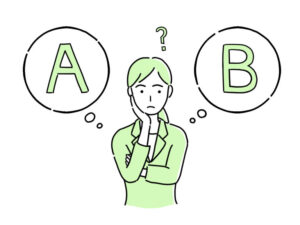
財形貯蓄が向いているタイプ
財形貯蓄は、「貯金が苦手」「つい使ってしまう」という人に特におすすめです。
毎月の給与から自動で天引きされる仕組みのため、
・自分で管理しなくても勝手にお金が貯まる
・意識しなくても「強制的に積み立て」できる
・将来必要な資金(引っ越し、結婚、マイホーム、教育資金など)を確実に準備したい
という方にぴったりです。
また、
・「確実性・安全性重視」「元本保証がほしい」という方
・投資が怖い・株や投資信託に抵抗感がある方
にも財形貯蓄は安心して利用できます。
特に以下のような公務員の方には相性が良いです。
社会人1年目、貯蓄の習慣がない
- 銀行の貯金だとすぐに下ろしてしまってなかなか貯められない
まとまった資金を数年単位で準備したい
住宅取得や老後資金を少しずつ貯めたい
子育て世帯で教育費の計画を立てたい
選ばないほうがいい人・他の資産運用と併用する場合のポイント
一方で、財形貯蓄は「お金を効率よく増やしたい」人には向いていません。
例えば、
金利の低さをカバーしたい
インフレ対策や将来の物価上昇が心配
資産運用にチャレンジしたい(NISA、iDeCoなどを重視したい)
まとまった資金を自由に動かしたい
こういった考えの方には、財形貯蓄だけに頼るのはおすすめしません。
特に、20代~30代で投資リスクを取れる方は、「財形で現金をしっかり確保しつつ、NISAやiDeCoなどで資産運用にも挑戦」という組み合わせ運用がベストです。
【結論】
財形貯蓄は「貯める習慣作り」「元本保証」「将来必要な資金の確保」に最適。
ただし「お金を増やす」「インフレ対策」には向いていません。自分のライフプランや資産運用の目的に応じて、他の制度とバランス良く併用するのがおすすめです。
よくある質問(Q&A集)

Q1. 財形貯蓄は途中でやめられますか?どうやって解約するの?
A.
途中解約は可能ですが、手続きが必要です。
勤務先の担当者に「解約希望」を伝え、所定の書類を提出します。(よく分からなければ総務担当や営業に来た銀行や労金の営業に聞いてみましょう)
ただし、「財形住宅貯蓄」や「財形年金貯蓄」は、目的外で解約すると過去の利息に遡って課税されることがあるため注意しましょう。
解約には数日~1週間ほどかかることも多いので、急な現金化には向きません。
解約理由や状況によって必要書類が異なる場合があるため、早めに担当部署へ相談するのがおすすめです。
Q2. 住宅財形はどんなときに使える?どんなメリットがある?
A.
住宅財形は「住宅の新築・購入・リフォーム」など住まいに関する資金使途で利用できます。
大きなメリットは、「元本550万円までの利息が非課税」「公的な住宅ローン(財形住宅融資)が利用しやすい」点です。
実際、住宅購入を予定している方は財形住宅貯蓄を活用することで「資金の準備」と「融資の選択肢」を広げることができます。
ただし、用途が限定されるので、マイホーム計画がある方向けです。
Q3. NISAやiDeCoとの違いは何ですか?
A.
NISA・iDeCoはいずれも「投資で増やすこと」に重点を置いた非課税制度ですが、
財形貯蓄は「元本保証・強制積立」に特化した“貯蓄”メインの仕組みです。
| 制度名 | 安全性 | 利回り | 税制優遇 | 引き出し | 向いている人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 財形貯蓄 | ◎(元本保証) | △ | △(住宅/年金のみ) | △(やや不便) | 貯金苦手な人・強制力が欲しい人 |
| NISA | △(商品による) | ◯~◎ | ◎(非課税) | ◯ | 増やしたい人・投資に興味ある人 |
| iDeCo | ◯(商品による) | ◯ | ◎(所得控除) | ×(60歳まで) | 老後資金を積み立てたい人 |
つまり、「絶対に元本割れしたくない」「確実に貯めたい」人には財形貯蓄、「お金を増やしたい」「投資にも挑戦したい」人はNISAやiDeCoがおすすめです。
ライフステージや目的によって併用を検討しましょう。
Q4. 財形貯蓄は家族でも利用できる?
A.
財形貯蓄は「公務員本人」または「財形制度を導入している勤務先に勤めている本人」のみが利用できます。
家族名義では利用できませんが、ご自身が積み立てた資金は「子どもの進学」「家族のマイホーム資金」などにも使えます。
Q5. どの金融機関で始めるべき?おすすめはある?
A.
財形貯蓄の取扱金融機関は、銀行・信用金庫・労働金庫などさまざまです。
金利・利子補給・サービス内容は職場によって差があります。
迷ったら、「奨励金や上乗せ金利がある金融機関」を選ぶとお得です。
まずは福利厚生担当や職場に来る営業担当に、金利や優遇制度の有無を確認してみましょう。
まとめ・公務員の資産形成に財形貯蓄は必要か?FPとしての結論
ここまで公務員の財形貯蓄制度について、メリット・デメリット、実際の利用データや体験談、他の資産形成制度との比較まで詳しく解説してきました。
それでは最終的に「財形貯蓄は必要なのか?」FP(ファイナンシャル・プランナー)としての視点から、結論をまとめます。
財形貯蓄は「貯める仕組み」としては非常に有効
財形貯蓄の最大の強みは、「給与天引きによる強制力」と「元本保証」です。
公務員のように安定した収入があり、職場で制度が用意されているなら、“貯蓄のスタートダッシュ”には最適といえます。
特に、社会人として働き始めたばかりの方や、
「貯金が苦手でつい使ってしまう」という方には強くおすすめできます。
また、マイホーム資金や教育資金、急な出費に備える“生活防衛資金”として財形を利用するのは、とても理にかなっています。
ただし「お金を増やす」目的には限界がある
一方で、金利の低さ・インフレリスクは無視できません。
「資産をしっかり増やしたい」「インフレに負けない資産運用をしたい」のであれば、NISAやiDeCoなど投資型の非課税制度との併用が必須です。
私自身も財形貯蓄で基礎を作り、その後は投資信託やNISAへ全振りすることで資産形成の幅を広げてきました。
こうしたバランス運用が、今の時代は特に大切だと実感しています。
ライフプランに応じて「賢く併用」するのが最適解
FPとしての結論は、
財形貯蓄は「貯める習慣」「堅実な資金づくり」に最適
投資で「お金を増やす」にはNISA・iDeCo等も活用する
目的ごとに使い分け、「リスク分散型の資産形成」を目指そう
ということです。
公務員である強みを活かし、「貯める」と「増やす」の両立を意識して、あなたにぴったりの資産形成を始めてみてください。
【関連記事】
公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】