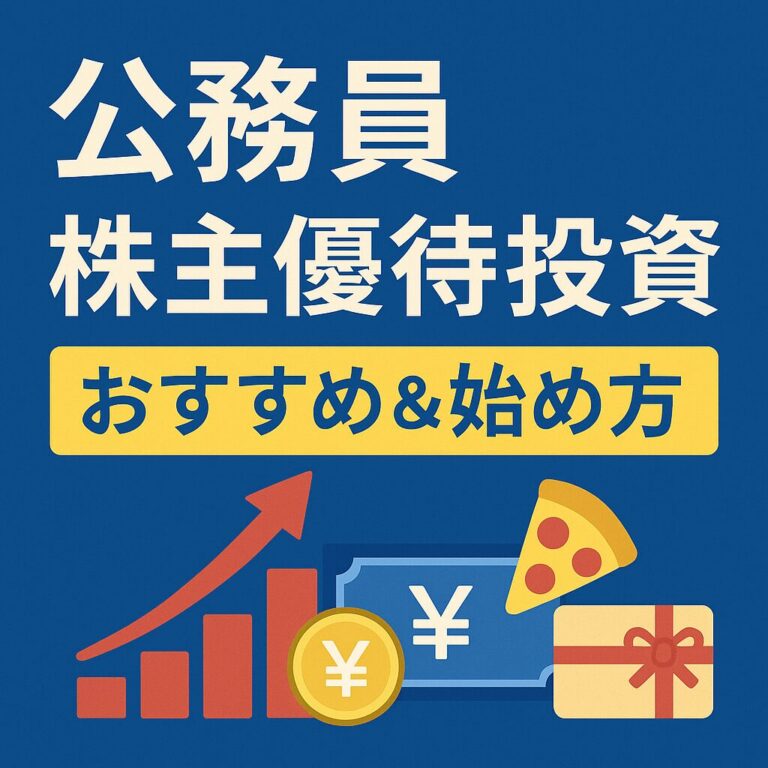「株主優待」という言葉にワクワクする公務員の方も、最近は増えてきました。
“日用品や食事券がタダでもらえる”
“家族で外食費を浮かせられる”
など、優待のある生活は家計にも、日々のちょっとした楽しみにもなります。
でも、
「公務員でも本当に株主優待を受け取って大丈夫?」
「副業禁止にあたらない?」
「どんな優待が本当にお得?」
そんな疑問や不安を持つ方も多いはずです。
私は元県職員&FPとして、実際に株式投資を9年以上実践してきました。
この記事では、「優待に特化」して、公務員が安全に・お得に株主優待を活用する方法を、具体例とともに解説します。
2025年最新の優待おすすめ銘柄、実体験で分かった「得するコツと失敗談」、職場規定や法律の疑問への明快な回答まで、優待投資デビューを後押しする決定版ガイドとして、どこよりもやさしく・詳しくお届けします。
「今年こそ優待生活を始めたい」「家計や暮らしをちょっと楽しくしたい」そんな方に、“公務員×優待投資”のリアルな実践ノウハウをまとめてお伝えします。
公務員こそ株主優待を活用すべき理由

「株主優待」とは、株式を一定数以上持っている投資家に対し、企業が自社の商品やサービス、クオカード、食事券など“ちょっと嬉しいプレゼント”を送ってくれる制度です。
一見、株主優待は「株で儲けたい人」や「投資のプロ向け」のものだと思われがちですが、実は“コツコツ型・堅実志向”の公務員こそ、この制度のメリットを最大限に活用できる存在です。
優待投資の魅力――「節約」と「楽しみ」の両立
公務員の給与は安定しているものの、近年は「物価高」「家計の節約」「将来の年金不安」など、家計管理の意識が高まっています。
そんな中で、株主優待は“持っているだけで日々の生活が少し豊かになる”実用的な特典。
たとえば毎年3月に、
お米や日用品が届く
人気チェーンの食事券やクオカードがもらえる
家族で外食費やレジャー費が節約できる
――といった実益が大きいのです。
たとえば「家族3人分で年に2万円相当の優待をゲット」すれば、その分を貯金や旅行費用に回すこともできます。
優待株投資=ギャンブルではない「守りの資産運用」
「株式投資=危ない」「ギャンブルっぽい」というイメージを持つ人も多いですが、優待投資の基本は“現物株を長期で保有”する堅実なスタイル。
投機的に売買を繰り返す必要はなく、「決まった株数を数年以上持つだけでOK」という手軽さが、公務員のライフスタイルにぴったり合います。
優待だけでなく配当金を出している企業も多い
- 優待目的でもっていたら、株価が値上がりしてさらに大きく資産が増えることもある(逆に資産が減るリスクもあります)
長期保有者に“優遇制度”がある銘柄も多数
「毎年必ずもらえる“優待”が家計の助けに」という安心感があり、投資初心者にも入りやすいのがポイントです。
公務員でも“副業禁止”に当たらないから安心
「株主優待って副業にならない?」と不安に思う方もいますが、株主優待の受け取りは副業扱いにはなりません(※後述の章で詳しく解説)。
勤務先の就業規則に触れる心配が少ないので、安心して始めることができます。
「家族みんなで楽しめる」&「教育にも役立つ」
優待の種類は非常に豊富で、
スーパー・外食チェーンの食事券
日用品やお菓子
図書カードや映画チケット
- 家電
など、家族や子どもと一緒に使えるものも多いのが特徴。
実際、私も「優待が届くたびに家族で箱を開けるのが楽しみ」になり、家計にも優しいイベントになっています。また、子どもと一緒に株主優待について考えることで、金銭教育や経済の仕組みを学ぶきっかけにもなります。
公務員に向いている「コツコツ型・長期投資」ができる
株主優待を狙った投資は、“短期で儲けよう”と考える必要がないため、
長期保有でじっくりコツコツ資産形成したい人
毎年一定の「優待収入」が欲しい人
に最適です。
公務員は本業が忙しいことも多いので、頻繁な売買や値動きチェックが不要な“手間のかからない投資法”としても、優待株の長期保有は非常に相性が良いと言えるでしょう。
公務員こそ株主優待を賢く活用することで、節約と楽しみの両立ができる!
安心・堅実な資産運用法としても優待投資はぴったりです。
公務員の株主優待投資、法律・規定はどうなっている?
「公務員は副業が禁止されている」と聞いて、株式投資や株主優待も“ダメなんじゃないか…”と心配になる方は多いはずです。
ですが、実は「株主優待投資」は公務員でも合法的にできる運用法であり、就業規則の観点からも多くの公務員が実践しています。
ここでは「公務員の投資規定」と「優待投資がOKな理由」、「名義分散」「インサイダー取引」「バレるリスク」など、知っておきたい法律・規定のポイントをやさしく解説します。
「副業禁止」と優待投資の関係
まず大前提として、日本の国家公務員法(第103条・104条)や地方公務員法(第38条)では、“営利企業への従事”や“副業”が原則として禁止されています。
しかし、株式投資や配当金・株主優待の受け取りは「資産運用」にあたり、副業とは見なされません。
【主な根拠】
株式の売買や配当金、株主優待の受け取りは「資産運用」として認められている
副業禁止の対象は「労働により報酬を得ること」であり、株主優待や配当はこれに該当しない
そのため、株主優待を目的とした投資であれば、公務員でも問題なく楽しめます。
インサイダー取引に注意!
株式投資で唯一注意したいのが「インサイダー取引(内部者取引)」です。
公務員の場合、
上場企業に直接関わる部署に勤務している
内部情報(未公表の重要事項)を業務で知った
などの場合、その会社の株を買ったり売ったりすることは、法律違反(金融商品取引法)になります。
たとえば「企業の合併・買収」「大型契約の情報」などを職務上知った場合、その情報が公表される前に売買するのは絶対にNGです。
【インサイダーの具体例】
都道府県の工事発注・入札情報を職務上知った場合、その関連会社の株式売買
公表前の業績アップ情報を知って、その会社の株を売買
このようなケースでは、「その企業の株を売買しない」ことが最善策です。
業務時間中の取引は絶対にNG
副業にはあたらない株式投資ですが、当然業務時間中に投資行為を行った場合、最悪懲戒処分になります。
実際に、勤務時間中に売買を繰り返したとして、懲戒処分になった公務員の事例は多数あります。
【参考】
公務員の株式投資は副業になる?バレるリスク・確定申告・処分事例まで元公務員FPが解説
【2025年版】公務員におすすめの株主優待銘柄ランキング10選

「優待投資を始めたいけど、どの銘柄を選べばいいか分からない」「失敗しない優待株は?」――
そんな公務員の方向けに、2025年最新のおすすめ優待株を“安全性・実用性・お得感”の観点から厳選してご紹介します。
公務員が優待株を選ぶ基準
財務の安定性・上場企業としての信頼度
倒産リスクの低い「大型優良企業」を優先。実用性の高さ
食事券・日用品・金券など、家計や生活に役立つもの。優待利回り・配当利回り
優待だけでなく配当金も含めた“実質的なお得さ”で選ぶ。長期優遇の有無
「長く持つほど優待がグレードアップ」する銘柄は公務員に向いている。改悪リスクの低さ
業績が安定しており、過去に優待改悪や廃止が少ない会社。
おすすめ優待銘柄ベスト8(2025年最新版)
(※2025年7月時点の最新情報・各銘柄の内容や条件は公式サイトで要確認)
1位:イオン
【優待内容】優待カード(3%~7%還元)+自社ギフトカード(1,000円~10,000円・半年ごと)
【特徴】イオン系スーパーの利用者必携。買い物のたびに“自動節約”効果。
【実体験】イオンの店舗近くに住んでいる知人が大絶賛。
2位:FOOD&LIFE COMPANIES(スシロー)
【優待内容】食事優待券(1,650円~16,500円・半年ごと)
【特徴】スシローが近くにある人は大活躍。
【実体験】母がスシロー株を持っていて優待が届いたら食べに行こうと誘われて御馳走になっています。
3位:カッパ寿司
【優待内容】食事優待券(3,000~12,000円相当・半年ごと)
【特徴】カッパ寿司によく行く人には超お得。
【実体験】母が保有していて、優待が届いたら御馳走になっています。
4位:丸亀製麺
【優待内容】食事優待券(3,000円~15,000円・半年ごと)
【特徴】近くに丸亀製麵があればかなりラッキー
【実体験】母が保有していて、よく一緒に食べに行っています。丸亀製麵は一回の食事がそんなに高くないので、何度も通って無料で食べています。
5位:ライザップ
【優待内容】チョコザップ割引券(半年半額~1年半額)+優待ポイント付与+優待券(5,000円~10,000円)
【特徴】家電や日用品をゲットできる。長期保有優遇あり。チョコザップ利用料が半額になる。
【実体験】年によって優待商品が変わるが、キッチン家電なども充実。私は5年間毎年優待でキッチン家電をもらい続けています。
6位:すかいらーくホールディングス
【優待内容】食事割引カード(2,000円~17,000円・半年ごと)
【特徴】ガスト・バーミヤンなどで使える。家族外食派に特に人気。
【実体験】月イチの外食が“優待で無料”に。子どもが大喜び。
7位:日本マクドナルドHD
【優待内容】食事券(バーガー・サイド・ドリンクのセット×6回分シート×1冊~5冊・半年ごと)
【特徴】子育て世代に圧倒的人気。日常使いできる。
【実体験】週末ランチで家族全員分がタダに。子どもとの“ご褒美タイム”に最適。
8位:コメダホールディングス(3543)
【優待内容】電子マネー(1,000円分・半年ごと)
【特徴】コメダ珈琲店を利用するなら絶対おすすめ。
【実体験】休日にモーニング利用で“タダ感”を満喫。
その他おすすめジャンル・銘柄(サブリスト)
「図書カード」「ギフト券」優待の企業
「子育て世帯向け」…ベネッセHD、アトム等
「外食系」…吉野家、松屋フーズ、クリエイト・レストランツHD
おすすめしない優待株(注意点あり)
株価が大きく下がりやすい新興企業
業績が赤字続き・減配常連
「優待廃止」が頻繁な企業(例:最近の外食チェーン等)
公務員の場合は「安定・長期保有」に向く大型・有名企業が安心です。
長期保有で“優遇”される優待も要チェック
最近は「3年以上保有で優待内容がアップ」「100株以上の長期保有で追加優待」など、“コツコツ持ち続ける人”に有利な制度も増えています。
公務員にぴったりのスタイルなので、積極的に狙いましょう。
公務員の私が株主優待で得したリアル体験談
「本当に優待ってもらえるの?」「どのくらい家計が助かるの?」――
そんな疑問を持つ方のために、実際に私が公務員時代から実践してきた株主優待投資のリアルな体験談をお伝えします。
初めての優待到着、その感動と実感
私が最初に株主優待を受け取ったのは、30歳過ぎた頃、公務員8年目の頃でした。
「ライザップ」株を保有し、持っている株数に応じたポイントをもらい、カタログから優待を申し込む形でした。
カタログには、キッチン家電や美容器具、生活雑貨、服など幅広い商品が掲載されていました。
思わず「これもいい、あれも欲しい」と一人で盛り上がり、最終的に「オーブントースター」と「ホットプレート」と「掛け時計」と「洗顔パック」などを選びました。
数週間後、大量の段ボールが届き、このときの「ご褒美感」は、今でも忘れられません。
お金の心配をせずに“贅沢な気分”を味わえたことで、「優待って本当に生活を豊かにしてくれるんだ」と実感しました。
家族で優待をフル活用したエピソード
それからというもの、母も優待株をたくさん保有するようになりました。
「スシロー」「カッパ寿司」「丸亀製麺」「ヤマダ電機」「すかいらーく(ガスト)」など生活に直結する優待株を集めました。
週末の外食や、ちょっとしたランチが“優待券で無料”に
「クオカード」や「割引券」が毎年自動的に届く
「今年は何円分の優待が届くかな?」と家族で楽しみにしながら、優待品が届くたびに外食に行くのが、母と私の恒例になりました。
私が受け取った優待の実例(2024年・ライザップ)
参考までに、私が2024年にライザップの優待で受け取った&ポイントで買った商品を一部ご紹介します。
2024年はこのほかにジムのチョコザップが1年間無料になり、1万円相当のポイントが届き買い物に使いました。
| 商品名 |
|---|
| スチーム&ベイク トースター(ブルーノ) |
| マルチスティックブレンダー(ブルーノ) |
| どろあわわ洗顔×20パック程度 |
| 置時計×3個(ブルーノ) |
| 半袖ジャージ |
| 掛け時計×2個(ブルーノ) |
| サンダル(ノースフェイス) |
| 顔パック |
| 加湿器(ブルーノ) |
| ファンヒーター(ブルーノ) |
| グリルポット(ブルーノ) |
優待投資を始めて感じたメリットと家計の変化
日々の生活が少し楽しくなる
普段の生活が、ちょっとした“優待イベント”で彩り豊かに。外食・日用品・レジャー費の節約
「今日は優待券で外食しよう」「日用品のストックが届いた」と家計に余裕。家族で経済やお金の話を自然にできる
優待株の話題をきっかけに、子どもと「お金の仕組み」「企業研究」の話もできるようになった。
失敗談と反省点
もちろん良いことばかりではありません。
かつて“高利回り”に釣られて業績の不安定な企業の株を買い、優待廃止や減配にあってしまったことも…。
また、優待目的で買った株の株価が大きく値下がり、優待品をもらってもトータルで見たら全然マイナスということも。
「安定企業」「長期保有向き」を選ぶ大切さを、身をもって学びました。
公務員が優待投資を始める具体的なステップ
「実際にどうやって優待投資を始めたらいいの?」という方のために、口座開設から優待株の購入・管理までの流れを、初心者にも分かりやすく手順ごとに解説します。
【参考記事】
【公務員のための株式投資入門】初心者でも失敗しない始め方・注意点を元公務員FPがやさしく解説
1. 証券口座の選び方・開設手順
まずは証券会社の口座開設が必要です。
公務員の場合でも、一般的なネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)が使えます。
特に優待投資をする場合、以下のポイントで証券会社を選ぶと安心です。
証券会社選びのポイント
手数料の安さ(現物株取引のコストが低い)
優待情報・検索機能が充実している
スマホアプリの使いやすさ
サポートの対応(チャットや電話相談など)
私自身は「管理がしやすい・使いやすい・取り扱い商品が多い」SBI証券と楽天証券を使い分けています。
どちらも無料で簡単に口座開設でき、最短翌日から取引可能です。
【参考記事】
【2025年最新】公務員向けおすすめ証券会社4選を元公務員FPが比較!実体験で語る選び方と注意点
開設の手順(流れ)
公式サイトから口座申込み(本人確認書類アップロード・マイナンバー登録)
郵送で書類が届くので、案内に従って初期設定(場合によってはネットで完結可能)
入金が済んだら、株の購入ができるようになる
2. 優待株の探し方と買い方
証券口座を作ったら、いよいよ「どの株を買うか」です。
初心者でも分かりやすい「優待銘柄の探し方」をご紹介します。
優待株の探し方
証券会社の「株主優待検索」機能を活用
たとえば「3月優待」「食事券」「長期優遇あり」など条件を細かく設定できる
優待情報サイトや雑誌(「株主優待ガイド」「ダイヤモンドZAI」等)を参考にする
公式HPで「優待の内容・取得条件」を必ず確認する
優待株の買い方
優待権利日(権利確定日)の数日前までに必要株数を購入
100株単位で買える銘柄がほとんど(NISA口座でもOK)
「長期保有特典」を狙う場合は、年単位で持ち続ける
注意点
権利確定日直前の“優待取り”は、株価変動が激しいこともあるので注意
一度に多銘柄を買い過ぎず、少額から“分散投資”が安心
3. 優待株の保有・管理のポイント
株を買ったら、「あとは放置」…ではなく、優待や配当の管理も大事です。
保有中の注意点
優待の内容や権利条件は“毎年”変わることがあるので、公式HPや証券会社の案内を時々チェック
優待品は登録住所に届くので、住所変更があれば忘れずに証券会社にも連絡を
長期保有特典がある場合、「継続保有」の条件(半年ごと・年1回など)を要確認
管理のコツ
受け取った優待を家計簿や専用ノートで“見える化”すると楽しい
スマホアプリやExcelで管理リストを作るのもおすすめ
配当金の通知や株主総会案内も忘れず保管
4. 家族での優待拡大法
配偶者や父母も証券口座を開設して100株ずつ持てば、その分優待が受け取れる
ただし「名義貸し」はNG。実際に本人が管理できる場合に限る
未成年口座(ジュニアNISAは2023年終了)も利用可能
家族みんなで楽しめる“プチイベント”として盛り上がる
5. NISAやiDeCoとの併用
優待株は「NISA口座」で買えば、配当や売却益が非課税になるメリットあり
iDeCoは“優待目的”には向かないが、併用して将来の資産形成も進めたい
実践例:「私がやった優待投資の始め方」
私の場合、まずは「生活に役立つものをもらえる企業・好きな企業・応援したい企業・値上がりが期待できる企業」を探し購入。
探す際は、株式投資入門書、優待株に関する本、株の雑誌などを参考にしました。
最初の1年で家計の負担が減った感覚が持てたことで、無理せず少しずつ買い増ししていきました。
母にもアドバイスをし、母は持ち株数は増やさないかわりに、たくさんの企業を少量ずつ分散投資してリスクを抑えて優待投資を楽しんでいます。
優待投資は「難しそう」に見えて、実は手順通りに進めれば誰でも始められます。
コツコツ少額からスタートし、管理や家族での活用も楽しみましょう!
株主優待投資のメリット・デメリット
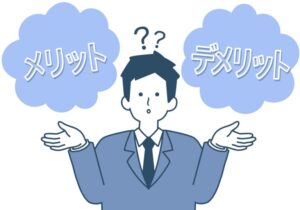
株主優待投資は“やってみると本当に楽しい”反面、メリットだけでなくデメリットや注意点も存在します。
ここでは、公務員が優待投資を行う上で「本当に知っておくべきポイント」をわかりやすく整理します。
メリット一覧
1. 節約効果が大きい
食事券や日用品、ギフト券など現金の支出が減るため、家計の節約に直結します。
たとえば私の家計では、日用品・雑費の年間出費が優待開始後、5万円以上減りました。
2. 日々の生活が豊かになる
「優待が届くのが楽しみ」「家族でカタログを見ながら選ぶ」など、ちょっとしたワクワク感や生活の“彩り”が増えます。
優待券で外食する日は、子どもが「今日はごちそう!」と喜んでくれるのも嬉しいポイント。
3. 配当金も同時にもらえる
優待株の中には配当を出している企業もあり、株主優待+配当金がダブルでもらえます。
現金収入が毎年入るため、実質利回りが高くなります。
4. 長期保有でさらに有利に
最近は「3年以上保有」などの条件で、長期株主だけが受けられる優遇制度も増加中。
公務員のようにコツコツ続けられる人に有利です。
5. 金融リテラシー・子どもの教育にも役立つ
優待投資を通じて「経済」「企業活動」「金融」の知識が自然と身につき、家庭でも“お金の話題”が増えます。
子どもと一緒に経済教育ができるのも隠れたメリット。
デメリット一覧
1. 株価下落リスクがある
優待目的であっても、株価が大きく下がる可能性はゼロではありません。
たとえば企業の業績悪化や経済危機などで株価が下がると、含み損が出ることも。
2. 優待内容が改悪・廃止されることがある
最近は「優待制度の廃止」「条件改悪」も増えています。
たとえば以前は外食チェーンの優待が充実していましたが、利益悪化を受けて廃止や縮小例も目立ちます。
3. 管理の手間がかかる
複数銘柄を持つと「いつが権利確定日?」「どこに届く?」と管理が大変になることも。
株主優待・配当・株主総会の案内など郵送物も増えるため、整理・記録をしっかりしましょう。
4. 「優待クロス」「権利取り」には注意
短期目的での“クロス取引”や“権利取り”は、手数料や株価下落でかえって損をすることもあります。
基本は長期保有スタンスが安心です。
5. 分散しないとリスクが偏る
1つの銘柄だけに資金を集中させると、「優待廃止」「業績悪化」のリスクが高まります。
最低でも5~10銘柄に分散投資を心がけましょう。
優待投資が向いている公務員タイプは?
コツコツ型・堅実志向の人
家族と楽しみながら資産運用したい人
「投機」より「安定収入」を重視したい人
逆に「短期間で大きな利益を狙いたい」「売買を頻繁にしたい」方には向かないかもしれません。
優待投資は“節約・楽しみ・勉強”のメリットが多い反面、株価や制度変更リスクには注意!
デメリットも理解し、管理や分散を心がけて長く楽しみましょう。
Q&A|公務員と株主優待投資でよくある疑問

ここでは、優待投資をこれから始めたい公務員の方が感じやすい「リアルな疑問」を、ひとつずつ丁寧に解決していきます。
ネット上でもよく検索されるロングテール・サジェストワードを意識して網羅しています。
Q1. 優待目的の株式投資は“副業”にならないの?
A. なりません。
株主優待や配当金の受け取りは、「資産運用」に該当します。
公務員の副業禁止規定は「労働で対価を得ること」が対象なので、株式投資はOKです(ただし、インサイダー取引等は厳禁)。
Q2. 優待はどれくらい家計の節約になる?
A. 優待内容や保有銘柄数によりますが、年間2万円~5万円以上の節約効果も可能です。
私や母の場合、
外食費:年間2万円以上が無料
日用品:年間5万円以上が無料
Q3. 家族名義でどこまで優待をもらえる?
A. 家族全員が100株ずつ保有すれば、原則それぞれ優待がもらえます。
たとえば「自分・配偶者・子ども(未成年口座)・父・母」でそれぞれ購入すれば、1銘柄で5つ分の優待を獲得可能。
ただし、「名義貸し」はNG。
名義ごとに実際の管理ができることが前提です。
Q4. 職場に“バレる”ことはある?
A. 通常はほぼありません。
ただし、
売買益が大きくなり「確定申告」が必要になる場合(住民税申告で気づかれるケースあり)
職場独自の細かいルールがある場合
は、念のため人事担当や総務課に事前相談しておくと安心です。
Q5. NISAやiDeCoと併用できるの?
A. できます。
NISA口座で優待株を購入すれば、配当や売却益が非課税で受け取れます。
iDeCoは“優待目的”には向きませんが、将来の資産形成として併用は大いにアリです。
Q6. 優待だけ目当てで投資しても損しない?
A. 必ずしも得とは限りません。
優待利回りにだけ注目して買うと、株価の下落や優待廃止リスクがあります。
「優待+配当+企業の安定性」で総合的に判断し、分散投資を心がけましょう。
Q7. インサイダー取引ってどう気を付ければいい?
A. 「職務上知り得た未公開情報」を使って株の売買をしないのが鉄則です。
勤務先や取引先の株を買う
業務で得た情報で売買する
などは絶対NGです。
不安な場合は、その会社の株を一切取引しないのが安心です。
Q8. 優待改悪・廃止はどう備えたら?
A. ひとつの銘柄だけに頼らず、
複数銘柄に分散
企業の業績や過去の優待履歴をチェック
長期保有優遇など、安定感のある企業を選ぶ
のがベスト。
優待の「廃止リスク」は常に念頭に置きましょう。
Q9. 優待券の使い忘れや管理ミスはどう防ぐ?
A. 家計簿やスマホの「優待管理リスト」がおすすめ。
有効期限や利用先、家族で使う日を決めておくと“使い忘れ”を防げます。
Q10. どんな人が優待投資に向いている?
A. コツコツ型で、家計を楽しく節約したい人。
短期間で大きく儲けたい人
頻繁に売買したい人
にはあまり向きません。
優待投資に関する疑問・不安は「ルール・リスクを知って堅実に楽しむ」ことで解決できます。
迷った時は、信頼できる証券会社のサポートやFPなどの専門家のアドバイスも活用しましょう!
まとめ|公務員が優待投資で幸せになるために
ここまで、「公務員 株式投資 株主優待 おすすめ」をテーマに、優待投資の始め方・おすすめ銘柄・注意点・実体験などを総合的に解説してきました。
最後に、公務員が優待投資で“本当に幸せ”になるためのポイントをシンプルにまとめます。
1. ルールを守れば公務員も安心して優待投資できる
株主優待の受け取りは「副業」ではなく資産運用です。
インサイダー取引や職場独自の規則
名義貸しや虚偽申告
- 業務時間中での株売買
こうしたNG行為さえ避けて、法令と職場ルールをきちんと守れば、公務員でも堂々と優待投資が楽しめます。
2. 「生活を楽しむ」ための優待投資を
株価の値動きや一攫千金を狙うよりも、「生活をちょっと豊かにする」「家族とワクワクを共有する」ことが、優待投資の本当の醍醐味。
外食や日用品が“優待で無料”に
家族で届いたカタログやギフトを選ぶ楽しみ
「今日は優待券でご褒美外食」など小さな幸せを積み重ねる
これが優待投資の一番の魅力です。
3. 続けるほど得をする「コツコツ長期保有」スタイルが最強
配当+優待+長期保有特典+株価上昇の“4重取り”
分散投資でリスクを下げる
年間で受け取れる優待や現金収入が増えていく楽しみ
コツコツ投資で「生活の質」と「資産の安定」を同時に実感できるのが公務員×優待投資の強みです。
4. 家計の“お守り”にも、将来の“お楽しみ”にも
優待株は、
生活費の節約
教育・レジャー・老後の備え
家族の会話やマネー教育
など、今と未来の両方に役立ちます。
5. 迷ったら、まずは“好きな企業・使いたい優待”から一歩
最初から完璧を目指さなくても大丈夫です。
小さく始めて、徐々に銘柄を増やす
家計簿やノートで“優待収入”を見える化
家族でワイワイ楽しみながら資産形成
“公務員らしい堅実な投資スタイル”で、日常も将来も安心&豊かにしていきましょう!
この記事のまとめポイント
優待投資は公務員にも最適な資産運用法
ルールを守って「安心・堅実」に
家計も暮らしも“ちょっと幸せ”に
続けるほどお得が増える「コツコツ型」がおすすめ
迷ったらまずは1銘柄、好きな優待から!
次のステップは?
「優待投資、やってみようかな」と思った方は、ぜひ今日から証券口座開設や情報収集を始めてみてください。
“生活を豊かにする投資”として、あなたの資産形成やご家族の笑顔につながることを願っています。
【関連記事】