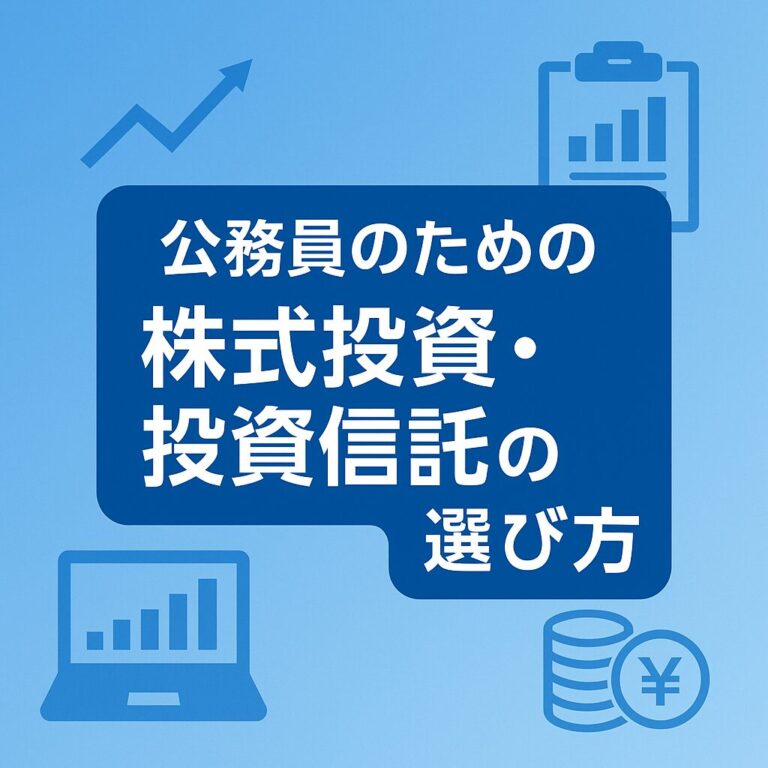近年、公務員の間でも「将来の資産形成」や「老後資金の不安」に対する関心が高まっています。
実際、物価上昇や年金制度の先行き不透明感から、「自分自身でもしっかりお金を増やしたい」「給与以外にも収入源がほしい」と考える公務員の方が増えています。
一方で、
「公務員でも株式投資や投資信託はできるの?」
「何を選べばいいのかわからない……」
「本業に支障が出たり、規則に違反したらどうしよう」
といった不安や疑問を感じている方も多いのではないでしょうか。
私自身、現役公務員として働いていたとき、資産運用に興味はあったものの
「公務員は株をやってもいいのか」
「副業規定に引っかからないのか」
「どうやって始めればいいのか」
「どの株を買ったらいいのか」
など、最初は分からないことだらけでした。
実際に証券口座を開設し、株式や投資信託でコツコツ運用を始めてみて、はじめて分かったこと、感じたこともたくさんあります。
この記事では、「公務員 株式投資 投資信託」で検索された方に向けて、
公務員でも実践できる株式投資・投資信託の選び方のポイント
公務員ならではの注意点(副業規定や倫理規定、税金)
初心者でも失敗しないための実践ポイント
実際に資産運用を始めた体験談やリアルな失敗談
おすすめの証券会社や商品の選び方、具体的な銘柄例
などを「元公務員FP」の目線から、専門用語をわかりやすく、具体的に解説していきます。
また、2025年時点で最新のNISA・iDeCo情報や、公務員に適した積立投資の始め方も網羅。
「何から始めていいか分からない」という超初心者の方でも、この記事を読めば、投資の基本と具体的な選び方がしっかり理解できる構成です。
さらに、現役公務員やそのご家族が安心して資産運用にチャレンジできるよう、Q&A形式でよくある疑問にも丁寧に回答。
「自分にもできるかも」と感じてもらえる記事を目指しました。
これから資産運用を始めたい現役公務員・公務員志望の方、またはそのご家族の方は、ぜひ最後までご覧ください。
公務員の株式投資・投資信託の基本

公務員もできる!資産運用の全体像
資産運用と聞くと、「自分には関係ない」と感じる方もいるかもしれません。
しかし、実際は公務員こそ、安定した給与収入をベースに着実に資産形成できる立場にあります。
資産運用の基本は「将来のためにお金を働かせること」。
預貯金だけではお金はなかなか増えませんが、株式投資や投資信託といった金融商品をうまく活用することで、長期的に資産を増やすことが可能です。
公務員の資産運用では、以下のような選択肢がメインとなります。
預貯金(リスクなし・リターンも少なめ)
株式投資(個別株投資)(企業の株を直接購入し、値上がり益や配当を狙う)
投資信託(プロが選んだ複数の株や債券に少額から分散投資できる)
iDeCoやNISA(税制優遇のある積立投資)
「資産運用=難しいもの」と身構える必要はありません。
むしろ、しっかり知識を身につけて早くから始めた人ほど、有利になるのが資産運用の世界です。
公務員には副業の制限がありますが、「株式投資・投資信託」は「資産運用」であり、原則として副業にはあたりません。
ただし、「業務時間中に売買する」「インサイダー取引」などは完全にアウトです。
株式投資と投資信託の違いを初心者向けにやさしく解説
株式投資(個別株投資)と投資信託は、どちらも「お金を増やすための手段」ですが、仕組みやリスク、向いている人が異なります。
ここではそれぞれの特徴をやさしく解説します。
株式投資(個別株投資)とは?
企業の株(=会社のオーナー権の一部)を直接購入する方法。
株価が上がれば売却益(キャピタルゲイン)、配当金(インカムゲイン)を得られる。
どの企業の株を買うか、自分で調べて決める必要がある。
大きく増える可能性もある一方、株価が下がれば損失を被るリスクも。
- 優待をゲットできる(企業による)
投資信託とは?
投資のプロが多くの人から集めたお金をまとめて、さまざまな株や債券に分散して運用する商品。
1本買えば「自動的に分散投資」できるので、初心者にもおすすめ。
基本的には「長期でコツコツ積み立て」がメイン。
銘柄選びの手間が少なく、値動きも個別株より緩やか。
【比較まとめ表】
| 項目 | 株式投資 | 投資信託 |
|---|---|---|
| 投資対象 | 個別企業の株 | 複数の株や債券など |
| 主な利益 | 売却益・配当 | 基準価額の上昇・分配金 |
| 株主優待 | あり(企業による) | なし |
| リスク | 比較的大きい | 分散でリスク抑えやすい |
| 初心者向き度 | △(選定が難しい) | ◎(手間が少ない) |
「まずは少額で投資信託から始めてみる」のも、公務員初心者にはおすすめです。
公務員が株式投資・投資信託を始めるメリット・デメリット
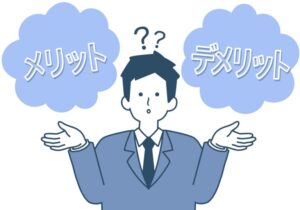
メリット:資産形成・インフレ対策・老後資金の準備
公務員が株式投資や投資信託を始める最大のメリットは、長期的な資産形成ができることです。
特に近年は物価上昇(インフレ)や年金制度の将来不安もあり、「預貯金だけでは将来が不安」という声が公務員の中でも増えています。
給与以外の資産形成ができる
公務員は安定した収入が魅力ですが、給与だけで将来の不安を完全に解消するのは難しい時代になっています。投資による副収入や資産の増加が、将来の安心につながります。インフレ対策になる
物価が上昇していくと、現金や預貯金の実質価値は目減りします。一方、株式や投資信託は企業の成長や経済の発展とともに資産価値が上昇しやすい特徴があります。老後資金の準備ができる
公的年金だけでは将来の生活に不安が残るという方も多いでしょう。早いうちから投資を始めておくことで、老後の資金準備がしやすくなります。特にiDeCoやつみたてNISAは、長期の積み立て投資に向いています。少額からコツコツ始められる
今は証券会社のネット口座なら、投資信託は月100円から積立できるサービスもあります。「難しい」「お金持ちしかできない」という時代ではありません。
デメリット:リスク・本業への影響・副業規定
一方で、株式投資や投資信託にはデメリットや注意点もあります。
元本割れのリスクがある
株や投資信託は、価格が上下します。思ったように増えないだけでなく、場合によっては元本を割るリスクもあります。特に短期間での大きな利益を狙ってしまうと、損失も大きくなりがちです。本業に悪影響が出る可能性も
「株価が気になって仕事に集中できない」「売買のタイミングが気になってしまう」など、本業に影響を及ぼすケースもあります。投資はあくまでも本業(公務)に支障をきたさない範囲で行うことが大切です。副業規定・倫理規定の確認が必要
原則として資産運用は副業には該当しませんが、営利目的での「短期売買」「大量取引」や、職務上知り得た情報を使った投資(インサイダー取引)は明確な規則違反です。また、年間で一定額以上の利益が出た場合は確定申告も必要になります。タイミングによっては損をすることも
「流行っているから」「友達が儲かったから」といった理由だけで始めると、高値づかみになってしまうことも。冷静な判断が求められます。
【体験談】実際に資産運用を始めて感じたこと
私自身、県職員時代(30歳頃)に株式投資(個別株投資)をはじめ、結婚を機に投資信託も始めました。
最初は「本当にお金が増えるのかな?」「損したらどうしよう」という不安が大きかったです。
ですが、
・しっかり企業分析してから株価が下がったところで買い、買ったら基本的には売らない長期投資に徹する
・毎月コツコツ積み立てを続ける
うちに、少しずつ増えていくのを見て「資産形成の手応え」を実感できました。
もちろん、一時的に大きく下がったときもあり「やっぱり怖いな」と思うこともありましたが、「長期投資で我慢して持ち続けていれば自然と戻るはず」と自分に言い聞かせて乗り切りました。
結果として、長期で見ればしっかりプラスになっています。
投資は「短期間で大儲け」を目指すものではありません。
公務員という安定した立場を生かして、無理なく、少額から、着実に資産形成していくのがポイントだと実感しています。
公務員が知っておきたい株式投資の選び方
公務員向きの投資スタイル・分散投資の基本
公務員は「本業が忙しい」「急な残業や異動も多い」など、投資にあまり時間を割けない人も多いはずです。
そこでおすすめなのが「長期・分散・積立」の投資スタイルです。
長期投資:5年、10年といった長い期間コツコツ続けることで、短期的な値動きに振り回されず、資産が安定して増えていきます。
分散投資:特定の1社や1つの業界だけに集中しないこと。複数の企業や業界、国・地域に分散することで、リスクを大きく下げることができます。
積立投資:毎月一定額を自動で積み立てる方法なら、忙しい公務員でも手間なく続けられます。価格が高いときは少なく、安いときは多く買える「ドルコスト平均法※」の効果も期待できます。
【※ドルコスト平均法】
ドルコスト平均法(どるこすとへいきんほう)とは、毎月決まった金額でコツコツと投資する方法のことです。たとえば「毎月1万円ずつ投資信託を買う」と決めておくと、値段が高いときは少しだけ、安いときはたくさん買うことになります。これを続けると、購入価格が平均化されて、値段が高いときにまとめて買ってしまうリスクを減らせるのです。株や投資信託の値段は毎日のように上下しますが、未来の値動きを正確に当てるのはとても難しいです。ドルコスト平均法なら、値段を気にせず自動的に買い続けられるので、感情に左右されにくく、初心者にも向いています。すぐに大きな利益が出る方法ではありませんが、長い時間をかけて少しずつ資産を増やしていけるのが特徴です。まさに「投資は時間を味方につける」という考え方に合った、安全性の高い投資方法といえるでしょう。
インデックス型とアクティブ型の違い
投資信託には大きく「インデックス型」と「アクティブ型」の2種類があります。
それぞれの特徴を知り、自分に合った商品を選ぶことが大切です。
インデックス型投資信託
日経平均株価やS&P500など、特定の指標(インデックス)に連動した運用を目指す投資信託です。
たとえば「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「ニッセイTOPIXインデックスファンド」などが代表例です。
運用コストが安く、シンプルでわかりやすいのが魅力。
長期・積立投資にも最適で、多くの公務員や初心者投資家が選んでいます。アクティブ型投資信託
運用のプロが独自の視点で銘柄を選び、インデックスを上回るリターンを目指す投資信託です。
たとえば「ひふみ投信」などが該当します。
大きなリターンを狙える可能性がある一方、コスト(信託報酬)は高めで、長期的にはインデックス型に劣る場合もあるので注意しましょう。
初心者や忙しい公務員には「インデックス型」の投資信託が基本的におすすめです。
投資信託とETFの違いまとめ
ここでよく混合される「投資信託」と「ETF」のちがいをまとめます。
| 比較項目 | 投資信託 | ETF(上場投資信託) |
|---|---|---|
| 買い方・売り方 | 証券会社や銀行のサイトで「金額指定」で購入(市場を通さない) | 株式と同じように証券取引所で「株価(市場価格)」で売買 |
| 価格の決まり方 | 1日1回だけ「基準価額」が決まる | 市場で株のように値段がリアルタイムで変動 |
| 売買のタイミング | 注文しても約定は1日1回 | 取引時間内ならいつでも売買可能 |
| 最低投資額 | 100円〜1,000円など少額から可能 | 1口(1株)単位なので数千円〜数万円程度から |
| 自動積立 | 可能(毎月定額で自動購入できる) | 基本的に自動積立はできない(自分で都度買う) |
| 手数料(信託報酬) | やや高めな商品が多い | 同じ内容でも投資信託より低めな傾向 |
| 使いやすさ | 初心者向け・ほったらかし向け | 自分で売買したい中級者〜上級者向け |
| 分配金 | 多くが分配金を出さず再投資(分配金はいらないからその分効率的にお金を増やしたい人向け) | 原則として分配金を出す(分配金を定期的にもらい心の支えとしたい人向け) |
| 代表例 | eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)など | バンガード米国高配当株式ETF など |
ざっくり言うと…
投資信託:自動積立や少額投資がしやすく、「ほったらかし運用」に向いている。
ETF:株のようにリアルタイムで売買でき、コストが低い分、自分でタイミングを考えて取引したい人向け。
✅ 初心者はまず「投資信託」でコツコツ積立から始め、投資に慣れてきたら「ETF」にステップアップするのが王道です。
コスト(信託報酬)・リスク・リターン比較
投資信託を選ぶうえで大事なのが「コスト」と「リスク・リターン」のバランスです。
コスト(信託報酬)
運用管理費用のこと。
たとえば「eMAXIS Slim」シリーズは信託報酬が年0.05~0.2%台と非常に安いです。
コストが低いほど、長期投資では最終的なリターンが大きく変わってきます。
アクティブ型は1.0~2.0%以上かかるものも多いため、よく比較しましょう。リスクとリターン
インデックス型は全体の市場平均と連動するため値動きは比較的安定。
アクティブ型は一時的に大きく増えることもありますが、プロでも市場平均に勝つのは難しいと言われています。過去の運用実績も参考に
純資産残高が多く、運用年数が長い商品ほど信頼性が高い傾向です。
ランキングサイトや証券会社の人気商品もチェックしてみましょう。
積立NISA・iDeCoとの相性
公務員が資産形成を始めるなら「NISA」や「iDeCo」との併用も強くおすすめします。
これらの制度は、税金面での優遇があり、効率的に資産を増やすことができます。
NISA
年間360万円まで、永年、運用益が非課税。
つみたて枠の対象商品は金融庁が厳選した低コスト・分散型の商品ばかりなので初心者も安心。iDeCo(個人型確定拠出年金)
毎月の掛金が全額所得控除となり、老後資金の積立に最適。
公務員の場合は「月2万円まで」ですが、長期積立なら将来の差は大きいです。
これらの制度を使いながら、低コストなインデックス型投資信託を中心に積み立てるのが「王道」です。
具体的な銘柄選定例と注意点
具体例
たとえば、分散投資の王道として人気が高いのが「eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)」です。
世界中の約50か国・数千社の株式に自動で分散投資でき、1本で“世界経済全体”の成長に乗ることができます。
米国株中心で運用したい場合は、「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」が代表的な選択肢です。
米国を代表する500社にまとめて投資でき、長期的な成長が期待できます。
どちらを選ぶか迷うときは、投資信託ランキングやNISA対象商品の人気上位を参考にしてみるとよいでしょう。
一つの目安としては、
- 今後もアメリカが世界経済をリードしていくと思う人 → eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) など
- アメリカ以外の先進国にも期待したいし、新興国企業も発展すると思う人 → eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン) など
- オルカンも良さそうだけど、新興国はリスクが高いと感じる人 → eMAXIS Slim 先進国株式 など
【選び方のコツ】
よくわからないうちは1社の個別株へ集中投資せず、まずはオルカンやS&P500のような分散性の高い投資信託から始める
信託報酬(手数料)はできるだけ低いものを選ぶ
人気が高く、長期間にわたり安定した運用実績がある商品を中心に選ぶ
【注意点】
「流行っているから」「SNSで話題だから」といった理由だけで選ばない
短期間で大きな利益を狙える商品はリスクが高く、初心者には不向き
職場などで知った非公開情報(インサイダー情報)を使った売買は違法なので絶対に行わない
✅ 迷ったら、まずはオルカン=世界全体の成長、S&P500=米国の成長という考え方で選ぶと失敗しにくいです。
【体験談】投資信託で積み立てを始めてみた感想
私も最初は「投資信託って難しいのでは?」と不安に思っていました。
でも、少額からなら心配なく始められると思い、
県庁時代にiDeCoで、
- 「たわらノーロード先進国株式」
- 「インデックスファンド海外新興国株式」
- 「三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド」
に月5,000円ずつ積み立てスタート。
退職して結婚してからNISAで、
- 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」
に毎月3,000円ずつ積み立てています。
最初の半年はマイナスになることもあり、「こんなものかな」と思っていましたが、1年続けていくうちに少しずつ運用益がプラスになっていきました。
一時的に株価が下がったときは「続けて大丈夫かな」と不安になりましたが、「長期目線でコツコツ積み立てることが大事」と自分に言い聞かせて継続。
結果、現在(2025年9月28日時点)は、
iDeCo:+13%
NISA:+15%
になっています。
「やってみてよかった」と心から思えました。
今後、とりあえず投資額を数万円程度まで段階的に増やしていこうと考えています。
※ここで示した商品はあくまで私の実例を取り上げたものであり、推奨しているわけではありません。最終的にどの商品が良いかは勉強をし、経験を積み、ご自身に合った商品をご自身の判断で決めましょう。
公務員ならではの注意点とQ&A
副業規定・倫理規定との関係
公務員が資産運用を始める際にもっとも気になるのが「副業規定」や「公務員倫理」との関係です。
多くの方が「株式投資や投資信託を始めたら副業になるのでは?」と不安に感じますが、結論から言えば、「資産運用(株式投資や投資信託)」は原則として副業には該当しません。
なぜなら、
株式投資や投資信託は“自分の資産を運用して増やす行為”であり、“労働”による収入ではないため
実際に人事院や多くの自治体でも「通常の範囲での資産運用は問題ない」とされています
ただし、注意すべきポイントもあります。
業務時間中の売買は、本業への影響や倫理規定上の問題となります
職務上知り得た非公開情報(インサイダー情報)を使った株の売買は、法律で禁止されており重大な処分の対象です
年間20万円超の利益が出た場合は確定申告が必要なので、納税の義務も守りましょう
本業に支障が出ないよう、「長期・積立・分散」を心がけ、節度を持った運用をおすすめします。
よくある質問(Q&A)
Q. 本当に副業にならない?バレたりしない?
A. 資産運用自体は副業扱いにはなりませんし、通常の運用であれば勤務先に知られることも基本的にありません。
Q. NISAやiDeCoは公務員も使える?
A. どちらも利用できます。iDeCoは掛金の上限が低め(月2万円)ですが、長期的にはしっかり差がつきます。
Q. 投資で損する可能性はある?
A. 投資には必ずリスクが伴うため、元本割れすることもあります。生活費を切り崩したり、無理な借金をしてまで投資するのはやめましょう。
税金・確定申告のポイント
株式投資や投資信託で得た利益(譲渡益や配当金・分配金)は、年間20万円を超えた場合、原則として確定申告が必要です。
NISAやiDeCo口座での運用益は非課税ですが、特定口座・一般口座での運用分は所得税・住民税がかかります。
特定口座(源泉徴収あり)を選べば、確定申告不要で自動的に税金が差し引かれます
NISA・iDeCoなら非課税枠で運用可能(確定申告不要)
年間20万円以下なら申告不要ですが、副業収入が他にある場合は合算して計算されます
税制は毎年変更される可能性があるため、気になる場合は証券会社のサポートや税理士に相談すると安心です。
失敗しないための実践ポイント&よくある失敗例
初心者がやりがちなミスと回避策
株式投資や投資信託は、知識ゼロのまま始めると「思わぬ失敗」をしてしまうことがあります。
特に公務員は「資産運用=難しい」「やってはいけないことが多そう」と身構えがちですが、ポイントを押さえれば安全にスタートできます。
主な失敗パターンと対策:
流行や噂で「なんとなく」買ってしまう
→「みんなが買っている」「SNSで話題だから」といった理由だけで商品を選ぶと、高値づかみや暴落リスクに巻き込まれやすいです。必ず自分で仕組みやリスクを理解してから投資を始めましょう。一気に大きな金額を投資する
→最初から多額をつぎ込むと、値動きが大きかったときに精神的な負担も大きくなります。まずは少額でスタートし、「慣れてきたら増やす」方針が基本です。運用成績を気にしすぎて途中でやめてしまう
→短期間での評価損益に一喜一憂しすぎると、せっかくの「長期投資のメリット」を活かせません。月1回だけチェックする・毎月自動積立にするなど、無理なく続けられる工夫をしましょう。必要な生活費や急な出費のお金まで投資に回してしまう
→投資は「余裕資金」で行うのが鉄則です。家計に無理のない範囲で取り組みましょう。
継続的な運用のコツと長期投資の大切さ
資産運用は「始める」より「続ける」ことが大切です。
長期・積立投資は、経済の波に一喜一憂せず、時間を味方につけることが最大のメリット。
世界経済の成長や複利効果を最大限活かすために、下記のポイントを意識しましょう。
毎月一定額をコツコツ積み立てる
→価格の高い・安いに惑わされず、「自動積立」を利用して習慣化するのがコツです。暴落時も慌てず続ける
→大きな下落局面でも「売らずに続けた人」が、最終的には利益を得ているデータが多いです。増やすことより「減らさない」ことを意識
→大勝を狙うよりも、「堅実に長く続ける」方が結果的に資産が増えやすいです。
【体験談】私の失敗とその後
私は途中、「デイトレード(短期売買)をすればもっと短期間で儲けられるのでは?」と考えて、よく調べもせずデイトレをはじめ、大失敗したことがあります。
「やっぱり投資は怖い」と思いましたが、そこでやめずに「なぜ失敗したのか」を振り返り、株に関する本もたくさん読み、以降は「長期投資」に切り替えました。
結果、無理なく続けることができ、運用益も安定して伸びています。
大事なのは「失敗しても株式投資をやめず、自分の投資のルールを決め、守り続けること」だと身をもって感じました。
図解:株式投資と投資信託の選び方フローチャート
Q1. 投資に使える時間や知識は多いですか?
↓
【YES】
Q2. 個別企業の業績やニュースを自分で調べて楽しめますか?
↓
【YES】→【個別株投資】がおすすめ!
(自分で調査して銘柄を選び、リスクとリターンをしっかり考えるタイプ)
【NO】 →【ETF投資】がおすすめ!
(幅広い企業にまとめて分散投資。簡単・手間が少ない)
【NO】
Q3. 毎月コツコツ積み立てる資金はありますか?
↓
【YES】→【インデックス型投資信託】が最適!
(長期・積立・分散投資でリスクを抑えて資産形成)
【NO】 → まずは家計の見直しや少額投資からスタートしましょう!
まとめ|公務員が安心して資産運用を始めるために
ここまで、公務員が株式投資や投資信託を始める際の基礎知識、選び方のポイント、実践例、注意点まで詳しく解説してきました。
公務員は「副業NG」など制約が多いと思われがちですが、長期・積立・分散の資産運用なら原則問題なく、むしろ“安定した収入”という強みを活かして堅実に資産形成できます。
まずは「少額から」「インデックス型投資信託」や「ETF」など、リスクの低い商品で慣れる
投資は「続けること」「ルールを守ること」が大事
本業(公務)への影響が出ないよう、生活に無理のない範囲でコツコツ積み立てる
「何から始めればいいか分からない」という方も、この記事のフローチャートや体験談を参考に、まずは証券口座の開設やつみたてNISAの設定など、一歩踏み出してみてください。
将来の安心や老後資金の準備は、早く始めた人ほど有利です。
焦らず、じっくり資産形成を始めましょう。
分からないことがあれば、信頼できる証券会社やFPに相談するのもおすすめです。
【関連記事】
【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説
【2025年最新】公務員のiDeCo完全ガイド|初心者向け始め方・メリット・デメリット・注意点を元公務員FPが解説