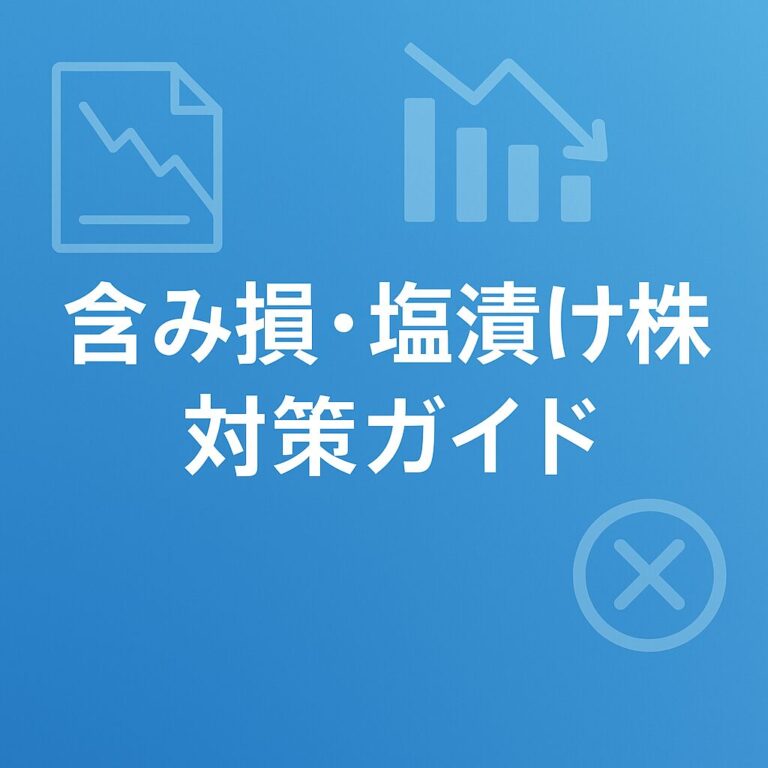「せっかく投資を始めたのに、気が付けば“含み損”や“塩漬け株”だらけ…」
そんな悩み、実は多くの公務員投資家が密かに抱えています。
私自身も現役公務員時代に、何度も「このまま放置していて本当に大丈夫なのか…」と不安に駆られ、悩み続けてきました。
投資は本来、将来の資産形成や家計のゆとりのために行うもの。
しかし、思わぬ値下がりで資金が“塩漬け”状態になったり、含み損を抱えてしまうと、「どう対応したらいいのか」「売るべきか、待つべきか」と判断に迷うことも多いですよね。
特に公務員の場合、「副業規定」や「倫理的配慮」など、一般の投資家以上に慎重になりがちです。
また、“失敗できない”というプレッシャーや、「誰にも相談できない…」という孤独感から、
【なかなか決断できずに放置→含み損拡大→自己嫌悪…】と負のスパイラルに陥りやすいのも特徴です。
この記事では、
「含み損・塩漬け株」を抱えてしまった時の正しい対処法
放置が招くリスクやNG対応例
私自身の失敗と再起のリアル体験談
公務員でもできる“再発防止”&リスク管理術
よくある疑問・Q&A
など、元公務員の視点&FP(ファイナンシャルプランナー)資格保有者としての知見を交え、やさしく・具体的に解説します。
この記事を読み終える頃には、不安や迷いがスッキリ晴れ、「どう動けばいいか」「これからの投資との向き合い方」がしっかり見えてきます。
まずは、含み損や塩漬け株の“正しい知識”から一緒に見ていきましょう。
含み損・塩漬け株とは?【基礎知識と用語解説】
含み損の意味と発生パターン
株式投資をしていると、「含み損」という言葉を必ず耳にします。
これは「保有している株の現在価格が、購入したときよりも下がっている状態」を指します。
例えば、1株1,000円で買った銘柄が、現在800円になっている場合、その差額200円が“含み損”となります(※まだ売却していないので実際には損失は確定していません)。
含み損は、投資をしていれば誰しも経験するものです。
株価は日々変動しますので、一時的にマイナスになることは珍しくありません。
しかし、特に初心者や慎重な性格の多い公務員の方の場合、「損失を確定するのが怖い」「もう少し待てば戻るかも…」と考え、なかなか売却に踏み切れず、ずっと“含み損”のまま保有し続ける人が多い傾向にあります。
「塩漬け株」とは?どんな状態?
一方で、「塩漬け株」とは、含み損を抱えたまま長期間保有し、売るに売れず放置している株のことです。
この「塩漬け」という表現には、「動かしようがない」「どうすることもできない」というニュアンスが含まれています。
塩漬け状態になる原因としては、
「そのうち株価が戻るだろう」と希望的観測で持ち続けてしまう
売却して損失を確定することを精神的に避けたい(いわゆる“損失回避バイアス”)
他の投資先への乗り換えが面倒
「まだ下がるかも」と怖くて買い増しもできない
など、心理的な要因が非常に大きいです。
公務員が抱えやすい投資ストレス
公務員の場合、特に「失敗できない」「慎重な性格」「本業が安定している」「プライドが邪魔をする」などの理由から、損切りや売却の判断が遅れがちです。
このような状態が長く続くと、
毎日株価チェックが憂鬱になる
投資そのものが楽しくなくなる
家計全体の資産効率が悪化する
本業にも悪影響が出る
など、放置によるリスクも大きくなります。
まずは、自分がどのパターンに陥っているかを客観的に知ることが、「含み損・塩漬け株」への最初の対処ステップです。
なぜ公務員に「含み損・塩漬け株」が多いのか?
公務員の投資スタイルの特徴と注意点
公務員という職業は、「安定した収入」「大きな変動が少ない仕事環境」などの特徴があります。
その一方で、投資においては慎重で失敗を極端に恐れる傾向が強くなりがちです。
具体的な特徴を挙げると、
短期売買よりも長期保有派が多い
本業が忙しく頻繁に株価をチェックできない
副業規定があるため、投資に対しても“怪しまれたくない”という心理が働く
周囲に投資相談できる仲間が少ない
このような背景が、「損失を抱えても放置する=塩漬け株が増える」構造を生みやすくしています。
実際の公務員投資家アンケート・私の経験談
例えば、SNSや投資系掲示板で「公務員 株式投資」と検索すると、「損切りできずに塩漬け株が10銘柄以上…」「何年もマイナスのまま放置している」という声が多数見つかります。
結局、株価は戻りましたが、資金効率が最悪な状態になってしまいました。
そのとき、「公務員は“損失を認める”ことがとにかく苦手だ」と痛感しました。
また、公務員は「副業禁止」「職務専念義務」など法的な縛りが強く、投資について“人に相談しづらい”ため、自己流で投資判断を続けてしまいがちです。
結果として、
情報不足で買い時・売り時を見失う
失敗しても相談できず悩みを抱え込む
「とりあえず持っておくか…」と、消極的な塩漬けが増える
というケースが非常に多いのです。
公務員投資家が陥りやすい「含み損・塩漬け」3大パターン
高値掴み後の放置
景気やニュースに乗せられて高値で購入し、その後下落→売るに売れず放置。分散投資のつもりが“分散塩漬け”
複数銘柄に分散したものの、全体的に含み損が広がり対応できなくなる。「配当・優待目当て」で妥協保有
配当や優待目的で買った株が下落しても、「まあ年1回優待もらえるし…」と持ち続ける。
こうした背景と実例を踏まえ、「自分がどのパターンに当てはまるのか」冷静に見つめ直すことが、公務員投資家にとって大きな第一歩です。
含み損・塩漬け株を「放置」してはいけない理由
資産形成に与える悪影響
含み損や塩漬け株を放置していると、資産形成の効率が大きく下がってしまいます。
なぜなら、動かせない“死に金”が増えることで、本来なら成長が見込める他の銘柄や資産にお金を回せなくなるからです。
たとえば、100万円分の株が50万円に下落したまま塩漬け状態になると、残りの50万円は「含み損」のまま資産全体にのしかかります。
この資金を新しい成長株やインデックスファンドに移していたら、数年後に大きく増やせたかもしれません。
塩漬け状態を放置することで、「将来の資産増加チャンスを自ら手放してしまう」リスクがあるのです。
メンタル・生活への影響
含み損や塩漬け株を気にし続けることで、精神的なストレスや日々の生活への影響も避けられません。
特に公務員は「ミスできない」「安定志向」が強いため、
「評価損益がマイナスのまま…」と毎日株価チェックが気になる
「失敗を認めたくない」「誰にも相談できない」ことで自己嫌悪や不安感が強まる
気分が沈み、本業のパフォーマンスや家庭生活にも悪影響を及ぼす
という悪循環に陥りやすくなります。
気が付けば、「投資が楽しいもの」ではなく、「悩みの種」になっていたのです。
「損切り」「ナンピン」など対処法の選択肢
塩漬け株を放置せず、適切な対処を考えることが大切です。
主な選択肢としては、
「損切り」:いったん損失を確定して現金化し、資金を再投資
「ナンピン」:下落したタイミングで買い増しし、平均取得単価を下げる(ただしリスクあり)
「配当・優待」狙いで長期保有(ただし、配当・優待の廃止リスクや資金効率低下に注意)
「ポートフォリオの見直し」や他資産へのシフト
- 「気にせず長期保有」:選定したときのストーリーが崩れない限り保有すると決めていれば塩漬け期間も気にしない(長期保有していればマイナスになることは多々ある)
いずれの方法にもメリット・デメリットがあるため、「自分に合った方法」「本業とのバランス」「家計全体のリスク許容度」を冷静に見極めることが重要です。
こうした理由から、含み損や塩漬け株を理由もなく“何もせず放置”することだけは避けるべきです。
公務員がやってはいけないNG対応例とそのリスク
よくある誤解・失敗例
含み損や塩漬け株への対応で、特に公務員がやりがちな「NGパターン」があります。
これらは資産形成を大きく遠回りさせるだけでなく、場合によっては本業や生活にも悪影響を及ぼします。
1. 何年も放置し続ける(現実逃避型)
「きっといつか戻るはず…」と何年も株価を見ないふりをして、実際は塩漬けのまま動かさないケースです。
時間が経つほど値動きに無関心になり、「資産が増えていない現実」から目を背けてしまいがちです。
2. ルールを決めずに感情で売買する(衝動型)
一時的な株価下落に動揺し、パニックになって底値で売却してしまったり、
「もう戻らないかも…」と根拠なく追加で買い増してさらに損失を膨らませてしまうことがあります。
3. ネットやSNSの噂話を鵜呑みにして対応を決める(情報迷子型)
「〇〇さんがこの株は上がると言っていた」など、根拠があいまいな情報で安易に判断し、
自分に合わない投資スタイルに流されてしまうのも失敗しやすいパターンです。
禁止事項・副業規定と注意点
公務員の場合、副業禁止規定や職務専念義務など、投資以外にも守るべきルールがあります。
株式投資自体は原則認められていますが、
「職務上知り得た非公開情報を元に売買しない」
「投資先企業との癒着・利害関係が疑われる行為をしない」
「投資情報の発信や投資アドバイスは副業とみなされるリスク」
など、一般の投資家よりも注意すべきポイントが多いです。
また、投資で失敗すると「公務員は真面目で失敗しない」というイメージと現実のギャップに苦しみ、誰にも相談できず一人で悩みを抱え込むこともあります。
リスクを最小限に抑えるために
NGパターンに陥らないためには、
投資ルールを最初に決めておく
本業に支障が出るほど投資にのめりこまない
必ず信頼できる公式情報や一次情報で判断する
必要ならFPや証券会社のサポートを利用する
といった「冷静な対応」と「ルール化」が何よりも大切です。
私が実践した!含み損・塩漬け株の対応【実体験ストーリー】
私が最初に「塩漬け株」に悩んだのは、公務員時代に初めて購入した「ライザップ」でした。
当時は「株価がとにかく安い」と、あまり深く調べずに購入。
しばらくは順調でしたが、2020年にコロナが発生、業績は傾き、株価が大きく下落。
気がつけば購入時から5割近くも値下がりし、立派な“含み損”状態になっていました。
最初のうちは「そのうち戻るだろう」と楽観視していましたが、1年経っても株価は回復せず、徐々に気持ちも重くなっていきました。
「損切りするのは負けた気がする」「売れなければ損しない」「いつか必ず上がる」と、結局3年以上も塩漬けのまま持ち続けてしまいました。(2021年に一度だけ暴騰したことがありましたが一瞬で元に戻りました)
決断のきっかけは「長期投資に関する本を多数読んだこと」
転機となったのは、不安をはねのけるために「大成功した個人投資家の長期投資に関する本」を多数読んだことでした。
本から一番学んだ事は、
- 「長期投資では下がったとしても損切は基本的にしない」
- 「一生売らないと思えるような企業を見つけ投資する」
- 「大きな利益を得るためには我慢が必要(利益は我慢料)」
ということでした。
そこで私は、「あえて損切りラインを決めず、コロナ禍はいつか終息する、今は我慢の時、絶対売らない」と覚悟を決めました。
最終的に、コロナ禍から4年後に株価が急騰、含み益が購入額の3倍程度まで上昇しました。
「逆転満塁ホームラン」「我慢が報われた」とその時の快感は忘れられません。
ただ、まだまだ株価が上がると考えていたので、そのときは売りませんでした。
「失敗から学んだこと」と再起への行動
この経験から学んだのは、
含み損や塩漬け株を何も考えず思考停止状態で「放置する」のは最悪の選択
対策方法をネットに求めず、成果を出している投資家が書いた良書に求める(答えは本に書いてある)
長期に持ち続ければ、優良企業ならいずれ上がってくる
暴落は買い込むチャンス
ということです。
今では、自分なりの投資ルールやリスク管理を徹底することで、含み損や塩漬け株に悩まされることもなくなりました。
株歴7年が経つ頃から、達観し始めて、今では株価が上がっても下がっても常に冷静でいられるようになりました。
自分としては、株は動きのある貯金だと思っています。
このように、失敗や苦い経験も「学び」として活かせば、その後の資産運用の土台になります。
大切なのは、「何もせずに放置する」のではなく、自分で現状を受け止め、次にどう動くかを前向きに考えることです。
公務員のための「損切り」「見直し」「戦略再構築」具体策
含み損や塩漬け株を解消し、資産運用の効率を高めるには「損切り」や「見直し」「戦略再構築」が不可欠です。
しかし、公務員の立場や性格上、「大胆な行動」に出るのが苦手な方も多いのではないでしょうか?
ここでは、無理なく実践できる現実的な対処ステップと、冷静に判断するためのポイントを紹介します。
具体的な対処ステップ(時系列・判断フロー)
1. 自分の投資状況を“見える化”する
まずは、保有株の「取得価格」「現在価格」「含み損益」「配当利回り」などをエクセルやノート、アプリで整理しましょう。
全体像を把握するだけで、気持ちが落ち着き、「本当に対応すべき株」が見えてきます。
2. 目標とルールを決める
短期から中期での売買を目標としている場合は、「損切りライン」「利益確定ライン」「保有期間」「投資の目的(配当重視・成長重視など)」をあらかじめ設定することが大切です。
例えば「購入時から8%・10%・15%下落したら売却」など、感情に左右されず淡々と行動できるマイルールを作ることが大切です。
逆に長期投資と一度決めたら、損切はせず、保有し続けましょう。ただし、日々保有企業の情報を集め、業績が急落したり、社長が変わったり、新規事業がうまくいかなかったり、災害が発生したときなど自分の考えているストーリーが崩れた場合は売りましょう。
3. 迷ったら第三者の意見や公式情報を参照
どうしても判断に迷う場合は、本や証券会社やFP、信頼できる個人投資家の友人のアドバイスを参考に。
また、必ず企業のIR資料や公的機関の情報もチェックして根拠ある判断を意識しましょう。
4. 実際に「損切り」や「買い増し」を実行する
ルールを決めたら、迷いなく実行。
実際に行動することで、気持ちがスッと楽になり、次の投資判断にも自信が持てるようになります。
5. 結果を記録して振り返る
売却や損切り後は、その結果や気づきを必ず記録しておきましょう。
「なぜこの判断をしたのか」「今後同じ失敗を防ぐにはどうするか」を振り返ることが、“投資リテラシー”の向上に直結します。
エクセルやアプリで管理する方法
公務員の方には、Excelや家計簿アプリの活用を強くおすすめします。
保有銘柄・購入日・取得単価・現在値・含み損益・配当履歴などを一覧管理
損切りラインや目標価格も「条件付き書式」などで自動で色付け
定期的なメモ・振り返り欄を設けることで、感情に流されにくい仕組みを作る
無料の株式管理アプリ(マネーフォワードMEや証券会社アプリ)も便利ですが、Excelならカスタマイズが自由です。
資産ポートフォリオの組み直し方
「塩漬け株のせいで資産全体のバランスが崩れている…」という場合は、思い切って資産配分(ポートフォリオ)を再構築しましょう。
たとえば、
株式だけでなく投資信託・iDeCo・NISA・債券・現金など複数資産に分散
業種や銘柄も“集中”ではなく“分散”を意識
塩漬け株を処分して、新たな有望銘柄やインデックスファンドへ乗り換える
といった“全体最適”の視点が大切です。
一度ポートフォリオを見直すと、リスクを分散しながら着実な資産形成が目指せます。
どこまで耐える?売却・保有の判断基準
含み損や塩漬け株に直面したとき、「どこまで待てばいいのか」「本当に売るべきなのか」迷う人はとても多いです。
特に公務員の場合、慎重な性格や本業の忙しさから、「判断を先延ばし」にしてしまいがちです。
ここでは、売却や保有の判断基準を冷静に整理し、迷いなく行動できるポイントをまとめます。
売るべきか・持ち続けるべきかの判断基準
まず考えたいのは、「今後、その銘柄に回復する理由があるのか?」「株価が下がった理由は?」という視点です。
【売却を検討すべき主なケース】
企業の業績悪化が続き、今後も回復見込みが薄い
配当や優待が廃止された、あるいは減配が発表された
市場全体が下落しているのではなく、その銘柄だけ急落している
こういった場合は「執着せず、一度リセットする勇気」も大切です。
逆に、
【保有を検討してもよい主なケース】
一時的な市場全体の下落(暴落・コロナショック等)で、企業の本質的価値は維持されている
配当・優待が安定していて、長期でみれば回復も見込める
中長期で応援したい企業・信念の持てるビジネスモデル
この場合は、焦って売らず「長期的な視点でホールド」も選択肢となります。
再浮上・反転を狙う銘柄と損切りラインの設定法
「反転するかも」と感じる銘柄でも、感情任せの“ガマン”だけではリスクが高くなります。
「この水準まで戻れば売る」
「ここまで下がったら潔く損切りする」
など、短期売買の場合は、あらかじめ具体的な「売却ライン」「損切りライン」を決めておくのが鉄則です。
おすすめは、
取得価格から○%下落したら売る(例:8%マイナス)
四半期ごとの業績・配当を必ず確認し、変化があれば即対応
これらの「数字」や「ルール」をExcelに入力しておくと、迷いが減ります。
冷静な判断を保つためのコツ
感情に左右されやすい投資ですが、冷静な判断を保つコツとして、
必ず一晩寝かせてから判断する
SNSやネットの噂ではなく、公式IR情報や証券会社レポートを優先
自分の投資目的(配当・値上がり益・優待など)を再確認し、「今その銘柄が目的に合っているか」自問する
必要ならFPや第三者、成功している個人投資家に相談してみる
特に公務員は「投資で失敗してはいけない」「周りに知られたくない」と感じやすいですが、悩みを一人で抱え込まず、客観的な意見や数字データで判断することが大切です。
メリット・デメリット総まとめ【損切り/塩漬け/放置】
含み損や塩漬け株に直面したとき、「損切り」「塩漬け」「放置」など、いくつかの選択肢があります。
それぞれの方法には一長一短があるため、ここでメリット・デメリットを整理し、比較表も交えて解説します。
【損切り】のメリット・デメリット
【メリット】
損失を確定することで、資金を他の有望な投資先に回せる
メンタル的なストレスや“気がかり”から解放される
投資の失敗を認めて、次に活かすことができる
【デメリット】
実際に損失が確定し、心理的に“負け”を認めなければならない
その後、株価が戻った場合は「早まった」と感じることがある
売却タイミングを間違えると“底値売り”になるリスク
【塩漬け・長期保有】のメリット・デメリット
【メリット】
配当や株主優待を受け取り続けることができる場合がある
一時的な下落からの回復で、将来的に損失が解消される可能性も
税金上、売却損失を確定せずに“含み損”として持ち続けられる
【デメリット】
資金が固定化し、他の投資に回せない(機会損失)
配当や優待が廃止・減配されるリスク
精神的なストレスや「いつ売るべきか」の迷いが続く
【放置】のメリット・デメリット
メリット
一時的に判断を先延ばしできることで、すぐの決断を避けられる
感情的な“狼狽売り”を防ぐケースもある
デメリット
問題を先送りし続けることで資産効率が悪化
決断を後回しにしている間に、さらに株価が下落するリスク
投資の本来の目的(資産形成・安定化)から逸脱しやすい
比較表:選択肢ごとのメリット・デメリット
| 対応策 | 資産効率 | 精神的負担 | 将来の回復期待 | 投資再スタートのしやすさ |
|---|---|---|---|---|
| 損切り | ◎ | ◯ | △ | ◎ |
| 塩漬け | △ | × | ◎ | △ |
| 放置 | × | × | × | × |
一方で、長期で回復を信じて持ち続けるのも一つの戦略ですが、必ず自分なりのルールや基準を持って対応しましょう。
含み損・塩漬け株に関するよくあるQ&A
ここでは、公務員投資家の方から寄せられやすい「含み損」「塩漬け株」についての疑問や悩みを、Q&A形式で解説します。
※体験談や公務員目線も交え、具体的に回答します。
Q. どこまで待てばいい?“我慢”と“損切り”の線引きは?
A.
「どこまで耐えるか」は多くの方が悩むポイントですが、明確なルールを作ることが一番大切です。
たとえば、「購入時から8%下落したら必ず売る」「四半期ごとに業績・配当をチェックして見直す」など、自分なりの“判断基準”を設定しましょう。
私自身も、「なんとなく持ち続ける」ことで損失が膨らんだ経験があります。
ルールを決めておくことで、迷いを減らし、感情に流されにくくなります。
Q. 配当や優待だけ狙って塩漬け株を放置しても大丈夫?
A.
配当や株主優待がある銘柄を「とりあえず持っておく」のも戦略のひとつですが、配当・優待が廃止や減額されるリスクもあります。
また、株価の下落が続くと、最終的には「塩漬け状態」の資金効率が悪くなることも。
定期的に企業のIR情報や決算発表を確認し、「本当に保有し続ける価値があるか」を見直すクセをつけましょう。
Q. 他の資産運用方法の選択肢は?
A.
株式以外にも、投資信託・債券・iDeCo・NISA・現金預金など多様な選択肢があります。
特に公務員は「安定重視」「リスク分散」を意識した資産運用が向いています。
たとえば、
投資信託で長期運用
公的制度(iDeCo・NISA)を活用し節税しながら資産形成
生活防衛資金をしっかり確保した上でリスク資産にチャレンジ
など、“塩漬け株だけに固執しない”柔軟な考え方も大切です。
Q. 失敗したら、もう投資はしないほうがいい?
A.
失敗や含み損の経験は、多くの投資家が通る“成長の通過点”です。
大事なのは「失敗から何を学ぶか」。
一度きりでやめてしまうのではなく、ルールや投資スタイルを見直しながら続けていくことで、資産運用の実力が確実にアップします。
私も最初の失敗で投資をやめていたら、今のように資産を増やすことはできませんでした。
このように、よくある疑問を一つ一つ解消しながら、投資を前向きに続けていくことが大切です。
まとめ|公務員の株式投資、含み損・塩漬け株は“仕組み”で乗り越えよう
公務員の株式投資において、含み損や塩漬け株の悩みは誰もが一度は通る道です。
しかし、「どうせ戻るだろう」と何もせずに放置するだけでは、資産効率も、気持ちもどんどん悪化してしまいます。
本記事で紹介したように――
まずは自分の投資状況を客観的に“見える化”しよう
短期売買のときは損切りや利益確定など「ルール化」して、迷いなく行動できる仕組みを作ろう
Excelで日々の投資を管理し、定期的に振り返ろう
必要なら信頼できる人に相談し、「一人で抱え込まない」ことも大切
- 迷ったとき不安なときは、「成功した個人投資家の長期投資に関する本」に答えを求めよう
本業や家計全体のバランスを保ちながら、“長期スタンス”でリスク管理しよう
失敗や含み損を恐れる必要はありません。
大切なのは「放置せず、自分で向き合う」「経験から学び、再発防止策を身につける」ことです。
私自身も、何度も苦い思いをしながら、「投資は“仕組み”で管理するもの」と実感しました。
これから投資を始める方も、すでに塩漬け株に悩んでいる方も、今日から小さな一歩を踏み出してみてください。
【関連記事】
公務員向けおすすめ株式投資本14選|初心者安心!元県職員FPが体験談で厳選
公務員が失敗しない個別株の選び方|初心者向け実践ガイド【元公務員FP体験談】