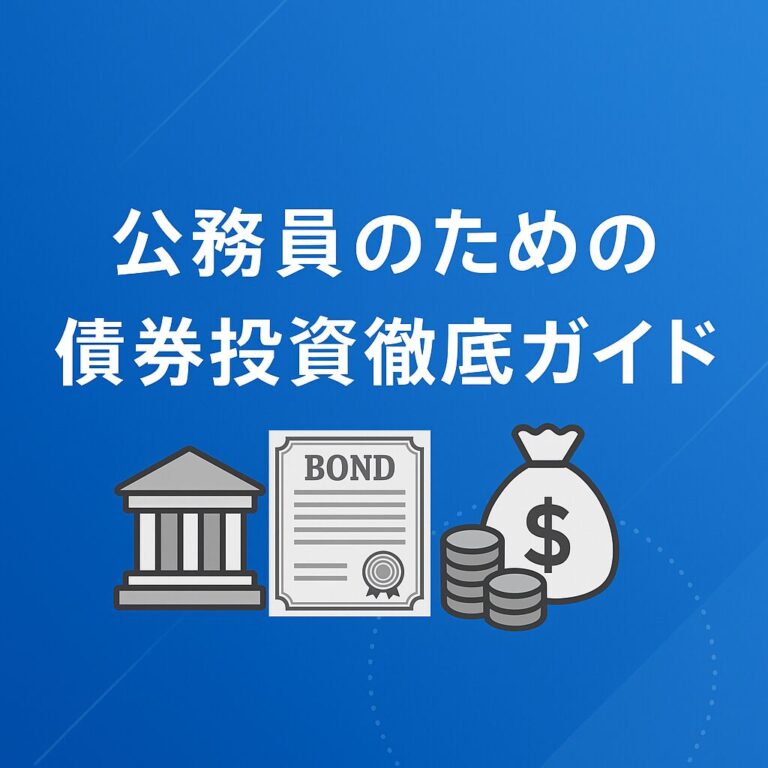「債券投資」と聞いても、ピンとこない方が多いかもしれません。
公務員は給与が安定しているぶん「リスクは取りたくない」「資産運用はハードルが高い」と感じがちです。
でも、物価上昇や将来の年金不安、定年後の生活資金を考えると、少しでも自分のお金に働いてもらう準備が欠かせません。
そんなときに注目したいのが、元本割れリスクが低く、預貯金より利回りが期待できる「債券投資」です。
「株式投資は値動きが大きくて怖いけど、債券なら挑戦できるかも」と考える公務員やそのご家族が増えています。
「そもそも債券って何?」
「公務員でも投資して大丈夫?」
「どんな商品を選ぶべき?」
「リスクや注意点は?」
このページでは、元公務員FPが自身の経験・失敗談を交えながら、公務員に特化した債券投資の基本・始め方・メリット・注意点をわかりやすく解説します。
制度変更リスクや最新の法規制、実際の運用例、図解比較までしっかりカバー。
「今の生活を守りながら、お金にも安心して働いてもらう方法」を一緒に探っていきましょう。
公務員が債券投資を始める理由と基礎知識

そもそも債券とは?|超入門
債券(さいけん)は、ざっくり言えば「国や企業が必要なお金を集めるために発行する借用証書」のことです。
たとえば「日本国債」は国が、「社債」は企業が、「地方債」は地方自治体が資金調達のために発行します。
投資家はその債券を買うことで「お金を貸す」立場になり、満期まで保有すれば元本が返ってきて、その間は利息(クーポン)を受け取る仕組みです。
債券の最大の特徴は、預貯金よりも高い利回りが期待できるのに、株式ほど値動きが激しくない点です。
たとえば日本国債は「ほぼ元本割れしない」とされる超安全資産。
企業の社債や外国債券はリスクが少し高まりますが、そのぶん利息も大きくなります。
「投資」というとギャンブルのように思われがちですが、債券は安定志向の方にこそピッタリの資産運用方法です。
特に公務員のように大きなリスクは避けたい、でも将来のために少しでもお金を増やしたい——そんな方におすすめなのです。
公務員が資産運用で債券を選ぶメリット・向いている人
公務員が債券投資を検討する一番の理由は「安定性の高さ」です。
公務員の給与は安定していますが、将来の昇給ペースや年金、物価上昇の不安は避けられません。
「手堅く増やしたい」
「リスクは最小限にしたい」
「資産運用はやりたいけど損するのは怖い」
……そんな方にこそ債券投資は向いています。
【債券投資のメリットはこんな方におすすめ】
預貯金だけでは物足りないけど、リスクは抑えたい
株式投資の値動きにはついていけない
教育資金や住宅資金など、確実に増やしたい目的がある
定年退職後の生活資金やセカンドライフ資金をじっくり貯めたい
「守りながら増やす」資産運用をしたい
私自身も現役公務員時代、「株式投資は難しそうだし失敗したくない」と悩んでいました。
そんなとき、株式投資の本で出てきたのが債券でした。
私自身は最終的にリスクを取ってリターンを増やしたいという思いから、債券投資はしませんでしたが、
「投資を始める一歩が不安」
「ある程度まとまった額のお金があり、少しでもいいから堅実に増やしていきたい」
という方には、まずは債券という選択肢もありだと思います。
債券投資の基本とリスク
債券投資の種類(国債・社債・地方債・外国債券など)
債券には、いくつかの種類があります。投資先によってリスクやリターン、目的が異なるので、自分に合った債券を選ぶことが大切です。
主な債券は以下の4つです。
1. 国債(こくさい)
国が発行する債券です。
日本の場合「日本国債」がこれにあたり、もっともリスクが低いとされています。
利回り(年率でどのくらい増えるか)は低めですが、国が破綻しない限り元本が返ってくる安心感があります。
公務員の方が「初めての債券投資」で最初に選びやすいのがこの国債です。
2. 地方債(ちほうさい)
都道府県や市町村など、地方自治体が発行する債券です。
こちらも比較的リスクは低いですが、国債より少し高い利回りが期待できます。
地域を応援したい方や、地元の発展に貢献したい方にも人気です。
3. 社債(しゃさい)
企業が発行する債券です。
大企業が発行するものから、やや小規模な会社まで幅広く、利回りは国債や地方債より高くなる傾向です。
その分、企業の経営状態が悪化した場合、元本が戻らないリスクもあります。
「多少リターンを増やしたい」「応援したい企業がある」という方に向いています。
4. 外国債券
海外の政府や企業が発行する債券です。
為替変動リスク(円安・円高で損益が変わる)や、発行国の経済状況によるリスクもありますが、利回りが高いものも多く、分散投資のひとつとして利用されます。
投資初心者はまず国内債券で慣れてから、外国債券へ広げていくのがおすすめです。
【参考:主な債券の比較表】
| 種類 | 主な発行者 | 安全性 | 利回り | 主なリスク |
|---|---|---|---|---|
| 国債 | 日本政府 | ◎ | △ | ほぼなし |
| 地方債 | 都道府県・市町村 | ○ | △〜○ | 地方自治体の財政悪化 |
| 社債 | 企業 | △ | ○ | 企業倒産、信用リスク |
| 外国債券 | 海外政府・企業 | △〜× | ○〜◎ | 為替、国・企業の信用不安 |
債券のメリット・デメリットを徹底比較
債券投資には多くのメリットがありますが、注意すべきデメリットやリスクも存在します。
ここで、公務員が知っておきたい「良い点・注意点」をしっかりまとめておきます。
【メリット】
元本が返ってくる確率が高い(特に国債・地方債)
毎年安定した利息(クーポン)がもらえる
株式と比べて価格変動が小さく、値下がりリスクが低い
分散投資で全体のリスクを減らせる
NISAやiDeCoでも運用できる場合がある(後述)
【デメリット】
利回りは定期預金より高いが、株式ほど大きく増えない
途中売却時は価格が下がることもある(市場金利の変動など)
企業や国・自治体が倒産、破綻した場合は元本割れの可能性
外国債券は為替リスクが大きい
インフレ(物価上昇)で実質的な価値が減ることも
私の元上司で債券好きな人がいますが、その人は国債や社債に分散投資したことでリーマンショックやコロナショック時にも資産の値動きが抑えられ、「本業に集中できる安心感」を強く感じましたとのことです。
一方で、為替リスクを甘く見て外国債券に投資し、思ったより利益が伸びなかった経験もあるとのことでした。
リターンだけでなく、リスクも理解して運用することが重要です。
金利・為替・信用リスクとは
債券投資において避けて通れないリスクが3つあります。
やさしく解説します。
金利リスク
市場金利が上がると、保有している債券の価格は下がります。
逆に金利が下がれば債券価格は上昇します。
満期まで持てば元本は返ってきますが、途中で売却する場合は価格変動に注意が必要です。信用リスク
発行体(国や企業など)が財政難や倒産で「元本や利息が払えなくなるリスク」です。
国債はほぼ心配ありませんが、社債や外国債券は事前に信用格付けを確認して選びましょう。為替リスク
外国債券を保有する場合、円安・円高によって日本円での受取額が変動します。
為替リスクを避けたい場合は「為替ヘッジあり」の債券商品を選ぶ方法もあります。
これらのリスクを抑えるには、「分散投資」や「信用格付けの高い債券を選ぶ」ことが大切です。
実践!公務員のための債券投資の始め方
債券購入の流れ(証券口座開設・選び方)
債券投資を始めるには、まず証券会社で口座を開設する必要があります。
最近はオンラインで簡単に申し込める証券会社が増えており、スマホやパソコンだけで口座開設が完了します。
ここでは、債券購入までの一般的な流れを紹介します。
証券口座を開設する
主要ネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)では、債券の取り扱いも豊富です。
口座開設時に本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)が必要です。入金する
口座開設後、自分の銀行口座から証券口座へ入金します。
多くのネット証券は即時入金サービスがあり、ストレスなく投資を始められます。債券商品を選ぶ
証券会社のサイトで「債券」カテゴリを選び、国債・地方債・社債・外国債券などから自分の目的やリスク許容度に合った商品を探します。
重要なのは、「利回り(年間どれくらい増えるか)」と「信用格付け(安全性)」、「満期(いつ元本が返ってくるか)」をチェックすることです。注文・購入する
気になる債券があれば、証券会社の画面から「購入」ボタンを押して注文内容を確認し、購入手続きを完了します。運用・満期まで保有or売却
満期まで保有すれば元本が返ってきますし、途中で売却することも可能ですが、その時の市場価格に左右されます。
【豆知識】
個人向け国債は1万円から購入でき、ネット証券なら手数料無料のことがほとんどです。
債券投資デビューには最適です。
元公務員FPのリアル体験談(元上司の話):実際に債券を運用してみた
私は実際に債券投資はしていないので、ここでは元上司で債券好きな人に聞いた話を書きます。
その人が初めて債券投資にチャレンジしたのは、公務員時代に「銀行預金の金利が低すぎる」と気付いたのがきっかけです。
当時は“安全第一”で、日本国債を証券会社で毎月1万円ずつ積み立てることから始めることに。
はじめは「本当に利息が受け取れるのか」と半信半疑でしたが、半年後には年2回の利息がきちんと口座に振り込まれているのを見て「これなら安心して続けられる」と実感。
その後、少しずつ社債や外貨建て債券にも挑戦しましたが、思ったより為替の値動きが大きく、ドル安のタイミングで評価額が下がったことも…。
それでも「リスク分散」の大切さや、「預金だけでなく、債券や株式にも分けておくことで心の余裕ができる」ことを身をもって体験できた。
ポイントは、「最初は安全な国債や格付けの高い債券から始めること」。
慣れてきたら少しずつ他の債券や投資商品に広げていくと、自分に合った資産運用スタイルが見えてきます。
iDeCo・NISAで債券投資は可能か
最近は「NISAやiDeCoで債券投資はできるの?」という質問も多いです。
実際、どちらの制度でも債券を活用することは可能ですが、選べる商品や税制メリットに違いがあります。
NISA(新NISA)
投資信託の中には債券を主な投資対象とする「債券型投資信託」が多くあります。
NISA口座なら、これらの投資信託を購入し、運用益や分配金が非課税になります。
ただし、個別の国債や社債はNISA口座で直接買うことはできません(通常口座を使います)。iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoでも「国内債券型」「外国債券型」の投資信託が選択肢に入っています。
運用益が全額非課税&所得控除のメリットがあります。
公務員も2017年以降iDeCo利用が解禁され、将来の年金準備や資産の分散先として債券型投信は有力です。
【注意】
NISA・iDeCoの「商品選び」は非常に重要です。
リスクやコスト、運用方針をよく比較し、自分のライフプランに合うものを選びましょう。
公務員の債券投資における注意点と制度リスク

副業禁止規定・倫理規定と債券投資の関係
「公務員は投資をしても大丈夫なの?」と心配される方も多いですが、債券投資自体は法律や服務規律上、原則として問題ありません。
なぜなら、株式や債券の「配当・利息」を受け取る行為は、“資産運用”であって“営利目的の事業”ではないためです。
ただし、以下の点には必ず注意してください。
勤務時間中に取引を行うのはNG(本業に支障が出る場合、懲戒対象になり得ます)
「投資助言業」や「貸金業」など第三者への金融サービスは完全NG
私自身も公務員時代は、金融資産の運用は「副業」ではないという原則を人事担当に確認してからスタートしました。
不安な場合は、所属先の人事課や信頼できるFPに事前に相談しておくと安心です。
法改正・最新ニュースのチェックポイント
制度やルールは年々変わるため、公務員として資産運用をするなら最新の法改正情報や金融庁・財務省の発表は必ずチェックしましょう。
2024年新NISA制度のスタート:債券投資信託にも選択肢が拡大。
iDeCo商品ラインナップの拡充:国内外債券型の新商品が追加されることも。
債券に関する税制改正:利子課税や源泉徴収ルールの変更など。
金融庁・財務省の公式発表や証券会社のお知らせは定期的に目を通すのがおすすめです。
【参考リンク】
最新制度への理解が浅いと、損をしたり、意図せず規定違反となるリスクも。定期的なチェックを心がけましょう。
やってはいけない失敗例とその対策
債券投資は「守り」のイメージがありますが、過信は禁物です。
私がよく聞く失敗パターンを紹介します。
よくある失敗例
利回りだけ見て格付けの低い社債や新興国債券を買い、元本割れ
為替リスクを考えずに外国債券へ集中投資し、円高で大きくマイナス
満期前に急な出費で売却し、市場価格が下がっていて損失発生
分散投資せず、債券だけに偏った運用で資産全体のバランスを崩す
対策はシンプルです。
なるべく格付けの高い債券・投資信託を選ぶ
外貨建ては為替ヘッジ付を選ぶ、もしくは割合を抑える
緊急資金は預金でキープ、債券は余裕資金で運用する
債券と他資産(株式・現金など)のバランスを意識する
「安心のために投資したのに、不安やストレスが増えてしまった」——こんな事態を防ぐには、「無理のない範囲」「分かりやすい商品」「自分で納得して選ぶ」ことが最重要です。
比較表・図解で分かる!債券と他資産の違い
「債券と他の資産(株式・預金・投資信託など)は何が違うの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
ここでは、公務員の資産形成に役立つよう、主要な資産の特徴を比較表とイメージ図でわかりやすくまとめます。
主な資産タイプの特徴比較表
| 資産タイプ | リスク | リターン | 流動性(売却のしやすさ) | 主なメリット | 主なデメリット |
|---|---|---|---|---|---|
| 預金 | 最低 | 最低 | ◎(すぐ引き出せる) | 元本保証・即現金化 | 金利がほぼゼロ |
| 債券 | 低め | 低〜中 | △(満期まではやや低い) | 比較的安全・利息収入 | 中途売却で元本割れあり |
| 株式 | 高め | 中〜高 | ◎(市場で売買可) | 配当や値上がり益 | 価格変動が大きい |
| 投資信託 | 低〜高 | 低〜高 | ◎(原則いつでも売買) | 分散投資・少額からOK | 商品によってリスク差 |
| 不動産 | 高め | 中〜高 | △(売却に時間がかかる) | 家賃収入・値上がり益 | 初期費用・空室リスク等 |
債券は「預金と株式の中間」的な役割。
安定収入を得たい方や「守りの運用」重視の方に最適。
よくある質問(Q&A)

Q1. 債券投資は元本保証ですか?
A. 国債や地方債はほぼ元本保証に近いですが、社債や外国債券は発行体の信用リスク(倒産・デフォルト)や為替リスクがあり、元本割れの可能性があります。
Q2. 公務員でも債券投資はバレませんか?
A. 個人での資産運用(債券購入)は副業には当たりませんが、不安な場合は人事課などに確認しましょう。
証券会社の口座情報が勤務先に通知されることも基本的にありません。
Q3. どれくらいの金額から始められますか?
A. 個人向け国債は1万円から、投資信託での債券投資は100円からでもスタートできます。
Q4. 債券投資の運用益や利息には税金がかかりますか?
A. はい。20.315%の源泉分離課税がかかりますが、NISAやiDeCoを活用すれば一定額まで非課税にできます。
Q5. 途中で売却したらどうなりますか?
A. 市場金利や価格変動の影響で、元本割れや利益減少の可能性があります。
満期まで持つとリスクは抑えやすいです。
まとめ・次の行動へのアクション
債券投資は「リスクを抑えながら資産をじっくり増やしたい」公務員にとって、最適な選択肢の一つです。
安定収入と安心感を両立しやすく、将来に向けた備えにもぴったり。
ただし、過度なリターンを求めたり、分散を怠るとリスクを取り過ぎることもあります。
まずは証券口座を開設し、1万円から国債を試すことから始めましょう。
NISAやiDeCoを活用し、少額から経験を積み、金融リテラシーを高めるのが成功のコツです。