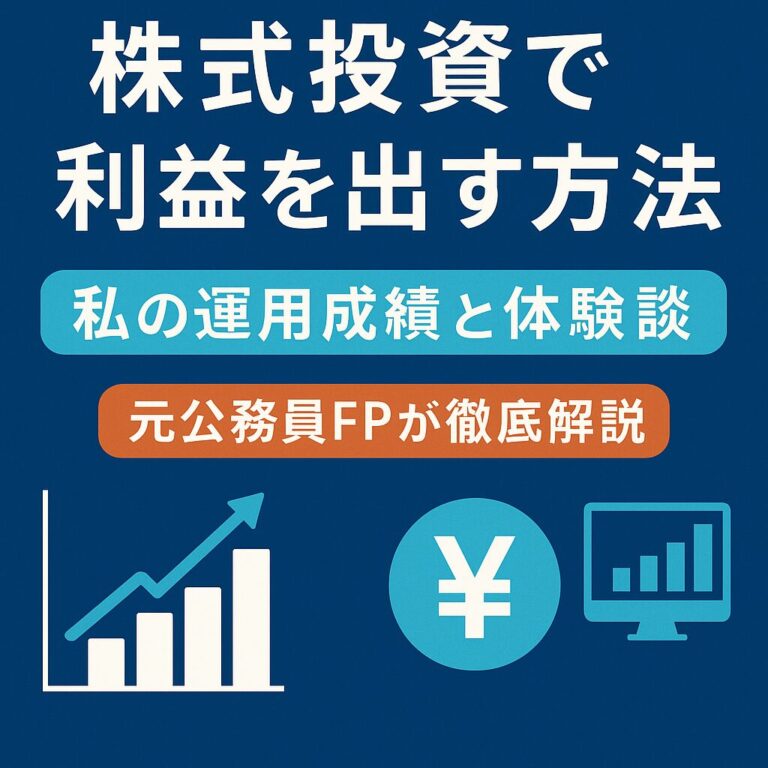公務員でも株式投資で本当に利益を出せるの?
この疑問、きっと多くの現役公務員やこれから資産運用を始めたい方が一度は抱える悩みだと思います。
近年、将来の不安や物価の上昇をきっかけに、「給料だけに頼らず、しっかり資産を増やしたい」と考える公務員が増えています。
ですが一方で、「投資ってなんだか怖そう」「本当に利益が出せるの?」「ほかの公務員はどうしているの?」と不安を感じている人も少なくありません。
私自身も県職員として働きながら、2017年から思い切って株式投資をスタートしました。
正直、最初は不安だらけで、証券口座の開設から銘柄選びまで、右も左もわからない状態。
それでも「将来のために、まずは少しでも行動してみよう」という気持ちで、一歩を踏み出したのが始まりです。
最初は小さな金額からスタートし、少しずつ売買を繰り返していくうちに、利益が出る楽しさや、逆に失敗したときの悔しさも実感しました。
特に公務員という安定した職業だからこそ、「大きなリスクは避けたい」「コツコツ積み上げたい」と感じている方も多いはず。
私の体験や、実際にどうやって運用成績を伸ばしてきたのかも、この記事のなかでリアルにお伝えしていきます。
この記事では、公務員の立場から「株式投資で利益を出す方法」「運用成績の考え方・数字の見方」「私自身の売買履歴やリアルな体験談」まで、分かりやすく解説します。
初心者の方やこれから始めたい方にも役立つ内容にまとめていますので、安心して最後まで読み進めてみてください。
あなたもこの記事をきっかけに、株式投資で着実に資産を増やせる“きっかけ”をつかんでもらえたら嬉しいです。
公務員でも株式投資で利益を出せるのか?

「公務員は本当に株式投資で利益を出せるのか?」
これは、実際に多くの公務員やそのご家族が気になっているテーマです。
まず結論から言えば――公務員でも株式投資で利益を出すことは十分可能です。
ただし、「楽して簡単に儲かる」というものではありません。むしろ公務員という職業の特性上、「大きなリスクを取らずに着実に資産を増やしたい」と考える方が多いのも事実です。
最近では、NISAやiDeCoといった非課税制度の普及もあり、株式投資を選ぶ公務員も年々増加中です。
特に、公務員のイデコ加入率は、会社員に比べ増加率が高いです。
現在、公務員のイデコ加入者は714,570人です。
(2025年4月時点、データ元:「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況」)
公務員は約340万人なので(参考資料:国家公務員の数と種類)、加入率は約21%、だいたい5人に1人がイデコに加入していることになります。
たとえば「公務員 株式投資 利益 運用成績」などで検索してみても、
・毎月コツコツ積み立てて、長期的に資産を増やしている
・配当金を受け取りながら、老後資金をしっかり確保している
といった体験談や成功例が多く見られます。
一方で、公務員ならではの「副業規定」や「職場の目」が気になり、
・投資はしてみたいけど本当に大丈夫?
・バレたりしないの?
と不安を感じてなかなか一歩を踏み出せない人も多いのが現実です。
ここで一つ強調しておきたいのは――
株式投資は「資産運用」であって、一般的な副業には当たらないという点です。
公務員法でも、上場株式や投資信託への投資は副業規定の「営利企業等の従事制限」には該当しません。
つまり、「自己責任」で資産運用する範囲であれば、まったく問題なく取り組めます。
(もちろん、インサイダー取引や勤務時間中での取引はご法度です)
とはいえ、公務員にとっては「投資で失敗したら生活に影響が…」「元本割れが怖い」という不安もつきものです。
私自身も最初は同じような不安を抱えていましたが、少額から始めて経験を積むことで、少しずつ自分に合った投資スタイルが見えてきました。
例えば私は、はじめて購入した銘柄が思うように値上がりせず「このまま損したまま終わるのでは?」とドキドキしたこともあります。
けれども、焦らずに長期目線で我慢して保有し続けることで、トータルではしっかり利益を残しています。
株式投資で利益を出すためには、
・焦らず長期保有でコツコツ継続する
・リスクをしっかり管理する
・自分の投資目的を明確に持つ
この3つがとても大切です。
これから株式投資を始める方や、今まで利益が出なかった方も、正しい知識と方法を身につければ「公務員でも十分に利益を出すことはできる」というのが、私自身の実感です。
次の章からは、公務員の資産運用事情や「利益を出すための具体的なポイント」について、さらに詳しく見ていきます。
公務員の資産運用事情・実態(アンケート・データ)
公務員といえば「安定した職業」というイメージが強いですが、実際には多くの公務員が「資産運用」に関心を持っています。
特に近年は、物価上昇や将来の年金不安などから「給料+α」で資産を増やしたいと考える方が増えてきました。
ある金融機関の調査によると、30代~50代の現役公務員の約35%が、すでに投資信託や株式投資などの資産運用を行っているというデータもあります。
また、NISAやiDeCoの利用が広がったことで、これまで投資経験がなかった公務員も「少額からならやってみよう」と一歩を踏み出しやすい環境になっています。
周囲の公務員仲間に話を聞くと、
「最初は怖かったけど、iDeCoや積立NISAから始めてみたら、意外と簡単だった」
「同僚が資産運用をしていると聞いて、自分も興味を持った」
という声がたくさんあります。
さらに、昨今は公務員向けのマネーセミナーや、職員互助会での「FPによる資産形成講座」なども増えてきました。
こうしたセミナーでは、実際に投資をしている公務員の方が講師として体験談を語ったり、
「無理のない範囲での資産運用の始め方」や「リスクとの向き合い方」などが解説されており、
“昔はタブー視されがちだった投資”が、今や「自己防衛のための当たり前の選択肢」として受け入れられつつあります。
私も20代半ばくらいにFPによるセミナーに参加した記憶があり、「お金の勉強って大事だな」と思った経験があります。
実際、私の職場でも資産運用について話す機会が増え、
「投資信託でコツコツ増やしてるよ」
「iDeCo、節税にいいからぜひおすすめ」
「子どもの教育資金づくりにNISAを活用している」
といった会話が日常的になってきました。
また、独自のアンケートや口コミサイトを見ると、
「貯金だけでは増えないと気付いて投資を始めた」
「給与だけでは将来が不安だった」
「投資で生活が大きく変わったわけではないが、気持ちに余裕ができた」
といった意見も目立ちます。
公務員の場合、「身バレ」や「副業規定」に敏感な方も多いですが、上場株式や投資信託の“資産運用”は公務員法上まったく問題なし。
むしろ「正しい知識を持ったうえで、賢く資産運用する」のが“新しい常識”になりつつあります。
このように、今や多くの公務員が「将来への備え」として株式投資を活用している時代。
投資は決して特別な人だけのものではありません。
次の章では、そうした公務員が実際に株式投資で利益を出すためのポイントについて、具体的にお話しします。
公務員が株式投資で利益を出すためのポイント
公務員が株式投資で着実に利益を出すためには、他の職種と同じように「正しい知識」と「無理のない運用方針」が欠かせません。
ただ、公務員特有の事情や性格も踏まえると、次のようなポイントを意識することがとても重要です。
1.少額・分散から始める
最初から大きな金額を一度に投じるのはおすすめしません。
株式投資は「元本保証」がないため、最初はNISAやiDeCoの活用も含めて、少額からスタートするのが安全です。
また、1つの銘柄だけに集中せず、複数の株や投資信託を「分散投資」することでリスクも抑えられます。
たとえば、配当が安定している大型株や、業績の安定した企業を選ぶのも良い方法です。
2.長期目線での運用を心がける
株式投資の世界では「短期間で大きく儲ける」のはとても難しいものです。
むしろ、毎月コツコツ積み立てていく「長期投資」のほうが、結果的に安定して資産を増やす近道です。
これは公務員のような安定した職業だからこそ「大きなリスクを取らずに、じっくり資産を増やせる」大きなメリットでもあります。
3.感情に流されず、冷静な判断を徹底する
「株価が急落して不安になった」「SNSで話題の銘柄に飛びついて失敗した」――こうしたパターンは株式投資の失敗あるあるです。
公務員は本来、冷静な判断力や継続力を持っている方が多いので、その強みを活かして「一時的な上げ下げに一喜一憂せず、ルールを決めて淡々と投資を続ける」ことが大切です。
4.情報収集と自己学習を怠らない
株式投資は「知識が武器」になります。
基本的な経済ニュースや企業の決算情報、業界動向などを定期的にチェックしましょう。
最近は、YouTubeや証券会社の無料セミナー、株式投資本なども豊富です。
分からないことがあれば無理に投資せず、まずはじっくり学んでからスタートしましょう。
5.自分の投資目的と許容リスクを明確にする
「なぜ株式投資をするのか?」「どれくらいのリスクなら許容できるか?」を最初にしっかり決めておきましょう。
「子どもの教育資金を10年かけて増やしたい」「老後の生活資金を少しでも厚くしたい」「お金持ちになって公務員を早期リタイアしたい」など、明確なゴールがあると、途中で投資をやめたり感情的な売買をしてしまうリスクも減らせます。
私自身、最初は「損をしたらどうしよう…」と不安でしたが、
・長期投資を行う(一度買った株は売らない)
・売買を行いつつ、株式投資本をたくさん読み、知識を習得し続ける
・一時的な株価の変動で慌てて売らない
など、シンプルなルールを守ることで、着実に運用成績を伸ばすことができました。
株式投資の利益の仕組み|運用成績の考え方と計算方法
株式投資を始めたばかりの方にとって、「利益ってどうやって生まれるの?」「運用成績って何を基準に考えればいいの?」と疑問に思うことも多いはずです。
ここでは、株式投資の利益の基本的な仕組みや、運用成績(リターン)の考え方をやさしく解説します。
1. 株式投資で得られる2つの利益(値上がり益・配当金)
株式投資で得られる利益は、大きく分けて次の2つです。
(1)値上がり益(キャピタルゲイン)
これは、「買った株が値上がりし、売ったときに得られる差額の利益」です。
例えば、ある企業の株を1株1,000円で買って、後日1,500円になったタイミングで売れば、1株あたり500円の値上がり益を得られます。(NISA利用時)
(2)配当金(インカムゲイン)
企業が利益の一部を株主に分配するのが「配当金」です。
たとえば、1株あたり年50円の配当金が出る株を100株持っていれば、1年間で5,000円の配当収入になります。
配当金は、株を保有している限り定期的にもらえるため、「コツコツ利益を積み重ねたい」という公務員にも人気があります。
2. 運用成績(リターン)はどうやって測る?初心者向けにやさしく解説
投資の「運用成績」とは、どれだけ自分の資産が増えたか(または減ったか)を数字で表したものです。
一般的には、「元本(投資したお金)」に対して、1年間でどれくらい利益が出たかを「利回り(リターン)」という形で見ます。
【例】1年間の運用成績の計算方法
たとえば、年間で10万円を投資し、1年後に11万円になっていれば、利益は1万円。
この場合、利回り(リターン)は「1万円 ÷ 10万円 × 100 =10%」となります。
株式投資の場合、「含み益(まだ売っていないけど値上がりしている利益)」も計算に入れて運用成績を見ていきます。
3. 利益や運用成績が出るまでの期間・目安
「どれくらいで利益が出るの?」という疑問もよく聞きます。
株価は日々上下しますが、「すぐに大きな利益を狙う」よりも、「長期でじっくり増やす」スタンスが公務員には向いています。
実際、数年単位で資産を増やしている人も多いです。
【参考】
1年で数%~10%前後のリターンを目指すのが現実的な目標(投資信託の場合)
長期投資なら複利効果で「10年で資産が数倍~10倍」などになるケースも(個別株の場合)
私自身、最初は「1年間で数倍になればいいな」という淡い気持ちで始めましたが、現実を良く分かっていませんでした。
株の世界では1年で数十%上がればかなり素晴らしいことです。
運よく2倍3倍になる株もありますが、それは決して多くはありません。
短期間に大儲けしたい人には株式投資は向いていません。
元公務員FPのリアルな実践例・運用成績(体験談)
私が実際に株式投資を始めたのは、まだ県職員として働いていた頃でした。きっかけは、「お金持ちになって早く公務員をリタイアしたい」「お金持ちになって慈善家になりたい」「お金持ちになって家族と幸福な時間を過ごしたい」という素朴な思いでしたが、投資については全くの素人。最初は証券口座の開設にも戸惑い、ネットで情報を調べたり、株式投資の入門書を何冊も読みながら手探りでスタートしました。
最初に購入したのは、当時最も安く買える「ランド」とテレビCMでなじみの「メガネスーパー」でした。「まずは失敗しても痛手の少ない金額で経験を積もう」と考えていました。ランドは数か月間株価があまり動かず、「本当にこれで利益が出るのかな?」と半信半疑だったのを今でも覚えています。ただ、メガネスーパーは買った直後に急騰し、短期間で数十%の利益が出てビギナーズラックも経験しました。
その後、もう少し短期間でお金持ちになりたいという気持ちが芽生え、公務員退職後に半年間程度デイトレードに専念しました。しかし、結果は数十万円のマイナス。メンタル的にもかなり厳しく私にはデイトレードは向いていないと判断し、撤退しました。
デイトレード後、改めて株式投資に関する本を読み漁り、「長期投資」の魅力にハマり、それからは「日本株への集中・長期投資」を行うことにしました。その際、NISAが始めった時期と重なっていたので、基本株を購入する際はNISAを利用していました。NISAは非課税なので、配当や値上がり益も100%入ってくるので大きなメリットでした。
2019年からの具体的な売買履歴でいうと、ズバリ
- 「ネットマーケティング」(上場廃止)
- 「ライザップ」
- 「鎌倉新書」
- 「Mimaki」
に長期集中投資を行っています。
「原則買ったら売らない」を方針に売買してきました。ただし、例外的に売買したものもあります。
「ネットマーケティング」は、2021年7月に413円で購入しました。約1年後の2022年8月にベインキャピタルによる株式公開買い付け(TOB)が行われ、結局約898円で売却し、見事2倍株となりました。
「ライザップ」は、2019年あたりから長い期間買い増しを続けていて(135円~230円あたりで購入)、2倍になったところである程度売ったこともありますし、現金が必要になったときに時々売ったこともあります。一次含み益が3倍を超えましたが、そこから下がって今は低迷しています。
「鎌倉新書」は、2022年8月9月に600円代で購入し、途中売ったりもしたことがありますが、長期保有を続けています。
「Mimaki」は、820円程度で購入し、一度も売らず持ち続けています。現在は2,135円になっています(2025年7月21日現在)。
プラスの時期、マイナスの時期両方を長く経験してきていますが、「長期保有」「下がっても思い描いたストーリーが崩れなければ売らない」というルールを守ることで、トータルでは資産を着実に増やすことができきています。
株式投資を通して一番大切だと感じたのは、「マイナスのときや暴落時に株式市場から退場せず、我慢強く長期保有を続けること」。
SNSやネット掲示板では「短期間で大きく稼いだ」という声もよく見かけますが、私自身は「うまくいって数年で数倍」くらいの気持ちで運用するのが性に合っていました。
2024年に結婚して家族ができてからは、妻の理解も得ながら個別株投資を継続しつつ、教育資金や老後のために新たにNISAを活用し「投資信託」にも投資を開始しました。コツコツと毎月積み立てていて、個別株ほどのインパクトはないですが、1年で11%程度の利回りできていて(2025年7月時点)、やり始めてよかったなと感じています。
これからも実際の売買履歴や実感をもとに、より良い資産運用を目指していきたいと思います。
初心者公務員におすすめの投資スタイル

株式投資にはさまざまなスタイルがありますが、特に初心者の公務員の方におすすめしたいのは、「長期・分散・積立」の3つを組み合わせた堅実な投資方法です。
ここでは、安心して始められる投資スタイルを、わかりやすく解説します。
1. 長期投資
まずおすすめしたいのは「長期投資」。
株式投資は、短期間で大きな利益を狙うよりも、5年・10年とじっくり時間をかけて資産を増やす方が、リスクも少なく、結果的に利益が出やすいです。
株価は短期的には上がったり下がったりしますが、長い目で見れば経済成長や企業の業績向上にともない、資産は増えやすくなります。
特に公務員は安定収入があるので、生活資金に余裕がある分、焦らずに長期でじっくり運用できるという強みがあります。
私自身も、毎月一定額を積み立てて長期で持ち続けることで、含み損が出ても慌てず「いずれ上がるだろう」とどっしり構えられるようになりました。
2. 分散投資
「分散投資」は投資の大原則です。
一つの銘柄や業界だけに集中してしまうと、その会社や業界にトラブルがあった時、大きな損失を受けるリスクがあります。
国内外の複数企業の株や、ETF(上場投資信託)、投資信託を組み合わせて投資することで、リスクを大きく減らすことができます。
例えば、業種や規模の異なる複数の企業に分散して投資する、または「TOPIX連動型ETF」など幅広い企業に投資できる商品を利用するのも有効です。
分散することで、どこか一社が大きく下落しても他でカバーでき、安定した運用成績につながります。
私も「ライザップ(ジム)」「ネットマーケティング(婚活アプリ)」「鎌倉新書(終活)」「ミマキ(プリンタ)」と全く異なる業種に投資していました。
ただ、分散し過ぎは私は良くないと思います。初心者には管理しきれないので、中級者以上になるまでは「5~10銘柄」or「投資信託」がベストと考えます。
3. 積立投資(ドルコスト平均法)
初心者の方には「積立投資」も非常におすすめです。
毎月決まった金額をコツコツ投資することで、高値掴みのリスクを減らし、平均購入価格を抑える効果が期待できます。
この手法は「ドルコスト平均法」とも呼ばれ、価格変動リスクの緩和に効果的です。
私自身も、NISAやiDeCoなどの非課税口座を活用して毎月積み立てを続けていることで、株価の上げ下げに振り回されることなく、着実に資産を増やすことができています。
4. 公務員の生活に無理のない範囲で
投資資金は「余裕資金(使う予定のないお金)」から出すことが大切です。
生活費や教育資金、急な出費に必要なお金には手を付けず、月1万円や2万円など“無理のない範囲”で始めることを心掛けてください。
失敗しないための注意点とNG行動

株式投資は資産を増やす大きなチャンスである一方、間違った行動や知識不足が原因で損をしてしまうこともあります。
特に投資初心者のうちは、注意したいポイントと避けるべきNG行動をしっかり押さえておくことが大切です。
1. 一攫千金を狙わない
「短期間で大きく儲けたい!」という気持ちは誰にでもあります。
しかし、株式投資は“すぐに大儲けできる”ものではありません。
むしろ「大きな利益=大きなリスク」であり、過度な期待や一攫千金狙いは思わぬ損失につながりがちです。
特にSNSやネットの体験談で「◯ヶ月で資産が2倍に!」といった成功談を見ると焦ってしまうかもしれませんが、多くは一時的なもので、再現性が高い方法ではありません。
“着実に、地道に、コツコツ増やす”というスタンスが長続きする秘訣です。
2. 余剰資金だけで投資する
株式投資に使うお金は、必ず「なくなっても生活に困らないお金(余剰資金)」だけにしましょう。
生活費や急な出費があるときに無理をして投資を続けてしまうと、いざという時に株を安値で売らざるを得なくなり、損をする可能性が高くなります。
「将来必要なお金」と「投資に回すお金」をしっかり分けることが、心に余裕を持った投資につながります。
3. 感情的な売買をしない
株価は毎日のように上がったり下がったりします。
大きく下がったときに怖くなって売ってしまったり、逆に急騰したときに飛びついてしまうと、結果的に損をするパターンも少なくありません。
私も最初の頃、株価が下がるたびに不安になり「今のうちに売った方がいいのでは…」と悩んだことが何度もあります。
でも、「最初に決めたルール(積立や長期保有)」を守ることで、最終的には株価が回復してプラスになったことも何度も経験しました。
4. 十分な情報収集をせずに投資しない
「なんとなく有名だから」「友達が儲かったと言っていたから」といった理由だけで投資先を決めるのは危険です。
最低限、その企業の業績や業界のニュース、今後の成長性について自分でも確認してから投資判断をしましょう。
また、公務員の場合は「副業規定」など法律面も気になるところですが、通常の株式投資(上場株や投資信託)は副業にはあたりません。
ですが念のため、自分の所属する自治体や組織の規定も確認しておくと安心です。
5. 流行りの情報や“噂話”に振り回されない
一時的な流行やSNS上の“熱狂”に踊らされてしまうと、冷静な判断ができなくなります。
投資の世界は、冷静さと「自分のペースを守ること」が何より大切です。
よくある質問Q&A|公務員の株式投資・利益・運用成績

ここでは、公務員の方からよく寄せられる「株式投資」「利益」「運用成績」に関する疑問や不安について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。
Q1.どれくらいの利益が出れば“合格点”と言えるの?
A.
株式投資の“合格点”は人それぞれですが、一般的には年利5~10%のリターンを目標にすると、堅実で現実的です。
例えば100万円を運用して、年間5万円~10万円ほど増えれば十分「成功」といえます。
短期間で資産を2倍にしたい…といった目標はリスクも高く、失敗の原因になりがちです。
私自身も「1年で数倍にしたい」と最初のころは高い目標設定をしていましたが、プラスどころかマイナスになることも多くあり、メンタルがきつかったです。
Q2.利益が出た場合、税金や確定申告は必要?
A.
株式投資の利益には、20.315%の税金(所得税・住民税含む)がかかります。
ただし、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、証券会社が自動で税金を引いてくれるので確定申告は原則不要です。
一方、NISA口座を利用すれば、売買益も配当金も非課税。
「節税しながら資産を増やしたい」という公務員の方には、NISAやiDeCoの活用がおすすめです。
Q3.投資していることが職場や同僚にバレることはある?
A.
基本的に「株式投資をしていること」が職場にバレる心配はありません。証券口座の情報は本人以外には公開されませんし、税金も自動で処理されるためです。
上場株式・投資信託への投資は副業には該当しません。
気になる場合は、自分の所属する自治体の規定を確認するか、人事担当に「資産運用はOKか」と相談してみるのも良いでしょう。
Q4.どんな銘柄を選ぶと安定した利益が出せる?
A.
公務員の場合、「高配当・業績安定・分散性」のある銘柄や「投資信託」が特におすすめです。
例えば、生活に欠かせないインフラ系や大型の優良企業は、長期的にも安定した運用が期待できます。
Q5.損失が出た場合、どうすればいい?
A.
損失が出た場合は、「慌てて売らずに、なぜ損失が出たのかを振り返る」ことが大切です。
一時的な下落で感情的にならず、「長期で考えて持ち続ける」「分散して他の銘柄でカバーする」など、落ち着いて行動しましょう。
また、年間で損失が出ても翌年以降の利益と相殺できる「損益通算」や「繰越控除」などの制度もあるので、税金面でも活用できます。
Q6.副業禁止規定に引っかからない?
A.
通常の株式投資や投資信託は「資産運用」であり、公務員の副業規定には該当しません。
ただし、未上場株や個人での企業経営・投資マンション運用などは“営利活動”とみなされるケースもあるので要注意。
「上場株式の売買」や「投資信託の積立」であれば、まったく問題なく続けられます。
公務員が株式投資で利益を出すメリット・デメリット
株式投資は「資産運用の王道」と言われますが、公務員の立場ならではのメリットと、気を付けておきたいデメリット・注意点もあります。
両面をしっかり理解し、自分に合ったスタイルで取り組むことが大切です。
メリットまとめ
1.将来の資産形成ができる
給料やボーナスだけでは将来が不安…という声も多いですが、株式投資なら長期的に資産を増やせる可能性があります。老後資金、教育資金、マイホーム資金など、さまざまな目的に合わせて計画的にお金を増やせます。
2.時間を味方に「複利効果」が働く
長期投資では「複利効果」が期待できます。たとえば、毎年5%ずつ増えれば10年後には1.6倍、20年後には2.6倍に。コツコツ積み立てて増やすことで、将来の安心につながります。
3.非課税制度を活用できる
NISAやiDeCoなど、公務員も利用できる非課税口座があります。これらを使えば、売買益や配当金が非課税になり、より効率よく資産を増やせます。
4.本業に影響が出にくい
株式投資は“副業”ではなく「資産運用」なので、職場の規定に抵触せずに続けられます。仕事をしながら、空き時間や週末に資産形成ができるのも魅力です。
5.経済や社会の勉強になる
企業の業績や経済ニュースに自然と関心が向き、金融リテラシーもアップ。自分のお金を守る力がつくのも大きなメリットです。
デメリット・注意点まとめ
1.元本割れのリスクがある
株式投資は預金と違い、価格が下落すれば元本割れ(投資したお金が減る)リスクがあります。リーマンショックやコロナショックのような経済危機時には一時的に大きく下がることも。
2.感情に左右されやすい
値動きがあるたびに「不安」「焦り」が生まれ、冷静な判断ができなくなることもあります。特に投資初心者のうちは、感情的な売買をしないように注意が必要です。
3.過度なリスクテイクに注意
「もっと利益を増やしたい」と思うあまり、ハイリスクな銘柄や投機的な取引に手を出すと、思わぬ損失を被ることがあります。自分のリスク許容度を超えた運用は避けましょう。
4.知識や情報収集が不可欠
投資は自己責任。最低限の知識や情報収集ができないと、失敗のリスクが高まります。
無理に流行や噂話に流されず、「自分なりの判断基準」を持つことが大切です。
まとめ|公務員が株式投資で安定して利益を出すために
公務員として働きながら株式投資をすることは、今や特別なことではなく、「将来に備えるための賢い選択肢」の一つとなっています。
今回の記事を通して、「公務員でも株式投資でしっかり利益を出せるのか?」「どんな運用成績を目指せばいいのか?」「どうすれば安心して始められるのか?」といった疑問が少しでも解消されていれば嬉しいです。
まず大前提として、公務員の株式投資は「副業」ではなく、法的にも認められた“資産運用”です。
副業禁止規定に引っかかる心配もなく、NISAやiDeCoなどの非課税制度を活用しながら、ご自身のペースでコツコツと資産を増やすことができます。
株式投資の利益は、「値上がり益(キャピタルゲイン)」と「配当金(インカムゲイン)」の2つ。
短期間で大きなリターンを狙うのではなく、年利5~10%の堅実な目標を持って「長期・分散・積立」の王道スタイルを実践することが、着実な資産形成への近道です。
もちろん、株式投資にはリスクもあります。
「元本割れ」や「感情的な売買による失敗」など、注意点も多いですが、
・余裕資金で始める
・しっかり情報収集する
・一時的な値動きに左右されずルールを守る
この3つを守れば、初心者でも安定して利益を積み重ねることは十分可能です。
私自身も、最初は小さな一歩から始めて、失敗や成功を繰り返しながら、
「投資の楽しさ」や「資産が増えていく実感」を味わってきました。
特に公務員は安定した収入基盤がある分、焦らずにじっくりと資産運用に取り組める環境があります。
「給料だけでは将来が不安」「少しでも家計の余裕を増やしたい」と考えている方には、株式投資はぜひチャレンジしてほしい資産運用法です。
最後に、「無理のない範囲で、コツコツと続ける」――
これこそが、公務員の資産運用成功の最大の秘訣です。
この記事が、あなたの“はじめの一歩”や“継続の勇気”になれば幸いです。
【関連記事】
【2025年最新】公務員向けおすすめ証券会社4選を元公務員FPが比較!実体験で語る選び方と注意点