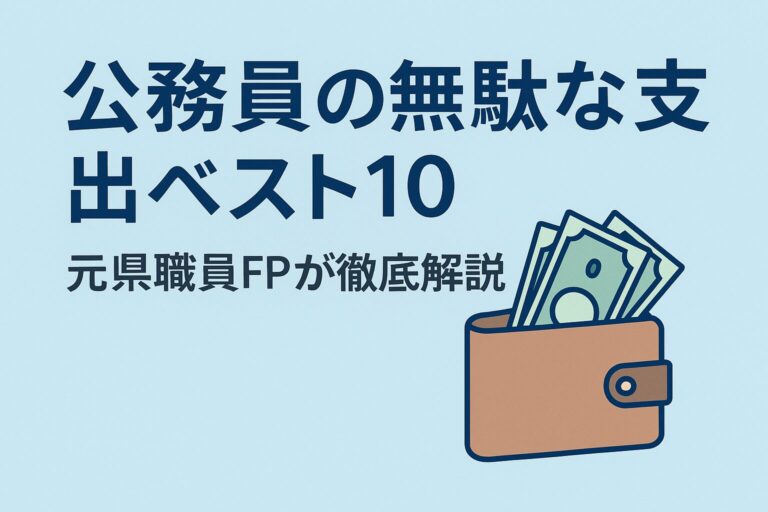「公務員は収入が安定しているから大丈夫だよね」──そう言われること、ありませんか?
私自身、県職員として働いていたころ、同じことを何度も言われました。
でも実際は、安定しているがゆえに“気づかない無駄な支出”が積み重なっているケースを山ほど見てきました。
毎月黒字のはずなのに、なぜか貯金が増えない。
ボーナスが入っても一瞬で消える。
気づけば生活費が膨らみ、将来の資産形成に回せるお金が残らない──そんな相談を、公務員同僚・後輩から何度も受けてきました。
そしてこれは、公務員家庭に共通する“構造的な問題”でもあります。
- 互助会費や組合費
- 飲み会文化
- 資格取得費用
- 住居費
- 保険 など
こういった「公務員ならではの出費」が、想像以上に家計を圧迫しています。
しかし、心配しなくても大丈夫です。
この記事では、元県職員の私(伯爵)が、公務員生活9年の経験+FP視点から、公務員が気づきにくい“無駄な支出ベスト5” を分かりやすく整理し、今日から改善できる実践的な節約ポイントをお伝えします。
この記事を読むと、
✅ 公務員特有の無駄な支出がどこに潜んでいるか
✅ どの支出を優先して見直すべきか
✅ 今すぐ始められる具体的な節約方法
が「体系的に」理解できます。
✅【第1章】公務員が“無駄な支出”に気付きにくい理由
公務員が「無駄な支出」に気づきにくいのは、決してあなたの性格や努力不足ではありません。
これは“構造的にそうなりやすい仕組み”が公務員という職業の中に存在しているからです。
まずはこの「仕組み」を理解すると、節約の方向性が一気に明確になります。
✅ 安定収入ゆえの「油断の積み重ね」
公務員の給与は、毎月ほぼ一定です。
民間のような営業成績による変動や、急な配置転換で給与が大幅に変動することは少ない。
その「安定」が安心感を生みますが、一方で家計に対する危機感が低くなりやすいという欠点があります。
特に以下のような心理が働きます:
「毎月安定して入ってくるから、多少の支出はなんとかなる」
「来月のボーナスで調整できる」
「昇給があるから、今は大丈夫」
でも現実は──
安定ゆえに“気づかない小さな支出”が積み上がり、気づいたら毎月の支出が膨らんでいる。
これは多くの公務員が陥る“職業特有の油断”です。
✅ 自治体文化・互助会・組織特性による固定負担
公務員には、公務員ならではの“文化経費”があります。
互助会費
組合費
職場での差し入れ文化
歓送迎会
異動時の花束代
私自身も、県庁時代は「毎月の数千円〜1万円」が当然のように引かれていました。
誰も疑問を持たないため、「それが無駄なのか?」という考えにすらたどり着けないのが実態です。
互助会や組合はもちろん必要な役割があります。
しかし、実際に支払っている額が家計にどれくらい影響しているのか把握している人は少ない。
“必要だから払っている”のではなく、“習慣として払っている” 感覚になりがちです。
✅ 部署による残業の差
公務員の仕事は部署ごとに全く違う。
忙しい部署 → 激務・そのかわり残業代が出て収入はアップ
定時あがりできる部署 → 残業がないので収入は元々の手取りのみ
部署ごとの働き方の違いがそのまま「家計の収入・支出構造」に直結します。
✅「無駄」が見えない理由を理解すると節約の方向性が明確になる
無駄な支出は、“個人の失敗”ではなく“職業特性の延長”で起きている。
だからこそ、罪悪感を持つ必要はありません。
むしろ、仕組みを理解したうえで、
「どこから削ると効果が大きいのか?」
「どの支出は優先的に見直すべきか?」
を見極めることが大事です。
次の章では、元県職員である私が実際に見てきた「公務員の無駄な支出ベスト10」を、現場感覚も交えて具体的に紹介します。
✅【第2章】公務員の無駄な支出ベスト5(一覧+深掘り解説)
ここからは、元県職員として9年間働いてきた私が見てきた、「公務員が気づきにくい無駄な支出」を5個に絞って、具体的に解説します。
特に「なぜ無駄になるのか」「どう改善すべきか」に焦点を当てています。
あなたの生活に当てはまるところが必ずあるはずです。
✅① 飲み会
公務員の飲み会文化は、部署によってかなり強烈です。
- 上司との付き合いの飲み会
- 先輩・同僚・後輩との飲み会
- サークルの飲み会
課や係などの歓送迎会
退職者見送り会
- 新年会、暑気払い、忘年会など季節的な飲み会
- 仕事の慰労会
- 関係者との親睦会
- 職員宿舎での飲み会
✅節約ポイント
毎回参加する必要はない
新人時代を過ぎたら「家庭の都合」を理由に断る
職場文化でも“強制参加”ではない
参加するなら1次会だけにする
✅② 互助会・組合費の惰性支払い
公務員の給与明細には、毎月のように「互助会費」「組合費」が入っています。
互助会:福利厚生を名目にした組織費
組合費:労働環境改善のための組織費
どちらも否定しませんが、利用頻度に対して金額が高くつくケースが多い。
ほとんど使っていないのに月1,500〜3,000円払っている人が多数です。
✅節約ポイント
退会可否を必ず確認する(自治体によって可能)
互助会の“使っていないサービス”を棚卸しする
組合費は自分の価値観と役割に応じて見直す
✅③ 資格試験費用の無計画支出
- 資格試験の受験料
書籍の購入
- 通信教育の受講料
勉強意欲が悪いわけではないが、目的と効果を整理しないまま受験・購入してしまうケース、いわゆる「資格コレクター」になってしまう公務員が多いです。
公務員になる人は真面目で向上心が高いので、つい資格取得に走る人も多いですが、いったん立ち止まってほしいと思います。
✅節約ポイント
「本当に仕事に必要か?」「その資格を取れば間違いなく仕事・生活にプラスになるか?」を軸に判断
中古書籍を活用
- 一番安い通信講座を探す
✅④ 医療保険・生命保険
公務員は人生や生活に安定を求める人が多いです。
そのため、医療保険や生命保険にお金をかけすぎている人が多数見受けられます。
保険会社の営業さんもよく職場に回ってくるので、余計によく考えずに契約してしまっている人が多いのが実情です。
そもそも公務員には共済があったり、高額医療費制度など手厚い福利厚生があったりで、そこまで手厚い医療保険に入る必要もないと私は感じています。
もちろん、その人その人で考え方や家族構成が違うので一概にはいえませんが、ぜひ加入する際は補償内容をじっくり確認してもらいたいと思います。
✅節約ポイント
- ネット保険が安い
共済+高額療養費で十分なケースが多い
医療保険は「最低限」で可
- 医療保険・生命保険に関する節約術系の本を一冊読む
- 医療保険や生命保険に掛けるお金を貯金に回したほうがコスパは良いことが多い
✅⑤ アパート代
激安職員宿舎があるのに見栄をはって高い民間のアパートに住むのは論外
職員宿舎は単身用:月8,000円程度、世帯用:20,000円程度(私の県では)
✅節約ポイント
職員宿舎に引越し
民間のアパートで暮らすにしても安い物件で十分(目安:私の肌感覚的には手取りの20%未満にしておいたほうがいい)
公務員の強みの1つが「宿舎の安さ」。
家賃相場の半額〜4分の1になることもある。
家賃4万円の民間 → 宿舎1万円未満
家賃7万円の民間 → 宿舎3万円未満
家賃は固定費の王様。
ここを押さえると一気に節約が進みます。
✅【第3章】元県職員の私が実際に経験した“隠れコスト”
ここからは、本にもネットの記事にも載らない“現場のリアルコスト”について、私自身の経験を交えて具体的にお話しします。
一般論ではなく「実際に9年間公務員として働いてきた人間が肌で感じた負担」。
この「一次情報」こそ、あなたの節約判断に大きなヒントを与えてくれるはずです。
✅ 昼食代だけで月2万円以上を浪費
正直に言います。
私が県庁時代にもっとも無意識で垂れ流していたのは「昼食代」と「飲み物代」でした。
当時の私のルーティンはこんな感じでした。
朝:コンビニで缶コーヒー(150円)
昼:職場近くのラーメン屋やカレー屋など(700〜1000円)
午後:自販機でエナジードリンクやコーヒー(150〜200円)
- 夕方:残業前に自販機でコーヒーやお茶(150円)
これだけで 1日1,000円近く。
1,000円 × 20営業日 = 月2万円
1年で24万円です。
でも当時の私は、数字として計算すらしていませんでした。
なぜなら──
「毎月給料が一定で、残業代もあるから大丈夫だろう」
という油断があったからです。
節約の第一歩は「無意識の支出に気付くこと」です。
私はこの無意識を見直し、朝水筒にコーヒーをドリップ、お昼は職員食堂で日替わり定食にしただけで、昼食代を月10,000円程度まで抑えられました。
✅ 通勤費が跳ね上がった経験
私が県庁にいたころ、県庁に職員駐車場がなかったので、毎日車で通勤したときはコインパーキングに停めていました。
1日停めて800円というところを見つけて愛用していましたが、それでも通勤手当に駐車場代は含まれないので、完全に自己負担でした。
また、朝はバスで通勤したとき、夜の残業が遅くなり終バスに乗り損ねるとタクシーで宿舎まで帰る生活でした。
タクシー代は1回2,500円程度。
もちろん手当は支給されないので、こちらも自己負担です。
心も財布も寂しい思いをしていました。
多忙な時期で駐車場やタクシーを多用した月は通勤費だけで2万円近くお金が飛んでいました。
✅ 互助会・組合費の「辞めづらさ」の実態
公務員を経験した人なら分かるはず。
互助会や組合費は、辞めようと思っても「しれっと流される」空気があります。
私も新人時代は
「とりあえず加入するもの」
という雰囲気の中で、何も疑わずに加入していました。
月1,000〜2,000円ほどの支出ですが、年間1万円〜2万円。
退職するまでに累計10万円以上を払っている計算になります。
しかも、利用頻度はほぼゼロ。
「互助会費がどこに使われているか分からない」
と感じていた同僚も多かったです。
節約の本質は、“惰性の支出”を断ち切ることにあります。
加入・継続は悪ではありません。しかし…
どのくらい使っているか?
本当に役立っているか?
金額と価値が釣り合っているか?
を定期的に見直すことが必要です。
✅ “隠れコスト”を知るだけで節約の方向性が変わる
私が公務員時代に気づいたのは、節約は「大きなガマン」ではなく「無意識を可視化する作業」だということ。
- 飲み代
小さな飲み物代
昼食代
互助会費・組合費
通勤費
必要以上の保険
- 家賃
これらは、見直せば節約効果が非常に大きい「構造的ムダ」です。
この章の経験談は、すべて今でも私の節約・家計管理の軸になっています。
あなたの生活にも同じ部分が必ずあります。
✅【第4章】公務員家庭が貯金を増やすための行動ステップ
ここまでで、公務員の無駄な支出がどこに潜んでいるのか、そしてどれを優先的に見直すべきかが整理できてきたはずです。
ここではそれを「行動につながるステップ」に落とし込みます。
3つのポイントを押さえるだけで、公務員家庭は無理なく貯金体質へ変わります。
✅① 最初に「支出の棚卸し」から始める(現状把握がすべての出発点)
節約を始めるとき、多くの人がいきなり「電気代を減らそう」とか「食費を抑えよう」としがちです。
しかし、これは遠回り。
まずやるべきは“棚卸し”=現状の支出を見える化することです。
✅棚卸しの手順
通帳(クレジットカードのオンライン明細含む)を3ヶ月遡って見る
紙の家計簿や家計簿アプリ(マネーフォワード/家計簿Zaimなど)で記録
「自動引き落とし」をすべてリストにする
重要なのは、“無意識で払っている固定費”がどれかを知ること。
3ヶ月の明細を見ると、必ず以下が出てきます:
互助会費
組合費
キャリアのスマホ代
サブスク
保険料
自動車関連
食費・飲み物代
これを一度 「数字として自分の目で確認する」ことが、節約の9割です。
公務員は仕事が忙しいほど、この確認作業が後回しになりがち。
だからこそ“見える化”が重要になります。
✅② 「投資をする前に固定費を削る」が鉄則(資産形成の最短ルート)
公務員は安定収入のため、「とりあえず投資から始めよう」と思ってしまう人が多いです。
しかし実は、投資より先に固定費削減をするほうが資産形成スピードは爆速になります。
✅理由
固定費削減はリスクゼロ
一度削れば“永続的に効果が続く”
浮いたお金をそのままNISA・iDeCoに回せる
投資の元本が増える → 複利効果UP
例えば:
通信費で月5,000円削減
保険見直しで月5,000円削減
家賃で月30,000円削減
合計 月40,000円の節約=年間480,000円の投資元本 が増える。
これを10年間積み立てると、積立額が480万円となり、評価額は617万円と100万円以上の差が出ます。(想定利回り5%と仮定した場合)
✅まずやるべき順番
- 家計簿をつけ支出額の把握(3ヵ月程度)
- 宿舎・安い家賃のアパートに引越し
通信費を格安SIMに
医療保険・生命保険・自動車保険の見直し(最小限の補償・ネット保険への切り替え)
✅③ 共働き公務員の家計分担ルール(ここが崩れると節約が続かない)
公務員は共働き家庭が多く、それ自体は家計的には大きなメリットです。
しかし、ここで支出管理が曖昧になる家庭が多い。
✅典型的な失敗
各自の給与が安定 → どちらも家計管理を“相手任せ”
生活費が不透明
お互いの口座に支出が分散
どれだけ貯金できているのか見えない
結果的に、“二人で働いているのに貯金ゼロ”という状態になる。
✅改善ポイント
- 固定費(通信費・保険)は2人まとめて見直す
食費・日用品はルール化(例:40,000円/月など)
夫婦で月1回“家計ミーティング(2人で一緒に家計簿をつける)”を実施
夫婦で数字を共有すると、節約スピードは驚くほど速くなる。
✅④ 少額からNISA・iDeCoへ移行する流れ(節約→投資の最短ライン)
節約で生まれた余剰資金は、確実に未来の資産へ変換することが重要。
✅おすすめの順番
- 家計の見える化
固定費削減
余剰資金の確定
NISAに月1〜2万円
iDeCoに月1~2万円
✅【第5章】FAQ(公務員の“無駄な支出”と節約に関するよくある質問)
節約を始めると、必ず湧いてくる疑問や不安があります。
ここでは、私が県庁職員時代に同僚から実際に何度も相談された質問を中心に、根拠付きで分かりやすく回答します。
✅ Q:公務員は副業禁止だけど、投資はしてもいいの?
結論:
株式投資・投資信託・NISA・iDeCoは“副業ではなく資産運用”なので問題ありません。
国家公務員・地方公務員ともに「営利企業に従事すること」「事業を起こすこと」が制限対象ですが、投資は事業ではなく“資産形成”扱いです。
ただし注意点は2つ:
企業から報酬を受け取る形の投資(講師・顧問・広告など)はNG
インサイダー取引は絶対にNG
👉日常のNISA・iDeCo・投資信託の積立は全く問題ありません。
✅ Q:互助会費って本当に辞められる?辞めたら怒られる?
自治体によりますが、退会可能なケースが多いです。
ただし「職場文化」として“辞めづらい雰囲気”があるのが実態。
元県庁職員の私が言えるのは、
退会しても仕事に影響はない
本当に使っていなければ退会して良い
退会は「書面一枚」でできる自治体もある
実際に私の同期は数名退会していましたが、全く問題ありませんでした。
なんなら労働組合も退会した上司も複数人いました。
ただし、退会前にサービス内容を再確認しましょう。
✅ Q:飲み会を断り続けても大丈夫?職場の空気が心配です…
大丈夫です。
しっかり配慮すれば問題ありません。
飲み会は「任意参加」です。
参加しない=協調性がない、という時代ではありません。
実際、私の県庁でも、若い世代は飲み会参加率が徐々に低下していました。
✅断るときのコツ
「家庭の都合」を理由にする
「一次会だけ」参加する
押し付け文化があった部署もありましたが、最終的には“普段の仕事の姿勢”が評価されます。
✅ Q:残業代が減って家計が苦しい。どうすればいい?
残業代は「安定収入の上乗せ」なので、もともとそれに依存しすぎると家計が不安定になります。
✅すぐできる3ステップ
1️⃣ まず固定費を削減(家・通信費・保険・車)
2️⃣ 残業代が出ない生活前提で家計を設計
3️⃣ 浮いたお金をNISAなどの“積立投資”に回す
残業が減る=悪ではありません。
むしろ健康的な働き方のチャンス。
家計を“安定優先”に再設計すれば問題ありません。
✅ Q:節約してもストレスがたまります。継続のコツは?
節約は「我慢」ではなく「仕組み」。
継続のコツは次の通りです。
節約対象を“固定費だけ”に絞る
毎日の節約はしない
効果が大きいものから順に削る
家計簿は“ざっくり”でOK
夫婦は数値を共有
無理をしない・削る場所を間違えない。
これが節約の基本です。
✅【まとめ:公務員の無駄な支出は“仕組み”に気づけば確実に減らせる】
公務員の家計は、一見「安定しているように見えて」、実は見えないところで無駄な支出が積み重なっています。
飲み会文化、互助会・労働組合費、昼食・飲み物代、住居費用、保険……。
こうした“公務員特有の支出構造”は、放置すれば毎月1〜2万円、年間10〜20万円規模でお金が消えていきます。
しかし、この記事で紹介したステップを実践すれば、公務員家庭の家計は確実によくなります。
✅支出の棚卸し
✅固定費の削減
✅夫婦(または単身)の家計共有
✅NISAなどの積立投資への移行
✅残業代が減っても貯金が増える仕組みづくり
大事なのは「我慢」ではなく「仕組み」。
節約も投資も、あなたの人生を豊かにするツールです。
無駄を減らすこと=ストレスを増やすことではありません。
むしろ、気づいてしまえば、驚くほど簡単に改善できます。
最後にひとこと。
無駄な支出を減らすことは、自分の人生に時間とお金の余裕を取り戻すことです。
今日からできることをひとつだけ始めてみましょう。
それが未来の安心につながります。
✅【関連記事リンク】
以下の記事も合わせて読むと、節約と投資が“線でつながり”、理解が深まります👇
- 公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】
- 公務員の株式投資と家計管理!失敗しない両立のコツを元公務員FPが解説
- 公務員の自動車保険はネットで安く!元公務員FPの失敗しない選び方と保険比較
- 【2025年最新】公務員のiDeCo完全ガイド|初心者向け始め方・メリット・デメリット・注意点を元公務員FPが解説
【注意喚起・免責】
互助会費や組合費の退会・変更については、自治体・職場ごとに規定が異なるため、最終判断は所属先の総務担当へ確認してください。
投資は元本保証ではありません。ただし、本記事で記載しているNISA・iDeCoの制度部分は公式情報(金融庁)に基づいています。