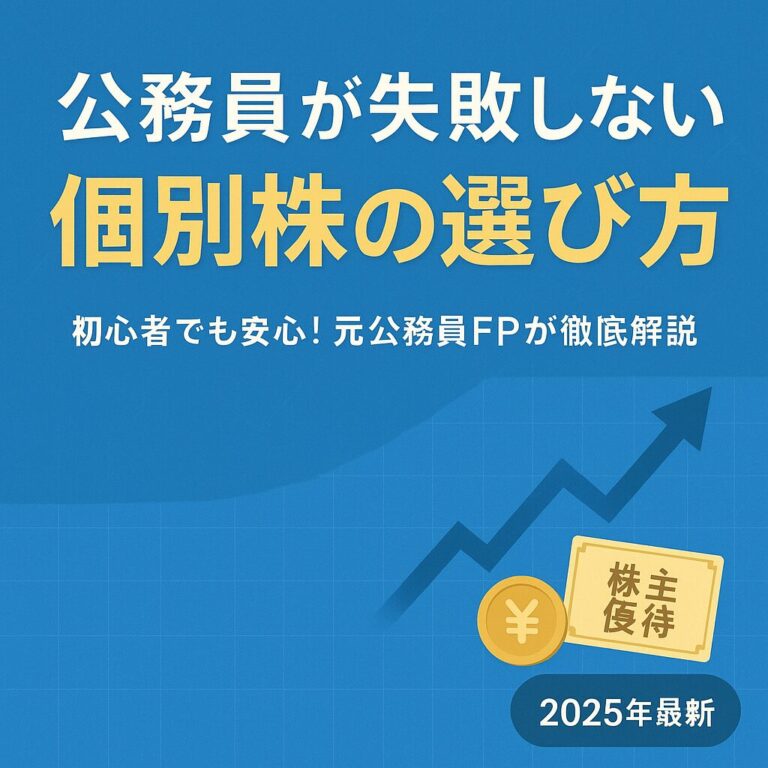「公務員は安定しているから資産運用なんて必要ない」と思っていませんか?
しかし、現代は将来の年金や物価上昇、予測不能なリスクがつきものの時代。
公務員であっても“自分でお金を増やす力”が欠かせなくなっています。
特に、「個別株投資」は、NISAやiDeCoなど国の制度拡充も追い風となり、多くの現役公務員やそのご家族から注目されるようになりました。
でも実際は、
「どんな銘柄を選んだらいい?」
「副業規制やインサイダーの心配は?」
「初心者でも失敗しない選び方が知りたい!」
こんな不安や疑問を抱えている方がほとんどです。
私自身も、元県職員(公務員)として働きながら独学で個別株投資を始めました。
最初は「何を基準に選べばいいのか」まったくわからず、失敗と反省の連続でした。
でも経験を積むうちに、公務員ならではの“守り”と“攻め”のバランスが大事だと痛感するように——。
このページでは、
公務員のルールや注意点
初心者でもわかる銘柄の選び方
実践ステップとリアルな体験談
まで、まるごとわかりやすく解説します。
“安心して個別株投資に踏み出したい”現役公務員・ご家族の方のための完全ガイドです。
この1記事で、あなたも「納得できる投資の一歩」を踏み出せます!
なぜ今、公務員にも株式投資・個別株が注目されるのか
公務員の資産運用事情と時代背景
近年、公務員の間でも「将来に備えてお金を増やしたい」という意識が強まっています。その理由は大きく分けて3つあります。
年金や退職金の不安
少子高齢化の影響で、「将来本当に十分な年金がもらえるのか?」と心配する声は年々増えています。かつては「退職金と年金で安泰」というイメージがありましたが、今は「自助努力で備える」ことが当たり前になってきました。インフレや物価上昇リスク
物価がじわじわと上がる中、「預金だけだとお金の価値が目減りしてしまう」という危機感も。特に2020年代に入ってからは、食料品や生活費の上昇を実感しているご家庭も多いでしょう。NISAやiDeCoなど資産形成制度の拡充
国が後押しする形で、NISAやiDeCoといった“お得に資産運用できる制度”が続々と登場。公務員も利用可能になり、「投資が特別な人だけのもの」から「誰でもできる身近なもの」に変わりました。
こうした背景から、公務員の方も「資産運用=自分ごと」として真剣に考える時代になったのです。
なぜ投資信託より個別株なのか?
資産運用というと、まず投資信託(インデックス投資)を思い浮かべる人も多いですが、実は個別株にも独自の魅力があります。
成長株で大きなリターンを狙える
たとえば成長企業の株を長期で保有し、10倍・20倍と値上がりすることも夢ではありません。配当金や株主優待が楽しめる
毎年の配当や、飲食・生活用品の株主優待は公務員の家計にも嬉しいポイント。自分で企業を選ぶ“面白さ”と“納得感”
業績や将来性を自分なりに調べて、納得して買える——投資信託とは違う「自己決定感」があります。
もちろん、リスクや注意点もあるので「分散投資」や「長期目線」が鉄則ですが、うまく取り入れれば投資信託と個別株の“いいとこ取り”も可能です。
公務員の副業規制・インサイダー・長期投資との関係
ここでよく出てくる質問が、
「公務員でも株を買っていいの?」
「インサイダー取引って何?」
「短期売買はダメ?」
というもの。
結論から言うと、一定のルールを守れば公務員でも株式投資は可能です。
ただし、「職務上知り得た未公開情報を利用して売買しない」など、インサイダー取引を徹底的に避ける必要があります。
また、公務員は「本業最優先」の立場なので、勤務時間中の短期売買やデイトレードはNGです。
あくまで「長期投資」「余裕資金での運用」が基本です。
こうした時代背景や制度面をふまえて、「公務員でも安心してできる個別株投資の選び方」を、このあと詳しく解説していきます。
公務員が個別株を選ぶときに絶対知っておくべきルール

公務員の副業規制と株式投資
まず大前提として、「公務員=投資NG」ではありません。
公務員の副業規制(地方公務員法・国家公務員法)で禁じられているのは、「営利目的の副業」や「兼業」です。
しかし、自身の資産運用としての株式投資は原則OKとされています。
ただし、「事業的規模」や「経営参加」にあたる場合は要注意。
たとえば、
株の売買を勤務時間中繰り返す(デイトレーダー化)
会社経営に関与する規模で株主になる
こうしたケースは“本業に支障をきたす副業”とみなされる可能性があるため、「本業優先」かつ「個人の資産運用の範囲内」に収めることが重要です。
インサイダー取引の注意点
公務員の場合、業務上で特定の企業や業界に関する「未公開情報」を得る場面もゼロではありません。
このような情報を利用して株式売買を行うと「インサイダー取引」となり、法律違反として重い処罰を受けます。
例:自治体のインフラ発注に関する内部情報、提携や補助金の決定内容、災害関連の公的支援情報など
※これらを利用した売買は絶対にNG
「自分には関係ない」と思いがちですが、公務員だからこそ“疑われやすい立場”であることを自覚し、常に「情報の公平性」を守る意識が必要です。
家族名義・親族の運用はどうなる?
よく「家族や親の名義で株を買えば大丈夫?」という疑問も聞きます。
結論から言うと、「名義を変えても実質的に自分が運用していれば責任は免れません」。
名義を利用した“抜け道”は、不正行為とみなされるリスクもあるため絶対に避けましょう。
また、家族が上場企業や関係団体に勤務している場合は、そちらもインサイダー規制の対象となります。
家族全体で「情報管理」の意識を高めておくことが大切です。
よくあるQ&A:公務員の投資OK/NGライン
Q1. 普通に証券口座を開設して株を買うのはOK?
→ はい。通常の範囲内の運用なら問題ありません。
Q2. 配当収入や売買益は申告が必要?
→ 原則、確定申告が必要(特定口座の源泉徴収ありにしていれば不要)ですが、NISA口座での運用なら非課税枠の範囲内であれば申告不要です。
Q3. 同僚に投資の話をしても大丈夫?
→ プライベートな会話なら問題ありませんが、業務情報の漏洩や投資勧誘は絶対NG。
個別株の基本|初心者でも失敗しないための銘柄選定ポイント
個別株とは?メリット・デメリット
「個別株」とは、日経平均や投資信託のような“まとめ買い”ではなく、特定の企業の株式を一社ごとに購入する投資方法です。
メリット
自分で好きな企業を選べる
「応援したい会社」「将来性を感じる業界」など、自分の意思で投資先を選択できます。大きな値上がり益(キャピタルゲイン)を狙える
成長企業や新興企業を早期に見つければ、大きなリターンを得ることも可能です。配当金や株主優待がもらえる
企業によっては毎年の配当や、食事券・商品などの株主優待も魅力。
デメリット
値動き(リスク)が大きい
業績悪化や不祥事などで、株価が急落することも。情報収集や分析が必要
業績・ニュース・業界トレンドなど、勉強や手間もかかります。
初心者が見るべき指標(PER・PBR・配当利回りほか)
個別株を選ぶときは「なんとなく有名だから」ではなく、客観的な数字(指標)も必ずチェックしましょう。
PER(株価収益率)
株価が利益の何倍まで買われているかを見る指標。一般的に低いほど“割安”と言われますが、業界によって適正水準は異なります。PBR(株価純資産倍率)
会社の資産と比べて株価が高いか安いかを示します。1倍前後が一つの目安。配当利回り
「株価に対して1年でもらえる配当金の割合」。高すぎると逆に減配リスクもあるので要注意。自己資本比率・ROE・売上高成長率
財務健全性や成長性を見る指標。初心者はここも意識しましょう。
配当・優待・成長性…何を重視するべき?
安定した収入がほしい:配当・優待重視型
大きな値上がり益を狙いたい:成長株重視型
両方バランスよく持ちたい:分散投資型
自分の投資目的やリスク許容度に合わせて、何を重視するか軸を決めるのが大切です。
長期・短期どちらが公務員向き?
結論:公務員には長期投資が圧倒的におすすめです。
短期売買は本業に支障をきたすうえ、インサイダーリスクも高まります。
余裕資金で5年10年とじっくり構える姿勢が、安全・確実にリターンを得るコツです。
よくある失敗例とリスク管理
話題の銘柄に飛びついて高値掴み
→ SNSやニュースだけで判断しない。一社集中で大損
→ 複数社・複数業種に分散を推奨。自分ルールがなく、損切りできない
→ あらかじめ「いくら下がったら売る」など、ルールを決めておく。
公務員におすすめの個別株選びステップ【実践編】

スクリーニングと情報収集のコツ
個別株投資のスタート地点は、「銘柄をどうやって絞り込むか」です。
まずは証券会社の「スクリーニング機能」や「ランキング」を活用しましょう。
スクリーニングで見るべき条件例:
時価総額(安定企業は中型・大型株から)
業種(分散投資のため複数業界を選ぶ)
配当利回り(3%前後を目安に)
PER/PBR(業界平均と比べる)
【手順イメージ】
証券会社のスクリーニング画面を開く
配当利回り、時価総額、PER等で条件を設定
表示された銘柄をピックアップして調査リストに追加
情報収集のコツ
会社の公式IR(投資家情報)ページを必ずチェック(特に「決算説明会資料」が分かりやすいのでおすすめ)
Yahoo!ファイナンスや会社四季報の評価も参考にする
SNSや掲示板は話半分でOK(過熱気味の銘柄は避ける)
会社四季報・IR資料の見方
四季報の基本の読み方:
売上高や経常利益が毎年伸びているか(成長性)
自己資本比率などの財務体質
業績予想の「増益」「減益」マーク
配当推移、優待内容
IR資料のポイント:
「決算説明会資料」や「事業計画」を読むと企業の方向性がわかる
社長メッセージや新規事業に注目
初心者でもできるチェック方法:
四季報は最初は難しく見えるかもしれませんが、「右肩上がりの数字が多い会社」「赤字続きでない会社」を選ぶだけでもリスクは減らせます。
利益が出た場合の税金・確定申告
株式投資で得た利益には税金がかかります(通常20.315%)。
ただし、NISA口座なら年間投資枠内での利益は非課税です。
特定口座(源泉徴収あり)にしておけば、確定申告の手間もほとんどかかりません。
配当も同じく課税対象ですが、NISAや配当控除も活用できます。
【ワンポイント】
「利益が出て申告が必要になったらどうしよう?」と不安な公務員も多いですが、証券会社が自動で計算してくれるので、初心者はまずNISAから始めましょう。
【体験談】私が個別株投資を始めた理由・選び方
個別株投資を始めた理由
私自身、元公務員時代に
「一生公務員として働き続けるのは嫌」
「お金持ちになって慈善家になりたい」
「裕福になって家族と幸せな日々を過ごしたい」
という気持ちが強くなり、大きな利益を狙って最初から個別株投資でスタートしました。
最初は右も左もわからず、「四季報って何?」状態。
ですが、「株式投資の入門書」や「株関連雑誌」である程度知識をつけ、実際に数万円程度で株の売買をして経験を積んでいきました。
初めて買った株は、当時最も安く購入できた「ランド」と、なじみのあった「メガネスーパー」です。
最初は「値動きが気になってソワソワ」しましたが、段々と長期投資の大切さを実感し、現在は「3銘柄への集中・長期投資」をしています。
投資を始めたおかげで「経済やニュースに興味を持つ」「お金の知識が増えた」など、思わぬプラスもたくさんありました。
失敗もありましたが、「自分で納得して選んだ株を持つ安心感」「会社を応援している株主の気持ち」は何物にも代えがたいと感じています。
【私の個別株の選び方】
私の株の選び方は、株の本を何十冊も読み、9年間の株式投資での経験を経て身につけてきたものです。
- 四季報やスクリーニングで「今後成長しそうな企業」「応援したくなるような事業をしている企業」を10社ほどピックアップ
- 会社HPに掲載されている「決算説明会資料(パワーポイント資料など)」をしっかり読む
- ファンダメンタルズ分析をする(重要な指標は一通り確認し、割安か・財務は健全かを確認)
- 自作のチェックシートで最終チェック(たくさんの書籍から株を選ぶ際のキーワードや数値をExcelに整理してあり、それに照らし合わせて投資先としてどうかを最終判断)
- 買いたい企業が決まったら、あとは「暴落後」や「根拠がないのに株価が異常に下がり過ぎている」と思ったときに複数回に分けて買う(逆張り)
- 一度買ったら、基本的に売りません。(自分が思い描いた成長ストーリーが崩れない限り売りません)
公務員が避けるべき個別株&ありがちな失敗パターン

公務員と相性の悪い銘柄の特徴
個別株投資では「何を買うか」も大事ですが、「何を避けるか」も同じくらい重要です。
特に公務員の場合、次のような銘柄は避けるのが無難です。
値動きが激しい新興企業・テーマ株
短期間で大きく上がることもありますが、下落リスクも非常に高いです。本業に集中したい公務員にはストレスの元に。経営不安や赤字が続く会社
「復活に期待!」と手を出しがちですが、倒産リスクや減配リスクが高く、安定した資産形成には不向きです。複雑なビジネスモデルや仕組みが分かりにくい会社
自分で理解できない企業は避けるのが鉄則。「なんとなく有名だから」「SNSで話題だから」で買うのは危険です。配当利回りが極端に高すぎる株
高配当につられて飛びつくと、業績悪化による減配・無配のリスクが。数字だけで判断せず、配当の持続性も調べましょう。
負けやすい投資パターンとその回避法
個別株投資には“ハマりやすい落とし穴”がいくつかあります。
代表例とその対策をまとめます。
【よくある失敗例】
「一発逆転」狙いで資金を集中投下
→ 分散投資の基本を忘れずに。「全部この株!」は危険です。
SNSやネット掲示板の情報に流される
→ 他人の意見は参考程度に。自分のルール・基準で判断を。
損切りできず塩漬けに
→ あらかじめ「自分が思い描いたストーリーが崩れたら売る」と決めておきましょう。
利益確定を急ぎすぎて成長株を早売り
→ 本来の目的や企業の将来性を見失わないように。
【実例】私がやらかした失敗談と学び
早く大きな利益を得たいと思い、半年間デイトレードに手を出した時期がありました。
ただ、現実は甘くなく、多くの資産を失い、またメンタルもしんどくなり退場しました。
デイトレで利益を出している人はごく一部の人であり、大多数の人は損していると思います。
この経験から
「デイトレードのような短期売買には手を出さない」
「原則、長期投資をする。一度売ったら手放さないイチオシの企業を探して安く買う」
という“自分ルール”を守ることで、今では落ち着いて長期保有できています。
公務員のための個別株投資Q&A・よくある疑問にプロが回答

Q1. NISAやiDeCoで個別株は買える?どちらがおすすめ?
A.
NISA口座では、国内外の個別株を購入できます。配当金や売買益が非課税になるメリットは大きいです。一方、iDeCoは原則として投資信託がメインで、個別株の直接購入はできません。
公務員にとっては、「まずNISAで個別株」「iDeCoは分散型の投資信託」と使い分けるのがおすすめです。
初心者はNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)を有効活用しましょう。
Q2. 「株式投資していることが職場や家族にバレる?」「不利益はある?」
A.
証券口座開設や取引は基本的にプライバシーが守られます。ただし、配当所得や売却益が多額の場合、確定申告が必要になり、家族の扶養や税金関係で影響が出る場合も。職場への届出義務はありませんが、本業に支障が出るような売買や、経営参加レベルの保有は避けましょう。
Q3. 途中で転職・退職した場合はどうなる?
A.
株の保有や取引自体は継続できます。ただし、退職時は職場からの「守秘義務」も頭に入れておきましょう。転職先で新たなインサイダー情報に触れる場合は、その業界・会社の株を避けるなど、自己管理が必要です。
Q4. 家族・配偶者の名義で株を買うのは大丈夫?
A.
家族名義でも実質的に本人が運用・指示している場合は、公務員本人の責任が問われる場合があります。脱税やインサイダー防止の観点からも、名義貸しはおすすめできません。家族全体で「情報管理」と「ルール厳守」の意識を持つことが重要です。
Q5. 生活防衛資金・資金管理のコツは?
A.
「生活費の半年分〜1年分は現金で確保」が基本です。残りの余裕資金で投資を行いましょう。
いきなり全額投入せず、少額からスタート
生活に必要な資金を取り崩さないルールを守る
【ワンポイント】
「投資は余裕資金で」が鉄則。
急な出費やライフイベントにも備え、無理のない範囲で継続しましょう。
まとめ|公務員が個別株投資を成功させるために大切なこと
ここまで、公務員が個別株投資を行う際の基本や注意点、実践ステップを詳しく解説してきました。
最後に、投資で後悔しないための大切なポイントをおさらいします。
失敗しないための3箇条
ルール厳守・本業最優先
公務員として、インサイダーや副業規制など「守るべきルール」は最重要。本業に支障がない範囲で、余裕資金で投資を楽しみましょう。分散投資と長期目線
一社集中や短期売買はリスクが大きくなりがち。複数業種・複数銘柄への分散と、5年10年といった長期スタンスが“安定”と“成長”の両立に役立ちます。自分の軸・目的を忘れない
「なぜ投資するのか」「何のためにその株を買うのか」を明確にし、人の噂や流行ではなく“自分の納得感”を大切に。
今日からできる一歩
まずは証券口座のスクリーニングや、四季報・IRの読み方を試してみる
NISA枠など、非課税制度の活用を検討する
「どんな企業なら応援したいか」「生活に身近な会社は?」を考えて、気になる銘柄をリストアップ
私自身も「投資の勉強は難しそう」と最初は二の足を踏みましたが、小さな一歩を踏み出したことでお金や社会への興味も深まりました。
日々コツコツ積み重ねることで、資産運用の知識も着実に増えていきます。
【関連記事】
【2025年最新】公務員向けおすすめ証券会社4選を元公務員FPが比較!実体験で語る選び方と注意点
【公務員の株式投資】いくらから始める?初心者が失敗しない最適な金額を元公務員FP体験談で徹底解説!