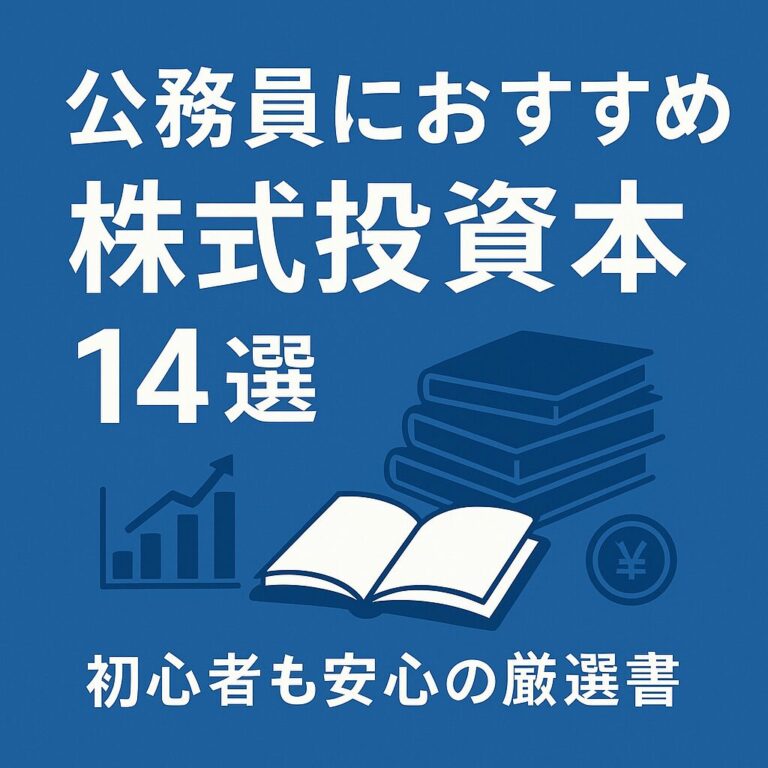株式投資に興味はあるけれど、
「何から始めたらいいのかわからない」
「公務員でも投資をして大丈夫なの?」
と不安に感じていませんか?
実は、これはかつての私自身も同じでした。
公務員という立場上、副業禁止の規定や倫理的なプレッシャーがある中で、「もし職場にバレたらどうしよう」と躊躇していたのです。
しかし、今の時代、公務員であってもルールを守れば“資産運用としての株式投資”は認められています。
多くの自治体や公的機関でも、一定の範囲で資産形成が推奨されるようになりました。
とはいえ、ネットには断片的な情報や極端な意見も多く、「何を信じて始めればいいのか迷ってしまう」人も多いはずです。
私も最初は右も左もわからず、情報の渦に巻き込まれました。
そこで強くおすすめしたいのが「信頼できる書籍から体系的に学ぶ」こと。
株式投資の基本からリスク管理まで、本なら正しい知識をしっかり身につけられます。
この記事では、元県職員でFP資格を持つ筆者が、公務員や投資初心者でも安心して学べるおすすめ株式投資本を厳選してご紹介します。
自分自身の体験談や、読者のタイプ別の選び方、失敗しない注意点もあわせて、あなたの“最初の一歩”をしっかりサポートします。
公務員でも株式投資はできる?基本をやさしく解説
「公務員は株式投資をやっても大丈夫なの?」
この疑問、私も最初はずっと心のどこかで引っかかっていました。
実際、資産運用を考える公務員の多くが最初につまずくのがこのポイントです。
結論から言うと、公務員でも株式投資は原則として問題ありません。
国家公務員法・地方公務員法で禁止されているのは、主に「信用失墜行為」や「営利企業への従事」などであり、自分の資産を運用する行為(=株式投資)自体はNGではありません。
もちろん注意点もあります。
【公務員が株式投資で気を付けるべきポイント】
勤務時間中に株の売買をしない(勤務外で取引すること)
職務上知り得た内部情報をもとに売買しない(インサイダー取引の厳禁)
株式投資に関する副業(情報商材販売や講師業など)をしない
つまり、「公務員としての信頼を損なわない」「職務と関係のない範囲で自己責任で投資をする」という2点を守れば、株式投資はOKです。
なぜ今、公務員の株式投資が注目されているのか?
近年、20代〜40代の現役公務員でも「老後資金」「教育費」「将来の不安」を理由に、早いうちから資産形成を始める動きが急増しています。
私の周りにも、「NISAやiDeCoで資産運用している」という同僚がここ数年で一気に増えました。
物価や社会保険料の上昇、年金制度への不安
昇給やボーナスだけに頼れない将来像
安定収入ゆえに“積立型投資”に向いているライフスタイル
こうした背景が、「公務員こそ長期目線の投資に向いている」と言われる理由です。
株式投資は「副業」ではなく「資産運用」
多くの公務員が気になる「副業禁止」ですが、株式投資は「個人の資産管理」に該当し、副業とはみなされません。
ただし、
勤務外に行うこと
職務と利害関係がないこと
情報漏洩や信頼失墜行為がないこと
この3つを守るのが大前提です。
私も初めて株を買うときは「本当に大丈夫かな?」と不安でしたが、調べれば調べるほど、「ルールを守れば問題ない」と分かり、安心して一歩踏み出せました。
次章では、そんな初心者公務員が「何から学び始めるのが最善か?」を分かりやすく解説します。
株式投資の第一歩は「本」で学ぶのがベストな理由
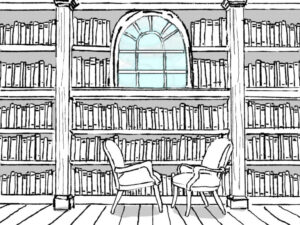
「株を始めてみたいけど、何から手を付けたらいいか分からない…」
実は私自身もまったく同じ気持ちでした。
今ではYouTubeやSNSでも投資情報があふれていますが、本から学ぶことの価値は、時代が変わっても揺るぎません。
なぜ“本”なのか?公務員がまず書籍から学ぶべき3つの理由
1. 信頼性が段違いに高い
書籍は、経験豊富な投資家や金融の専門家によって執筆され、出版社のチェックも入ります。
ネットやSNSは誰でも発信できる分、誤情報や誇張、宣伝目的の記事も多いですが、本は情報の正確性や体系性が桁違いです。
2. 初心者向けに“つまずかない”工夫がされている
投資本は「まったくの初心者でも分かる」ように、用語や仕組み、リスクまで段階的に解説されています。
私も「NISAって何?」「株って何から始めるの?」という初歩の初歩から、本のおかげで順を追って理解できました。
3. 通勤やスキマ時間にも最適。公務員ライフに合う
公務員は毎日忙しいですが、生活リズムは規則的な人が多いです。
本なら通勤・昼休み・寝る前など、10分単位で少しずつ知識を積み上げられるのが大きな強みです。
ネット情報との違いと、私の体験
ネットには最新情報やリアルタイムなニュースという良さがあります。
一方で、「誰が書いたか分からない」「話題が極端」「全体像がつかみにくい」というデメリットも。
私も最初はネット記事を片っ端から読んでいましたが、断片的な知識がバラバラに頭に残るだけで、「何から始めたらいいのか?」が全く見えませんでした。
ネット:気になる銘柄や最新ニュースをチェックする
この使い分けができると、正しい知識の上に「今役立つ情報」を積み重ねられるようになります。
私が本から学び始めて良かったと実感した話
私自身、公務員時代に資産運用を考え始めた頃、最初に手に取ったのは『ZAiが作った株入門』という本でした。
投資の基礎用語や株の仕組み、口座開設の流れまで丁寧に書かれていて、「これなら自分にもできるかもしれない」と思えたことを今でも覚えています。
また、株には優待や配当があること、うまくいけば何十倍にも資産が増える可能性があることが分かり、お金持ちになりたいという夢があった自分にとって、「こんなに良いものはほかにない」と感銘を受けました。
本を読み終わる頃には、証券口座を開く準備ができており、「投資って特別な人がするものではない」と考えが180度変わったのです。
いま振り返っても、あの1冊が私の投資人生のスタート地点だったと思います。
書籍から学ぶことで、無駄な遠回りや情報迷子をせず、安心して一歩を踏み出せます。
次章では、実際に私が選んで読んだおすすめ本などをタイプ別に紹介していきます。
公務員におすすめの株式投資本14選【初心者〜中級者向け】
ここからは、私自身の経験とFPとしての知見をもとに、「初心者でも理解しやすい」「公務員の生活に合った」株式投資本を14冊厳選してご紹介します。
実際に自分が手に取り、役立った本や、投資仲間から高評価だった本を中心にラインナップしています。
読者のタイプや投資スタイルによって“合う本”は違いますので、ぜひ自分にぴったりの一冊を見つけてください。
◆ 超初心者向け|まずは“株とは何か”をざっくり理解したい人へ
①『めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ZAiが作った株入門』
私が一番最初に読んだ株の入門本です。投資初心者でもすぐに実践できる株式投資の基本やコツを、人気雑誌ZAi編集部がわかりやすく解説した一冊。株の仕組みや口座開設、注文方法、銘柄選び、チャートの見方、分散投資、配当・株主優待まで、イラストや図解を多用しながら丁寧に説明。投資の失敗例や注意点も紹介されており、初心者が安心して株を始められるようサポートする内容となっています。
②『株の超入門書』
株式投資をこれから始めたい人のために、株の仕組みや基礎知識をわかりやすく解説した一冊です。株とは何か、市場のしくみ、証券会社の選び方、口座開設の手順から、注文方法、銘柄の選び方、チャートの見方、配当や株主優待の基礎、さらにはリスクや注意点まで丁寧に紹介しています。初心者がつまずきやすいポイントも具体例を交えて説明されており、投資の第一歩を安心して踏み出せる内容になっています。。
◆ 実話・ストーリー系|モチベーションを高めたい人へ
③『どん底サラリーマンが株式投資で2億 今息子に教えたいお金と投資の話』
経済的に苦しい状況から株式投資で2億円を築いた著者が、息子に伝えたいお金の知識や投資の本質を語る一冊です。投資を始めた理由、失敗と成功の体験談、資産形成に必要な考え方、リスクとの向き合い方、そして「なぜお金の勉強が大切か」など、初心者にもわかりやすく解説。家族で話し合いたいリアルなお金の話と投資の入門知識が詰まっています。
④『50万円を50億円に増やした投資家の父から娘への教え』
わずか50万円から50億円まで資産を増やした著者が、自身の成功・失敗経験をもとに、投資で大切な考え方やお金との向き合い方を娘に伝える形でまとめた一冊です。リスク管理の重要性や長期投資のコツ、資産を守り増やすための戦略など、具体的かつ実践的なアドバイスが豊富。投資初心者や家族でお金の教育をしたい人にもおすすめできる、実用性の高い入門書です。
⑤『わが投資術』
著者が40年以上の投資経験で培った独自の投資哲学と実践ノウハウを詳しくまとめた一冊です。日本株を中心に、どのように銘柄を選び、どんな基準で売買判断をしてきたか、また成功と失敗の実例を交えながら、自らの投資スタイルを具体的に解説。短期的な儲けではなく、長期的な資産形成を重視し、再現性のある投資法と相場への向き合い方を学べる内容となっています。
◆ ファンダメンタル・決算分析が学べる本|中長期投資志向の方に
⑥『ファンダメンタル投資の教科書』
企業の業績や財務内容といった「ファンダメンタルズ」を重視し、株式投資で安定して利益を上げるための理論と実践を解説した入門書です。決算書の読み方、企業分析のポイント、割安株の見つけ方、成長企業の見極め方など、基礎から応用まで体系的に紹介。データに基づいた投資判断の大切さや、長期的な資産形成を目指すための考え方を、初心者にも分かりやすくまとめています。
⑦『バフェットの財務諸表を読む力』
世界的投資家ウォーレン・バフェットが重視する「財務諸表の読み方」を、初心者にもわかりやすく解説した一冊です。損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書などの基本から、バフェット流の着眼点や分析方法まで丁寧に紹介。実際の企業事例を交えながら、数字の裏にある企業価値や経営の本質を見抜く力を身につけられる内容です。長期投資家にとって必携の実用書となっています。
◆ 小型株・成長株系|利益を狙う集中投資派に
⑧『エナフン流株式投資術』
個人投資家として成功した著者・エナフンが実践してきた独自の株式投資法をわかりやすく解説した一冊です。成長株への長期投資を軸に、銘柄選びの基準や投資タイミング、企業分析のコツ、メンタル面の重要性などを、自身の体験談や成功・失敗例を交えて紹介。初心者でも無理なく実践できるシンプルかつ再現性の高い投資法が詰まっており、堅実に資産を増やしたい人におすすめです。
⑨『小型株集中投資で1億円』
著者が小型株(時価総額の小さい銘柄)に狙いを定め、集中投資によって1億円の資産を築いた実践的なノウハウをまとめた一冊です。小型株ならではの成長性や値上がりのチャンスを活かす銘柄選び、集中投資のリスクとリターン、売買タイミング、情報収集の方法などを、実例とともに具体的に解説。リスク管理やメンタルの持ち方にも触れ、着実に資産を増やしたい投資家に役立つ内容となっています。
⑩『株の学校』
株式投資の基礎をゼロから学べる初心者向けの実践ガイドです。証券口座の作り方や売買の仕組み、チャートの見方、企業分析の基本、そしてリスク管理の手法までを体系的に解説。さらに銘柄選びのコツや分散・長期投資の考え方など、投資スタイルを身につけるための内容も充実。具体的な事例と図解が豊富で、実践しながら自然とスキルアップできる構成。これから株を始めたい人にとって、安心して第一歩を踏み出せる一冊です。
◆ 投資メンタル・行動心理系|長く投資を続けたい人に
⑪『株はメンタルが9割』
株式投資で勝ち続けるためには「知識やテクニック」よりも「メンタル(心理面)」が何より大切だと説く一冊です。欲や恐怖に流されず冷静に行動するための考え方や、自信を持って売買判断を下すための自己管理術、相場の波に振り回されないためのメンタル強化法などを、著者の実体験や具体例を交えながらわかりやすく解説。投資初心者から経験者まで役立つ“心の教科書”となっています。
⑫『勝つ投資 負けない投資』
65万円を150億円に増やした“究極の個人投資家”片山晃氏(ペンネーム:五月)と、TOPIXに負けたことのない“不敗の機関投資家”小松原周氏による共著です。前半は片山氏が実践的な銘柄選定の手法や売買判断を、後半は小松原氏がポートフォリオ構築やメンタルの重要性、機関目線からのリスク管理を解説。2015年刊行後好評を博し、2024年1月に改訂版が発売されました。最新相場環境と心理面への対応も加筆され、初心者にも熟練者にも役立つ普遍的内容が凝縮されています。
⑬『株式投資の未来』
ジェレミー・J. シーゲル教授による投資の名著です。100年以上にわたる市場データから示されるのは、投資家にとって真に利益をもたらすのは「成長株」ではなく、「永続する企業」への長期・分散投資だということです。特に配当の再投資が累積リターンの97%を占めるという驚くべき事実を提示し、「成長の罠」に陥らない分析を展開します。さらに、世界経済の人口動態やポートフォリオ戦略も論じており、資産形成の基本を学べる普遍的な教科書です。
⑭『個人投資家入門』
人気投資ブロガー・エナフンがまとめた、初心者から中級者へステップアップするための投資ガイドです。全13レッスン構成で、投資に向けた心構え、貯金から投資への転換、銘柄探索法、企業分析、チャート読み、成長株発掘法、バリュー分析、売買実践、情報リテラシー強化、失敗からの学びなど、必要な知識と行動が段階的に網羅されています。特に「やるべきこと」「やってはいけないこと」を明確化し、再現性の高い投資習慣を身につけさせる内容で、初心者にとっての“決定版”とされています
【タイプ別比較表】
| タイプ | 書籍名 | 読者レベル | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 超初心者 | ZAiの株入門/超入門書 | 初心者 | 図解・口座開設・イラスト解説 |
| 実話系 | 2億本/父から娘/わが投資術 | 初心者〜中級者 | ストーリーで投資観を学ぶ |
| ファンダ系 | ファンダ教科書/バフェット | 中級者 | 財務分析の基本 |
| 小型株系 | エナフン/小型株集中/株の学校 | 中級者 | 成長株投資・集中投資 |
| メンタル系 | メンタル9割/勝つ投資/未来/入門 | 初心者〜中級者 | 長期投資の精神・哲学 |
どの本も、実際に“使える”知識が身につくものばかりです。
次の章では、こうした本と出会ってどのように考え方・行動が変わったか、私自身の体験談をお伝えします。
【体験談】株式投資本を読んで価値観が変わった話
私が株式投資に興味を持ち始めたのは、公務員として6年ぐらい働き、漠然と「お金持ちになって幸せに暮らしたい」「収入を増やしたい」という気持ちが高まりつつあるときでした。
貯金も全然貯まっていかないし、この先結婚をして、結婚資金、子どもの教育資金、老後資金、住宅ローン返済…いずれも「給与だけで何とかなるのか?」と漠然とした不安を抱えていました。
当時の私は、投資=ギャンブルというイメージが強く、「公務員がやっていいの?」「職場にバレないかな?」と基本的なことさえ理解できていませんでした。
そんな中、書店でふと目に留まったのが『めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ZAiが作った株入門』でした。
最初の1冊が“投資への恐怖”を取り除いてくれた
そんな中、書店で手に取った『めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ZAiが作った株入門』が私の価値観を大きく変えてくれました。
それまでは「株なんて特別なお金持ちやプロだけがやるもの」と思い込んでいましたが、
この本は本当にやさしく、具体的に、投資の基礎や失敗しないためのコツを教えてくれます。
「最初は少額からでOK」
「仕事中は取引しない、無理せずマイペースで続ければいい」
「長期でコツコツ続けるのが大切」
など、知らなかった“当たり前”がどんどん腑に落ちていきました。
「これなら自分にもできるかもしれない」と心から思えた瞬間です。
行動が変わったきっかけは“もう1冊”との出会い
その後、自然に『どん底サラリーマンが株式投資で2億』という実話本を読みました。
これは、精神的にも金銭的にも苦しい状態から「投資で人生を立て直した」という実録ストーリーで、読みながら何度も感情が揺さぶられました。
公務員という安定した職業に就いていても、将来を見据えて「自分でも資産を育てていくんだ」という意識を強く持たせてくれた1冊でした。
“副業”ではなく、“人生設計の一部”としての投資という考え方を、この本が与えてくれたと思います。
投資は「知識」よりも「考え方」
今ならはっきり言えます。
無知こそが一番のリスクです。
私は、本を通して知識を得ただけでなく、投資に対する“ものの見方”自体が大きく変わりました。
もし本を読んでいなければ、未だに投資=危険、怖いもの、と避けていたかもしれません。
どんな立場の人でも、正しい知識と考え方さえ身につければ、
「投資=怖い」から「投資=未来を自分で作る手段」へと価値観がきっと変わります。
株式投資本の選び方と注意点【失敗しないために】
「株の勉強を本から始めよう!」と思って書店やAmazonをのぞくと、あまりにも多くの投資本が並んでいて、どれを選べばいいのか分からなくなってしまうこともあります。
特に公務員のように慎重なタイプの方は、「間違った本を選んで損をしたくない」という気持ちが強いはず。
私も様々な株やお金の本を読んできましたが、実際にかなり役立った本に出会えるのは5冊に1冊程度でした。
これまでかなりのお金と時間を費やしてきました。
50冊以上は読んでいます。
が、今でも本棚にいれてすぐ手に取れる状態にしている良本は20冊程度です。
あなたには効率的に有用な情報を得てほしいので、ここでは、失敗しないための「投資本の選び方」と「注意点」を解説します。
本を選ぶときの3つのポイント
① 自分のレベルに合っているか?
投資本には、超入門レベルから上級者向けまで、さまざまな難易度があります。
最初の1冊で専門用語が飛び交う難解な本を選んでしまうと、挫折の原因になりかねません。
例:
初心者:『ZAiの株入門』『株の超入門書』
中級者:『ファンダメンタル投資の教科書』『バフェットの財務諸表を読む力』
まずは「図解中心のやさしい本」を選ぶのが鉄則です。
② 著者や出版社の信頼性をチェック
投資関連の書籍は、著者の実績や経験が重要な信頼の指標になります。
長年の実績を持ち結果を出している個人投資家、ファンドマネージャー、証券会社出身者など、しっかりした経歴がある人の本を選びましょう。
また、出版社も投資専門誌を発行している会社が安心です。
③ 内容が“実用的”か“精神論”に偏っていないか?
読んでいて気持ちが高揚する本(「誰でも億万長者!」系)は、一時的にはモチベーションになりますが、具体的な学びが少ないことも多いです。
できれば、「感情を動かす本」と「実務を学べる本」をバランスよく読むのが理想です。
よくある失敗とその対策
| 失敗例 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 内容が難しすぎて挫折した | レベルが合っていない | Amazonレビューで「初心者向け」の声が多い本を選ぶ |
| 著者の主張が極端すぎて信用できなかった | インフルエンサー本・広告本 | 著者の経歴や出版元を確認する |
| 読んだだけで満足してしまった | 行動につながらない内容 | チェックリスト付きやワークがある本を選ぶ |
本は読むだけじゃなく「実践」してこそ意味がある
どんなに良い本を読んでも、行動しなければ知識は身につきません。
ぜひ本を読み終わったら――
証券口座を開設してみる
積立や購入シミュレーションをしてみる
少額でETFや投資信託を買ってみる
こうした“小さな一歩”を実践してみてください。私も最初は勇気がいりましたが、その一歩が自信につながります。
よくあるQ&A|公務員×株式投資本の疑問

ここでは、公務員や資産運用初心者の方からよくいただく「株式投資本に関する疑問」について、わかりやすくお答えしていきます。
読み始める前の不安や、購入後のモヤモヤを解消するヒントになれば幸いです。
Q1. Kindleなどの電子書籍でも問題ない?
A.
電子書籍でもまったく問題ありません。
スマホで通勤中やスキマ時間に読めるので、忙しい公務員にはむしろ便利な面も多いです。
ただし、図解が多い本やマーカー・付箋を活用したい場合は紙の本がやはりおすすめです。
私も実は「本に直接書き込みたい」「すぐ手に取って何度も見返したい」タイプなので、基本は紙派です。
自分のスタイルや使い方に合わせて選んでOKです。
Q2. 本はどんな順番で読むのが効果的?
おすすめの流れは以下のとおりです。
超入門書でざっくり理解(用語・仕組みを学ぶ)
例:『ZAi入門』『株の超入門書』実話やストーリー系で動機付け・イメージ形成
例:『どん底サラリーマンが〜』『父から娘へ』中級者向けで戦略や分析力を高める
例:『ファンダメンタル投資の教科書』『エナフン流投資術』メンタル・長期戦略で継続力を強化
例:『株はメンタルが9割』『株式投資の未来』
…という4段階です。
一気に難しい本に飛びつくよりも、「分かる→やってみたい→実践→深掘り」の順が、着実に知識が身につきやすいと実感しています。
Q3. 本を読んでも利益が出ません…
これは非常に多い悩みです。
ただし、以下のような点を確認してみてください。
本の内容を「行動」に移していますか?
- 本の内容をExcelなどにまとめていますか?
長期投資など基本を守っていますか?
1冊読んで満足していませんか?
株式投資で利益を出すには、「知識×実践×継続」がカギになります。
本は“武器”であり、それを使うのは自分自身です。
私自身、最初の数年はデイトレでうまくいかずマイナス続き。
でも本で長期投資や小型株集中投資の考え方に出会い、考え方を変えてからは資産が安定して増えるようになりました(本を読んだあと実際に投資スタイルを変えたことで、資産が3倍になった経験もあります)
本を読むだけでは成功しませんが、「本を読んだからこそ、成功への道筋が見えるようになった」のは間違いありません。
次章では「まずこの1冊から始めたい」という方へ向けて、タイプ別のおすすめ本をもう一度整理してお伝えします。
まとめ|まず手に取るべきはこの1冊
ここまで、公務員におすすめの株式投資本を14冊紹介しながら、学び方・選び方・体験談・注意点・Q&Aまでを解説してきました。
最後に、「結局どれから読めばいいの?」という方に向けて、タイプ別に“最初の1冊”を提案します。
✅ 初心者でとにかくわかりやすい本が欲しい方へ
『めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ZAiが作った株入門』
これから株を始める人にとって、最もハードルが低く、実用的な1冊です。
用語の解説、証券口座の開設方法、買い方・売り方など、株式投資の「とっかかり」がこの1冊で網羅されています。図やイラストも豊富で、疲れていてもサクサク読めるのが魅力です。
✅ 投資への一歩が踏み出せずにいる人へ
『どん底サラリーマンが株式投資で2億』
数字や理屈ではなく、「投資で人生を変えた人の実話」が心を動かしてくれます。
公務員としての安定を得た後でも、将来への不安を感じる人は多いはず。
そんな時に、背中を押してくれるのがこの本です。
“感情”に訴える投資本は意外に少なく、行動変容につながりやすい一冊です。
✅ ステップアップしたい方へ
『ファンダメンタル投資の教科書』
『バフェットの財務諸表を読む力』
実際に投資を始めてみて、「次は銘柄分析や企業研究もしたい」と感じたら、これらの本が非常に役立ちます。
数字が苦手な方にも配慮された構成になっているので安心です。
投資は“自分で学び続ける姿勢”が大切
株式投資は「短期間でお金が増える魔法」ではありません。
だからこそ、本でしっかり基礎を学び、少額からコツコツ積み上げていく姿勢が、公務員のような安定志向の方にこそ合っています。
私自身も、本を読むことで「知らないことが怖い」から「分かってきたから少しやってみよう」に変わりました。
知識があれば、焦らず、周囲に流されず、自分の判断で動けます。
【関連記事】
【公務員のための株式投資入門】初心者でも失敗しない始め方・注意点を元公務員FPがやさしく解説
公務員が失敗しない個別株の選び方|初心者向け実践ガイド【元公務員FP体験談】