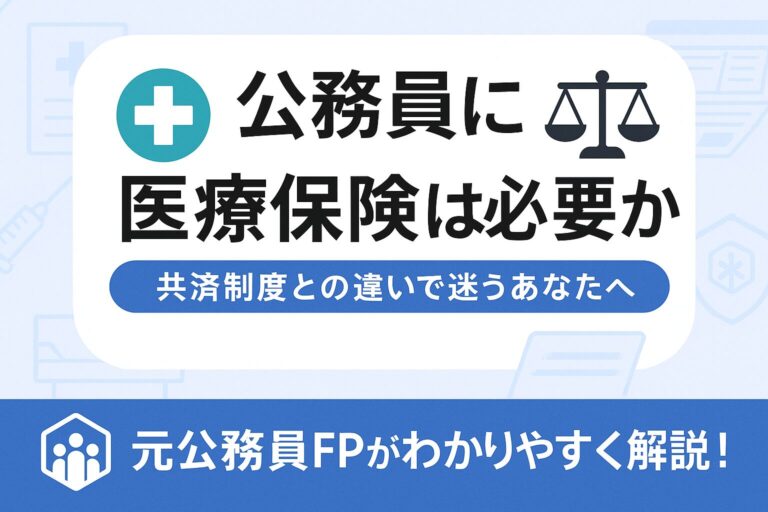「公務員って医療保険、入った方がいいの?」
そんな疑問を持つ方は少なくありません。
実は私自身も、県職員時代に同僚と「医療保険って無駄じゃない?」と何度も話し合ったことがあります。
また、医療保険に関する書籍も読み、自分が入っている保険って本当に必要かなと検討したこともあります。
結論から言えば、公務員にも医療保険が必要なケースと、必要ないケースの両方があります。
なぜなら、公務員には民間企業にはない「共済組合」や「高額療養費制度」といった手厚い医療保障制度がある一方で、貯金が少ない方や家族に扶養者がいる場合は、保険の役割が大きくなるからです。
この記事では、
– 医療保険の仕組みや種類
– 公務員の医療保障制度との違い
– 保険が必要なケース・不要なケースの判断基準
– 私自身の体験談や、実際に起こった公務員の医療リスク
– 医療保険のメリット・デメリット
– 入るならどんな保険?比較ポイント
などを、FP資格を持つ元県職員の視点からわかりやすく解説していきます。
迷っているあなたに、「結局どうすればいいのか」が見える記事になるよう、一次情報・体験談を交えながら丁寧にまとめました。
公務員に医療保険は必要?まず結論から

「公務員に医療保険は必要か?」という問いに対する結論は、「人によって必要なケースと不要なケースがある」です。
ただし、公務員という立場上、民間企業に勤める人より“医療保険が不要なケースが多い”のは事実です。
なぜなら、公務員は「共済組合」や「高額療養費制度」「病気休暇制度」など、手厚い医療保障制度に守られているからです。
たとえば、入院費が高額になっても、自己負担の上限は「高額療養費制度」により決まっています。
さらに、療養中の給与も「病気休暇」や「傷病手当金」で一定期間カバーされるため、経済的なリスクが大幅に軽減されています。
実際、私が県職員として勤務していたとき、長期入院を経験した上司がいましたが、医療費の自己負担は上限で止まり、給与も保障されていたため、「民間保険に頼らなくても生活に困らなかった」と話していました。
一方で、すべての公務員が医療保険に入らなくて良いわけではありません。
次のような方は医療保険が有効に働くことがあります。
まだ若くて貯金が少ない
子どもがまだ小さく、家計に余裕がない
- 自分自身・子供が病弱
- シングルマザー・シングルファザー
退職後に医療費がかさんだ場合の備えをしたい
がんや生活習慣病の家系で、不安がある
医療保険は、単に「損か得か」では測れない“安心料”としての側面もあります。
自分や家族にとって、もしものときの「備え」が必要だと感じるなら、少額の医療保険をかけておくのは一つの選択肢です。
つまり、
「ある程度の貯金があり、制度の内容を理解している人」→ 医療保険は“不要”の可能性が高い
「備えが少なく、もしもの出費が不安な人」→ 医療保険は“必要”な可能性がある
という考え方です。
本記事では、こうした判断ができるように、「医療保険の仕組み」や「公務員制度のカバー範囲」、そして「実例」や「判断基準」を網羅的に解説していきます。
医療保険の基本|どんな仕組みで、どんなときに使える?
まずは、そもそも「医療保険とはどんなものか?」を簡単に整理しましょう。
医療保険とは、病気やケガによって入院・手術などの医療費が発生したときに、保険金が支払われる仕組みのことです。
医療費は健康保険(または共済組合)によって3割負担に抑えられていますが、それでも入院が長引いたり、先進医療を受けたりすれば、高額になるケースもあります。
そんなとき、医療保険に入っていれば、あらかじめ定めた給付金(たとえば入院1日5,000円、手術1回10万円など)が支払われ、経済的な不安を軽減できるのです。
医療保険の種類と保障内容
医療保険は、大きく分けて以下の2種類に分類されます。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 定期型 | 保険期間が10年、20年など決まっていて、満了時に見直しが必要。保険料は比較的安い。 |
| 終身型 | 一生涯の保障。保険料はやや高いが、将来の見直しが不要。 |
また、保障内容もさまざまです。
入院給付金:1日あたりいくら支払われるか(例:5,000円/日)
手術給付金:1回の手術につき定額(例:10万円)
通院給付金:入退院後の通院日数に応じて支払い
先進医療特約:技術料の全額(数十万円〜数百万円)を保障
一時金特約(がん保険など):がんと診断されたら100万円支給など
このように、医療保険は「入院・手術」などのイベントが起きたときに支払われる“給付型”の保険であり、生命保険(死亡保障)とは別物です。
月額保険料の相場と支払い期間
保険料は、年齢・性別・保障内容によって異なりますが、以下が目安です。(私の加入していたネット保険の例)
| 年齢 | 月額保険料(終身型・入院5,000円・手術給付あり) |
|---|---|
| 20代 | 1,500円〜2,500円程度 |
| 30代 | 2,000円〜3,000円程度 |
| 40代 | 3,000円〜4,500円程度 |
| 50代以降 | 4,500円〜6,000円以上 |
支払いは「65歳まで払う」「終身払いにする」など選べますが、途中解約すると返戻金はほとんどない(掛け捨て型が多い)点には注意が必要です。
公務員の医療保障制度|ここまでカバーされている
公務員には、一般の会社員とは異なる「共済組合」という独自の健康保険制度があり、その保障内容は非常に手厚いのが特徴です。
「医療保険は本当に必要なのか?」を考える際、この共済組合による医療保障の内容を正しく理解しておくことが欠かせません。
ここでは、公務員が加入する共済組合の医療保障制度について、具体的に解説します。
共済組合の給付制度とは?
共済組合は、公務員や一部の私立学校教職員が加入する医療保険制度です。
民間の健康保険組合に比べ、以下のような独自の給付制度があります。
高額療養費の支給:自己負担が高額になった場合、独自の基準で追加の給付あり
一部負担金払戻金:高額療養費制度の自己負担上限を超えた分がさらに還付される
出産費用や葬祭費なども手厚い
つまり、民間の健康保険では自己負担が約8万円程度になる入院でも、共済組合ではさらに負担が減る可能性があるのです。
また、定期健康診断やがん検診などの予防医療も手厚く、費用補助が出る場合もあります。
【支給事例】
70歳未満の組合員(標準報酬月額34万円)が入院し、医療費が100万円かかった場合↓
療養の給付 700,000円
高額療養費 212,570円
一部負担金払戻金 62,400円
最終的な自己負担額 25,030円
(参考:地方職員共済組合HP)
高額療養費制度・傷病手当金・病気休暇
すべての健康保険制度に共通する「高額療養費制度」により、医療費が高額になっても自己負担の上限が決まっています。
たとえば、月の医療費が100万円かかっても、実際の自己負担は以下のように抑えられます。
例:年収約500万円の公務員が入院・手術 → 自己負担は約8万円前後/月(+食事代など)
また、病気やケガで働けなくなった場合も、「病気休暇制度」や「傷病手当金」が支給され、半年~2年程度は収入がゼロになることは基本的にありません。
【病気休暇】:原則、最大90日(自治体により異なる)、給与全額支給
- 【休職】:最初の1年間、給与の80%支給(国家公務員の場合)
【傷病手当金】:最大1年6ヶ月、給与の約6割相当が支給(地方公務員は制度のない自治体も)
私が県職員だったころ、体調を崩して長期で休んだことや耳の手術で1週間近く入院したことがあります。
その際も病気休暇が適用され、給与は全額支給されました。
民間であれば有給を使い切ると欠勤扱いになったり、給与が減ることを考えると、公務員の保障制度は極めて強力です。
退職後の医療保障
退職後は共済組合を脱退し、国民健康保険または任意継続組合員(最大2年)として医療保障を受けることになります。
このように、公務員の現役時代はもちろん、退職後の一定期間まで医療保障は安定しており、「医療保険がなくても困らない」という意見が出やすいのも納得できます。
医療保険が「必要な人」と「不要な人」の違い
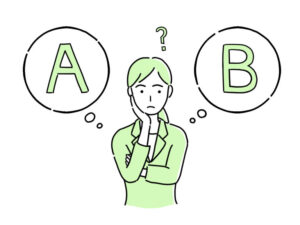
公務員の医療保障制度は非常に手厚いため、「医療保険はいらないのでは?」と思う方も多いでしょう。
しかし、実際にはライフスタイルや家族構成、資産状況などによって必要性は大きく変わります。
ここでは、「医療保険が必要な人」と「不要な人」の違いを、具体的な視点から解説します。
医療保険が“不要”な人の特徴
以下のような方は、医療保険に加入しなくても共済制度や自己資金で十分対応できる可能性が高いです。
貯金がある(目安として100万円以上)
扶養家族がいない、または家計に余裕がある
20代〜40代で健康状態が良好
保障制度(高額療養費制度・病気休暇制度など)を理解している
「確率的に損をする保険よりも、自分で備える方が合理的」と考える人
- お金の勉強が好きな人
たとえば、私自身は30代前半で医療保険を見直し最も安いプランに切り替えました。
本当は全て解約したかったのですが、営業の人にどうしてもお願いと引き止められまして、、、(苦笑)
仮に入院しても「高額療養費制度+附加給付」で医療費は月数万円程度。
数日程度の病気であれば病気休暇で給与も減らず、家計にダメージはないと判断したためです。
このように、自己防衛力が高い人にとっては、医療保険は「不要なコスト」になり得ます。
医療保険料の分をそっくり「貯金」や「投資」に回した方がよっぽど実益になると私は思います。
結果的にですが、実際私の場合、手術や入院は1回あっただけなのでもらった給付金よりも支払ってきた保険料のほうが圧倒的に多いです。(結果論ですが)
その分を貯金に回しておけばよかったと40歳になって後悔しています。
医療保険が“必要”な人の特徴
一方、以下のような人は、医療保険が精神的・経済的な安心材料になる可能性があります。
貯金が少ない(50万円未満)
共働きではなく、家計を一人で支えている
小さな子どもがいる、または親の介護などの扶養責任がある
がんや糖尿病などの家族歴があり、将来が不安
- 極度な心配性な人
お金のことに関して無頓着な人(お金の勉強が面倒くさい人)
また、退職後の医療費増加を不安視する人や、万が一の際に家族に迷惑をかけたくないと考える人も、医療保険を“安心料”として評価する傾向があります。
「損得」ではなく「安心度」で考える
医療保険の判断は、「掛けた保険料に見合った給付金がもらえるか?」という損得計算では測れません。
なぜなら、保険は本来、起きるかわからないリスクに対して備える“安心料”だからです。
特に、心配性な方や、家計の収支がカツカツな方にとっては、毎月数千円で安心を買えるなら、それが“精神的リターン”となることもあります。
体験談|医療保険に入っていて助かった/入ってなくて後悔した話
医療保険の必要性は、「実際に病気やケガを経験したかどうか」で感じ方が大きく異なります。
ここでは、私自身や周囲の公務員仲間が体験したリアルなエピソードを通して、医療保険の価値についてお伝えします。
【体験談①】保険に入っていてラッキーだった(筆者体験談)
私自身の話です。元々、先天性難聴(左耳のみ)であった私は、あるとき治せる手術があることを知り、1週間程度入院・手術をしました。
そのときは民間の医療保険に加入しており、入院5,000円/日、手術給付20万円程度という保障内容。結果的に、
入院7日×5,000円=35,000円
手術給付金=200,000円
合計235,000円の保険金が給付されました。
入院中は食事代や差額ベッド代、雑費などで予想以上に出費がかさみましたが、結果的に高額療養費制度と医療保険のおかげでかなりのプラスとなり、プチボーナスとなりました。
【体験談②】保険に入っていなくて少し後悔した(40代・男性)
こちらは上司の話です。
上司は公務員時代、医療保険には加入していませんでした。
「共済組合があるし、カラダが丈夫な方だから問題ない」と思っていたそうです。
独身貴族を謳歌していた人で、金使いが荒かったので、貯金がほとんどない人でした。
ところが40代半ばのとき、腰椎ヘルニアを発症して、10日間の入院+ブロック注射治療を受けることになりました。
治療費自体は高額療養費制度のおかげで約8万円で済みましたが、入院中の差額ベッド代(1日3,000円×10日)や、通院交通費・雑費・仕事の調整など、予想以上の出費と負担がありました。
「たしかに医療費自体は少なかったけど、雑費がかさむのと、精神的な余裕がなかったのがきつかった。保険に入っておけばよかったかな…」と感じたと言っていました。
結論:保険の“金額”より“気持ちのゆとり”
このように、医療保険の価値は「経済的な損得」だけでなく、「安心感」や「急な出費への対応力」にも直結します。
いざというときに「あってよかった」と思える
思いがけない出費も“お守り代”としてカバーできる
経済的な余裕がないときに、保険金が精神的な支えになる
こうした実体験を踏まえると、「医療保険は不要!」と一概には言い切れないと、私は今でも感じています。
公務員が医療保険に入る前にチェックすべきポイント5つ
医療保険に加入するかどうかを判断する際、ただ「入っておけば安心」という理由だけではなく、自分自身の状況を冷静に整理することが大切です。
とくに、公務員のように手厚い保障制度に守られている立場であればなおさら、必要性を慎重に見極めるべきです。
ここでは、医療保険に入る前に必ずチェックしておきたい5つのポイントを紹介します。
① 自分の貯金額(生活防衛資金)が十分か?
医療保険の最大の役割は「医療費の急な出費への備え」です。
つまり、すでに手元に医療費に充てられる貯金がある人にとっては、保険の必要性は相対的に低くなります。
たとえば、1回の入院で自己負担が8万円前後としても、生活防衛資金が100万円程度あれば、多くのケースに対応可能です。
② 家族構成や収入の安定性
一人暮らしで生活に余裕がある方
共働きでパートナーの収入がある家庭
このような場合は、収入のストップに対する不安が少なく、医療保険の優先度は下がります。
一方で、
子どもがいて教育費がかかる
- 病弱でよく体調を崩している
配偶者が専業主婦(主夫)で、収入源が自分だけ
- シングルマザー&シングルファザー
という場合は、入院・手術で収入が減ったときの影響が大きいため、“念のための保険”が有効に働くケースもあります。
③ 勤務先の共済組合・制度を把握しているか
公務員といっても、所属する共済組合によって給付内容は微妙に異なります。
また、自治体によっては病気休暇の日数制限が厳しいことも。
加入中の共済組合の【附加給付の内容】や【傷病手当制度】などを一度確認しておきましょう。
✅公式サイトや人事課に確認すればすぐに把握できます。
④ 健康状態と既往歴
将来的に入院や手術のリスクが高いと感じる方は、早いうちから保険に入っておく選択もアリです。
特に、次のような方は要検討です。
家族にがん・糖尿病・心疾患の人がいる
過去に入院・手術の経験がある
健康診断で指摘を受けたことがある
保険は健康なうちでないと加入できないか、条件付き(部位不担保など)になるので、慎重な見極めが必要です。
⑤ どのくらいの“安心感”を求めるか?
最後は、完全に価値観の問題です。
たとえば、
数万円の出費でも精神的に不安になる人
「損をしてもいいから、安心を買いたい」人
- とにかく心配性な人
こうした人にとっては、医療保険は合理性以上に“心のゆとり”を与えるツールです。
逆に、「確率的に損な商品はイヤ」という考えなら、保険より貯金・投資を優先する選択肢も有効です。
このように、医療保険の加入前には制度・資産・家族状況・健康・価値観など、多角的にチェックしてから判断することが大切です。
医療保険のメリット・デメリットを整理しよう
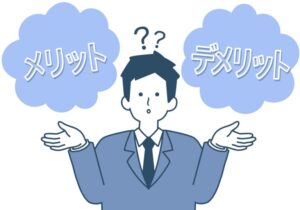
医療保険に入るかどうかを判断するうえで、「メリット」と「デメリット」を整理しておくことはとても重要です。
「安心だから入る」「無駄だから入らない」といった感覚的な判断ではなく、制度の特徴を理解したうえで、自分に合った判断をするための材料になります。
以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。
医療保険のメリット
① 突然の出費に備えられる
入院や手術などの突発的な医療費は、家計にとって大きな負担になります。
特に若いうちは貯金が少ないケースも多く、急な10万円超えの出費に備えられるのは大きな安心材料です。
② 精神的な安心感が得られる
病気になったとき、「保険があるから大丈夫」と思えること自体が、強いメンタルサポートになります。
特に子育て中の家庭や、一家の大黒柱として働いている方にとっては、“心の保険”としての役割も大きいです。
③ 医療制度だけではカバーしきれない費用にも対応
差額ベッド代、通院費、交通費、付き添いの家族の負担など、公的医療制度ではカバーされない“間接的な医療費”が意外と多いもの。
医療保険の給付金は、こうした雑費にも柔軟に使えます。
④ 若いうちに加入すれば保険料が安く済む
保険は、健康状態がよく若いうちに加入すると、終身で見たときの保険料が抑えられます。
年齢を重ねてからでは、持病や既往歴によって加入が難しくなることもあります。
医療保険のデメリット
① 経済的に“損”になる可能性が高い
医療保険は確率的に見ると、「保険料の総額 > 給付金」となることが多く、損をする可能性が高い商品です。
とくに共済組合が手厚い公務員の場合、保険を使わないまま何十年と払い続けるケースも少なくありません。
② 入っていてもすべての病気に対応できるとは限らない
保険には「対象外」の病気や、「○日以上の入院でないと給付されない」などの条件が設定されていることもあります。
万能ではないという点を理解しておく必要があります。
③ 解約返戻金がない(掛け捨て)
多くの医療保険は掛け捨て型で、途中で解約しても返ってくるお金は基本的にゼロです。
「もったいない」と感じて解約する人も少なくありません。
④ 保険料の負担が家計を圧迫することも
月5,000円程度の保険料でも、30年払い続ければ180万円になります。
「この金額を貯金や投資に回した方が良かった」と感じる人もいます。
以上のように、医療保険には安心や備えといった利点がある一方で、「損をする可能性」や「制度の過信」による誤解もあります。
自分の価値観と照らし合わせて、必要かどうかを“納得して判断する”ことが何より大切です。
医療保険に入るならこの方法|商品選びのコツとおすすめ比較
ここまで読んで「やはり不安だし、医療保険に入っておこうかな」と思った方に向けて、公務員に適した医療保険の選び方と、おすすめの比較ポイントを解説します。
医療保険は「何となく有名な会社を選ぶ」「安いからこれにした」という決め方だと後悔しがち。
自分に合った保障内容をしっかり選ぶことが、後の安心感に直結します。
共済・民間のどちらを選ぶべき?
まず、公務員であれば検討すべきは以下の2パターンです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 共済(自治体職員共済・教職員共済など) | 割安でシンプルな保障。団体加入なので手続きも簡単。 |
| 民間保険(生命保険会社・ネット保険など) | 商品バリエーションが豊富。特約で自由にカスタマイズ可能。ネット保険は安い。 |
共済は毎月の保険料が抑えられており、「最低限の保障でいい」という方にはコスパが高い選択肢です。
一方、がんや三大疾病など特定リスクに重点を置きたい場合や、先進医療を手厚くカバーしたい場合は、民間保険が有利です。
保険商品を選ぶときの5つのチェックポイント
① 入院給付金額と支払い限度日数
→ 1日5,000円 or 10,000円、日数は60日 or 120日型が主流。
自分の希望と照らし合わせて。
② 手術・通院・先進医療の特約
→ 手術回数や通院時の給付があると実用的。
先進医療特約は一律200万円まで保障されるケースが多く、保険料も月100円〜200円と割安。
③ 保険料の払込期間と更新方式
→ 終身払い vs 65歳払込終了など。
更新型(10年更新など)は途中で保険料が大きく上がることもあるので要注意。
④ 解約返戻金の有無(貯蓄型か掛け捨てか)
→ 基本的には掛け捨て型が多い。
貯蓄型を選ぶと保険料が高額になるため、公務員には掛け捨て+貯金で備える戦略が合理的。
⑤ ネット保険 or 対面販売か
→ ネット保険(楽天生命、メディケア生命など)はシンプル&格安。
ただし、自分で比較・理解する力が必要。
対面型(県民共済・大手保険会社)は説明が丁寧だが割高傾向。
公務員に人気の医療保険(2025年版)
以下は、共済と民間保険で人気のあるプラン例です。
| 保険商品名 | 特徴 | 月額目安(30代・男性) |
|---|---|---|
| 都道府県民共済(入院2型) | 掛け金2,000円〜の格安保障 | 2,000円~ |
| コープ共済「たすけあい」 | シンプル&柔軟な保障設計 | 2,000円~ |
| 楽天生命 スーパー医療保険 | ネット完結・先進医療保障あり | 約1,700円~ |
| チューリッヒ生命 終身医療保険プレミアムZ | 幅広い保障から自由に選べる終身医療保険 | 約1,200円~ |
| SBI生命 終身医療保険Neo | とにかく格安 | 約1,100円~ |
※あくまで目安。年齢・性別・プランで変動します。(2025年7月25日調査)
加入・見直しのタイミング
20代〜30代のうちに終身タイプで入ると保険料が抑えられる
結婚・出産・住宅購入などのライフイベント時は見直しチャンス
職場の福利厚生制度と重複しないかを確認
加入する前に、無料の一括見積もりサイト(保険の窓口、保険市場など)を活用するのもおすすめです。
ネットでシミュレーションして、複数社を比較することが失敗を防ぐコツです。
まとめ|「安心を買う」意味を考えて自分で判断しよう
ここまで、公務員が医療保険に入るべきかどうかを、制度面・経済面・体験談・選び方など多角的に解説してきました。
改めてポイントを整理すると、以下のようになります。
✅ 公務員は医療保障が手厚い
共済組合の附加給付、高額療養費制度、病気休暇などがあり、医療費負担や収入減少リスクが低い
貯金がある程度あり、制度を理解しているなら、保険に頼らずとも十分対応できる可能性が高い
✅ それでも医療保険が必要な人もいる
貯金が少ない
扶養家族がいる
もしもの出費が精神的に不安
退職後の医療費に備えたい
このような方にとって、医療保険は“経済的損得”よりも“精神的なゆとり”を得る手段になります。
✅ 「損しないこと」より「安心して暮らせること」が大切
保険というのは本来、「万が一」に備えて“安心を買う”ものです。
確率的に損か得かを計算することも大事ですが、それだけでは割り切れない「価値」もあります。
例えば、
保険に入っていたおかげで、入院中も気持ちが楽だった
医療費の心配をしなくて済んだ
家族が「入っててよかったね」と言ってくれた
こうした“安心感”は、数字には表せません。
最後にお伝えしたいのは、「正解は人それぞれ」ということです。
家族構成
収入状況
貯金額
健康状態
性格や価値観
これらを総合的に考えて、「自分にとって納得できる判断」をすることが、後悔のない選択につながります。
【関連記事】
公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】