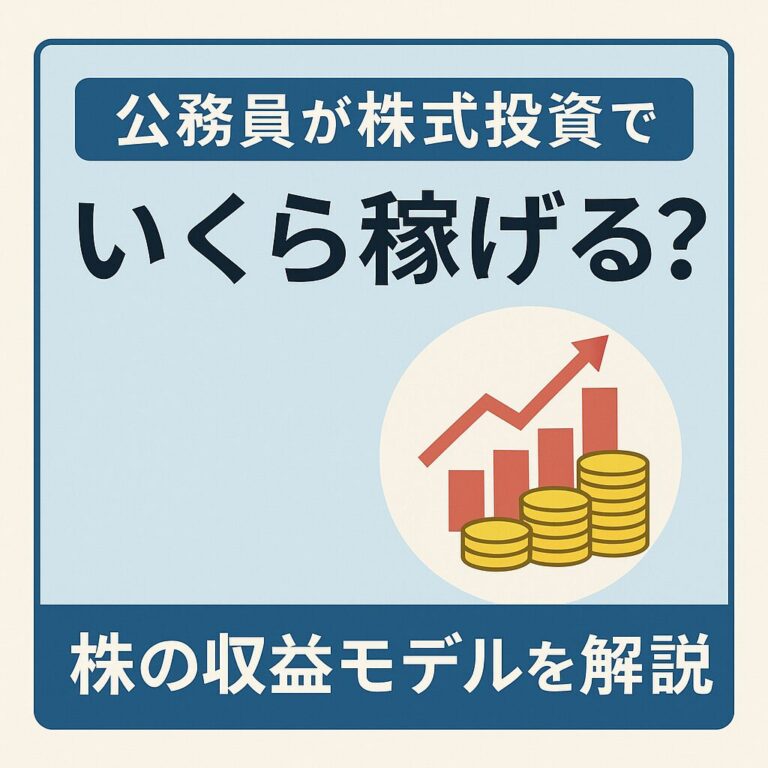株式投資は、公務員でも合法的に行える資産運用の一つです。
しかし「実際にどれくらい稼げるのか?」は、投資信託を選ぶか、個別株を選ぶか、投資額や運用期間によって大きく異なります。
たとえば投資信託なら、市場全体に分散して運用するため、安定的に年数%〜10%程度のリターンを狙える可能性があります。
一方で個別株の場合は、銘柄選び次第で結果が大きく変わります。
なかには数年で株価が2倍、3倍、さらには10倍以上(テンバガー)になる銘柄も存在します。
ただし、その分リスクも高く、銘柄選定や売買タイミングを誤れば大きな損失を抱えることもあります。
この記事では、「公務員が株式投資でいくら稼げるか?」をテーマに、
投資信託の収益シミュレーション例
個別株の収益シミュレーション例(複利運用・テンバガー事例を含む)
双方のリスク、注意点、そして私自身の実体験
を具体的な数字と事例で元公務員FPがわかりやすく解説します。
読み終える頃には、自分に合った投資スタイルと現実的な収益目安が見え、安心して資産形成を始めるための判断材料が手に入るはずです。
投資信託(インデックス型・アクティブ型)の収益シミュレーション

投資信託は、複数の株式や債券を組み合わせて運用する金融商品です。
公務員にとっては、個別株よりもリスクを抑えながら資産を増やしやすい選択肢といえます。
ここでは、インデックス型とアクティブ型、それぞれの運用結果をシミュレーションします。
インデックス型の収益例
インデックス型は、日経平均やTOPIX、S&P500など市場全体の動きに連動するタイプです。
過去の実績をみると、長期的には年平均3〜7%程度のリターンが期待できます。
【シミュレーション(年利5%想定)】
月1万円を20年間積み立て
年利5%で運用すると、元本240万円 → 411万円(+171万円)
年利7%なら、元本240万円→521万円(+281万円)
この結果から分かるように、少額でも長期間積み立てることで、複利効果により元本の1.5〜2倍近くまで資産を増やせる可能性があります。
ただ、あくまで可能性で、もうしかしたら元本を割るリスクもあります。
アクティブ型の収益例
アクティブ型は、市場平均を上回るリターンを狙って運用する投信です。
成功すれば年8〜10%以上のリターンを出すこともありますが、手数料が高く、成績が安定しないファンドも多いです。
シミュレーション(年利10%想定)
月1万円を20年間積み立て
元本240万円 → 759万円(+519万円)
ただし、全てのアクティブファンドがこの成績を出せるわけではなく、平均するとインデックス型に劣るケースも多いため、過去実績や運用方針をよく確認して選ぶ必要があります。
このように投資信託は、堅実に資産を増やしたい公務員に向いていますが、次に紹介する個別株投資は、もっと大きなリターンを狙える可能性があります。
個別株投資の収益シミュレーションとテンバガー事例
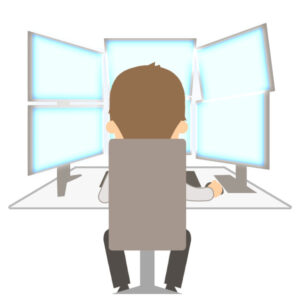
個別株投資は、特定の企業の株式を直接購入する方法です。
企業の業績や成長性に投資するため、投資信託よりもリターンの幅が大きくなる反面、損失の可能性も高まります。
平均的な個別株投資のリターン
過去のデータによると、日経平均採用銘柄全体の長期的な年平均リターンは約5〜7%程度です。
しかし、個別株の場合、選んだ銘柄の成績が市場平均を大きく上回ることもあれば、大きく下回ることもあります。
【シミュレーション(年利7%想定)】
100万円を20年間運用 → 404万円(+304万円)
年利10%なら → 733万円(+633万円)
この数字だけ見ると投資信託と似ていますが、個別株は選び方次第で結果が大きく変わります。
数倍数十倍になる高成長銘柄(テンバガー)の可能性
「テンバガー(10倍株)」と呼ばれる、株価が10倍以上になる銘柄は、長期投資家の夢の存在です。
例えば、
ファーストリテイリング(ユニクロ):20年間で株価約23倍
ソフトバンクグループ:20年間で約19倍
セリア:20年間で約31倍
- レザーテック:5.6年間で約166倍
- メタプラネット:1年で約135倍
このほかにも、5~10年で数倍になった銘柄は調べると結構あることが分かります。
もちろん、こうした銘柄は事前に見極めるのが難しく、運も大きく関わります。
また、株価が急上昇した後に暴落するケースもあるため、利益確定のタイミングも重要です。
私の経験談
私はライザップの株を持っていますが、コロナ禍で暴落し、一時資産が-50%まで(資産が半分)になったこともあります。
しかし、そこで耐えぬき、数年後には株価が3倍程度まで上昇しました。
結局、まだまだ株価は上がると欲をかいているうちに、みるみる株価は下がっていき、ほぼ元通りになったという経験をしました。
この経験から、大化け株を狙うなら下がった時は売らずに我慢をすることが大事、欲をかきすぎないことも大事だと実感しました。
このように、個別株は「大きく稼げる可能性」も「大きく損する可能性」も高い投資です。
次は、投資信託と個別株の収益性やリスクを比較し、どちらが公務員に向いているかを整理します。
投資信託と個別株の比較|収益・リスク・時間効率
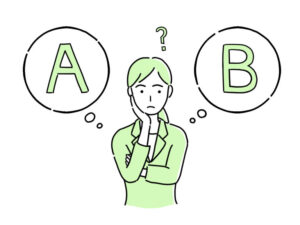
投資信託と個別株は、どちらも株式市場に投資する手段ですが、性質や結果は大きく異なります。
ここでは、収益性・リスク・時間効率の3つの観点から比較します。
比較表(概要)
| 項目 | 投資信託 | 個別株 |
|---|---|---|
| 年平均リターン目安 | 3〜7%(アクティブ型で8〜10%も) | 5〜7%(平均)〜数百%(成功時) |
| リスクの大きさ | 中(市場全体の変動) | 高(企業業績やニュースに左右) |
| 商品選びに必要な時間 | 小(積立設定後は放置可) | 中〜高(企業分析・売買判断が必要) |
| 分散投資のしやすさ | 高(数百銘柄に分散) | 低(自分で複数銘柄を買う必要) |
| 大化け株の可能性 | ほぼなし(市場平均に連動) | 高(数倍〜10倍以上の可能性あり) |
| 向いているタイプ | 安定志向・ほったらかし投資派 | 積極的・分析好き・高リスク容認派 |
収益性の違い
「投資信託」は市場全体の成長を取り込み、安定的に資産を増やせる可能性が高いです。年5〜7%程度の複利運用で、20〜30年後には元本が2倍以上になることも珍しくありません。
「個別株」は平均的には投資信託と同程度ですが、選んだ銘柄によっては大きく差がつきます。うまくいけば短期間で数倍以上のリターンを得られますが、逆に半分以下になることもあります。
リスクの違い
「投資信託」は分散投資されており、1社の業績悪化が全体に与える影響は小さいです。
「個別株」は1社の悪材料(不祥事、業績不振など)で株価が急落するリスクが高く、集中投資は特に注意が必要です。
時間効率の違い
「投資信託」は購入後の管理がほぼ不要で、仕事が忙しい公務員にも向いています。
「個別株」は企業研究、決算チェック、売買判断などに時間を割く必要があります。忙しい時期は放置しがちになり、機会損失や損切り遅れのリスクもあります。
このように両者は特性が異なるため、公務員の場合は「投信で土台を作り、個別株で上乗せを狙う」ハイブリッド型が現実的です。
リスクを理解する|公務員ならではの注意点

公務員が株式投資を行う場合、民間会社員とは異なる立場やルールがあるため、一般的な投資リスクに加えて職務上の制約や制度面の注意点も意識する必要があります。
一般的な投資リスク
価格変動リスク
株価は景気や金利、為替、企業業績など多くの要因で上下します。短期的な暴落も珍しくなく、元本割れの可能性があります。流動性リスク
出来高の少ない銘柄は、売りたいときに売れない、または希望価格で売れない場合があります。特に地方上場企業や小型株は要注意です。集中投資リスク
特定銘柄に資金を集中させると、その企業の悪材料で資産が大きく目減りする危険性が高まります。
公務員ならではのリスク・制約
インサイダー取引の禁止
職務で知り得た未公開情報を利用して株取引を行うことは、金融商品取引法違反となり、懲戒処分や刑事罰の対象になります。特に自治体や国の事業関連企業、発注先企業の株は慎重に扱うべきです。勤務時間中の売買禁止
当然ですが、勤務時間中に株売買や価格チェックを行うのは懲戒対象になることがあります。売買は必ず勤務外で行いましょう。資産公開義務の可能性
一部の役職(特定ポストや高位職)では、資産公開制度の対象になる場合があります。多額の株式保有は公開対象に含まれることがあります。副業規制との関係
株式投資は「資産運用」であり副業には当たりませんが、デイトレードのように頻繁に売買して多額の利益を得る場合、勤務態度や職務専念義務の観点から問題視される可能性もあります。
このように、公務員は投資リスクと合わせて職務上の信用リスクも考慮しなければなりません。
Q&A:公務員からよくある質問と回答

ここでは、公務員の方からよくいただく株式投資に関する疑問に、わかりやすくお答えします。
Q1:月いくらから始められますか?
A:株式投資は100円単位の投資信託積立からでも始められます。
少額であれば家計への負担も少なく、経験を積みながら徐々に投資額を増やせます。
個別株の場合は1株から購入できる「単元未満株(S株・ミニ株)」を利用すれば、数千円〜1万円程度で始められます。
Q2:NISAを使うとどれくらい増やせますか?
A:仮に月3万円(年36万円)を年利5%で20年間運用した場合、
元本:720万円
運用益:513万円
合計:約1,233万円
NISAを使えば運用益が非課税になるため、この513万円分の税金(約104万円)を節約できます。
さらに年利7%や10%で運用できれば、利益額は大きく増えます。もちろん資産が減るリスク(元本割れ)はあります。
Q3:特定の銘柄は狙い目ですか?
A:一概には言えません。公務員は職務関連企業の株は避けるべきですし、短期的な値動きに惑わされると失敗しやすいです。
銘柄選びに時間を割けない場合は、まずはインデックス型投信で市場全体に投資し、余剰資金で個別株を少額買う方法が現実的です。
Q4:大化け株を狙ってもいい?
A:もちろん可能ですが、資産全体の一部で行うのがおすすめです。
例えば資産の80%は安定的な投資信託で運用し、残り20%で成長株を狙うと、リスクを抑えつつ高リターンの可能性を残せます。
【ワンポイント】
株式投資の正解は人によって異なります。
投資額・期間・リスク許容度を考え、自分に合った配分を見つけることが大切です。
まとめと次のステップへのご案内
この記事では、公務員が株式投資で「いくら稼げるのか」を、投資信託と個別株それぞれのシミュレーションや実例を交えて解説しました。
本記事のまとめ
投資信託
年平均リターンは3〜7%(アクティブ型で8〜10%も)
月1万円の積立でも20年で約1.5〜2倍に資産が増える可能性
時間をかけずに分散投資でき、公務員向き
個別株
平均リターンは投信と同程度だが、銘柄によっては数倍〜10倍以上も
高リスク・高リターンで、銘柄選びと売却タイミングが重要
成功例もあるが、損失リスクも大きい
公務員ならではの注意点
インサイダー取引禁止、勤務時間中の売買禁止
職務関連企業の株は避ける
資産公開制度やコンプライアンスを意識する
関連記事
- 【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説
- 【2025年最新】公務員のiDeCo完全ガイド|初心者向け始め方・メリット・デメリット・注意点を元公務員FPが解説
- 公務員のための株式投資(投資信託)の選び方【元公務員FP経験談&解説】
- 公務員が失敗しない個別株の選び方|初心者向け実践ガイド【元公務員FP体験談】
次に取るべき行動
自分のリスク許容度を把握(損失をどこまで受け入れられるか)
投資信託か個別株かを選択(または両方を組み合わせる)
NISAやiDeCoなど非課税制度を最大限活用
少額から始めて経験を積む
株式投資は、資産を増やす強力な手段ですが、「どれくらい稼げるか」よりも「リスクをコントロールできるか」が成功の鍵です。
まずは少額から始め、時間を味方につけて着実に資産を増やしましょう。