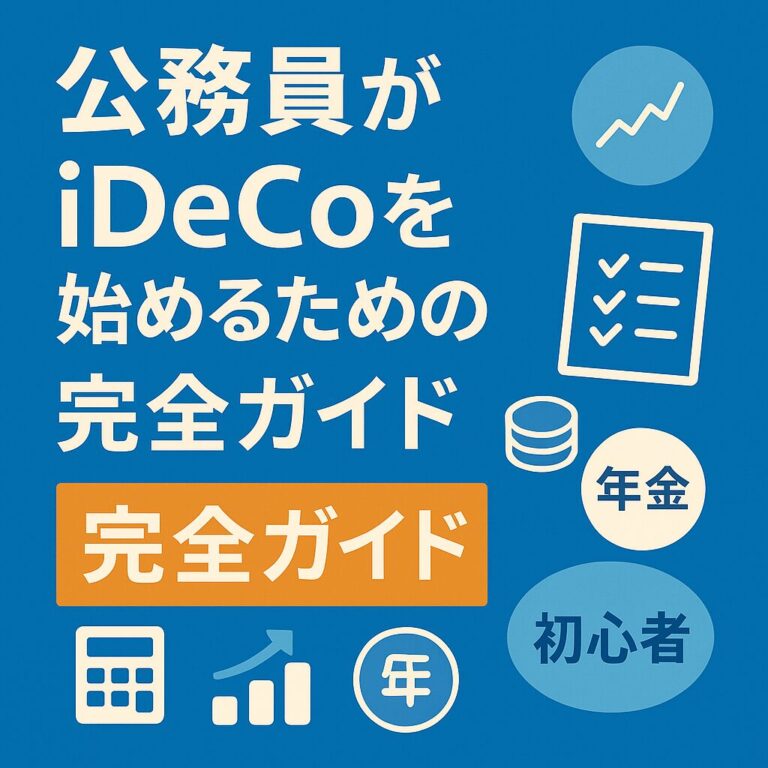「公務員だけど、iDeCoって本当に始めて大丈夫?」
「何から始めればいいのか、金融機関選びもよく分からない…」
「メリット・デメリットを正直に知りたい」
そんな悩みを抱える現役公務員・公務員志望者、そして資産運用が初めての方に向けて――
本記事では『公務員×iDeCo』に完全特化し、2025年最新の情報で初心者でも分かるようやさしく丁寧に解説します。
私は元県職員で、実際にiDeCoの運用経験もあり、資産形成に悩んだリアルな体験談も交えながらお伝えします。
「税制優遇って本当にお得なの?」「始めるリスクやデメリットは?」
――こうした疑問もすべてカバー。上位サイト以上に実践的かつ現場目線で分かりやすさを徹底します。
「2024年から新NISAも始まった今、iDeCoとの使い分けは?」
「公務員が後悔しないために本当に知るべきことは?」
初心者の方もこの記事を読むだけで、
・iDeCoの仕組み
・公務員の具体的な始め方
・メリット/デメリット
・失敗しないコツ
・よくある疑問や注意点
まで、まるごと一気に理解できる内容になっています。
ぜひ最後までじっくり読んで、不安や疑問を解消し、あなたの資産形成の第一歩を一緒に踏み出しましょう!
iDeCo(イデコ)とは?公務員でもできる?

iDeCo(イデコ)は「個人型確定拠出年金」という、将来のために自分で年金を作る仕組みです。
毎月決まった額を積み立てて、自分で選んだ運用商品でお金を増やし、60歳以降に年金や一時金として受け取ることができます。
最大の魅力は、掛金が全額所得控除となり、節税メリットが大きいこと。
投資で得た利益も非課税です。
iDeCoの基本概要
iDeCoは「自分でつくる年金」。公的年金(厚生年金や共済年金)だけでは将来が不安…という方にとって、資産形成の強い味方です。
原則として20歳〜65歳未満であれば、会社員・自営業者・主婦(夫)・公務員まで、ほぼ誰でも加入できます。
【iDeCoの仕組みまとめ】
毎月一定額(5,000円~上限あり)を積み立て
自分で金融機関・商品(元本確保型/投資信託など)を選ぶ
60歳以降に「年金」または「一時金」として受け取る
掛金は全額所得控除=所得税・住民税が軽減
運用益も非課税
公務員もiDeCoに加入できる?過去との違い
実は、公務員のiDeCo加入は2017年1月から解禁されました。
それ以前は「共済年金があるから追加の年金制度は不要」という扱いで、原則加入できませんでした。
しかし、年金制度の一元化や老後資金の重要性が高まったことで、公務員も他の職種と同じく「個人型DC」に参加できるようになったのです。
【公務員のiDeCo加入のポイント】
2017年1月より、すべての現役公務員が対象
申込時は「共済組合員」の区分で申請
掛金の上限は「月20,000円」まで(2025年現在)
NISAなどとの使い分けも重要
これにより、公務員も「老後資金の自助努力」が必要な時代に突入したといえます。
「公務員は年金が手厚い」は昔の話?
「公務員なら年金が多いからiDeCoはいらない」と思われがちですが、現実は変わりつつあります。
共済年金の上乗せ分(職域加算)はすでに廃止され、今は会社員とほぼ同じ水準。
しかも物価上昇や社会保障制度の見直しが続く中、老後資金を自分で準備する必要性が高まっています。
つまり、公務員も資産形成は“他人事ではない”時代です。
このような時代背景をふまえ、「なぜ今、公務員でもiDeCoなのか?」を本記事でしっかり解説していきます。
公務員がiDeCoを始めるメリット・デメリット
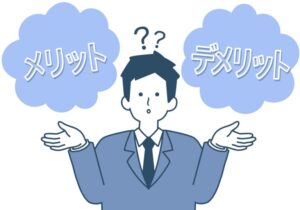
公務員の方がiDeCoを始める際に、必ず知っておくべき「メリット」と「デメリット」を、元公務員FPの視点で分かりやすく解説します。
iDeCoの主なメリット
1. 掛金が全額所得控除!圧倒的な節税効果
iDeCo最大の魅力は、毎月の掛金が全額所得控除となることです。
たとえば、毎月1万円を積み立てる場合、年間12万円が所得から差し引かれるため、その分だけ所得税・住民税が安くなります。
たとえば年収400万円・25歳・月5000円の掛け金なら、年間で9,000円以上の節税効果が得られます。
参考:iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
2. 運用益も非課税!投資初心者に有利
通常の投資だと、利益に約20%の税金がかかりますが、iDeCoなら運用で得た利益も全額非課税。
長期間の資産形成には、じわじわ効いてくる大きなアドバンテージです。
3. 老後資金を着実に積み立てられる
iDeCoは原則60歳まで引き出せないので、「将来の自分のために強制的にお金を貯められる」という点でもメリットがあります。
「つい使ってしまう」「計画的な貯蓄が苦手」という方にもおすすめです。
4. 公的年金を上乗せできる
年金制度改革で、公務員の老後資金も自助努力が不可欠になりました。
iDeCoは公的年金(厚生年金)に上乗せして受け取れるので、将来の不安対策に直結します。
5. 小額から始められ、リスクを抑えた運用も可能
iDeCoは月5,000円から始められます。
元本確保型商品(定期預金など)を選べば、リスクを抑えたい初心者でも安心して運用できます。
iDeCoの主なデメリット・注意点
1. 原則60歳まで引き出し不可
メリットにもありましたが、iDeCoの大きな特徴が「60歳までお金を引き出せない」ことです。
ライフプランが変わりやすい若手世代や、住宅購入・教育資金などの予定がある方は、「必要になったときに使えない」リスクを必ず意識しましょう。
2. 運用次第では元本割れも
投資信託型の商品を選んだ場合、元本割れのリスクもあります。
特にリスクの高い商品を選ぶと、老後の資金が思ったより増えない可能性も。
「運用商品選び」と「分散投資」の大切さを忘れずに。
3. 掛金額に上限がある
公務員のiDeCoは、月20,000円が上限(2025年現在)。
会社員や自営業者に比べると掛金が少なめなので、「ガッツリ積み立てたい」方は注意が必要です。
4. 口座管理手数料がかかる
iDeCoでは、金融機関によって口座管理手数料が発生します(多くは年間2,000円程度)。
商品や金融機関の選び方次第で、コストを抑える工夫が必要です。
5. 退職・転職時の手続きが必要
公務員を退職・転職する際は、iDeCoの移管手続きが必要です。
うっかり放置してしまうと資産運用にロスが出る場合もあります。
他の資産形成制度との違い(新NISA・つみたてNISAと比較)
最近は「新NISA」や「つみたてNISA」といった制度も人気ですが、それぞれ特徴が異なります。
iDeCo…節税メリット最強。60歳まで引き出せない
新NISA…いつでも引き出せるが、所得控除はなし
組み合わせ活用も可能(両方やる人も多い)
「教育資金・自動車・住宅購入など途中で下す可能性があるお金」はNISA、「老後資金専用」はiDeCo、と使い分けるのがおすすめです。
公務員のためのiDeCoの始め方・口座開設の流れ【初心者でもわかる】
「iDeCoに興味はあるけど、実際どうやって始めるの?」
そんな疑問を持つ方のために、公務員がiDeCoをスタートするための具体的な手順を、できるだけやさしく、順を追って解説します。
1. まずは事前準備!必要書類や条件をチェック
公務員がiDeCoに加入する場合、事前に用意しておくべきものがあります。
本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
基礎年金番号の分かる書類(年金手帳やねんきん定期便など)
勤務先(共済組合)への届出書類(後述)
また、「共済組合員であること」が申込時に必要となります。
すでに退職していたり、臨時職員の場合は手続き方法が異なる場合があるので注意しましょう。
2. 金融機関を選ぼう!選び方のコツ
iDeCoは、銀行・証券会社・保険会社など、たくさんの金融機関で申し込みできます。
どこを選ぶかで「手数料」「商品ラインナップ」「使いやすさ」が変わります。
【金融機関選びのポイント】
口座管理手数料が安いか?
…ネット証券は手数料無料や安いプランが多くおすすめ(例:SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)投資信託など商品のラインナップが豊富か?
スマホやパソコンで管理しやすいか?
3. 申込手順とスケジュール
実際の申込の流れは、以下のようになります。
金融機関のWebサイト等からiDeCoの資料請求・仮申込(証券会社によってはWEB申込・書面申込選べる場合あり)
必要書類が自宅に届く(加入申出書、共済組合員用書類など)
「加入申出書」の一部を勤務先(共済組合)に提出し、記入・押印してもらう※
全書類を金融機関に郵送
審査・口座開設(通常1~2か月かかる)
初回掛金の引き落とし→積立スタート!
※2024年12月からiDeCo加入時の事業主証明書の提出が不要。ただし、iDeCo掛金の納付方法で「事業主払込」を希望される公務員は、「事業主払込に関する証明書(職場から証明もらう必要あり)」の提出が必要になります。
勤務先にiDeCo加入を申請することに抵抗がある人も多いですが、「公務員も積極的に資産形成を」と国が推奨しています。
書類に不備があると開設までさらに時間がかかることも。余裕を持って準備しましょう。
4. 公務員特有の注意点
掛金上限は月20,000円
…会社員より少なめなので、無理のない範囲で設定しましょう。ケースによっては勤務先(所属長や担当部署)にiDeCo加入の意思を伝える必要あり
…正直に「老後資産形成のため」と伝えれば、特に不利になることはありません。
5. 申し込みから積立開始までの期間
iDeCoは「申し込んだらすぐ始められる」わけではありません。
口座開設から初回掛金の引き落としまで、早くても1~2か月は見ておきましょう。
年度末や年度始めは申請が集中し、さらに時間がかかることもあるため、早めの行動が安心です。
公務員のiDeCoで選べる商品と運用のコツ
iDeCoは「何にお金を預けて、どのように増やしていくか」を自分で選べる制度です。
公務員がiDeCoで選べる商品は、大きく分けて「元本確保型」と「投資信託型」の2種類。
ここでは、それぞれの特徴や初心者向けの選び方、失敗しにくい運用のコツを解説します。
1. 元本確保型の商品(定期預金・保険タイプ)
元本確保型は、その名の通り「預けたお金(元本)が減らない」ことが特徴です。
定期預金タイプ
銀行預金と同じイメージで、リスクがなく安心。ただし、現在は金利が非常に低いため、増える金額はごくわずかです。保険商品タイプ
保険会社の商品。満期時に元本以上が戻る場合もありますが、手数料や途中解約時の制約があることも。
「絶対に損したくない」「投資が怖い」「まずは少額で様子を見たい」という初心者には、この元本確保型が選ばれることも多いです。
ただし、iDeCoの本来のメリット(節税や運用益非課税)を最大化したいなら、次の「投資信託型」も検討がおすすめです。
2. 投資信託型の商品(国内株式・外国株式・バランス型など)
投資信託型は、複数の株や債券などに分散投資できる仕組みです。
国内株式型
日本の株式に投資。値動きは大きめですが、長期的に成長を狙えます。外国株式型
アメリカや新興国など海外の株式に投資。リスクはありますが、リターンも大きい傾向。バランス型
複数の資産(株式・債券・REITなど)を組み合わせた商品。リスクを分散したい初心者にも人気です。債券型
リスクが低く、値動きも安定。ただし、大きな増加は期待しにくい。
投資信託型は値動きがあるため、「一時的に元本割れする可能性がある」点を理解しておきましょう。
ただし、長期でコツコツ積み立てれば、短期の値動きに一喜一憂せず、資産が成長しやすいのも特徴です。
※可能性は低いですが、年金として受け取る際に元本割れを起こしている場合も絶対ないとは言い切れません。でも、ある程度リスクを取らないとリターンは望めません。
3. 初心者のための失敗しにくい商品選び
「元本確保型+バランス型」の組み合わせが安心
最初は「半分ずつ」や「バランス型だけ」といった分散投資が不安を減らします。手数料も確認!
運用商品ごとに手数料(信託報酬)が違うので、できるだけ低コストの商品を選ぶのがコツです。運用商品は後から変更できる
iDeCoでは、途中で商品の「配分変更」や「スイッチング(乗り換え)」が可能です。始めてみて不安なら、年に1回など見直してもOK。
4. 配分やリバランスのポイント
最初に「リスクをどこまで取るか」を決める
年に1回程度は「配分」を見直す(リバランス)
生活防衛資金はiDeCo以外で確保しておく
「すべて投資信託で攻める」「半分は定期預金」など、あなたの性格や家計状況に合わせて調整しましょう。
また、iDeCoは60歳まで引き出せないので、「急な出費」に備える資金は必ず別にキープしておくことが大切です。
元公務員FPの体験談:実際にiDeCoを始めてみたリアルな実感

ここからは、実際に私自身がiDeCoを始めた体験談をお話しします。
「リアルな利用者の声」を知ることで、読者の不安が少しでも和らげば幸いです。
1. 申し込みから初回積立までの流れ
私がiDeCoに興味を持ったのは、公務員時代に「老後資金は本当に十分なのか?」と疑問に思ったのがきっかけでした。
まずはiDeCoに関する雑誌を読み、ある程度知識を増やしました。
公務員もiDeCoに加入できるようになったと聞き、2017年(32歳)にネット証券(楽天証券)で資料請求をスタート。
手続き自体はそれほど難しくありませんが、「共済組合用の証明書類を職場に提出し、記入・押印してもらう」というステップが少し手間取りました。
職場の担当者も「iDeCo加入は初めて」という様子で、私の申請が一番乗りだったようです。
書類を郵送し、口座開設通知が届くまで約2ヶ月程度。
初回の掛金引き落とし(2017年6月)まで、意外と時間がかかった印象です。
2. 実際の運用スタートと感じたこと
勉強を進めるうちに「投資信託型だと非課税メリットをもっと活かせる」と思い、「投資信託型」の3商品を積み立てることにし、スタートしました。
やはり投資は怖い、という気持ちもありましたが、「節税メリット」だけでも十分お得だと感じていました。
少し値動きが不安なときもありましたが、「長期で積み立てる」というiDeCoの特性を信じてコツコツ継続。
1年後には、リターンがプラスになっていたのを見て「やってよかった」と実感しました。
3. 感じた疑問・不安・工夫したこと
「本当に職場に言っても大丈夫かな?」と最初は不安だったが、全く問題はありませんでした。
商品選びで悩んだときは、SBI証券や楽天証券の人気ランキングや、信託報酬(手数料)、雑誌のランキングを参考にして決定。
途中で配分変更(リバランス)も簡単にできたので、「最初に完璧を目指さなくても大丈夫」と安心できました。
4. 実際の数字データ(例)
毎月積立額:5,000円
商品:国内株式+先進国株式+新興国株式の3つ
運用利回り:2017年6月~2025年7月で「+11.88%」※
※例えば、月5000円で利回り12%、積み立て10年だと、積立した額60万円が115万円になっている感じです。
予想以上の成績でリターンもなかなかのものになっています。そこに、「節税効果+非課税運用」効果もありiDeCoを始めた価値は十分あると感じました。
よくある質問Q&A【2025年最新版】

ここでは、公務員のiDeCoについて実際によく寄せられる質問とその答えを、分かりやすくまとめました。
気になる点はここでしっかり解消しましょう。
Q1. 公務員がiDeCoをやると副業扱いになる?職場にバレる?
A. 副業にはなりません。
iDeCoは“自分の老後資金を自分で積み立てる”制度であり、副業には一切該当しません。運用益や節税効果を得ても、就業規則や服務規律に違反する心配は不要です。職場への申請や書類手続きはありますが、不利益を受けたり評価に影響することはまずありません。そもそも国が公務員もiDeCoをやるよう推奨しています。
Q2. 年末調整や確定申告で何か特別な手続きが必要?
A. 基本的には、年末調整で控除を申請できます。
iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象。
通常は、口座管理会社から送られてくる「控除証明書」を年末調整で提出すればOK。
副業など他に確定申告が必要な場合は、申告書類に記載して控除できます。
Q3. 掛金はどのくらいから始められる?増減はできる?
A. 最低5,000円から、1,000円単位で増額可能です。
公務員の場合、上限は月20,000円(2025年現在)まで。途中で掛金額を変更したり、一時的に掛金を止める(休止)ことも可能です。ただし、変更の反映には1~2ヶ月ほどかかることがあるので注意。
Q4. 退職や転職をした場合、iDeCoはどうなる?
A. 勤務先が変わった場合も、iDeCoは引き続き運用可能です。
退職後は「企業型DC」や「自営業者用iDeCo」など、状況に応じて手続きすれば継続できます。放置していると「運用指図者」となり掛金が積み立てられなくなることもあるため、必ず手続きの変更を忘れずに!
Q5. 60歳より前にお金を引き出したくなったら?
A. 原則、60歳までは引き出せません。
iDeCoの大きな特徴です。どうしても必要になった場合は、積み立て停止(休止)はできますが、原則として資金を引き出すことはできません。「生活防衛資金」は必ずiDeCo以外で用意しておきましょう。
Q6. iDeCoと新NISA・つみたてNISAはどう違う?両方やる意味ある?
A. それぞれ制度の特徴が異なるので、両方使い分けている人が多いです。
iDeCoは「所得控除」が最大メリット。老後資金づくり専用。
新NISAは「いつでも引き出せる」柔軟性が魅力。
「老後資金専用はiDeCo、それ以外のお金はNISA」という使い分けがよく選ばれています。
Q7. どんな商品を選ぶべきか分かりません…
A. 迷ったら「バランス型」から始めてみるのがおすすめ。
後から商品を変えたり、配分を見直すことも可能です。少額から無理なく始めて、徐々に運用スタイルを固めていきましょう。
- 「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」←アメリカの大企業に分散投資できる
- 「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」←全世界の企業に分散投資できる
Q8. 他にも知っておきたい細かいポイントは?
手数料は必ずチェック(商品や金融機関ごとに違う)
毎年「控除証明書」が届くのでなくさないように!
給与天引きで掛金を払いたい場合は勤務先への申請が必要
年度末・年度始めは口座開設や書類手続きが混み合うことがあるので早めの準備を
iDeCoは「始める前の疑問」を解消し、少額から気軽に始めてみるのがコツです。分からないことは証券会社や金融機関のカスタマーサポートも活用しましょう!
公務員のiDeCoで後悔しないための注意点&チェックリスト
iDeCoは老後資金を作るのに非常に有効な制度ですが、「知らずに始めて後悔した…」というケースも少なくありません。
ここでは、公務員がiDeCoを利用する際に押さえておきたい注意点や、失敗しやすいポイントを分かりやすくまとめます。
1. 60歳まで絶対に引き出せない「資金拘束リスク」
iDeCoは原則60歳まで積み立てたお金を引き出すことができません。
住宅購入や教育資金、急な出費など「将来使うかもしれないお金」までiDeCoに入れてしまうと、後で困ることに…。
無理のない金額で積み立てることが後悔しないコツです。
2. 投資商品による元本割れのリスク
「元本確保型」以外の投資信託型商品は値動きによる元本割れのリスクがあります。
特に、株価が大きく下がったタイミングで焦って売却したくなる人もいますが、長期運用が前提の制度なので、短期的な値動きに一喜一憂せず、コツコツ積み立てを続けることが大切です。
3. 退職・転職時の手続き漏れに注意
公務員を退職・転職した場合、必ずiDeCoの移管手続きが必要です。
これを怠ると、積立停止や運用指図者(掛金の拠出ができず、運用のみになる)に自動的に切り替わる場合があります。
転職先が企業型DCを採用している場合は、そちらへの移換も検討しましょう。
4. 掛金の上限に注意(公務員は月20,000円まで)
会社員や自営業者と比べて、公務員のiDeCoは掛金の上限がやや低めです。
「もっと積み立てたい!」と思っても限度があるため、余裕資金は新NISAなど他の制度と併用するのがおすすめです。
5. 手数料や商品選びの“見えないコスト”に注意
iDeCoの運用では、口座管理手数料や信託報酬(商品ごとの運用管理費用)がかかります。
金融機関や選んだ商品によって、年間コストに差が出ることも。
「手数料が安い金融機関」や「低コストの商品」を選ぶことが長期的には大きな差となります。
6. 年末調整・控除証明書の提出を忘れずに
毎年10月〜11月頃に「小規模企業共済等掛金控除証明書」が金融機関から届きます。
これを職場に提出し忘れると、所得控除が受けられなくなってしまうので、必ず年末調整のタイミングで提出しましょう。
7. 失敗しないためのチェックリスト
□ 積み立てる金額は無理なく続けられる額に設定したか?
□ 生活防衛資金(急な出費に備えるお金)はiDeCo以外で確保しているか?
□ 投資商品ごとのリスクと手数料を確認したか?
□ 年末調整の控除証明書を忘れずに提出できているか?
□ 商品配分(リバランス)は年1回など定期的に見直しているか?
【将来の資産シミュレーション例】
たとえば、
25歳からiDeCoを始め、毎月1万円を40年間積み立て、年利3%で運用できた場合
→9,260,595円(元本480万円+運用益4,460,595円)+40年間の節税額72万円
同じ積立でも、「運用益が非課税」「所得控除で節税」できるのがiDeCoの強み。
しっかり制度を活かすことで、将来の安心につながります。
まとめ|公務員がiDeCoを始める前に知っておきたいこと
ここまで、公務員がiDeCoを始めるうえで押さえておくべきポイントを、初心者にも分かりやすく解説してきました。
公務員は「年金が手厚いから大丈夫」と思われがちですが、年金制度改革や物価上昇、長寿化社会の到来により、自助努力による資産形成がますます重要になっています。
iDeCoは、公務員にも開かれた「老後資金づくりの強い味方」です。
iDeCoの最大のメリットは、「節税」と「運用益の非課税効果」。
毎月無理のない範囲で積み立てを続けることで、20年後・30年後・40年後の自分の生活に大きな安心をもたらします。
一方で、「60歳まで原則引き出せない」「元本割れリスク」「手続きの手間」など、デメリットもあります。
そのため、生活防衛資金や急な出費に備えるお金は、必ず別に用意した上で、iDeCoは“老後専用口座”として活用するのがコツです。
【これだけは忘れずに】
無理なく続けられる金額で積立を設定
投資商品はリスク・コストをしっかり確認
年末調整の控除証明書提出も忘れずに
退職・転職時は移管手続きを忘れずに
NISAや積立NISAと併用しながら、あなたのライフプランや将来設計に合わせて活用しましょう。
この記事が、あなたの「iDeCoデビュー」の後押しになれば幸いです。
【関連記事】
【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説
【2025年最新】公務員向けおすすめ証券会社4選を元公務員FPが比較!実体験で語る選び方と注意点