公務員の皆さん、「iDeCo(イデコ)で将来のためにお金を積み立てたいけど、実際に毎月いくら積み立てればいいのか、なかなか決められない……」と悩んでいませんか?
私自身も現役公務員時代、「無理なく積み立てて、将来どれくらい増えるの?」と何度もシミュレーションしながら悩んだ経験があります。
この記事では、公務員がiDeCoで失敗しない積立額の決め方・シミュレーション方法を、初心者にもわかりやすく、リアルな体験談や注意点・具体的な数字データを交えながら徹底解説します。
「iDeCoってそもそもやる意味ある?」「積立上限は?」「シミュレーションツールってどう使う?」そんな疑問にも一つひとつ答えていきます。
今まさに
iDeCoを始めるか迷っている
いくら積み立てるか悩んでいる
公務員の制度的な特徴がよくわからない
という方は、この記事を読めば後悔しないiDeCo活用の第一歩が踏み出せます。
公務員がiDeCoを利用するメリット・デメリット
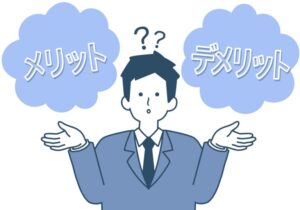
公務員のiDeCoは「やるべき?」をFPが解説
公務員として働いていると、「老後は年金や退職金があるから、iDeCoまでは必要ないのでは?」と感じる方も多いでしょう。
ですが、現代の年金制度やライフスタイルを考えると、iDeCoの活用は公務員にも大きなメリットがあります。
ここでは、現役公務員やこれから公務員を目指す方がiDeCoを始めるべきかどうか、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。
公務員がiDeCoを利用する主なメリット
老後資金の「自助努力」ができる
近年、公的年金だけでは老後の生活が不安という声が多くなっています。iDeCoを利用することで、将来の資金を自分で確実に積み立てられるのが最大のメリットです。掛金が「全額所得控除」され節税に
毎月積み立てた金額が、その年の所得から控除されます。つまり、課税所得が減る=所得税や住民税が安くなるので、現役時代から家計に優しい制度です。運用益も「非課税」
通常、投資信託や株式で得た運用益には約20%の税金がかかりますが、iDeCo内で得た運用益はすべて非課税。複利の力を最大限に活かせます。受け取り時も「税制優遇」あり
受け取り時には「退職所得控除」や「公的年金等控除」が使え、一般的な運用よりも税金がかなり優遇されます。
公務員がiDeCoを利用する際のデメリット・注意点
原則60歳まで引き出せない
iDeCoは「老後の資産形成」が目的なので、原則として60歳になるまでお金を引き出すことができません。「急な出費があるかも」と思う場合は、無理な金額での積立は避けましょう。積立上限が会社員や自営業者より低い
公務員は月額20,000円(年額24万円)までしか積み立てられません(2025年7月現在)。他の職種と比べて限度額が低いため、「大きな資産形成」を目指すにはやや物足りなさを感じるかもしれません。運用リスクがある(元本保証ではない)
iDeCoの運用先は「定期預金」「保険」「投資信託」などさまざまですが、選び方によっては元本割れのリスクもあります。初心者はバランス型や元本確保型から始めるのも一つの手です。口座管理手数料がかかる
毎月または毎年、運営管理機関への手数料が発生します。銀行や証券会社ごとに異なるため、選ぶ際は手数料にも注目しましょう。
まとめ:公務員にもiDeCoは必要?
年金や退職金がしっかりあるとはいえ、将来のための自助努力がますます重要になっています。
とくに現役世代で資産運用や節税に興味がある人には、iDeCoは「やらない理由がない」ほどメリットが大きい制度といえます。
ただし、「無理な積み立て」や「リスクの取りすぎ」には注意しつつ、自分に合った積立額と運用スタイルを選ぶことが大切です。
公務員のiDeCo積立額の決め方とシミュレーション方法

iDeCoの「積立上限額」と公務員の制度的特徴
まず、公務員がiDeCoを利用する際に知っておきたいのが**「積立上限額」です。
公務員の場合、2025年7月現在の積立上限は月12,000円(年14万4,000円)までと定められています。
これは民間会社員や自営業者よりも低い設定ですが、逆に「これ以上積み立てたくてもできない」ので、「家計を圧迫しすぎない」**という安心感にもつながります。
【補足】積立上限は変更されることもあるため、必ず最新情報を確認しましょう。
毎月いくら積み立てるべきか?具体的なシミュレーション例
「実際、いくら積み立てるべき?」という疑問に答えるため、具体的なシミュレーション例を示します。
【ケース1】毎月1万円を35年間積み立てた場合(利回り3%)
- 現在30歳
毎月の積立額:10,000円
年間積立額:12万円
運用利回り:年3%
積立期間:35年
この条件でシミュレーションすると…
元本:420万円(10,000円×12カ月×35年)
運用益:約321万円
合計資産:約741万円
節税額:63万円
となります。
つまり、「コツコツ35年間続ければ約321万円+節税分の63万円のプラスが見込める」イメージです。
【ケース2】毎月1万円を35年間積み立てた場合(利回り5%)
- 現在30歳
毎月の積立額:10,000円
年間積立額:12万円
運用利回り:年5%
積立期間:35年
この条件でシミュレーションすると…
元本:420万円(10,000円×12カ月×35年)
運用益:約716万円
合計資産:約1,136万円
節税額:63万円
となります。
ケース1と同条件で、運用利回りを3%→5%に変えると、「運用益が約400万円」も上がりました。
【ケース3】上限の20,000円を35年間積み立てた場合
- 現在30歳
毎月の積立額:12,000円
年間積立額:14万4,000円
運用利回り:年3%
積立期間:35年
この条件でシミュレーションすると…
元本:840万円(20,000円×12カ月×35年)
運用益:約643万円
合計資産:約1483万円
節税額:126万円
となります。
もちろん、「運用利回り」によって将来の資産額は大きく変わります。
低リスクの元本保証型なら運用益は控えめ、株式やバランス型ならリターンは増えますが、元本割れのリスクも伴います。
シミュレーションツールの使い方(実例付き)
最近は、誰でも簡単に積立額や将来の資産額を計算できる無料の「iDeCoシミュレーションツール」が金融庁や証券会社のサイトで提供されています。
例:楽天証券のiDeCo節税シミュレーターの使い方
積立額(例:20,000円)と開始年齢を入力
想定運用利回り(例:3%)を入力
「計算する」ボタンを押す
これだけで、将来の受取額・元本・運用益が一目でわかります。
※運用利回りの目安
1%→リスクの回避を最優先、リターンは小さくて良い
3%→運用益は欲しいが、なるべく安全な運用をしたい
5%→リスクは覚悟の上で、ある程度のリターンが欲しい
【ポイント】
- 複数パターン(毎月5千円・1万円・2万円など)を比較してみる
- 運用利回りは「1〜6%」程度で何通りか試してみる
- 家計の余裕・今後のライフプランに合わせて無理なく設定する
公務員が積立額を決める時のコツ
生活費や急な出費を優先し、余裕資金から積み立てる
将来の子育て・教育費・住宅ローンなどを考慮して設定
途中で金額変更もできるので「まずは少額から」でもOK
iDeCo積立額のシミュレーション体験談
実際に私がやってみた積立シミュレーション
私がiDeCoを検討しはじめたのは、ちょうど30歳になったころでした。
当時は県職員として働きながら、子育てや住宅ローン、将来の教育費など、将来のお金の不安を少しずつ感じていました。
正直、「公務員なら年金も退職金もあるし、iDeCoまでしなくても何とかなるんじゃないか?」と考えていた時期もあります。
でも、老後2,000万円問題がニュースで話題になった頃、「やはり自分でも何か積み立てておいた方がいい」と思い直しました。
まず私が行ったのは、
- iDeCoの特集がされている雑誌を読んである程度知識を習得する
- 無料のiDeCo積立シミュレーションツールで将来の受け取り額をざっくり計算すること
です。
ステップ1:月5000円からスタート
最初は、積立最低金額の「5000円」でシミュレーションしました。
シミュレーターに「毎月5,000円」「運用利回り3%」「積立期間35年」と入力すると、約370万円になるという結果に。
「35年間で160万円ほど増えるのか。やはり“運用益非課税”は大きいな」と感じました。
あと、節税額が「約32万円」と試算されました。
節税額はその分を税として納めなくていいので、簡単に「32万円」お得と考えられます。
iDeCoはこの節税が地味にありがたい制度だとシミュレーションをして実感しました。
ステップ2:積立額を上限まで上げて再計算
次に、「もし月12,000円まで積み立てたら?」と上限額でもシミュレーション(当時は12,000円が公務員の上限。2025年7月現在では2万円が公務員の上限)。
35年後には約890万円になり、単純な貯金より約386万円ほど多く受け取れる計算に。
ステップ3:家族との相談と現実的な決断
ここで私は、家族と一緒に「家計を圧迫しないラインはどこか」を話し合いました。
このときはまだ結婚していなかったので、親と相談した形です。
子どもの進学費用や住宅ローン、急な出費にも備えたい
でもiDeCoもなるべくフル活用したい
結果、最初は最低掛金の「毎月5,000円」からスタートし、収入が増え家計の余裕が出てきたら少しずつ増やす方針に決めました。
ステップ4:実際に積立額を調整しながら運用中
途中で積立額を変更できることも大きな安心材料でした。
場合によっては、掛金を止めることもできます。
実際にiDeCoを始めてみて、「積立額は一度決めたら変えられない」というイメージは間違いだったと感じています。
公務員時代のリアルな悩みと決め方
実際にやってみて分かったことは、「最初から上限額を狙わなくてもいい」「途中で増減できる」という柔軟さです。
子どもの進学やマイホーム購入など、大きな出費があるときは積立額を減らす
逆に昇給や家計に余裕ができたタイミングで積立額を増やす
このように、ライフイベントごとに「見直しながら続けていく」のが長く続けるコツだと思いました。
私自身、公務員時代に「iDeCoを始めたことで資産運用や節税に興味を持ち、より将来のお金に向き合うきっかけ」になったのも大きな収穫です。
よくあるQ&A:公務員のiDeCoで迷いやすいポイント

Q1. 公務員のiDeCo、退職金や年金とどんな関係があるの?
A. 基本的には「別枠」と考えてOKです。
iDeCoは「私的年金」なので、公務員の退職金や厚生年金(共済年金)はそのまま受け取れます。
ただし、iDeCoの受取方法によっては退職所得控除・年金控除などの計算に影響が出ることがあるので、「受取時の税制優遇」の重なりをシミュレーションツールなどで確認しておくと安心です。
Q2. 積立途中で金額の増減や一時停止はできる?
A. はい、可能です。
iDeCoは「積立額の変更」や「一時的な停止」が年1回まで認められています。
例えば「今年は家計が厳しい」「出費が増えそう」などの事情があれば、積立額を減らしたり、0円にすることもできます。
ただし、変更には一定の手続き期間がかかるため、事前に証券会社や金融機関の窓口で確認しましょう。
Q3. 節税メリットは実際どれくらい?
A. 年間2万円~3万円以上の節税になるケースも珍しくありません。
たとえば年収400万円の公務員が毎月1万円(年12万円)iDeCoで積み立てた場合、所得税+住民税の合計で年間約1万8千円節税できます(税率等によって異なります)。
つまり「35年間で約63万円」の節税効果があるイメージです。
Q4. iDeCoをやめた場合や、途中で退職・転職したらどうなる?
A. 原則として、iDeCoは60歳まで引き出し不可ですが、退職・転職の場合も引き続き加入し続けられます。
公務員から会社員や自営業者へ転職した場合は、転職先の区分ごとに「積立上限額」が変わります。
また、転職手続きの際は「資格変更届」等の提出が必要なので、転職先に合わせて手続きを行いましょう。
Q5. 公務員でも投資初心者だけど、リスクが心配…
A. 投資信託だけでなく、元本確保型(定期預金など)も選べます。
iDeCoは「すべてを株や投資信託にしなければいけない」という決まりはありません。
運用リスクを取りたくない場合は、元本保証型の商品(定期預金・保険)を中心に選ぶ
少しリターンも狙いたい場合は「バランス型」「債券型」などリスク分散型も検討する
自分のリスク許容度や運用目的に合わせて選択しましょう。
Q6. もし死亡した場合はどうなる?
A. iDeCo資産は「相続財産」として遺族が受け取れます。
もしもの場合は、遺族が手続きを行えば、運用中の資産や積立分を受け取ることができます。
公務員iDeCoの注意点と落とし穴

公務員独自の注意ポイント
1. 積立上限額は絶対に超えられない
公務員のiDeCo積立上限額は月20,000円まで(2025年7月現在)と決まっています。
この上限は会社員や自営業者より低いので、「もっと積み立てて老後資金を増やしたい」と思っても、超えることはできません。
また、他の私的年金制度(例えば企業型DCや共済年金基金など)との重複加入も基本的に不可なので、制度の併用には注意が必要です。
2. 転職・退職時の手続きに注意
万が一、公務員を辞めて会社員や自営業者になる場合は、必ずiDeCoの「加入区分変更」の手続きが必要です。
これを忘れていると、せっかく積み立てた資産にトラブルが生じたり、掛金が一時的に拠出できなくなることも。
転職が決まったら、早めに証券会社・金融機関に連絡をして指示を仰ぎましょう。
3. 資産運用のリスクと配分ミス
iDeCoで選べる商品は「元本保証型(定期預金など)」から「リスク商品(株式投資信託など)」まで様々です。
「元本保証なら安心」と思って全部を定期預金にしてしまうと、ほとんど増えないまま終わることも。
逆に、リスク商品ばかりにしてしまうと、相場が下落したときに大きく元本割れする可能性もあります。
【アドバイス】
リスクを取るのが怖いという人の資産配分(アセットアロケーション)は、自分の年齢・リスク許容度・運用期間を考えて、元本保証型とリスク商品を組み合わせるのがおすすめです。
実際の失敗事例・よくある落とし穴
【失敗例1】積立額を高く設定しすぎて生活が苦しくなった
「せっかくだから上限まで積み立てよう!」と意気込んで20,000円を設定したものの、家計が厳しくなり途中で減額する羽目に。
無理をすると途中でiDeCoが嫌になってしまうので、最初は少額から始めて家計に余裕ができてから増やすのがおすすめです。
【失敗例2】運用商品を何も考えずに選んでしまった
「よく分からないから…」と証券会社のデフォルトのまま定期預金100%で始めてしまい、10年たってもほとんど増えなかったという声も。
また、「株式型ばかり」にしてリーマンショック級の暴落で大幅な含み損を抱えてしまったというケースもあります。
【失敗例3】退職・転職時の手続きを忘れた
転職した際にiDeCoの区分変更手続きを忘れて、数か月間掛金の拠出ができず、税制メリットを受け損ねたという声も少なくありません。
まとめ:落とし穴を避けるために
積立額は無理のない金額から始める
資産配分は元本保証型とリスク商品をバランスよく
制度や手続きの変更点を必ず金融機関で確認
長期的な視点で「見直し」「調整」しながら続ける
「失敗例」や「落とし穴」を知っておくことで、安心してiDeCoを活用できます。
おすすめの積立戦略と運用例

年代別の積立シミュレーション比較
iDeCoは「長く続けるほど有利」な制度です。
ここでは20代・30代・40代・50代の各年代で始めた場合のシミュレーションを紹介します(すべて運用利回り3%、上限20,000円で計算)。
※シミュレーションは、金融庁「つみたてシミュレーター」で計算しています。
【ケースA】20代から始めた場合(積立期間35年)
毎月20,000円 × 35年(420か月)
元本:840万円
運用益:643万円
将来受取額:1,483万円
【ケースB】30代から始めた場合(積立期間25年)
毎月20,000円 × 25年(300か月)
元本:600万円
運用益:292万円
将来受取額:892万円
【ケースC】40代から始めた場合(積立期間15年)
毎月20,000円 × 15年(180か月)
元本:360万円
運用益:94万円
将来受取額:454万円
このように、「スタートが早いほど複利の効果で運用益が大きく」なります。
「今からでは遅いかな…」と思っても、始めた時点からしっかり効果は出ますので、年齢に関係なくスタートするのが大切です。
積立額ごとの将来受取額イメージ
運用利回り3%・20年間で計算した場合(簡易シミュレーション):
| 毎月の積立額 | 総積立元本 | 運用益 | 将来受取額 |
|---|---|---|---|
| 5,000円 | 120万円 | 44万円 | 164万円 |
| 8,000円 | 192万円 | 71万円 | 263万円 |
| 10,000円 | 240万円 | 88万円 | 328万円 |
| 15,000円 | 360万円 | 132万円 | 492万円 |
| 20,000円 | 480万円 | 177万円 | 657万円 |
資産配分の考え方・実例
iDeCoの運用商品は大きく分けて「元本保証型」と「リスク商品型(投資信託など)」があります。
どちらか一方だけに偏るのではなく、自分のリスク許容度に合わせて分散するのがポイントです。
例1:リスクを抑えたい人(元本保証型中心)
定期預金:80%
バランス型投資信託:20%
例2:安定と成長のバランス型(一般的な公務員向け)
バランス型投資信託:50%
国内債券型投資信託:25%
国内株式型投資信託:15%
定期預金:10%
例3:積極運用型(リスク許容度が高い方向け)
バランス型投資信託:30%
国内外株式型投資信託:60%
国内債券型投資信託:10%
例4:さらに積極運用型(20~30代には一番おすすめ)
国外株式型投資信託:100%
若い人にはこのやり方を今は一番おすすめしています。
ズバリ「オールカントリー」や「S&P500」に連動した商品を買う。
例えば、eMAXIS Slim全世界株式(オルカン)やeMAXIS Slim米国株式(S&P500)。
ポイントは「自分がどれくらいリスクを許容できるか」を考えること。
年齢や家族構成、今後のライフイベントも意識して資産配分を決めましょう。
まとめ:公務員がiDeCoで後悔しないために
公務員でも、将来の備えは「自分で作る」時代になっています。
「年金と退職金だけで本当に大丈夫?」と不安になったとき、iDeCoは少額からでも始められる、とても頼もしい制度です。
ここまでのポイントを改めてまとめます。
iDeCoは節税・長期運用・老後資産形成の三拍子がそろった制度
公務員は月20,000円まで積立可能。家計やライフプランを考え、無理なく続けられる金額でスタート
運用商品は「元本保証型」か「リスク商品型」か、リスク許容度や年齢に合わせて分散を
シミュレーションツールを使い、「将来いくらになるか」をイメージしながら計画的に運用
積立額や運用商品は途中で変更OK。ライフイベントや家計状況に応じて柔軟に見直し
私自身、公務員時代に「なんとなく将来が不安…」というモヤモヤからiDeCoを始め、シミュレーションを繰り返す中で「このペースなら安心できそうだ」と前向きな気持ちに変わった経験があります。
iDeCoは「始めて終わり」ではありません。
家計や人生の変化に合わせて、時々シミュレーションし直し、「自分にちょうどいいペース」を探し続けていく――それが最大のコツです。
この記事が、公務員の皆さんが“後悔しない老後準備”の第一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。
【関連記事】
【公務員向け】iDeCoとNISAどっちがおすすめ?元公務員FPが失敗しない選び方を解説
