「公務員はiDeCoとNISA、結局どちらがお得なの?」
「初心者でも失敗しない選び方が知りたい!」
「両方使ってもいいの?」――
こんな疑問を持つ方に向けて、公務員・そのご家族・資産運用ビギナーでもすぐ分かる、2025年最新版の「iDeCo&NISA完全比較ガイド」をお届けします。
公務員も資産形成が必須となった今、税制優遇の2大制度「iDeCo」と「NISA」はほぼ必ず耳にする選択肢です。
しかし、「節税メリットの大きさ」「引き出し制限の違い」「どんな人に向いているか」など、本当に知りたい“リアルな損得”や“初心者のつまずきやすいポイント”は意外と分かりにくいものです。
私は元県職員FPとして、実際に両方を活用した経験や、同僚・受講生から寄せられた実践的なQ&Aも交えながら、公務員目線で分かりやすく比較解説していきます。
この記事では――
iDeCo/NISAの仕組みをゼロからやさしく
公務員が得するケース・損するケース
メリット/デメリットの本音比較
タイプ別のおすすめ選択例
失敗しない組み合わせ活用術
2025年最新の制度改正情報
実際に使ってみての体験談やQ&A
まで、1記事でまるごと網羅。
「いま何から始めるべきか」「私の場合はどっちが向いているのか」が必ず分かります。
迷っている方はぜひ、この記事を読んで一歩踏み出してみてください!
iDeCoとNISAの基礎知識をやさしく解説

まずは、「iDeCo」と「NISA」がどんな制度なのか、公務員でも分かるようにやさしく整理します。
そもそもiDeCo(イデコ)とは?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、「自分でつくる年金」です。
毎月一定額を積み立てて、自分が選んだ投資商品(定期預金や投資信託など)で運用し、60歳以降に年金や一時金として受け取る仕組み。
最大の特徴は、積立金額が全額「所得控除」となり、所得税や住民税が大きく減る点です。
また、運用益も非課税で再投資できるので、「節税」と「資産形成」を両立したい人向き。
【iDeCoのざっくり特徴】
掛金は毎月5,000円〜1,000円単位で設定可(公務員は月2万円まで/2025年現在)
掛金が全額所得控除(所得税・住民税の節税効果が高い)
運用益も非課税
60歳までは原則引き出しできない(“老後専用口座”)
投資信託、定期預金など幅広い商品から自分で選ぶ
NISA(ニーサ)とは?
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる制度です。
2024年から「新NISA」へリニューアルされ、今は“つみたて投資枠”と“成長投資枠”の2本立てとなりました。
【NISAのざっくり特徴】
つみたて投資枠:年間120万円まで、長期・積立・分散投資向け(対象商品は手数料が低い投資信託などに限定)
成長投資枠:年間240万円まで、株や投資信託・ETFもOK(売買自由度高め)
両枠あわせて年間360万円まで投資可能・最大1800万円まで(2025年現在)
運用益・売却益が非課税(最大20年間)
いつでも引き出し自由(制限なし)
公務員でもiDeCo・NISAは使える?
もちろん、両方とも公務員も利用OK!
iDeCoは2017年から公務員にも解禁され、今では多くの自治体職員・教員・公務員の方が加入中。
NISAも職種を問わず使える制度で、公務員でも家族でも口座開設可。
副業禁止規定が気になる人も多いですが、「iDeCo・NISAでの運用は副業に該当しません」。
安心して利用できます。
どちらも資産運用の強い味方!
iDeCoは「老後資金づくり専用」=大きな節税が可能、
NISAは「自由度の高い投資」=途中引き出しOKで生活資金・教育資金・資産運用全般に使いやすい、
という位置づけです。
それぞれの仕組み・メリット・制約をしっかり押さえておけば、「自分に合う使い方」が見えてきます。
次章からは、公務員が選ぶときに迷いやすいポイントや、両者の違い・比較をより具体的に解説します。
公務員がiDeCo・NISAを選ぶときのポイント
iDeCoもNISAも「税金が優遇されるお得な制度」ですが、公務員の場合は目的や家庭環境、将来設計によって、どちらを優先すべきかが変わってきます。
ここでは、公務員がiDeCoとNISAを選ぶ際に必ず押さえたいポイントや、よくある勘違い、注意点をやさしく解説します。
1. ライフステージや目的で選ぶのが基本
「老後資金をじっくり育てたい」ならiDeCo
60歳まで引き出せない=本気の老後資金専用
節税効果がとても大きい
「自動車、結婚式、住宅、教育資金、資産形成なども視野に入れたい」ならNISA
途中でいつでも引き出せる自由度
ライフイベント(結婚・住宅・教育)にも柔軟に対応
「どちらも使い分ける」人が増えている!
「資産形成」はNISA、「老後資金」はiDeCoに振り分けるのが王道
2. 家計・資産状況別のおすすめ選び方
まだ十分な貯金がない場合(生活防衛資金確保が最優先)
まずはNISAで積立や運用を始め、数年後にiDeCoもプラス
- NISAを始めるまでにまずは生活費の半年分は貯金を貯める
安定収入&貯金があり、長期的な資産づくりを重視したい場合
iDeCoを優先し、満額積立も検討
余裕があればNISAと併用
3. よくある勘違いと注意点
「iDeCoもNISAも同時にやると税務上マズい?」→問題なし!
両制度の併用OK、税金面のデメリットなし。むしろ両方のメリットを享受する人が多いです。
「副業禁止に引っかかる?」→心配無用!
資産運用(投資)は公務員の副業規定には該当しません。
「iDeCoは掛金を途中で下げたり止められる?」
金額変更や一時停止は可能。ただし反映には数ヶ月かかる場合あり。
「NISAは途中でいつでも引き出せる?」
いつでも引き出し自由。ただし、引き出した枠は再利用不可(翌年には復活します)。
4. 迷ったときは「使い道」から逆算する
「このお金は将来まで絶対に使わない」と思える分はiDeCo
「数年後に使う可能性がある」「途中で必要になるかも」と思う分はNISA
【徹底比較】iDeCoとNISAの違い一覧表(メリット・デメリット・注意点)
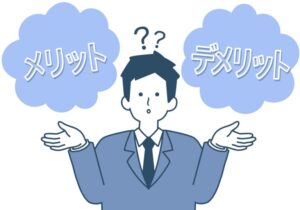
「iDeCoとNISA、何がどう違うの?」
公務員にとって最も気になる“損得ポイント”を中心に、一覧表と詳しい解説で徹底比較します。
iDeCoとNISAの違い早見表
| 比較項目 | iDeCo(イデコ) | NISA(新NISA/つみたてNISA) |
|---|---|---|
| 主な目的 | 老後資金の積立・運用 | 資産形成全般・幅広い使い道 |
| 税制メリット | 掛金全額所得控除+運用益非課税 | 運用益非課税 |
| 掛金/投資上限 | 月20,000円まで(公務員の場合) | 年間360万円まで(2025年現在) |
| 引き出し自由度 | 60歳まで原則引き出し不可 | いつでも引き出し可能 |
| 商品の選択肢 | 定期預金/投資信託など | 株/投資信託/ETF/REITなど幅広い |
| 手数料 | 口座管理手数料がかかる | 基本的に手数料はかからない(投資商品による) |
| 節税メリット実感 | 毎年の所得税・住民税で即実感 | 売却益や分配金への課税ゼロで実感 |
| 向いている人 | 老後資金を本気で貯めたい人 | 使い道を限定せず資産を増やしたい人 |
| 途中解約・変更 | 積立停止や金額変更は可能(引き出し不可) | 途中売却・引き出し自由 |
【メリット・デメリット比較】
■ iDeCoの主なメリット
掛金全額所得控除による圧倒的な節税
運用益も非課税
強制的に貯められる(老後資金がしっかり貯まる)
長期間積立で資産が育ちやすい
■ iDeCoの主なデメリット・注意点
60歳まで引き出せない(資金拘束リスク)
掛金上限がNISAより低い(公務員は月20,000円まで)
口座管理手数料などコストがかかる
投資商品の選択肢はNISAより少なめ
■ NISAの主なメリット
いつでも自由に引き出せる
非課税投資枠が大きい(年間360万円まで/2025年現在)
商品の選択肢が非常に広い(株・ETFもOK)
基本的に手数料はかからない(商品による)
■ NISAの主なデメリット・注意点
掛金の所得控除(節税効果)はない
投資で損が出た場合の税務優遇(損益通算や繰越控除)が使えない
1年の非課税枠は引き出すと再利用できない
投資額が大きくなるとリスクも増えるので注意
【公務員の視点でのチェックポイント】
定年退職までの年数が長い若手公務員ほどiDeCoの節税メリットが大きい
「貯金が苦手」「老後資金を確実に貯めたい」ならiDeCo、「ライフプランが変わりやすい20代・30代」や「マイホーム・教育資金も視野に入れたい」ならNISAが向く
両方併用してもOK。無理のない範囲で組み合わせるのがおすすめ
【実体験コラム】
私は32歳のときにiDeCoを月5000円から始めましたが、最初は「税制メリットがすごいからiDeCoだけでいい」と思っていました。
途中から資産形成のためNISAを活用しリスクをとり、日本の個別株への投資も始めました(数万円からスタート)。
30代後半で結婚し、子供ができ、教育費や住宅購入や自動車買い替えなど“大きい出費”が重なってきたのもあり、積み立てをしたいと考えるようになり、NISAでの積み立ても月数千円から始めました。
- 生活費の半年分→貯金
- 絶対に老後まで使わないお金(月:5千円~2万円)→iDeCo
- 余裕資金(月:数千円~数万円)→NISA(つみたて投資枠)
- 余裕資金(余裕資金の3割~5割程度)→NISA(成長投資枠)
に振り分けるのが、今は一番現実的だと実感しています。
公務員がiDeCoで得られるお得ポイントとデメリット
iDeCoは、公務員でも大きな節税メリットが受けられる“老後資金専用”の資産形成制度です。
ここでは、公務員がiDeCoを活用することで得られる本当のお得ポイントと、実際に注意すべきデメリットを具体的に解説します。
【1】公務員がiDeCoで得するポイント
1. 掛金全額が所得控除=圧倒的な節税効果!
iDeCo最大の魅力は「掛金全額が所得控除になる」こと。
たとえば、毎月1万円を積み立てた場合、年間12万円がそのまま所得控除になり、所得税・住民税が大幅に減ります。
例:年収400万円・30歳スタート・掛金5000円の場合→ 年間約9,000円程度の節税効果が得られることも(節税のイメージとしては9000円ゲットできるのと同じ)。
2. 運用益も非課税で再投資できる
通常の投資では利益に20%ほどの税金がかかりますが、iDeCoなら運用益もまるごと非課税。
長期で複利運用するほど効果が大きくなります。
3. 強制的に老後資金を貯められる安心感
iDeCoは「60歳まで引き出せない」というルールがあるため、“自分を律する仕組み”として非常に効果的です。
「どうしても貯金が苦手…」「老後資金だけは絶対に確保したい」という方には最適。
4. 小額から始められる
公務員の場合、月5,000円〜2万円まで(2025年現在)と、家計に無理なくスタートできる金額設定です。
【2】iDeCoのデメリット・注意点(公務員特有の視点も)
1. 60歳まで原則引き出し不可
最大のデメリットは「途中でお金を使いたくなっても引き出せない」こと。
急な出費やライフプランの変化に対応しづらいので、生活防衛資金を必ず別に用意しておくことが鉄則です。
2. 掛金の上限が低め
公務員のiDeCo掛金上限は月2万円までと、会社員や自営業者よりも低く設定されています。
「将来もっと積み立てたい」と考えている方は、新NISAなど他の制度との併用も検討を。
3. 口座管理手数料がかかる
iDeCoは、毎月(または毎年)口座管理手数料が発生します。
手数料は金融機関や商品によって異なりますが、長期間積立する場合は“低コスト”を重視しましょう。
4. 退職・転職時の手続きが必要
公務員を退職・転職する際は、「iDeCoの移管手続き」が必須です。
放置すると“運用指図者”扱いとなり、掛金が拠出できなくなる場合があるので要注意。
【3】私の実体験(積立・運用実感)
私も「老後資金はしっかり準備しておきたい」と思い、iDeCoを始めました。
最初は「手続きや制度が難しそう」と感じましたが、実際にやってみると「毎月コツコツ積み立てるだけ」なので意外と手間は少ないです。
iDeCoを始めるときも2ヶ月程度はかかりましたが、手続き自体は簡単でした。
年末調整で“節税の実感”を感じた時、「やってよかった」と思いましたし、強制的に積み立てられる安心感が、日々の家計管理にもプラスになっています。
気になる運用成績ですが、2017年6月~2025年6月の時点で運用利回り「+12%」と絶好調です。
月5000円、運用利回り+12%、積立期間8年の場合(例):60万円投資したものが、115万円になっているという感じです。
公務員がNISAで得られるお得ポイントとデメリット
NISA(新NISA・つみたてNISA)は、いつでも引き出せる自由度の高さと、運用益が非課税になる手軽さが最大の特徴です。
公務員にとっても、NISAは「将来のためだけでなく、さまざまなライフイベントにも柔軟に使える便利な資産形成ツール」です。
ここでは、そのお得ポイントと注意点、実際に使って感じたリアルな体験談をまとめます。
【1】NISAで得られる主なお得ポイント
1. 運用益・売却益がまるごと非課税!
通常の株式・投資信託の運用益や配当金・分配金には約20%の税金がかかりますが、NISAならこれらがすべて非課税。
たとえば「年間10万円の運用益」が出た場合、通常なら約2万円が税金で引かれますが、NISAならまるごと手元に残ります。
2. 途中でいつでも引き出しOK
NISA最大のメリットは「引き出しの自由度」。
教育資金やマイホーム資金など、ライフイベントで急にお金が必要になった場合でも、資産を途中で取り崩して使えるので、安心して積み立てができます。
iDeCoのような資金拘束リスクがありません。
3. 投資できる金額や商品の幅が広い
新NISAは年間最大360万円まで投資OK(2025年現在)
株式・投資信託・ETF・REITなど幅広い商品を自由に選べる
「つみたてNISA」なら、金融庁が厳選した低コスト・優良ファンドのみ
4. 口座管理手数料が無料
基本、NISA口座の管理手数料は無料。
コスト面でも始めやすい制度です。
【2】NISAのデメリット・注意点
1. 所得控除(節税効果)はない
iDeCoのような「掛金全額が所得控除」といった節税メリットはありません。
NISAは「運用益・売却益が非課税になるだけ」です。
2. 非課税枠の再利用はできない
NISAは「その年に引き出した分の非課税枠を再度使うことができない」制度です。
(例:年間360万円のうち100万円分を途中で売却しても、その年は追加で100万円分投資できるわけではない)
3. 投資で損をした場合の「損益通算」「繰越控除」が使えない
通常の証券口座では、損失が出た場合に税金面で優遇される制度(損益通算・繰越控除)がありますが、NISAではこれが使えません。
4. 投資リスクがある
NISAも元本保証ではありません。
選ぶ商品やタイミングによっては、元本割れリスクがあることも忘れずに。
【3】私の体験談(NISA活用のリアル)
私は公務員時代から「お金持ちになりたい」「もっと資産を増やしたい」「早めに公務員をリタイアしたい」という気持ちからNISAを2017年に旧NISAを始めました。
積立はiDeCoでしていたので、NISAでは積極的にリスクをとって大きなリターンを目指すこととし、日本の個別株への長期投資・集中投資を行ってきました。
8年間の運用の中で、一番下がったときで「資産が-50%」、一番上がったときで「資産が3倍」になり、今に至ります。
また、結婚を機に、NISAでも積立を始めたいと思うようになり、新NISAでまずは「月数千円」から投資信託の積立をスタートしました。
iDeCoと違い、気軽に始められるうえ、生活費や教育資金が急に必要になったときも、「すぐに引き出せる安心感」がとても大きいです。
節税インパクトはiDeCoほど大きくないものの、「使い勝手が良い」「無理なく続けられる」という点では本当に便利だと感じています。
【どちらを選ぶ?】タイプ別おすすめパターン診断
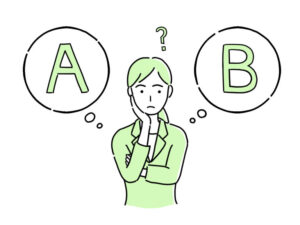
「結局、自分はiDeCoとNISA、どちらを優先すればいいの?」――
これが多くの公務員の方の最大の悩みです。
ここでは年代・家族構成・貯蓄状況・目的別に、おすすめのパターンを診断しつつ、リアルな活用例もご紹介します。
【A】20~30代の独身・若手公務員の場合
おすすめは…NISA優先+少額iDeCo併用!
まずはNISAで「貯蓄兼ねた資産運用」を気軽に始めてみるのが安心。生活防衛資金が十分にできたら、iDeCoも月5,000円など少額から開始するのがおすすめです。
予想外の出費やライフイベントが多い年代なので、「自由に引き出せるNISA」を使う安心感は大きいです。
【実例】
私の職場の元後輩(20代男性)は、私にアドバイスされて、NISAでの積み立てを少額ですが開始しました。将来のためiDeCoへの投資も検討中です。
【B】30~40代・子育て中・住宅購入を考えている場合
おすすめは…NISAとiDeCoの併用バランス型!
教育費やマイホーム頭金など、「数年以内に必要になるかもしれないお金」はNISAで運用。
「絶対に老後まで使わないお金」はiDeCoで積立。
生活費や急な出費への備えも、まずはNISAから優先し、貯蓄に余裕が出てきたらiDeCoを増額。
【実例】
私自身、子どもが小さいうちはNISA多め&iDeCo少な目で資産運用し、生活に余裕ができたタイミングでiDeCoの掛金も増額していこうと考えています。
【C】40~50代・資産形成に本腰を入れたい・収入安定の世代
おすすめは…iDeCo満額+NISA併用!
定年までの残り時間を活かして、iDeCoの掛金上限(公務員は月2万円)まで積み立て、大きな節税メリットを享受。
さらに、NISA枠もできるだけ活用し、老後資金を「複数の制度で分散」して育てると安心です。
【実例】
私の元上司(50代女性)は、iDeCoで老後資金を着実に積み上げつつ、NISAでより積極的に資産運用も行っています。「節税と資産運用のいいとこ取り」と満足している様子でした。
【D】こんな使い分けもおすすめ!
「ボーナスだけNISAで一括投資」+「毎月の給与からiDeCo」
「NISAで家計の余剰資金を運用」+「iDeCoで退職後資金を堅実に」
「家計やライフプランは人それぞれ違う」ので、どちらか一方だけにこだわる必要はありません。
家計簿アプリや資産管理ツールでシミュレーションしてみるのもおすすめです。
重要なのは「使い道」「必要なタイミング」を想定して、無理なく長く続けられる仕組みを作ること。
途中でライフスタイルや家計が変わったら、掛金や投資額も柔軟に調整してOKです。
よくある質問Q&A【2025年最新版】

ここでは、公務員がiDeCoやNISAを使う際に寄せられることの多い疑問・不安に、2025年最新版の情報で丁寧に答えます。
Q1. 公務員がiDeCoやNISAをやると副業扱いになる?
A. 副業にはなりません。
iDeCoもNISAも「自分の資産運用・老後資金づくり」のための制度であり、公務員の副業規定には一切該当しません。運用益や売却益、配当を得ても、職場に申請する必要はなく、評価や処分に影響することもありません。
Q2. iDeCoとNISAは同時に利用できる?
A. もちろん、両方併用できます。
むしろ、「iDeCoで老後資金、NISAで生活・教育資金や自由資金」と分けて活用する人が多いです。資金や目的ごとに無理のない範囲で使い分けましょう。
Q3. iDeCoやNISAの運用で損が出た場合、税金はどうなる?
A. 運用益が出なければ課税されません。
iDeCo・NISAともに元本割れした場合、課税されることはありません。ただし、NISAの場合は「損益通算」や「繰越控除」など、通常口座で可能な税務優遇が使えない点に注意しましょう。
Q4. 掛金・投資額は途中で変更できる?
A. どちらも変更可能です。
iDeCoは年に1回(または金融機関による)、NISAはいつでも投資額の増減や売却が可能です。家計の状況やライフイベントに合わせて無理なく調整してください。
Q5. 退職・転職した場合、iDeCoやNISAはどうなる?
A. 継続利用が可能です。
iDeCoは、退職・転職後も手続きをすれば引き続き積み立て・運用ができます(職種や加入区分によって掛金上限が変わることがあります)。
NISAは転職や退職に関係なくそのまま利用OKです。
Q6. どちらを優先すべきか迷ったら?
A. 「お金の使い道」と「必要なタイミング」で選ぶのがコツです。
60歳まで絶対使わない老後資金→iDeCo
いつ必要になるかわからない資金や、生活防衛資金→NISA
迷ったときは「まずはNISAから」始め、家計に余裕ができたらiDeCoを追加するのもおすすめです。
Q7. 金融機関ごとの違いはある?
A. あります。
iDeCoは特に「手数料」「商品ラインナップ」が金融機関によって異なります。NISAも取扱商品や使い勝手は証券会社によって違うので、「ネット証券(SBI証券・楽天証券・マネックス証券など)」が手数料・使い勝手の面でおすすめされることが多いです。
疑問や不安は、「公務員×資産運用」に詳しいFPや証券会社のサポート窓口に相談、あるいはNISAやiDeCoを特集している雑誌を参考にするのもおすすめです。無理なく安心して続けるために、しっかり調べてから始めましょう!
失敗しないためのチェックリスト&注意点
せっかくiDeCoやNISAを活用するなら、「あとで損した…」「思っていたのと違った…」とならないために、必ず押さえておきたい注意点やよくある落とし穴をまとめます。
始める前に下記を確認し、納得したうえで制度を使いこなしましょう。
【1】iDeCo・NISAを始める前に必ずチェック!
□ 生活防衛資金(急な出費や失業に備える現金)が十分にあるか?
生活費の3~6か月分の現金はiDeCoやNISAに回さず、手元に残しましょう。
□ 投資に回すお金の使い道・タイミングは明確か?
「老後資金」「教育費」「マイホーム資金」など目的ごとに制度を使い分けましょう。
□ 制度のメリット・デメリットを理解できているか?
iDeCoは60歳まで引き出し不可、NISAは非課税枠の再利用不可など、制約も要チェック。
【2】よくある落とし穴とその対策
iDeCoで無理な金額設定→家計が苦しくなった
→ 掛金は「無理のない範囲」で設定。途中で減額や一時停止も可能です。
NISAの投資枠を使い切ってから急な出費が発生した
→ 非課税枠は再利用できないため、余裕資金で運用を。
制度や商品選びで迷いすぎて、始めるタイミングを逃す
→ まずは少額・つみたてNISAやiDeCoのミニマムスタートもOK!途中で見直しや増額もできます。
【3】最新制度改正や金融機関の変更にも注意
制度の細かいルール(非課税枠や手数料)は定期的に見直されることがあります。
金融機関を途中で変えたい場合、手続きや期間がかかるので早めに調べておきましょう。
【4】運用後も“ほったらかし”にしない
年に1回は資産状況や商品配分を見直しましょう(リバランス)。
「投資商品が合っているか」「家計に無理はないか」も定期的に確認を。
【5】シミュレーションやFP相談も活用を
金融庁・証券会社・銀行のWebサイトでは、積立シミュレーションが無料で利用できます。
参考サイト:金融庁「つみたてシミュレーター」、iDeCo公式サイト「かんたん税制優遇シミュレーション」
不安があればFP(ファイナンシャルプランナー)や証券会社の窓口で事前相談を。
まとめ|iDeCo・NISAを賢く使いこなすために
iDeCoとNISAはどちらも、公務員の将来設計・資産形成にとって非常に強力なツールです。
ただし、「自分にはどちらが向いているか?」「家計や将来プランにどんな影響があるか?」を理解して上手に活用することが、最も大切です。
【ポイントのおさらい】
iDeCoは老後資金専用の“最強の節税口座”
⇒ 節税効果が大きいが、60歳まで引き出せない制約ありNISAは「自由度の高い非課税投資枠」
⇒ いつでも引き出せる柔軟性が魅力。目的別に分けて活用できる
【上手な活用のコツ】
生活防衛資金は必ず現金で手元に残し、「余裕資金」でiDeCo・NISAを活用する
目的や将来のライフイベントごとに、どちらの制度を使うか決める
迷ったらNISAから始め、家計に余裕が出てきたらiDeCoも追加する
定期的に制度の見直しや資産配分をリバランスする習慣をつける
【私からのメッセージ】
私自身も、公務員時代は「資産運用=難しいもの」というイメージを持っていましたが、iDeCoやNISAを活用しはじめてから「将来への不安が減り、家計にも安心感が出てきた」と実感しています。
まずは少額・無理なく、1歩を踏み出すことが大切です。
制度を味方につけて、あなた自身やご家族の明るい未来をしっかり準備していきましょう。
【関連記事】
【2025年最新】公務員のiDeCo完全ガイド|初心者向け始め方・メリット・デメリット・注意点を元公務員FPが解説
【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説
