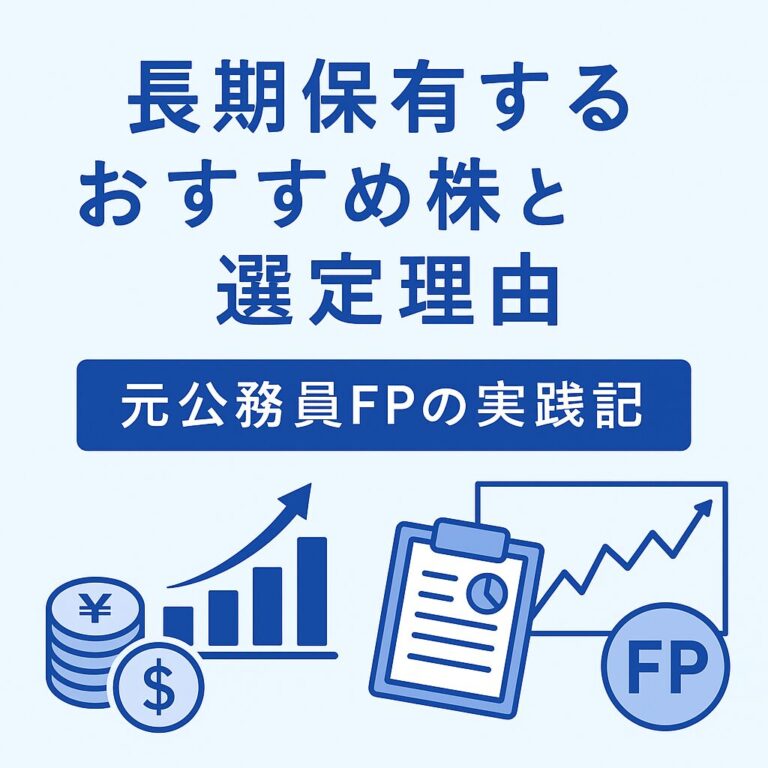株式投資で“長期保有”を続けることは、本当に資産形成に役立つのでしょうか?
私は元公務員であり、FP資格を持つ個人投資家(歴9年)として、自分自身の資産を守りながら少しずつ増やすことを目指してきました。
その中で、実際に何年も持ち続けている銘柄が「ライザップ(2928)」と「鎌倉新書(6184)」です。
公務員時代は「副業禁止」の不安や周囲の目もあり、積極的な売買やリスクの高い投資は控えていました。
そのため、じっくり時間をかけて成長する企業に投資し、配当や値上がり益を長期で狙うスタイルが自分には合っていたと感じています。
この記事では、
なぜこの2つの銘柄を選び、長期で持ち続けているのか
実際の配当や投資成績、感じたリスクや反省点
長期保有のリアルなメリット・デメリット
を、経験に基づいてできるだけ正直にお伝えします。
「長期保有すれば誰でも必ず勝てる」という単純な話ではありませんが、公務員や安定志向の方にもヒントになる投資スタイルや考え方が伝われば幸いです。
初心者や投資に不安のある方でもわかるよう、やさしい言葉で書きました。
それでは、私の実践記をどうぞご覧ください。
公務員FPが長期保有する理由と投資スタンス
長期保有とは?なぜおすすめなのか
「長期保有」とは、文字通り“株を長い期間持ち続ける投資スタイル”のことです。
短期売買で利益を狙うデイトレードやスイングトレードとは違い、数年~10年以上にわたり同じ銘柄を保有し、企業の成長や配当の増加をじっくり待つのが特徴です。
なぜ長期保有が多くの投資家から支持されているのでしょうか?
その理由は、以下のようなメリットがあるからです。
配当金や株主優待などの“インカムゲイン”が積み重なる
時間を味方につけて“複利効果”を活かせる
短期の株価変動に一喜一憂せず、落ち着いた資産形成ができる
売買手数料や税金の負担が少ない
優良企業であれば、企業の成長とともに資産も増える
- 企業を応援している実感がわきやすく、社会貢献の一環にもなる
特に公務員や、日中忙しい会社員の方には「相場を毎日チェックしなくて良い」「時間を自分の本業や家族に使える」という精神的な余裕も大きな魅力です。
投資方針・守りの運用スタンス
私は“守りの資産運用+応援したい企業を長く持ち続ける”を何より大切にしています。
具体的には、
生活資金や万一の予備費は絶対に投資に回さない
ある程度分散投資(複数銘柄や業種)をし、1社に全額をいれない
- 分散はしすぎない(特に資産が少ないうちは利益が分散してなかなか資産が増えていかないので注意)
- 購入時は徹底的に分析し、自分が納得し、本当に応援したいと思える企業にある程度集中投資(一度買ったら自分の思い描いたストーリーが崩れない限り売らない)
株価は四六時中確認しないが、企業分析や決算チェックは日々行い、業績悪化が明らかな場合は売却も検討する
株価の上がり下がりで一喜一憂せず、企業の本質や社会的な存在意義を重視
- 株の勉強を継続し、知識と経験を蓄え続け、リスクを可能な限り抑える
私が選んだ「ライザップ」と「鎌倉新書」はどちらも“ビジネスモデルや将来性に独自性があり、長く応援したいと思える企業”でした。
一方で、どんな銘柄にも「株価下落リスク」や「業績悪化リスク」はつきものです。
だからこそ、焦って売買するよりも、“自分が納得できるまでじっくり保有する”というスタンスを意識してきました。
次章からは、それぞれの保有銘柄について、なぜ選び、どう感じているかを体験談ベースでご紹介します。
保有銘柄1:ライザップ(2928)を選んだ理由と実体験
ライザップの魅力・将来性
「結果にコミットする」で有名なライザップは、フィットネス業界の革命児ともいえる存在です。
私は、単なるダイエットジムにとどまらず、健康ビジネスや関連企業のグループ展開など、多角的な成長戦略に魅力を感じてきました。
選定ポイントは――
独自ブランド力。誰でも名前を知っている。ブランド力を高めたくて悩んでいる企業は多いなか、アドバンテージ。
- 社長の持ち株比率が高く、意思決定がスムーズ。
チョコザップがようやく黒字転換し始めてきたところ。今後、回収フェーズに入っていく。
- チョコザップのフランチャイズ化が始まれば一気に店舗数と会員数が急増すると推察(今は全店直営店だが、都市部がメイン。地方はフランチャイズのほうがスムーズ)。
- チョコザップの海外進出が徐々に本格的になっている。海外でも一気に店舗数や会員数は伸びる可能性は十分ある。
- 「業績が上がれば復配をする」と社長が言っているので、復配時の株価上昇も期待できる。
現在、札幌証券取引所に上場中であり、今後業績が伸び、財務健全性も高まれば東証上場が期待できる(社長は「準備中」と述べている)。
- PERは割高となっているが、チョコザップの好業績がまだ加味されていない状態。利益が顕在化してくれば、一気に割安に進むと想定。
- 買収した多数のグループ会社が低空飛行のまま。逆に言えば、これらの会社がうまく回りだせば業績急拡大のチャンスあり。
- 5年以上ライザップを持っているが、社長のチャレンジ精神(新規事業構築力)と自社の会計状況を熟知している点が好印象。
正直、株価が大きく下がった時期もありましたが、「成長ストーリーが崩れていない」「経営陣の本気度が伝わる」と感じ、逆に買い増しのチャンスと捉えて長期保有を続けています。
過去の株価・配当・保有期間データ
私がライザップを初めて買ったのは2017年頃。当時はまだ「急成長のスター銘柄」として注目されていましたが、その後株価は大きく上下しました。
以下、しっかりと記録を付け始めた2019年からのデータです。
- 購入株価:コロナ禍で急落したときに大量に買い(140~250円)
株価推移:最安値は103円(コロナ暴落時)、最高値は579円、現在は200円台を推移
保有期間:5年程度(途中買い増し・一部利確もあり)
- 株主優待:多数の商品から優待が選べるので大満足(特にブルーノの調理家電がお得)
配当金:数年は無配だったが、業績回復の兆しとともに復配期待もあり
実際の投資成績・失敗や反省点も正直に
私のライザップ投資は、現時点で“トータルでは少しプラス”です。
しかし「短期で利益が出ない=失敗」とは思っていません。むしろ、
“自分の選択理由・成長ストーリーに納得できているか”
“冷静に企業分析を継続できるか”
を重視しています。
一方、
買い時・売り時をもっと慎重に見極めるべきだった
一時の人気や話題性だけで買い増ししすぎた局面も反省点
など、リアルな失敗もあります。
それでも「長期目線で持ち続けているからこそ、“会社の本質的な強み”や“経営改革の実態”も見えてくる」と実感しています。
今後は配当復活・中期経営計画の進捗・東証上場をじっくり見守りつつ、引き続き“応援株主”としてホールドする方針です。
保有銘柄2:鎌倉新書(6184)を選んだ理由と実体験
鎌倉新書の魅力・将来性
鎌倉新書は一見地味ですが、実は「終活」分野において圧倒的な実績を持つ企業です。
葬儀、墓、相続など“人生の節目”をサポートする情報提供サービスやマッチング事業を手がけており、今後の高齢化社会でますますニーズが拡大していくことに大きな可能性を感じました。
選定ポイントは――
終活・高齢者支援という社会的意義の高いビジネスモデルで素直に応援したいと思った。
終活市場にはまだまだ成長余地があると判断。
財務が非常に健全で、かつ現金や余剰金が豊富になる。余力を活かした「次なる一手」次第では化けると踏んでいる。
- 期間限定だが増配をしていて、予想配当利回り4.3%(2025年8月1日時点)は高配当株に入る。
- 時価総額が180億円(2025年8月1日時点)とまだまだ会社規模が小さい。今後の拡大が期待できる。
- 地方自治体と鎌倉新書のサービス連携数が急増している。国策に売りなし。
- 営業利益率が非常に良いビジネスモデル(13%)
- 5期連続で増収増益
過去の株価・配当・保有期間データ
私が鎌倉新書に投資したのは、2022年のことです。当時から安定した成長を続けており、
株価:購入時は630円、最高値は1197円、現在は500円台
保有期間:3年(途中で買い増し・一部利確も)
配当金:毎年安定して支払われており、増配も継続中
実際の投資成績・今後の見通し
鎌倉新書は、最初は『地味な業種だな』という印象もありましたが、会社説明資料や決算発表をじっくり読んでみると“社会の高齢化”と“ネット時代の情報マッチング”という二つの大きな潮流にしっかり乗っていることが分かり、納得して購入しました。
鎌倉新書は、安定した配当+中長期の株価成長の両方を目指せる銘柄です。私自身、
受け取った配当金を再投資に回すことで、資産全体の成長を実感
業績はコロナショック等の荒波はありましたが、長期で右肩上がりを維持
地味ながら“守りと攻め”を両立できる株であり、私にとっても「安心して長期で保有できる」存在でした。
もちろん、どんな企業も将来の業績悪化や業界再編リスクはあります。
今後も決算や業績、社会情勢をウォッチしながら、配当・成長のバランスを重視して保有を続けていくつもりです。
長期保有で気づいたメリット・デメリット
メリットまとめ
実際に何年も株を長期保有してみて、短期売買では得られないメリットを強く実感しています。
配当金や株主優待など“インカムゲイン”が積み重なる
ライザップや鎌倉新書のように、年に一度・二度の配当金が着実に積み上がっていくと、「自分のお金が働いてくれている」実感が持てます。複利効果が生きる
受け取った配当金をさらに再投資すれば、まさに“雪だるま式”に資産が増えていきます。これは長期保有だからこそ味わえる醍醐味です。株価の上がり下がりに動じなくなる
短期目線だと小さな値動きで不安になりがちですが、長期投資なら「一時的な下落も慌てず対応できる」メンタルが身につきます。企業と一緒に成長する喜びがある
株主として長く応援していると、経営方針や新サービスなどにも親しみが湧き、日常生活でもニュースを前向きに見られるようになります。
デメリット・リスク・注意点
もちろん、長期保有にもリスクやデメリットがあります。
実体験から感じた注意点を正直に挙げます。
業績悪化や無配リスク
企業の業績が悪化すれば、配当金が減ったり無配になったりするリスクがあります。ライザップも現在無配の時期です。株価の大幅下落で含み損が長期化する場合も
長期で持てば「いつか上がる」とは限りません。場合によっては“塩漬け株”となり、資金が動かせなくなることもあります。企業分析や情報収集は欠かせない
一度買ったら放置ではなく、決算資料や業界ニュースをチェックし続ける「最低限のメンテナンス」は必須です。生活資金や急な出費の備えは必ず現金で持つこと
「長期保有だから大丈夫」と全資金を株に突っ込むのは危険です。余裕資金だけで運用しましょう。
長期保有は、「安心感」と「成長の楽しみ」の両方が味わえる反面、“じっくり待つ忍耐”や“定期的な見直し”も欠かせません。
良い面も悪い面も理解した上で、自分に合った投資スタイルを見つけていきましょう。
Q&A「長期保有って本当に儲かるの?」「売り時は?」
Q1. 長期保有すれば誰でも儲かるの?
A. 必ず儲かるとは限りませんが、“損しにくい”投資スタイルです。
長期保有は、企業の成長や配当の積み重ねをゆっくり待つスタイルなので、短期の値動きで焦ることは少なくなります。
しかし、すべての株が右肩上がりに成長するわけではありません。
私自身も、ライザップで大きな含み損が続いたこともあります。
ポイントは「成長力があり、応援したい企業を選ぶ」「途中で慌てて売らない」の2つです。
また、配当や優待をコツコツ受け取ることで、株価が伸び悩んでもトータルでプラスになるケースもあります。
Q2. どんなときに売ればいいの?
A. 「自分の投資理由が崩れたとき」が売り時です。
会社のビジネスモデルや将来性に疑問を感じたとき
決算や業績で明らかに悪化が続くとき
社長交代など経営方針が大きく変わったとき
急にお金が必要になったとき(生活防衛)
私は「最初に決めた保有理由」がなくなったとき、あるいはライフプランの変化でお金が必要になったときは売却も検討しています。
「なんとなく不安」「値下がりでパニックになった」といった感情だけでは、基本的に売らないように心がけています。
Q3. 株価が大きく下がったとき、どうする?
A. 慌てて売らず、まずは企業分析・業績を再確認します。
大きく下落したときほど感情が揺さぶられますが、「企業価値や成長性に変化がないか」を落ち着いて分析します。
ライザップの株価急落時も、決算やIR情報をよく読んで、「自分はこの会社をまだ信じられるか?」を自問しました。
あと下がった理由もしっかり分析します。
下がった理由次第では買い増しする場合もあります。
Q4. 長期保有の最大のコツは?
A. “自分なりの投資理由”をはっきり持つことです。
雑誌やSNSの情報ではなく、「なぜこの企業を応援したいのか」「どんな未来を期待しているのか」を明確にしましょう。
そうすれば短期的な値動きにも振り回されにくくなります。
長期保有には“忍耐”や“継続的な企業観察”が必要ですが、それを乗り越えた先に「資産の成長」や「企業との信頼関係」が生まれます。
焦らず、着実にコツコツ続けていきましょう。
まとめ・注意喚起・次の行動案
まとめ
長期保有は、決して一発逆転やギャンブルではありません。
「じっくり企業と向き合い、配当や成長をコツコツ積み重ねる投資スタイル」です。
私がライザップと鎌倉新書を選び、実際に保有を続けてきたのも、
自分なりの“納得できる理由”があったから
急がず焦らず“応援株主”の気持ちで保有できたから
です。
株価の上下や一時の損益に一喜一憂せず、長い目で見て「この企業をこれからも応援したい」と思えるか?
配当や業績を“自分の人生の一部”として楽しめるか?
――それが長期保有の最大の醍醐味だと感じています。
注意喚起
本記事は特定の銘柄を推奨・勧誘するものではなく、「私個人の投資体験・考え方」をお伝えするものです。
投資は必ず“自己責任”で、ご自身の生活やライフプラン、リスク許容度に合わせて判断してください。
最新の企業情報や経済情勢、税制・制度は必ずご自身でも確認をお願いします。
【関連記事】
公務員が失敗しない個別株の選び方|初心者向け実践ガイド【元公務員FP体験談】