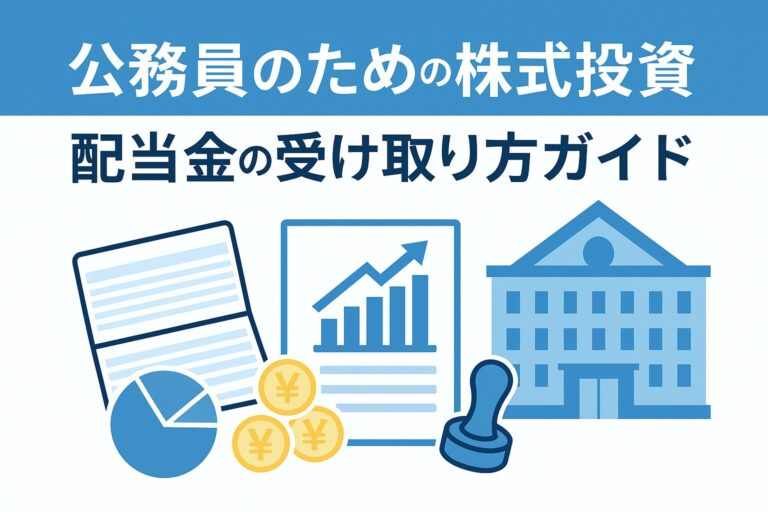株式投資の醍醐味のひとつが「配当金を受け取ること」です。
特に公務員の方は、給与以外で安定的に資産を増やしたいと考える方も多いでしょう。
しかし、
「公務員でも株の配当金をもらって問題ないのか?」
「受け取り方法はどれがベスト?」
「バレたり処分されたりしない?」
といった不安や疑問を持つ方も少なくありません。
本記事では、元公務員FPとして実際に株式投資・配当金受取を経験した筆者が、公務員でも安全に、かつ最大限メリットを得られる「配当金の受け取り方」を徹底解説します。
証券口座の選び方から、配当金受取方法の具体的な手続き、公務員ならではの注意点や、リアルな体験談・数字データまで網羅。
「初心者でもわかりやすく」「最新の制度変更リスク」や「バレないための注意点」まで余すことなく紹介します。
この記事を読めば、公務員として安心して配当金を受け取り、自分らしい資産形成ができるはずです。
公務員が株式投資で配当金を受け取るときの基本

配当金とは?初心者でもわかる仕組み
株式投資の魅力のひとつが「配当金」です。
配当金とは、株式会社が利益を株主に分配するお金のことで、持っている株の数に応じて定期的に受け取れます。
例えば、1株あたり年間50円の配当がある株を100株持っていれば、年間5,000円の配当金を受け取れる、というイメージです。
配当金の主なポイントは以下の通りです。
企業の利益に応じて支払われる(毎年変動する場合もあり)
一般的には年1~2回、企業によっては四半期ごとなども
株を保有しているだけで受け取れる「不労所得」のひとつ
企業業績によっては無配(ゼロ)になることもある
また、配当金は企業によって金額も回数もバラバラです。
上場企業の多くは配当を出していますが、「成長企業(ベンチャー系など)」は配当よりも事業投資を優先し、無配のケースも多いです。
配当金の主な受け取り方3パターン
配当金は、株主が好きな方法で受け取ることができます。
主な受け取り方は3つあります。
証券口座での受け取り(株式数比例配分方式)
証券会社の口座に自動的に入金される方式。ネット証券ユーザーの大多数がこれ。銀行口座での受け取り
指定した銀行やゆうちょ銀行などに配当金が振り込まれる方式。郵便局(ゆうちょ銀行)で現金受け取り
配当金領収証が自宅に届き、それを郵便局で現金化する方式。
現在、証券口座での受け取り(株式数比例配分方式)が最も一般的で便利です。
税制面でもメリットが大きく、受け取った配当金の履歴が証券口座で一目でわかります。
配当金の仕組みと受け取り方のパターンを知ることで、自分に合った受け取り方法を選ぶ準備ができます。
次章では、実際に証券口座を開設し、配当金の受け取り設定をする具体的な流れを詳しく解説します。
証券口座の開設から配当金受取設定まで

どの証券口座を選ぶべきか(ネット/対面・NISA/特定口座)
株式投資で配当金を受け取るには、まず証券口座の開設が必要です。
証券口座には大きく分けて「ネット証券」と「対面証券(店舗型)」がありますが、最近は手数料が安く使い勝手が良いネット証券(SBI証券、楽天証券、マネックス証券など)が圧倒的に人気です。
ネット証券なら、スマホやパソコンから口座開設の申し込みができ、書類提出や本人確認もオンラインで完結します。
また、配当金を効率よく受け取るためには「NISA口座」や「特定口座」の選択も重要です。
NISA口座:
年間一定額までの配当金や売却益が「非課税」になる制度です。
→配当金を非課税で受け取りたい場合は必ず利用しましょう(2024年から新NISAが始まり、より使いやすくなっています)。特定口座:
証券会社が税金計算・納付まで自動でやってくれる「源泉徴収あり」がおすすめです。
→確定申告の手間が減り、初心者や忙しい公務員にも便利です。
証券会社や口座の種類は「自分にとって一番管理しやすいもの」を選ぶのがコツ。
特に公務員の場合、仕事が忙しくて時間が取れないことも多いので、スマホアプリやWeb管理がしやすいネット証券&NISAを利用すると失敗しにくいでしょう。
配当金の受取方法(銀行振込/証券口座/ゆうちょ)
証券口座を開設したら、配当金の受取方法を設定しましょう。
最もおすすめなのは「株式数比例配分方式(証券口座受け取り)」です。
これを選ぶと、全ての保有株の配当金が自動で証券口座にまとめて入金され、税金も自動計算&納付されるので非常にラクです。
【主要な受取方法の特徴】
| 受取方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 証券口座受け取り(株式数比例) | 一括管理・自動入金・税制優遇・管理が簡単 | 口座を持っていないと不可 |
| 銀行振込 | 普段使いの銀行口座で受け取り可能 | 各銘柄ごと・手続きが面倒 |
| ゆうちょ/郵便局窓口 | 直接現金で受け取り可能 | 毎回窓口に行く必要がある |
設定は証券会社のマイページや書類提出で簡単に完了します。
受取方法の変更手続きの流れ
「受取方法を途中で変えたい」「配当金を他の銀行に振り込みたい」と思ったら、各証券会社のマイページから「配当金受取方法変更」の手続きを行いましょう。
ネット証券なら数分で申込可能、書類郵送も不要なケースがほとんどです。
【変更手順の例(SBI証券の場合)】
画面上部の「My設定」をクリック
「配当金受領サービス」をクリック
希望する受取方法を選択
確認画面で内容をチェックし、手続き完了
注意点
・配当金の受取方法は株ごとではなく「証券口座全体」で一括管理が基本
・設定変更の反映には「配当基準日」などでタイムラグが出る場合もあるので、早めに設定を済ませておきましょう。
公務員が知っておきたい注意点とリスク

副業規定との関係・バレるリスクは?
まず、「公務員が配当金を受け取っても副業規定違反にならないのか?」という点が、多くの方にとって最大の不安だと思います。
結論から言うと、配当金の受け取り自体は副業禁止規定に該当しません。
なぜなら、株式投資は「資産運用」であり、「自ら労務を提供して得る対価」ではないからです。
地方公務員法(第38条)や国家公務員法でも、「事業・営利活動への従事」が制限されていますが、自分のお金で株を買って配当や値上がり益を得る行為はOKとされています。
ただし、「業務時間内の売買」や「インサイダー取引」などは禁止されています。
配当金と税金(源泉徴収・確定申告・NISA)
配当金を受け取った場合の税金はどうなるのでしょうか?
基本的には、証券口座で受け取る「株式数比例配分方式」なら、証券会社が自動で源泉徴収(約20.315%)してくれるので、ほとんどの方は確定申告不要です。
NISAの場合
NISA口座で購入した株の配当金は「非課税」です。
つまり、税金が一切かかりません(ただし、NISA枠で受け取るには「証券口座での受け取り」設定が必須です)。
確定申告が必要な場合
配当金を「総合課税」で申告し、所得控除や配当控除を受けたい場合
複数の証券会社を利用している場合
年間の配当額や副収入が大きく、他の収入と合算して節税を図りたい場合
とはいえ、公務員の場合は「確定申告で余計な情報を出す」のが不安な方も多いので、「NISA」か「特定口座(源泉徴収あり)」で完結させるのが一番安心・簡単です。
制度変更・法改正リスク
株式投資や配当金の税制は毎年のように見直しが行われています。
たとえば、NISAの非課税枠や制度内容も2024年に大きく改正され、今後も税率や受取方法が変更される可能性があります。
公務員として安心して資産運用を続けるためには、最新の制度情報や税制変更にアンテナを張っておくことが大切です。
わからない場合は【金融庁や証券会社公式サイト】などの一次情報を必ずチェックし、必要に応じてFPなどの専門家に相談しましょう。
※公式情報リンク例:
実際にやってみた!配当金受取体験談&数字データ
証券口座開設から配当金受け取りまでの実例
ここからは、私自身が現役公務員時代に実際に体験した「株式投資と配当金受け取り」の流れをご紹介します。
私が最初に証券口座を開設したのは、ネット証券のSBI証券でした。
手続きは全てネット上で完結し、PCだけで申し込みができるので忙しい公務員生活の合間でもスムーズに進めることができます。
証券口座開設後、NISA口座も同時に申し込み。
初めて株を買ったときは「本当に配当金なんてもらえるのかな?」と半信半疑でしたが、半年後、初めての配当金が証券口座に自動的に振り込まれたときは感動しました。
たとえば私が持っている鎌倉新書のような中小型株でも、買う銘柄や株数にもよりますが、10万円なら数千円、100万円なら数万円の配当金が入金されます。
年間受取額・運用成績と実感
私の場合、値上がり益+配当金狙いで3銘柄を保有していて、年間10万円以上は配当金を受け取っています。
1つの銘柄は現在無配になっているので、復配を狙っています。
たとえば、1株当たり50円の配当が出る銘柄を100株持てば、年間で5,000円の配当金になります。
これを10銘柄に分散すれば、合計5万円。
さらに、配当利回りが高い銘柄や、増配傾向にある企業を選ぶことで、長期的には配当収入がじわじわと増えていくのが実感できます。
配当金の受け取りは「証券口座受け取り(株式数比例配分方式)」に一本化しておけば、税金も自動で差し引かれ、管理も非常にラクです。
実際の証券口座の画面で「○月○日に××円の配当金入金」と記載されているのを見ると、毎回ちょっとしたご褒美をもらったような気持ちになります。
配当金を増やすアイデア
私が実践している「配当金を増やすコツ」をいくつかご紹介します。
高配当・増配傾向のある銘柄を選ぶ
業績が安定していて、毎年配当を増やしている企業(いわゆる「連続増配株」)を中心に選ぶことで、将来的な配当収入アップを狙えます。NISA口座をフル活用
配当金が非課税になるNISA口座をできるだけ活用することで、手取りの配当収入を最大化します。再投資で複利効果を活かす
受け取った配当金を使わず、さらに追加で株を買うことで「配当の雪だるま効果(複利)」を狙います。分散投資で安定化
1社だけに集中せず、複数の業種・企業に分散して投資することで、リスク分散しつつ安定した配当収入を得やすくなります。
私自身、配当金の「ちょっとした副収入」が日々の生活の楽しみや安心につながっています。
次の章では、読者からよくいただく質問や公務員ならではの不安について、Q&A形式で解説します。
よくある質問Q&A

Q1. 配当金の受取方法は途中で変えられますか?
A. はい、途中で何度でも変更可能です。
配当金の受け取り方法(証券口座受け取り、銀行振込など)は、各証券会社のマイページやカスタマーサポートからいつでも変更できます。
ただし、変更の反映には「配当基準日」や「株主名簿確定日」などでタイムラグが生じる場合があるため、配当金を受け取る直前のタイミングではなく、余裕をもって手続きすることをおすすめします。
Q2. 公務員が配当金をもらうことで、職場にバレたり処分されたりしませんか?
A. 基本的にバレることはなく、処分リスクも極めて低いです。
配当金は資産運用による収入なので、原則として副業禁止規定には該当しません。
また、証券口座や銀行口座に配当金が入金されても、勤務先や人事に通知がいくことはありません。
ただし、「株取引の頻度が極端に多く、事実上の“トレーダー”状態」や「第三者の資金を預かって運用している」などは規定違反となる場合もあるので要注意です。
Q3. 配当金は確定申告しなければいけませんか?
A. ほとんどの場合は不要です。
特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座で受け取っている限り、証券会社が税金を自動で差し引くため確定申告は原則不要です。
ただし、複数口座を利用している場合や配当控除を活用して節税したい場合は確定申告が必要になるケースもあるため、不安な場合は税務署やFPに相談しましょう。
Q4. 配当金の受け取りで気を付けることは?
A. 配当金の受け取り設定と、税制・制度変更リスクです。
・「株式数比例配分方式(証券口座受け取り)」を選ぶことで管理や税金面が有利になります。
・NISA口座での受け取りも、必ず証券口座設定が必要です。
・税制やNISA制度の内容は頻繁に変わるため、毎年必ず最新情報を確認しましょう。
・わからない場合は、証券会社や金融庁、税務署の公式サイトを確認するのが安心です。
Q5. 配当金の額が少額でも証券口座で受け取れますか?
A. 1円単位でも証券口座で受け取れます。
配当金は1株から支払われるので、保有株数が少なくても大丈夫です。
私も投資当初は年数百円からのスタートでしたが、積み重ねることで徐々に配当収入が増えていきました。
配当金の受け取りや公務員としての不安については、誰もが最初は同じ疑問を持っています。
不明点は遠慮せず、公式情報やFP、証券会社のカスタマーサポートに相談しましょう。
配当金の活用アイデア
配当金を受け取ったら、「どんな使い道がいいの?」と迷う方も多いはずです。
おすすめの活用方法をいくつかご紹介します。
① 再投資で“配当の雪だるま”を作る
受け取った配当金でさらに株を買い増し、将来的な配当収入を増やす方法です。これを続けると“複利の力”が働き、10年・20年後の資産形成に大きな差がつきます。② 生活費やちょっとしたご褒美に使う
配当金で外食をしたり、趣味や子どものために使ったり。配当金が生活に「ゆとり」や「ちょっとした楽しみ」をもたらしてくれます。③ 投資信託やiDeCo・つみたてNISAの資金に充てる
他の資産形成商品と組み合わせて使うことで、より効率的な資産運用ができます。④ 緊急時の“安心資金”として残す
配当金をそのまま現金で積み立てておけば、急な出費やトラブルの時に役立ちます。
配当金は「受け取るだけ」で終わりではなく、“どう活かすか”によって人生の安心感も変わってきます。
次章ではまとめと今後の注意点、読者へのご案内をお伝えします。
まとめ
公務員が株式投資で配当金を受け取ることは、「副業禁止規定に抵触しない資産運用」として安心して始めることができます。
配当金の受け取りは証券口座受け取り(株式数比例配分方式)が最も手軽で便利、税金面でも有利です。
NISA口座の活用や再投資、管理アプリの利用などで、配当収入を着実に増やすことも十分可能です。
一方で、制度や税制は毎年変更されるリスクがあります。
必ず金融庁や証券会社の公式サイトで最新情報をチェックし、不明な点は専門家(FPや税理士)に相談しましょう。
この記事を読んで、少しでも配当金投資や資産形成に興味が湧いた方は、まずは証券口座の無料開設やNISA枠の活用を始めてみましょう。
疑問や不安があれば、お気軽に無料相談サービスや関連記事もご利用ください。
公務員でも、今日から“安全で地道な配当生活”をスタートできます!
【関連記事】
【元公務員FP解説】公務員向け高配当株ガイド|おすすめ銘柄と安全な選び方【2025年】
【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説