教育資金の準備について、「どうすれば安心して始められるんだろう…」と悩んでいませんか?
特に、公務員という安定した職業だからこそ、学資保険の選び方が一般の家庭とは少し異なる視点で求められます。
「返戻率だけ見ればいいのか?」
「ボーナス月の入金タイミングって重要?」
「本当に必要なのは学資保険だけ?」
このような疑問をお持ちの方に向けて、私は現役公務員として、学資保険を実際に検討・加入した経験から、“公務員ならでは”の視点で選び方と活用法を丁寧にご紹介します。
この記事では、
学資保険の基本からメリット・注意点まで丁寧に解説
実際の返戻率データや、私自身の具体的な実体験(「なぜこの商品を選んだのか」「どう家計に組み込んだか」など)を盛り込み
財形貯蓄やジュニアNISAなど他の方法との比較も交えながら、あなたの教育資金準備に最適な選択肢をご提案
…といった構成で、中学生にも分かるやさしい言葉を使って進めていきますので、どうぞ安心して読み進めてください。
それではまず、「そもそも学資保険とは?」から見ていきましょう。
学資保険とは?公務員が知っておきたい基本ポイント

学資保険は、子どもの教育資金を計画的に積み立てるための保険商品です。
毎月(または年単位・ボーナス単位)で保険料を払い込み、契約時に決めた時期(入学時や進学時など)に一時金や分割金として受け取れます。
特に高校・大学進学時にはまとまった費用が必要になるため、「教育資金の確実な準備手段」として多くの家庭で利用されています。
学資保険の基本的な仕組み
契約者:親や祖父母など保険料を払う人
被保険者:子ども(保険の対象)
満期時期:高校・大学入学など大きな教育費が必要になる時期に設定
返戻率:支払った保険料の総額に対して、受け取れる金額の割合(例:返戻率105%なら、100万円払って105万円受け取れる)
返戻率が高いほど有利ですが、元本割れする商品や、途中解約すると損をするケースもあります。
公務員が加入するメリット
安定収入で長期契約しやすい
民間では収入の変動が大きく、途中で保険料が負担になるケースがありますが、公務員は給与とボーナスが安定しているため、契約を途中で断念するリスクが低いです。ボーナス払いを活用できる
公務員のボーナスはほぼ確定して支給されるため、学資保険の支払いをボーナス月に集中させ、毎月の家計負担を軽くできます。団体扱い・共済経由の加入も可能
一部の自治体や共済組合では、団体扱いでの学資保険加入ができ、保険料が割安になる場合があります。
公務員が注意すべきデメリット
インフレに弱い
学資保険は契約時に受け取る金額が固定されるため、物価上昇(インフレ)が進むと実質的な価値が目減りする可能性があります。利回りの低さ
預貯金よりは高いものの、投資信託などの投資型商品と比べると運用益は低めです。途中解約で元本割れ
公務員は転職リスクが低いとはいえ、病気や家庭の事情で払い込みが困難になることもあります。その際、解約すると元本割れする可能性が高いです。
体験談:私が初めて学資保険を検討したきっかけ
私が学資保険を検討し始めたのは、妻が次男を妊娠した頃でした。
「子どもの教育費はコツコツと貯金しておけばなんとかなるだろう」と思っていたのですが、実際に試算してみると長女・長男・次男の大学・専門学校の費用で500万円以上はかかりそうだと分かってきて、その額を貯金することはできるけど、5人家族で生活しながらだとなかなか難しい額だと思いました。
さらに、40歳になった私の貯蓄が安定して増えていない状況に気づきました。
そこで「確実に教育費を確保できる方法」として、返戻率の高い学資保険に加入することを決めました。
元々学資保険に対して良いイメージがなかったのですが、よくよく調べてみると、返礼率が100%を超えれば、確実に払った額よりも多い額が返ってくることが約束されるので、途中で解約さえしなければとてもお得な保険だと考えるようになりました。
契約したのは月額9860円、積立期間15年、満額200万円、返戻率約115%の商品を契約。
毎月の家計負担を抑えつつ、確実に積み立てられる安心感を得ることができています。
公務員だからこそ考えるべき学資保険の選び方
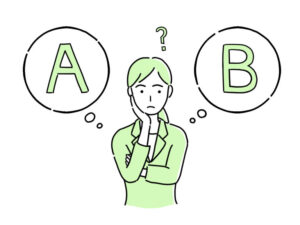
公務員は収入が安定している一方で、職業特性やライフプランを踏まえると、民間会社員や自営業とは異なる観点から学資保険を選ぶべきです。
ここでは、公務員ならではのチェックポイントを整理します。
1. 返戻率の目安と選び方
返戻率は学資保険選びで最も注目される指標の一つです。
たとえば、保険料の総支払額が200万円、満期時に受け取れる額が214万円なら、返戻率は107%です。
公務員の場合、高い返戻率の商品を長期で契約しやすいという強みがあります。
民間では景気変動で途中解約のリスクがありますが、公務員は解約リスクが低いため、返戻率重視で選びやすいのです。
返戻率の目安
105%以上 → 十分高い(条件によっては投資信託並みの利回り)
100~104% → 安定型(元本確保重視)
100%未満 → 元本割れ(早期解約や保障重視型に多い)
2. ボーナス払いと月払いのバランス
公務員のボーナスは年2回(6月・12月)支給がほぼ確定しています。
そのため学資保険の支払い方法を「ボーナス払い中心+月払い少なめ」に設定すれば、日常の家計負担を軽くしつつ積立が可能です。
私の場合、学資保険の保険料を
月払い:約1万円(年間12万円)
と契約しましたが、公務員を退職していなかったら、ボーナス払い:各5万円(年10万円)、月払い:2000円(年間2万4000円)に設定していたでしょう。
こうすることで、毎月の負担はほとんど感じず、ボーナス月にまとめて教育資金を確保できます。
3. 公務員ライフプランとの整合性
公務員のキャリアは定年まで比較的予測しやすく、給与カーブや昇給時期も概ね固定されています。
この特徴を活かし、
子どもが大学入学する時期
住宅ローンの完済時期
定年退職金の受け取り時期
などのイベントをあらかじめ想定して学資保険を組み込むと、資金計画に無理がなくなります。
たとえば、「長男の大学進学時に退職金の一部を利用 → 次男の学資保険を短期で契約」といった形でライフイベントに合わせた設計も可能です。
4. 公務員ならではの選択肢:共済や団体契約
自治体によっては共済組合経由で加入できる学資保険や、保険会社との団体契約による割引制度があります。
一般的な民間契約より保険料が安くなるケースもあるため、職場の共済担当や人事課で情報を確認してみましょう。
体験談:複数の見積もりを比較した結果
私は加入前に、民間3社の合計3パターンの見積もりを取りました。
民間A社:返戻率116%、保障は死亡時保険金あり
民間B社:返戻率112%、医療保障特約つき
民間C者:返戻率102%、保険料が安い
最終的には、返戻率と必要保障のバランスが取れていたA社を選びました。
決め手は、「万一のときの保障」と「将来の学費総額が明確に見える設計」でした。
会社ごとに、かなり返戻率や保険内容、掛金が変わってくるので、比較は必須!
学資保険とその他の教育資金準備方法を比較
教育資金を準備する方法は学資保険だけではありません。
公務員は安定収入という強みを持つため、「保険型」だけでなく「運用型」や「貯蓄型」との組み合わせが有効です。
ここでは代表的な3つの方法を比較します。
比較表:教育資金準備の代表的な方法
| 方法 | 特徴 | メリット | デメリット | 公務員との相性 |
|---|---|---|---|---|
| 学資保険 | 保険料を払い、満期に一時金・分割金を受け取る | 元本保証(商品による)、契約時に受取額が確定 | インフレに弱い、途中解約で元本割れ | ★★★★☆ |
| 財形貯蓄(財形教育) | 勤務先の給与天引きで貯蓄 | 天引きで確実に貯まる、非課税枠あり | 利率が低い、制度利用条件あり | ★★★☆☆ |
| NISA | 株や投資信託で運用、利益が非課税 | 高い運用益が狙える、非課税 | 元本保証なし、運用知識必要 | ★★★★☆ |
学資保険と財形貯蓄の組み合わせ
学資保険は確実性に優れますが、インフレリスクがあります。
そこで、財形教育貯蓄と併用すれば、給与天引きによる確実な積立と保険型の保障を両立できます。
特に公務員は財形制度を利用できる職場が多く、非課税枠(元利合計550万円まで)を活用可能です。
学資保険とNISAの組み合わせ
将来の学費を一部運用で増やす戦略です。
学資保険で最低限必要な金額(例えば大学入学時の入学金・初年度学費)を確保し、残りをNISAで運用します。
私の場合、次男の大学入学資金として学資保険で200万円を確保する予定、NISAでは年間約5万円ずつ投資信託に積み立てています。
NISAでの運用益は現在年平均11%ほどで推移しています(商品:オールカントリー)。
ケース別おすすめパターン
安定重視派(元本割れは絶対避けたい)
→ 学資保険+財形貯蓄バランス派(保障も増やしつつ少しは運用)
→ 学資保険+NISA攻めの運用派(運用リスクを取って増やす)
→ NISA中心+最低限の学資保険
公務員にとってのベスト戦略
公務員はローン審査が通りやすく、退職金も見込めるため、「必要額の半分は学資保険で確定、残りは運用で増やす」というハイブリッド型が理想です。
こうすることでインフレリスクを抑えつつ、資産成長のチャンスも取り逃しません。
注意すべき法改正・制度変更と公式情報へのリンク

学資保険は長期契約になるため、契約時の条件がずっと続くとは限りません。
特に近年は低金利・物価上昇・税制改正の影響で、商品の返戻率や販売条件が変わるケースが増えています。
公務員は安定収入が強みですが、長期契約ゆえに「気づいたら条件が悪化していた」という事態を避けるため、制度変更リスクに注意しましょう。
1. 金融環境の変化による返戻率の低下
近年、生命保険会社は運用利回りの低下により、学資保険の返戻率を引き下げる傾向があります。
契約後は返戻率が固定されますが、契約前に長期的な金利動向を確認しておくことが重要です。
2. 税制改正による影響
学資保険は教育資金贈与や生命保険料控除の対象になる場合があります。
しかし、税制改正により控除額や非課税枠が変動する可能性があります。
【過去の事例】
生命保険料控除の枠組み変更(新旧制度)
教育資金贈与の非課税措置の期限延長・短縮
贈与税の制度見直し
こうした変更は突然発表されることもあるため、契約後も定期的に税制ニュースをチェックしましょう。
3. 商品改定や販売終了リスク
生命保険会社は収益性や市場環境の変化に応じて商品を改定します。
「人気商品が数か月後に販売終了」というケースも珍しくありません。
私の知人(県職員)は、検討して長期間迷っていたら返戻率120%の商品が販売停止になった経験があります。
4. 制度変更の最新情報を確認できる公的機関リンク
長期契約の商品ほど、信頼できる一次情報源から最新情報を得る習慣が大切です。
以下は必ずブックマークしておきたい公式サイトです。
5. 公式情報を参照する際の注意点
発表日を必ず確認(古い情報を参考にしない)
施行日や経過措置の有無をチェック
保険会社のパンフレットも併せて参照(実際の契約条件は会社ごとに異なる)
実践例:公務員家庭のエピソード付きシミュレーション
ここでは、実際の公務員家庭を想定した学資保険活用例を紹介します。
数字はあくまでモデルケースですが、教育資金の見通しを立てる参考になります。
モデル家庭の条件
父:地方公務員(勤続10年、30代)
母:パート勤務(扶養内)
子ども:0歳(契約開始時)
学資保険契約期間:15年
払込方法:ボーナス払い中心(年20万円)+月払い少額(5,000円)
返戻率:107%(契約時点)
積立と受取の流れ
| 年齢 | 払込金額累計 | 年間払込額 | 返戻率 | 受取予定金額 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳(契約開始) | 0円 | 26万円 | – | – |
| 10歳 | 260万円 | 26万円 | – | – |
| 15歳(満期) | 390万円 | 26万円 | 107% | 約417万円 |
※金額は仮例。契約条件や商品により異なります。
受取時の使い道シナリオ例
高校入学時(15歳)
受取額の一部(100万円)を高校の入学金・制服・教材費に充当。大学入学時(18歳)
残額(約317万円)を入学金・初年度授業料・下宿準備費に充当。
体験談:我が家の場合
私の場合、
長女が生まれたタイミング:返戻率107%の学資保険
長男が生まれたタイミング:返戻率105%の学資保険
次男が生まれたタイミング:返戻率116%の学資保険
に加入しました。
契約の決め手は、「途中で解約しなければ確実に預けた額よりも多く返ってくる」というポイントでした。
株式投資をしている人間からしたら、確実に数パーセントから二十数パーセント増えて戻ってくるというのはかなりすごいなという感覚です。
実際、途中で教育費以外の出費(車の買い替え)がありましたが、学資保険分は途中解約すると元本を割る仕組みだったおかげで、もったいないと思い、教育資金を崩さずに済みました。
今振り返ると、この“強制的に貯める仕組み”こそが最大のメリットだと感じています。
ちなみにどこの学資保険にしたかですが、次男の学資保険を決める際は、返戻率の高さから
「明治安田生命」
「ソニー生命」
で迷いましたが、最終的に一番返戻率が高かった「明治安田生命」に決めました。ソニー生命さんも良かったのですが、資料請求ができなかったのと、契約前に必ずライフプランナーとの面談があることがネックとなりました。明治安田生命は、資料請求後、営業担当から電話があり、一度面談して契約内容を精査してから契約となりました。私で契約するよりも年齢が若い妻が契約したほうが返戻率が高くなるので、妻名義で契約しました。
Q&A:公務員から寄せられる悩みにお答え

学資保険については、公務員の方からも多くの質問をいただきます。
ここでは、実際に寄せられた相談や検索ニーズの高い質問をもとに、具体的にお答えします。
Q1. ボーナス払いと月払い、どちらが得?
A. 総支払額はほぼ同じですが、家計管理のしやすさで選びましょう。
公務員の場合はボーナス支給が安定しているため、「ボーナス払い中心+月払い少額」の組み合わせがおすすめです。
日常の生活費を圧迫せず、確実に貯められます。
Q2. 学資保険と共済の違いは?
A. 共済(例:県民共済・共済組合の学資制度)は、保険料が割安な場合が多いですが、返戻率や保障内容が民間保険に劣るケースもあります。
比較する際は「返戻率」「保障内容」「契約条件(途中解約可否)」を並べて確認しましょう。
※共済はシンプル設計が多く、保障重視なら選択肢に入ります。
Q3. 途中解約するとどうなる?
A. ほとんどの場合、元本割れします。
契約初期ほど解約返戻金が少なく、払込総額を下回ることが多いです。
公務員でもライフプラン変更(転勤や住宅購入)で解約せざるを得ないケースがあります。
契約前に、「無理なく払い続けられる金額」を必ず試算しましょう。
Q4. 学資保険はインフレに弱いと聞くけど大丈夫?
A. その通りで、学資保険は受取額が契約時に固定されるため、物価上昇時には実質的な価値が下がります。
これを補うには、学資保険で必要最低限(入学金+初年度学費)を確保し、残りはNISAなど運用型で備えるのが有効です。
Q5. 公務員はそもそも学資保険に入るべき?
A. 必須ではありませんが、「強制的に貯める仕組み」が欲しい人には向いています。
公務員は安定収入ゆえに「いつでも貯められる」と思いがちですが、実際には他の支出に回してしまうことも多いです。
確実に教育費を積み立てたいなら、学資保険は有力な選択肢です。
まとめと次へのステップ
この記事では、公務員が学資保険を検討・選択する際に知っておきたいポイントを、公務員ならではの視点と実体験を交えて解説しました。
公務員が学資保険を選ぶ際のポイントおさらい
返戻率は105%以上を目安に
長期契約しやすい公務員だからこそ、高返戻率の商品を選びやすい。ボーナス払いの活用で家計負担を最小化
安定したボーナスを学資保険の払い込みに充てることで、生活費に影響を与えにくい。ライフプラン全体で設計する
定年、住宅ローン、退職金の時期などと合わせて教育資金を準備する。共済や団体契約も比較対象に
職場経由の割引制度や団体契約で保険料が安くなる場合がある。インフレ対策に運用型も併用
NISAや投資信託で資産の一部を運用することで、将来の物価上昇リスクを軽減。
学資保険は「強制的に貯める仕組み」
私自身、学資保険に加入して強く感じたのは、「手を付けられない環境」こそが最大の価値だということです。
日常の支出に流用されず、満期時には確実に教育資金が準備できる――この安心感は他の金融商品には代えがたいものでした。
次のアクション
学資保険は「契約して終わり」ではなく、契約内容の見直しや他の資産運用との組み合わせが重要です。
この記事を読み終えたら、次の行動をおすすめします。
資料請求で複数社を比較
同じ条件でも返戻率や保障内容は異なります。
おすすめサービス→学資保険一括資料請求【トモママ】
職場の共済担当に団体契約の有無を確認
割引や特典がある場合があります。FP(ファイナンシャルプランナー)に相談
ライフプラン全体の中での位置付けを確認できます。
サイト内関連記事
- 公務員の団体保険|メリット・デメリットを元公務員FPが解説
- 公務員に医療保険は本当に必要?|現役公務員FPが語る保障の選び方とリアルな実体験
- 【2025年最新】公務員のための新NISA完全ガイド|初心者でも失敗しない始め方と注意点を元公務員FPが解説
注意喚起と公式情報リンク
学資保険や税制は法改正の影響を受けます。
最新情報は必ず公的機関の公式サイトで確認してください。
今すぐお子さんの教育資金計画を始めませんか?
下記リンクから無料で学資保険のシミュレーションや資料請求が可能です。
比較・検討は早ければ早いほど有利です。
