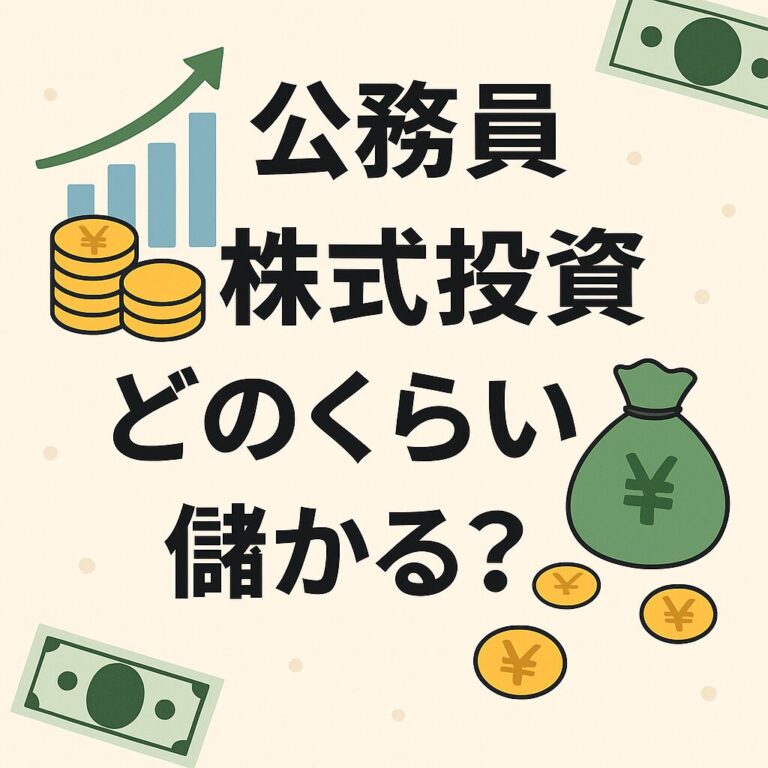「公務員でも株式投資をしてみたいけど、実際どのくらい儲かるの?」
──そう思ったことはありませんか?
私も県職員として9年間働いていた頃、周囲の公務員仲間から
「株って危なくない?」
「結局ギャンブルでしょ?」
とよく言われました。
けれど実際に投資を始めてみて分かったのは、株は“危険なもの”ではなく、“知識と継続で味方にできるもの”だということです。
もちろん、株価は上下します。
でも、正しい知識と冷静な判断を持てば、年3〜5%程度の堅実な利益を積み上げることは十分可能です。(絶対ではありませんが)
私自身、NISAでの積立や日本株の長期保有を通して、「思っていたより安定して増える」「働かなくてもお金が育つ」体験を実感しました。
この記事では、
公務員が株式投資でどのくらい儲かるのか(実際の数値イメージ)
私が実際に投資して得た“リアルな成果と反省”
公務員でも安心して始められる投資の考え方
を、元県職員FPの実体験を交えてやさしく解説します。
読めば、「投資=ギャンブル」という誤解が消え、“安定を守りながら資産を育てる”という新しい視点が手に入るはずです。
では、順に見ていきましょう。
🏦 第1章:公務員が株式投資で「どのくらい儲かる」のか?平均利回りと実態
「株って結局どのくらい儲かるの?」
──これは投資を考えるとき、誰もが一番気になるポイントでしょう。
結論から言うと、公務員が現実的に狙えるリターンは「年3〜5%」程度です。
もちろん「10倍株」や「数ヶ月で2倍になる銘柄」もありますが、そうした事例はごく一部。
平均値で見れば、堅実に長期で育てる投資のほうが圧倒的に成果が安定します。
💹 株式投資の平均利回りは年に数%が目安
株式市場全体の平均リターンを示す代表的な指数に「日経平均株価」があります。
2003年の底値7603円→2025年11月13日で51,281円となっています。
客観的にみれば、22年で6.7倍になっていて、平均年間利回りは実に約9%となります。
米国株の代表指数「S&P500」でみると、1985年11月1日の202円→2025年11月1日の6,737円となっています。
つまり、40年間で約33倍になっていて、平均年間利回りは約9%となります。
どの時点からの株価でみるかで利回りは大きく変わりますが、長期で見れば、数%は利益が出ているということが分かります。
そのため、公務員のように毎月安定した収入がある人は、NISAを活用して長期で年3〜7%を目指すのが現実的かつ堅実な戦略です。
【注意】
株はもちろん暴落するときもありますし、常に毎年数%利益が出続けてきたわけではないことに注意が必要です。
例えば、
- 購入1年目 -5%
- 購入2年目 -2%
- 購入3年目 +10%
- 購入4年目 +1%
- 購入5年目 +5%
こういった波があるのが株式投資です。
よく一律に年数%あがっていくというシミュレーションがありますが、あくまであれは「目安」にすぎません。
株って意外と儲からないんだなと思ったそこのあなた。
そんなことはありません。
確率は高くありませんが、なかには10倍以上になる株もあります。
例えば、
| レーザーテック | 約166倍 | 2031日 |
| ジャパンエンジンコーポレーション | 約33倍 | 10年 |
| 丸千代山岡家 | 約28倍 | 2135日 |
| 鎌倉新書 | 約26倍 | 932日 |
| 東映アニメーション | 約10倍 | 10年 |
などこのほかにも事例は多数あります。(底値付近から高値付近を掴んだ場合。←これをできる可能性はかなり低いですが。ある程度利益がでたら売ってしまうのが人というもの)
💰 株の利益は「値上がり益」と「配当金」の2種類
株式投資で得られる収益は、主に次の2つです。
| 種類 | 内容 | 公務員に向いている理由 |
|---|---|---|
| 値上がり益 | 安く買って高く売ることで得る利益 | 長期保有で時間を味方にできる |
| 配当金 | 企業から定期的に支払われる利益の分配 | 安定収入+再投資で雪だるま式に増える |
特に配当金は、銀行預金の金利0.2%(三井住友銀行・普通預金2025年11月14日時点)とは比べものになりません。
たとえば、配当利回り3%の株を100万円分保有していれば、年間3万円の配当が自動的に入るイメージです。
しかも、再投資を続けることで、複利の力が働きます。
10年・20年単位で見ると、この「小さな利益の積み重ね」が大きな差を生みます。
🧮 公務員が狙うべきは「派手さより継続」
私の経験上、公務員が株式投資を始める際に最も重要なのは、“儲けたい”より“続けたい”という発想を持つことです。
なぜなら、相場は短期では上下するものの、長期で見れば右肩上がりで成長していく。
一時の暴落で焦って売るより、淡々と積み立て続けるほうが結果的に利益が出るからです。
私がNISAで積み立ててきたときも、「最初の頃は含み損になる時期もあった」──それでも継続した結果、5年後には利回りが+10%以上の含み益となっています。
これは「大きく儲けた」というより、“安定して資産を育てた”という安心感が得られたという表現の方が正確です。
💼 第2章:元県職員FPの実体験|株で得た利益と損失のリアル
私が株式投資を始めたのは、県職員7年目あたりの頃でした。
当時は「お金に余裕がない」「もう少しお金の知識を深めたい」という気持ちから、株式投資の勉強を始めました。
結論から言えば、株で儲かる時期もあれば、損をする時期もある。
でもそれ以上に、「お金や経済の知識」や「企業分析のスキル」が身についたことが、何より大きな財産になりました。
ライザップ株:5年で-50%と+3倍を経験
私が最も印象に残っているのは「ライザップグループ(2928)」です。
2018年ごろに株価急騰を見て興味を持ち、一時的に株価が暴落してからの2019年の安値圏で購入しました。
取得単価は約170円~230円台。
買った直後の2020年にコロナが発生、株価はみるみる下がっていき、一時は投資額の「-50%」までになり、100万円以上の損失、「買ったのは失敗だったかな…」と思った時期もあります。
しかし、その後、コロナも終息、チョコザップ事業の好業績により、2024年には株価は一時570円台になり、投資額の「+約3倍」までいき、資産は1000万円を超えました。
これは、途中で手放さず、長期保有を貫いたことで報われたケースです。
短期的に見ればマイナスの時期もありましたが、「下落原因の分析」と「当初の長期保有の方針」を信じて待てたことが成功の要因でした。
鎌倉新書株:堅実成長型の企業で“2年で2倍”のリターン
もう一つが「鎌倉新書(6184)」です。
この会社は葬儀・供養・終活といった“人生の終末期”に関わるサービスを手がけています。
社会の高齢化とともに需要が増す分野だと感じ、2019年に1株600円台で購入。
それから2年で株価は1,200円付近まで上昇、結果的に「2年で2倍」になりました。
配当も安定しており、そこも長期保有の強い味方となりました。
この銘柄では「長期的な社会課題に沿ったビジネス」がどれほど強いかを実感しました。
地味な業種でも、安定して利益を出せる企業こそ投資価値があるという学びです。
オルカン:長期つみたてで安定利回り
結婚したのをきっかけに、NISAを利用した長期積立も開始しました。
購入したのは全世界株に投資ができる「eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)」、略してオルカン。
買ったあとの数か月は-数%が続いていましたが、2年経った今では評価額は投資額の「+22.82%」と高水準を記録しています。(2025年11月14日時点)
📉 損失を出した時に気づいた「焦らない」ことの大切さ
もちろん、すべてが順調だったわけではありません。
私も、株価ニュースに一喜一憂して“売り急いで後悔”したことが何度もあります。
例えば、コロナショック時には「まだ下がるかもしれない」と不安になり、優良株を損切りしてしまったこともありました。
その後すぐに株価が反発し、「なぜあの時冷静にいられなかったのか」と深く反省しました。
そこから学んだのは、
「値動きに振り回されず、“企業の本質”を見て判断すること」
ニュースよりも決算資料を読み、経営の方向性を見る。
この“考える投資”に変えてから、リターンが安定するようになりました。
💡 第3章:株で儲けるために必要な3つの考え方
株式投資で成果を出すために一番大切なのは、「どの株を買うか」よりも、“どんな考え方で投資を続けるか”です。
私も最初は、ニュースやSNSで話題の銘柄を追いかけて失敗しました。
しかし株の勉強を通じて、正しい考え方を身につけてからは、結果も心の安定も大きく変わりました。
ここでは、私が実際に意識している「3つの考え方」を紹介します。
🧭 ① 「短期で稼ぐ」ではなく「長期で育てる」
株式投資は、“すぐに儲かるもの”ではなく、“じっくり育てるもの”です。
短期で利益を追い求めると、どうしても感情に左右されやすくなります。
株価が上がると「もっと買いたい」、下がると「早く売らないと損する」。
──この繰り返しでは、長期的な利益は得られません。
一方で、長期的な視点を持つと「一時的な値下がり」が怖くなくなります。
なぜなら、株価の上下よりも、企業が長く利益を出し続けるかどうかが本質だからです。
10年で株価が約2倍になる=年平均+7%。
派手ではないけれど、10年後に資産が倍になる力は“静かな成功”です。
公務員のように安定した収入がある人こそ、焦らず、長期の時間軸で投資を育てられる立場にあります。
💰 ② 「余剰資金」で投資する=生活を壊さないルール
株で失敗する多くの人は、「生活資金に手をつけてしまう」ことが原因です。
投資はあくまで、“余剰資金=使わなくても困らないお金”で行うこと。
目安としては、
✅ 生活費6ヶ月分の貯金を確保したうえで投資を始める。
これが、精神的にも安心できるラインです。
私も本腰をいれて長期投資を始めたときは「余裕資金の400万円程度」で複数銘柄を時期をずらしながら購入し、その後は再投資せずに、“貯金”も増やし続けて、守りも固めています。
不安を抱えながらの投資は、判断を狂わせます。
生活が安定しているからこそ、株の値動きにも落ち着いて対応できるのです。
🪴 ③ 勝率より「継続率」が利益を生む
多くの人は「どの銘柄で勝てるか」を気にしますが、本当に大切なのは、“続ける仕組みを作ること”です。
人は感情の生き物です。
株価が下がると不安になり、上がると調子に乗る。
この心理を制御する唯一の方法が、自動・定期的に投資する“積立”です。
NISAで積立投資をすれば、
毎月同じ金額を自動で投資
相場が下がれば多く買える
上がれば利益が出る
という「平均化の仕組み」が働きます。
結果的に、勝率よりも継続率が資産を増やすカギになるのです。
⚖️ 第4章:公務員が株式投資を始めるときの注意点
公務員が株式投資を始める際に、最も多い質問がこれです。
「副業禁止なのに、株をやって大丈夫なんですか?」
結論から言えば──株式投資は問題ありません。
ただし、ルールやリスクを正しく理解しておくことが大切です。
私も県職員時代、同僚から何度も同じ質問を受けました。
「投資って公務員でもやっていいの?」
「バレたらまずくない?」
そんな不安を抱えたままだと、一歩踏み出すことができませんよね。
ここでは、公務員が安心して株式投資を始めるための注意点を3つにまとめました。
🧾 ① 「副業禁止」と「投資」はまったくの別物
公務員の副業を規定しているのは「国家公務員法」「地方公務員法」です。
禁止されているのは、“営利を目的とした事業や兼業”であって、株式投資・投資信託・NISA・iDeCoなどの資産運用は対象外です。
つまり、
企業経営に関与しない
他人の資産を管理しない
投資で得た利益を公務に影響させない
──これらを守っていれば、何の問題もありません。
実際、共済組合や公務員向け雑誌でも「NISA」や「iDeCo」が紹介されています。
制度としても“自分の資産を育てる行為”は推奨されています。
💬 注意すべきNG例
企業の役員になる
投資関連のブログやYouTubeで収益を得る
他人の投資を助言して報酬を受け取る
- インサイダー取引
こうした行為は「NG」ですので避けましょう。
💻 ② SNSやYouTube情報を“鵜呑みにしない”
最近は「この株を買えば儲かる!」という情報がSNSや動画であふれています。
しかし、そうした情報の多くは一部の成功体験や誇張表現にすぎません。
私も最初のころ、SNSで見た情報を信じて飛びつき、痛い目を見たことがあります。
結局、信頼できるのは「数字と根拠がある情報」だけです。
信頼できる情報源は、
金融庁
日本証券業協会
証券会社の公式サイト
書籍(FP監修や成功した個人投資家など)
などの一次情報・公的情報。
特に、金融庁のNISAガイドはとても分かりやすく整理されています。
SNSの情報は参考程度にとどめ、根拠のない“儲け話”には絶対に近づかない。
それが、公務員に求められる「慎重さ」を活かした投資姿勢です。
🪙 ③ 投資は「続けられる仕組み」を作るのがカギ
公務員にとって最大の強みは、安定した収入があること。
この安定を活かし、少額でも「続けられる仕組み」を作ることが重要です。
おすすめは、NISAを使った自動積立投資。
毎月1万円でも自動で積み立てていけば、相場を気にせず自然と“買い時・売り時の平均化”ができます。
📊 例:月1万円×年利4%で20年間積み立てると…→ 240万円の投資が364 万円に成長(+124万円)
(出典:金融庁つみたてシミュレーション)
このように、「時間」を味方につけるのが公務員投資の最適解です。
無理せず・焦らず・コツコツ積み上げる。
それが、最も再現性のある“成功の方程式”です。
🌿 第5章:株式投資を通じて得られる“お金以外”のメリット
株式投資というと「お金を増やす手段」と思われがちですが、実はそれ以上に大切なのが、お金以外の“学びと変化”です。
私自身、投資を始めたことで、日々のニュースの見え方が変わり、お金への不安が減り、人生に“心のゆとり”が生まれました。
ここでは、公務員が株式投資を通じて得られる3つの非金銭的メリットを紹介します。
🧠 ① 経済の流れが“自分ごと”になる
投資を始めると、新聞やニュースの内容が急に身近になります。
「円安」「金利」「日経平均」といった言葉が、自分の資産に直接関係してくるからです。
たとえば、
円安=輸出企業の株価上昇
金利上昇=金融株が強い
景気悪化=ディフェンシブ銘柄(食品・通信)が安定
こうした“経済のつながり”を体感できるのは、教科書では得られないリアルな学びです。
私も公務員時代は「経済ニュースなんて関係ない」と思っていました。
しかし今では、ニュースを見れば「この政策はどの企業に影響するかな?」と考えるようになり、経済を“読む力”が自然と身につきました。
💬 ② お金への不安が減り、精神的に安定する
株式投資を続けるうちに、「お金を使う=減る」ではなく、「お金を働かせる=増やす」感覚に変わっていきます。
これは大きな変化です。
将来に対する不安の多くは、「収入が止まったらどうしよう」という恐れから生まれます。
でも、株式投資で“お金が自分の代わりに働く”仕組みを持てば、たとえ収入が変化しても、「備えがある」という安心感が生まれます。
実際、私も配当が振り込まれるたびに、「少しでも自分の資産が働いてくれている」と感じ、心が落ち着きます。
「安心」は“金額”ではなく“仕組み”から生まれる。
株式投資は、心の余裕を育てる“もうひとつの給与”なんです。
🌱 ③ 仕事への視点が変わり、自分の成長につながる
株式投資をすると、企業経営や事業構造を見る目が磨かれます。
「この会社はなぜ利益を出せるのか?」
「どんな仕組みで人を動かしているのか?」
──こうした視点は、公務員の仕事にも活きてきます。
たとえば、
企業の効率化を学ぶことで、行政のムダに気づく
経済ニュースを読むことで、政策の背景が理解できる
数字で成果を見る習慣が身につく
投資は、社会の仕組みを理解する“最高の教材”です。
「お金のため」ではなく「学びのため」に続ける価値があります。
🌸 第6章:まとめ|株は“儲ける”より“育てる”が正解
ここまで見てきたように、株式投資は「短期間で儲けるための手段」ではありません。
長期的にお金を育て、人生に安心を増やすための知恵です。
私自身も、最初は「もう少しお金を増やしたい」という軽い気持ちから始めました。
しかし今では、投資を通して「お金」「仕事」「人生」に対する考え方が変わりました。
特に公務員は、毎月の収入が安定している分、焦らず・コツコツ・堅実に続けることができます。
これこそ、株式投資における最大の武器です。
🌱 今日からできる小さな一歩
投資は「始めてみること」が何よりも大切です。
いきなり大きな金額を動かす必要はありません。
まずは、次の3つのうちどれかひとつを実行してみてください。
NISA口座を開設して、月1万円の積立設定をしてみる
配当金が出る企業をひとつ調べてみる
お金に関する簡単な入門書を読んで、お金の仕組みを理解する
この“小さな行動”が、将来の安心を何倍にも変えていきます。
株は「当てる」ものではなく、「育てる」もの。
そして“焦らず・続ける”人が最終的に勝ちます。
お金を増やすことだけが目的ではありません。
投資を通じて、お金に振り回されない生き方を身につけることこそが、公務員として、そして一人の生活者としての「本当の安定」です。
株式投資は、「お金の不安を減らすための学び」です。
公務員の安定を土台に、少しずつ資産を育てていく。
それが、安心と自由を両立する生き方につながります。