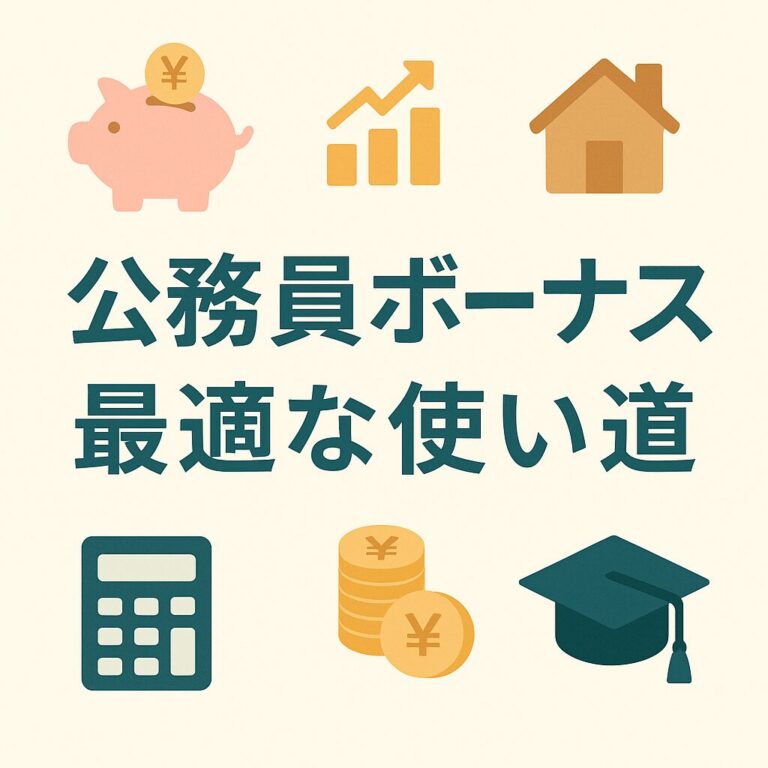「公務員のボーナスって、みんなどう使ってるんだろう?」
「気づけば貯金が全然増えていない…」
「投資やローン返済も気になるけど、何から手をつければいいのか分からない」
──もし今そんな悩みを抱えているなら、この記事はまさにあなたのための内容です。
結論から言うと、「ボーナスの正しい使い方」に“人それぞれ”という答えはありません。
大切なのは「順番」と「ルール」を決めておくことです。
私は県庁で9年間勤務し、毎年夏と冬にボーナス(期末・勤勉手当)を受け取ってきましたが、最初のころは“思いつき”で使って後悔ばかりしていました。
しかし、「配分ルール」を明確にした途端、ボーナスの満足度も貯金の増え方も大きく変わったのです。
この記事では、そんな私の実体験とFP(ファイナンシャル・プランナー)の知識をもとに、「若手公務員でも今日からマネできる“後悔しないボーナスの使い方”」をやさしく解説していきます。
公務員のボーナスは「年2回の家計チューニング日」にしよう
ボーナスの基本(期末・勤勉手当とは?)
正式には「期末手当」と「勤勉手当」と呼ばれ、年2回(多くの自治体では6月末と12月上旬〜中旬)に必ず支給されます。
たとえば、私が県庁で働いていたときは、6月30日と12月10日が支給日でした。
民間とは違い、必ず年2回支給されるのが公務員の良いところです。
額は勤続年数や人事評価によって変わりますが、20代〜30代前半の職員であれば手取りで30〜50万円ほどになる人が多いでしょう。
ここで重要なのは、このボーナスを「ご褒美の臨時収入」として使うのではなく、“年2回の家計チューニング日”として位置づけることです。
「ご褒美」ではなく「戦略資金」として使う考え方
多くの若手職員がやってしまいがちなのが、ボーナスを“勢い”で使ってしまうことです。
「半年頑張ったから自分へのご褒美に…」と高級家電を購入
「気づけば旅行や外食で消えていた」
「残りはなんとなく貯金口座へ」
このような“使い切り型”の使い方をしていると、ボーナスの満足度は一瞬で終わってしまい、数か月後に「結局お金が貯まらない」という悩みに直面します。
しかし逆に、ボーナスを「戦略資金」として計画的に配分すれば、貯金・投資・支出のすべてが自然と整い、1年間の家計が安定します。
ここで覚えておいてほしいキーワードが、「順番とルール」です。
私が学んだ“思いつき消費”と“ルール消費”の差
私自身、県庁職員1年目〜3年目のころは「思いつき消費派」でした。
夏のボーナスで新しいパソコン、冬は友人と旅行やショッピング──どれも楽しかったのですが、翌月のクレジットカード明細を見て青ざめるのが恒例行事。
「次のボーナスまで貯金ゼロ」「急な出費に対応できない」という不安も常に抱えていました。
ところが、30歳頃から“ルール”を先に決めるようにしたところ、状況は一変しました。
ボーナスを受け取る前に、
- 「貯金30%」
- 「投資20%」
- 「自己投資30%」
- 「娯楽20%」
というような順番と割合を先に決めておき、その通りに自動振替するようにしたのです。
その結果、
貯金は安定的に増えるようになり
毎月の家計に“余裕”が生まれ
投資も「続ける」ことが当たり前になり
お金の使い方が根本から変わりました。
この経験から学んだのは、「金額よりもルールが大事」ということです。
まずは「手取り金額」を正確に把握しよう
ボーナスの使い方を考える前に、最初にやるべきは「手取りの把握」です。
なぜなら、ボーナスは額面と手取りに大きな差が出やすいからです。
所得税・住民税
社会保険料
共済組合の掛金 など
これらが一気に天引きされるため、「支給額50万円」のはずが「手取り40万円前後」ということはよくあります。
「手取りがいくらになるか」を知ったうえで、そこから配分割合を考えることが大切です。
そして金額ではなく「割合」で考えるクセをつけると、毎回のボーナス時に迷わなくなります。
ボーナスの使い道は“順番”が9割!失敗しない5ステップ
ボーナスの正しい使い方は、「人によって違う」わけではありません。
最も大切なのは、「優先順位=使う順番」です。
順番を間違えると、「投資をしているのにお金が貯まらない」「保険ばかり払って家計が苦しい」といった“よくある失敗”につながります。
ここでは、私自身が実践してきて効果があった「5つのステップ」を、初心者向けにわかりやすく解説します。
① 生活防衛資金の確保(安心の土台をつくる)
最初にやるべきは、「生活防衛資金」(貯金)をつくることです。
これは、急な出費や想定外のトラブルに備える“安全網”のようなもので、ボーナスの最優先項目です。
▷ 生活防衛資金の目安
目安 → 生活費3か月分
たとえば、毎月の生活費が15万円なら、最低50万円程度は「何があっても手を付けないお金」として確保しましょう。
▷ どんな出費に備えるの?
引っ越し費用(人事異動)
車検・家電の買い替え
- 自動車修理
冠婚葬祭・ご祝儀
病気やケガによる一時出費 など
これらは、いつ発生するか読めません。
だからこそ、ボーナス時に安全網を一気に作ることが重要です。
▷ ポイント:日常口座と分ける
「防衛資金用の口座」を別にしておくと、うっかり使ってしまう心配がありません。
生活費←地銀
防衛資金←ネット銀行
などしっかり分けておくと安心です。
② 高金利ローンの繰上げ返済(借金返済は“投資”より優先)
生活防衛資金が確保できたら、次にやるべきは高金利の借金返済です。(該当者のみ)
たとえば、リボ払いやカードローンは年利15%前後が一般的。
これは投資で15%の利益を出すよりもはるかに難易度が高く、「借金を減らすこと=確実なリターン」になります。
【▷ 優先度の目安】
年利5%以上 → 迷わず返済を優先
年利3〜4% → 返済と投資のどちらが効果的か検討
年利1〜2% → 生活防衛・投資を優先してOK
私の友人も若手時代に便利だとリボ払いにはまっていた人がいましたが、金利のことを知らずに利用していて、あとで損していることに気が付きました。
そのときはボーナスで一気に返済したことで心理的なストレスが一気に減り、「投資に回せる余力」まで生まれていました。(リボ払いは絶対に止めておきましょう)
③ 保険・共済の見直し(重複を削って固定費を減らす)
次にやるべきは、保険の見直しです。
特に公務員の場合、「共済+団体保険+民間保険」と重複して加入しているケースが非常に多いです。
私も入庁5年目のころ、自分で整理してみたら「医療保険が3つ、がん保険が2つ」も入っていて、月に1万円以上ムダな保険料を払っていました。
【▷ 見直しのステップ】
保険・共済の契約内容をすべて書き出す
「入院」「通院」「死亡」「就業不能」など、保障内容を横並びで比較
不足があれば補う/重複があれば削る
ポイントは、「保障は“必要最小限”で十分」ということ。
条件や考え方にもよりますが、無理と加入しなくても問題ない人もいます。
公務員は共済組合からの給付が手厚いため、過剰な保険は“固定費の重し”になりがちです。
毎月の保険料が5,000円減るだけでも、年間で6万円。
その分をつみたてNISAに回せば、お金が“支出”から“資産”へと生まれ変わります。
④ NISA・つみたて投資・教育準備など“攻め”の資金へ
ここまでで「守りの3ステップ」が完了しました。
残った資金は、いよいよ“攻め”に使っていきましょう。
▷ NISA・つみたて投資
若手公務員にとって、一番のおすすめはNISA(少額投資非課税制度)です。
特に20代・30代は「時間」という最大の武器があるので、早く始めるほど効果が大きくなります。
まずは月々のつみたてをベースに
さらにボーナスで上乗せ投資
というハイブリッド運用が継続しやすく、相場の上下にも強いです。
▷ 自己投資・資格取得・健康への投資
本や資格講座、パソコンなどの“自分の能力を伸ばす投資”も、10%~20%程度なら積極的に使ってOKです。
スキルアップは将来の収入アップにつながる「長期のリターン」です。
⑤ 比率テンプレートで自動化する
ここまでの流れを“毎回ゼロから考える”のは大変です。
そこでおすすめなのが、割合テンプレートで使い道を自動化することです。
| 使い道 | 割合 | ポイント |
|---|---|---|
| NISA | 20% | 将来に向けた資産形成の中核 |
| 生活防衛資金(貯金) | 30% | 万が一への備え |
| 娯楽 | 20% | 旅行・交際費 |
| 自己投資 | 30% | 自分の成長につながる使い道 |
これひとつのベースにすれば、ボーナスを受け取るたびに迷うことがなくなり、家計管理が自動化されます。
私自身もこのルールにしてから、毎年のボーナス時期が「お金の不安」ではなく「資産を育てるチャンス」へと変わりました。
この割合をもとに、自分に適した配分に修正してみてください。
まとめ|“順番”を守るだけで家計は激変する
ここまでの5ステップをもう一度まとめます。
✅ 生活防衛資金で「安心の土台」をつくる
✅ 高金利の借金は「投資より先に」返す
✅ 保険・共済は重複を削って「固定費を軽くする」
✅ 残りでNISA・投資・自己投資へ「攻め」に回す
✅ 割合テンプレートで「迷わない仕組み化」
この“順番”さえ守れば、お金が自然と増えていく家計の仕組みができます。
次章では、ライフステージ別に「おすすめの配分テンプレート」を紹介し、あなたの状況に合った使い方をより具体的に見ていきましょう。
ライフステージ別|若手公務員の「ボーナス配分テンプレート」
ボーナスの「使い方の正解」は“順番”で決まりますが、もう一つ大切なポイントが「ライフステージに合った配分」です。
独身期・結婚初期・子どもができる前後では、お金の優先順位が変わるからです。
ここでは、若手公務員によくある3つのパターン別に、現実的な配分テンプレートとその考え方を紹介します。
「自分はどのステージに近いか?」をイメージしながら読み進めてみてください。
独身期|“攻め”を最優先して資産形成の型をつくる
こんな人におすすめ
20代〜30代前半の独身
実家暮らし or 家賃負担が軽い
大きな出費予定がない
独身期は、家計にかかる固定費が少ない「チャンス期」です。
この時期は“守り”より“攻め”を重視し、投資や資産形成の土台を早くつくることが将来の安心につながります。
ただ、私の考えとしては20代の独身期は大いに遊んだほうがいいという気持ちもあります。
そのため娯楽費も多めに設定しています。
▷ 配分テンプレート(例:手取り30万円)
| 使い道 | 割合 | 金額(例) |
|---|---|---|
| 投資(NISA・つみたて) | 20% | 6万円 |
| 生活防衛資金(貯金) | 20% | 6万円 |
| 高金利返済 | 10% | 3万円 |
| 自己投資(本・資格・スキル) | 20% | 6万円 |
| 娯楽 | 30% | 9万円 |
▷ ポイント
固定費が軽い時期は、NISAの枠を早めに埋める戦略が有効
自己投資も惜しまず行い、「稼ぐ力」を高めておく
趣味や旅行なども“予算化”して、メリハリをつける
私自身も独身時代に投資を始めたおかげで、30代後半の今は「お金が育っている感覚」を持てています。
若いうちから“攻めの姿勢”で行動しておくと、数年後の安心感がまったく違います。
結婚初期・共働き期|生活の安定と資産形成を両立する
こんな人におすすめ
結婚して数年以内
共働きで家計に余裕がある
まだ子どもがいない or 将来を考え始めたところ
この時期は、「生活の安定」と「将来への準備」をバランス良く進めることが大切です。
共働きの場合は一気に投資比率を上げるチャンスでもあります。
▷ 配分テンプレート(例:手取り35万円)
| 使い道 | 割合 | 金額(例) |
|---|---|---|
| 投資(NISA・つみたて) | 30% | 10.5万円 |
| 生活防衛資金 | 20% | 7万円 |
| 教育・将来準備(結婚式費用なども含む) | 20% | 7万円 |
| 自己投資(本・資格・スキル) | 10% | 3.5万円 |
| 娯楽 | 20% | 7万円 |
▷ ポイント
生活防衛資金は6か月分程度まで厚めに確保して安心感を高める
投資は夫婦で協力して「つみたて+ボーナス上乗せ」で育てる
教育・出産・マイホームなどの将来イベントを見据えて「準備枠」を設けておく
結婚初期は、「2人の家計ルール」を話し合う絶好のチャンスでもあります。
ボーナスの使い道を夫婦で一緒に決めておくと、家計の迷いが一気になくなります。
子どもができる前後|“将来のお金”を意識し始める
こんな人におすすめ
子どもを考えている or 妊娠・出産が近い
教育費の準備をそろそろ始めたい
将来のライフプランを見直したい
子どもができる前後は、家計の考え方が大きく変わるタイミングです。
この時期からは「未来への投資」を意識し、教育・出産費用・ライフイベントに備えることが大切です。
▷ 配分テンプレート(例:手取り35万円)
| 使い道 | 割合 | 金額(例) |
|---|---|---|
| 投資(NISA・つみたて) | 30% | 10.5万円 |
| 生活防衛資金 | 20% | 7万円 |
| 将来準備(マイホーム頭金、出産費用など) | 35% | 12.25万円 |
| 自己投資 | 5% | 1.75万円 |
| 娯楽 | 10% | 3.5万円 |
▷ ポイント
教育資金も「NISA」活用あり
出産・育児に向けて、家計の“固定費”をできるだけ軽くしておく
「子どもが生まれたら家計が厳しくなる」という不安を、事前準備で解消する
私も子どもが生まれる前に「準備枠」を設けたことで、出産後の家計の不安が大幅に減りました。(35歳頃には資産500万円以上ありました)
早めの準備は、心の余裕にもつながります。
ポイント|“割合ルール”は一度決めたら変えすぎない
どのライフステージでも共通して大事なのは、割合ルールを一度決めたら大きく変えないことです。
「投資が増えたから削る」「保険料が増えたから調整する」と毎回変えてしまうと、家計の基準がブレてしまいます。
たとえば、独身期は「投資35%」だった割合を、結婚後は「投資20%+防衛15%」にするなど、少しずつシフトさせる程度で十分です。
まとめ|「ステージ別の型」を持つと迷わない
ライフステージによってボーナスの使い方は変わりますが、考え方は常にシンプルです。
✅ 独身期は「攻め」を重視して投資を最大化
✅ 結婚初期は「安定と成長」を両立
✅ 子ども前後は「未来への準備」を優先
ステージごとに“型”を持っておけば、いざボーナスが入っても迷わずに使えるようになります。
次章では、初心者がつまずきやすい「NISA一括 vs 積立」問題について、失敗しない考え方を整理していきましょう。
NISAは一括?それとも積立?迷わない選び方
「NISAで投資を始めたいけど、一括で入れるのと毎月コツコツ積み立てるの、どっちがいいの?」
ボーナスの使い道として投資を考えたとき、誰もが一度はこの悩みにぶつかります。
結論から言えば、正解は人によって違いますが、“自分の性格と家計状況”に合った方法を選ぶことが大切です。
ここでは、初心者が迷わず選べるように、それぞれの特徴・メリット・デメリットをわかりやすく整理します。
一括投資の特徴|「時間」を買える効率的な方法
一括投資とは、ボーナスなどのまとまった資金を一度にまとめて投資する方法です。
▷ メリット
✅ 投資を「早く始められる」ため、運用期間が長くなる
✅ 非課税メリット(NISA枠)を前倒しで活用できる
✅ シンプルで手間がかからない
たとえば、30万円を一括で投資した場合、すぐにその全額が市場で運用されるため、複利の効果を最大限に活かせるのが大きな強みです。
▷ デメリット
❌ 投資直後に相場が下がると、含み損が大きく見えて不安になる
❌ 価格の動きが気になって、精神的なストレスが増える
❌ 「一度に使ってしまって家計が不安」という心理が出やすい
▷ 一括投資が向いている人
✔︎ 相場の上下に一喜一憂しない性格
✔︎ ボーナス以外にも生活資金の余裕がある
✔︎ 10年以上の長期投資を前提にしている
積立投資の特徴|「習慣化しやすい」安心の方法
積立投資は、毎月一定額ずつ投資するスタイルです。
特に初心者や投資経験が浅い人には、精神的なハードルが低くおすすめです。
▷ メリット
✅ 価格が高いときは少なく、安いときは多く買える「ドルコスト平均法」が働く
✅ 相場の上下を気にせず、淡々と続けやすい
✅ 家計のバランスを崩さずに続けられる
「投資をしている実感はあるけど、不安は少ない」──積立投資には、そんな“継続のしやすさ”があります。
▷ デメリット
❌ 投資額が少ないため、資産が増えるスピードは遅め
❌ ルールを決めないと「いつの間にか中断していた」ということもある
▷ 積立投資が向いている人
✔︎ 初めて投資をする・価格変動が怖い
✔︎ 他の支出(教育・旅行など)と両立させたい
✔︎ ボーナス以外の月々の家計も投資に組み込みたい
ハイブリッド戦略|“毎月つみたて+ボーナス上乗せ”が最強
一括と積立、それぞれにメリット・デメリットがありますが、実は両方の良さを組み合わせる「ハイブリッド戦略」が最も継続しやすく、成果も出やすい方法です。
▷ おすすめのやり方
毎月は無理のない範囲でつみたて(例:月1~2万円)
ボーナス時に追加で上乗せ(例:夏・冬に10万円ずつ)
具体例:年間の投資額イメージ
| タイミング | 投資額 |
|---|---|
| 毎月つみたて | 2万円 × 12か月 = 24万円 |
| ボーナス上乗せ | 10万円 × 2回 = 20万円 |
| 年合計 | 44万円 |
このようにルールを固定しておけば、相場を見ずに“自動で資産が育つ”仕組みを作ることができます。
性格別・おすすめ投資スタイル早見表
| 性格・状況 | おすすめ投資方法 | 向いている理由 |
|---|---|---|
| 相場の変動は気にならない | 一括投資 | 運用期間を最大化できる |
| 初めてで不安が大きい | 積立投資 | 心理的負担が少なく継続しやすい |
| 両方のメリットを活かしたい | つみたて+ボーナス上乗せ | 分散と効率を両立できる |
| ボーナスの使い道を固定したい | ボーナス上乗せ型 | 家計の一部として仕組み化できる |
私が実践している投資ルール(体験談)
私自身は最初から一括投資をしていました。
NISAを利用し、日本の会社に投資(個別株投資)しています。
ただし、いきない大金を投じるのは怖かったので、まずは少額で投資し、経験を積んだうえで百万円単位で数社の株を買いました。
結婚してからは安定さも欲しいと考え、月々投資するつみたて投資も開始し、結果的にハイブリッド型に落ち着いています。
まとめ|迷ったら「ハイブリッド型」でOK
✅ 一括投資は「時間を買う」方法。資金に余裕があり、長期運用に向く。
✅ 積立投資は「継続が簡単」な方法。初心者・慎重派に向く。
✅ ハイブリッド型は「いいとこ取り」。毎月つみたて+ボーナス上乗せが最も失敗しにくい。
投資の目的は「一番うまくやること」ではなく、「長く続けること」です。
焦らず、自分の性格と家計に合ったスタイルでコツコツ続けることが、最終的な成果につながります。
若手職員がやりがちなNG行動と回避策
ボーナスの使い方には「正解の型」がある一方で、“やってはいけないパターン”も存在します。
しかも、これらのNG行動は多くの公務員が無意識のうちに陥っている落とし穴です。
ここでは、特に若手職員がよくやってしまう6つのNGと、すぐにできる回避策を解説します。
NG1:ボーナス頼みの家計設計(毎月赤字→ボーナスで埋める)
よくある症状
毎月の生活費がギリギリ、または赤字
「ボーナスが入ったら返す」とカードの分割払いが習慣化
ボーナスが“貯蓄”ではなく“穴埋め”で消えていく
これは最も多い失敗パターンです。
「ボーナスで何とかなる」という家計構造は、一見うまく回っているようでも、実は毎月の支出が大きすぎるサインです。
▷ 回避策:「ボーナスで直す家計」ではなく「ボーナスで軽くする家計」に
通信費・サブスク・保険など、固定費の削減にボーナスを使う
自動車保険や火災保険の年払いをまとめて払うことで、月々の負担を減らす
「赤字→補填」ではなく「支出→軽量化」という順番に意識を切り替える
NG2:保険の入りすぎ・重複放置(共済+団体+民間)
よくある症状
医療保険・がん保険・就業不能保険に複数加入
「職場で勧められたから」と深く考えず契約
月1万円以上の保険料が“固定費の重荷”に
公務員は共済組合の給付が手厚いため、民間保険と重複しているケースが非常に多いです。
重複部分を放置すると、「増えない貯金」「積立に回せない資金」の原因になります。
▷ 回避策:「給付一覧」を作って“必要最小限”だけ残す
まずは共済・団体・民間すべての給付内容を横並びで比較
「死亡・入院・通院・就業不能」など、目的ごとに整理
重複があれば解約・見直し → 浮いた分はNISAや積立へ回す
私も見直しで生命保険、自動車保険合わせて月1万円程度の保険料が削減でき、その分を投資に回した結果、年間12万円近くを資産形成に充てられるようになりました。
NG3:高金利ローンを放置して“投資優先”
よくある症状
リボ払いやカードローンの残高があるのに、NISAを優先している
年利15%の借金を放置して、年利5%の投資をしている
「投資している自分」に満足してしまっている
金利の高い借金は、投資で得られるリターンを簡単に打ち消す「逆資産」です。
借金の返済は“地味”に見えますが、実は最も効率の良いお金の増やし方です。
▷ 回避策:「金利順」で返済をルール化する
年利が高いものから順番に返済(特に10%超は最優先)
少額でも「元金」を削っていくと心理的にも楽になる
投資は“借金ゼロ”を達成してから本格化するのが鉄則
NG4:ご褒美消費が止まらない(“次のご褒美”が癖になる)
よくある症状
「せっかくのボーナスだから」と家電や旅行を毎回購入
満足感がすぐに薄れて、次の大型消費を繰り返す
気づけば“買い物のためのボーナス”になっている
ボーナス消費は「一度やると癖になる」落とし穴です。
しかも、満足度がどんどん下がっていく「逓減効果」があるため、使えば使うほど満足できなくなります。
▷ 回避策:「1週間ルール」と「買い替え表」を導入
欲しいものがあっても1週間寝かせてから判断
家電・車・PCなどは「買い替え周期表」を作って事前に計画
欲しい物リストは「次回ボーナス用」に移動して冷静になる
NG5:“全部投資”で生活がギスギスする
よくある症状
ボーナスの全額を投資に回して、手元資金がゼロ
旅行や自己投資が我慢ばかりでストレスが溜まる
数か月後に「衝動買い」で使ってしまい台無しに
投資は大切ですが、「余裕がなくなるレベル」でやると継続できません。
“我慢の反動”で浪費するケースも少なくありません。
▷ 回避策:「楽しみ枠」を10~20%だけ確保する
趣味・娯楽用に10~20%だけ残す
「楽しみゼロ」にしないことが、長続きのコツ
将来のお金だけでなく、今の満足度も投資だと考える
NG6:支給直後に“気が大きくなる”行動
よくある症状
ボーナス支給日翌日に衝動買い・外食ラッシュ
「まだ口座にお金がある」と気が大きくなって使ってしまう
いつの間にか“配分ルール”が崩壊している
この「気が大きくなる」は、誰でも経験する“落とし穴”です。
特に入庁1〜3年目は金額も大きく感じるため、使いすぎる人が多くなります。
▷ 回避策:「受け取ったその朝」に自動振替を完了させる
ボーナス支給日の朝に、各口座へ自動振替を実行(それか給料天引きの利用も検討)
「使えるお金」を“物理的に減らす”仕組みをつくる
ほしい物リストは「次回ボーナス」用のメモに移動
まとめ|“やらないこと”を決めると家計は安定する
ボーナスの活用で大切なのは、「何をやるか」だけではありません。
同じくらい重要なのが、「何をやらないか」を明確にしておくことです。
❌ ボーナス頼みの家計 → ✅ 固定費削減に使う
❌ 保険の入りすぎ → ✅ 必要最小限だけ残す
❌ 高金利の放置 → ✅ 金利順で返済
❌ ご褒美連鎖 → ✅ 72時間ルール
❌ 全額投資でギスギス → ✅ 楽しみ枠5%
❌ 支給直後の浪費 → ✅ 受け取り当日に自動振替
「やらないことリスト」を意識するだけで、家計は驚くほど整います。
体験談|私が「ボーナス配分ルール化」で人生が変わった話
ここまでボーナスの使い方を「理論」としてお伝えしてきましたが、最後に私自身の実体験をお話しします。
これは、「思いつきで使っていた20代」と「ルールを決めて使うようになった30代」では、家計もメンタルもまったく別物になったという話です。
ご褒美優先だった新人時代:「楽しいけど、不安がつきまとう」
県庁に入庁して1〜3年目の私は、典型的な“ご褒美優先型”でした。
夏ボーナス → 新しいパソコン・ベッド購入
冬ボーナス → 旅行・ブランド品購入
もちろん、その瞬間は最高に楽しいです。
しかし、1〜2か月後には毎回こう思っていました。
「クレジットの支払いがキツい…」
「急な出費に全然対応できない」
「貯金は増えていないし、投資なんて夢のまた夢」
さらに異動で引っ越しが重なると、ボーナスの大半が家具・家電・移動費用に消え、「またゼロから…」という繰り返し。
せっかく頑張って働いても、“お金に振り回されている感覚”が常にありました。
ボーナスがしっかり支給されていたのに、20代前半は貯金が全くありませんでした。
ルール化のきっかけ:「目的別に口座を分ける」だけで激変
転機が訪れたのは、入庁7年目の夏です。
たまたま読んだ「お金に関する入門書」がきっかけでした。
そこで私は、次の3つのルールを自分に課しました。
割合を事前に決める:「貯金30%/投資20%/自己投資30%/娯楽20%」
ボーナス当日の朝に自動振替する:貯金分は給与天引きにして自動的に地銀の口座に入るようにし、投資分はすぐ証券会社の口座に仕分けました。
ご褒美は“残りで”と決める:最初から「ゼロにしない」設計にする
たったこれだけのことでしたが、結果は劇的でした。
効果①:「貯金が“自然に”増えるようになった」
まず一番大きかったのは、「貯金が勝手に増える」仕組みができたことです。
今までは“余ったら貯める”という発想でしたが、“最初に分ける”だけで年間50万円以上が確実に貯まるようになりました。
突発的な出費(引っ越し・冠婚葬祭・車検など)にも慌てず対応できるようになり、「お金の不安」が一気に減少しました。
効果②:「投資を“続ける”ことが当たり前になった」
それまでは「投資したい」と思っても、なかなか行動に移せませんでした。
しかし、ボーナス時に“自動的に投資用口座へ振り込む仕組み”を作ってからは、考えずに続けられるようになったのです。
相場が下がっても「ルールだから続ける」だけ。
気がつけば、投資を始めて8年、資産が目に見えて増えていく実感が持てるようになりました。
効果③:「家計に“余白”が生まれた」
固定費の見直しや保険の削減にもボーナスを活用したことで、毎月の支出が軽くなりました。
例えば、保険の見直しをしただけで月1万円の固定費削減。年間で約10万円の余裕が生まれ、その分を投資や自己投資に回せるようになったのです。
「お金が足りない」ではなく「お金に働いてもらう」という発想に変わったのは、この頃からです。
効果④:「ご褒美が“本当に嬉しい”と感じるようになった」
ご褒美を完全にゼロにするのではなく、「10~20%だけ残す」というルールにしたことで、使うお金への満足度が劇的に上がりました。
“なんとなく買う”ではなく“本当に欲しいものだけ”を選ぶ
衝動買いが減り、買った物に対する満足度が長続きする
お金の使い方に「後悔」がなくなる
ご褒美が“罪悪感”ではなく“達成感”に変わったことが、何より大きな心の変化でした。
まとめ|“ルール化”は人生の安心と成長を同時にくれる
このルール化をしてから、私のボーナスは単なる“ご褒美”ではなく、「家計の健康診断日」「資産を増やすスイッチ」になりました。
しかもこれは、特別な知識や才能が必要なものではありません。
誰でも今日からできる習慣です。
そして、1年、2年、3年と積み重ねるほど、家計の安定感と資産の伸び方は大きくなっていきます。
「今月も何とか乗り切った」という感覚から、「未来が楽しみだ」という感覚へ。
ボーナスの使い方一つで、お金との付き合い方そのものが変わるということを、ぜひ体感してみてください。
まとめ|“先に土台、残りで楽しむ”が後悔ゼロの鉄則
ここまで読んでくださったあなたは、もう「ボーナスを何となく使って終わり」にしない力を手にしています。
最後に、この記事の内容を振り返りながら、「今日からできる行動ステップ」を整理しておきましょう。
ボーナスは“ご褒美”ではなく“年2回の家計チューニング日”
まず一番大切なのは、ボーナスの本質的な役割を変えることです。
それは「半年頑張った自分へのご褒美」ではなく、「年2回の家計を整えるチャンス」として使うこと。
この考え方を持てるかどうかで、数年後の貯金額・資産額・お金の安心感は大きく変わります。
正解は“人それぞれ”ではなく“順番”
ボーナスの使い道に「正解はない」とよく言われますが、それは半分正しくて、半分間違いです。
本当の正解は、“自分に合った順番”で使うことです。
もう一度、鉄板の5ステップをおさらいしましょう。
✅ 生活防衛資金:3〜6か月分の生活費を安全網として確保
✅ 高金利ローン返済:年利の高い借金は“投資より先”に返す
✅ 保険・共済の見直し:重複を削って固定費を軽くする
✅ 投資・NISA・自己投資:“攻め”に資金を使う
✅ 割合テンプレート:「割合」で迷わない仕組み化
この順番さえ守れば、誰でも「使っても貯まる家計」を作ることができます。
ライフステージ別に“型”を持とう
若手のうちは、人生のステージごとにお金の優先順位が少しずつ変わっていきます。
独身期:NISA・投資を中心に“攻め”の姿勢を固める
結婚初期:生活の安定と資産形成をバランスよく両立
子ども前後:教育・将来資金への備えを少しずつ強化
「自分は今どのステージか?」を意識しながら、“今の自分に合った配分”を選んでいきましょう。
NG行動を避ければ、お金は自然と貯まっていく
やることを決めるのと同じくらい大切なのが、「やらないこと」を決めることです。
特に以下の6つは、若手公務員が最も陥りやすい落とし穴です。
❌ ボーナス頼みの家計
❌ 保険の入りすぎ・重複放置
❌ 高金利ローンの放置
❌ ご褒美消費の連鎖
❌ 全額投資で生活がギスギス
❌ 支給直後の衝動消費
これらを回避するだけで、家計の“ゆとり”と“資産の伸び”は驚くほど変わります。
今日からできる3つの行動ステップ
最後に、「この記事を読んだ今日からできること」を3つにまとめます。
🧭 割合ルールを決める
→ 紙1枚でもメモでもOK。「割合」を自分用に書き出す⚙️ 自動振替・自動つみたてを設定する
→ ボーナス当日の朝に自動で仕分けされる仕組みをつくる🔍 家計の点検をする
→ 生命保険や自動車保険の見直し・サブスクの見直し・格安スマホ(格安SIM)に切り替えなどを一度チェック
この3つを実践するだけで、次のボーナスから「後悔しない使い方」がすぐに始められます。
最後に|“先に土台、残りで楽しむ”が一生モノの習慣になる
お金の使い方は、「我慢するか」「浪費するか」の二択ではありません。
大切なのは、“先に土台を整えて、残りで楽しむ”という順番です。
この順番を守れば、
✅ お金が貯まるスピードが加速し
✅ 投資が「怖い」から「楽しい」に変わり
✅ ご褒美が「罪悪感」ではなく「達成感」に変わります
そしてその習慣は、あなたが30代・40代・50代と年齢を重ねても、ずっと使い続けられる一生モノの資産になります。
次のボーナスを“ただの臨時収入”で終わらせず、「未来を変えるお金」に変える第一歩を、今日から踏み出してみてください。
【関連記事】
公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】
公務員の株式投資と家計管理!失敗しない両立のコツを元公務員FPが解説