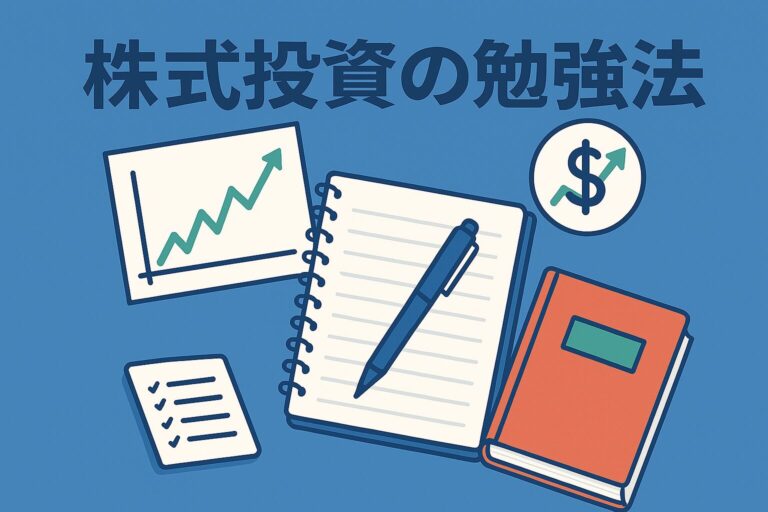「将来のために資産運用を始めたいけど、公務員でも本当に株式投資はできるの?」
「何から勉強すればいいのか全くわからない…」
そんな疑問や不安を感じていませんか?
近年、公務員の間でも「投資」や「お金の知識」の必要性が強く叫ばれるようになり、実際に株式投資に興味を持つ方が増えています。
しかし一方で、「副業禁止の規定」「職場や家族の目」「失敗したらどうしよう」という公務員特有の不安が、最初の一歩を踏み出す大きな壁になることも多いでしょう。
私自身も元公務員として、まったくの初心者から独学で株式投資を学び始めた経験があります。
最初は用語や仕組みが難しく感じたり、ネットや本の情報が多すぎて「結局どれが正しいの?」と迷う場面もたくさんありました。
この記事では、現役・元公務員FPの実体験と最新の投資教育ノウハウをもとに、「公務員が失敗しない・不安なく・効率よく株式投資を学ぶ方法」を、はじめての方にも分かるようやさしく解説します。
公務員におすすめの具体的な勉強法
独学でつまずきやすいポイントとその解決策
実際に投資を始めた体験談
Q&Aや注意点、次の行動まで
あなたの投資デビューを後押しする「完全ロードマップ」として、ぜひ活用してください。
公務員が株式投資の勉強を始める前に知っておくべきこと
公務員でも株式投資はできる?禁止・制限のルール
まず最初に、公務員が株式投資を行うこと自体は、法律や服務規程上、原則として認められています。
多くの公務員が「副業禁止」のルールに不安を感じますが、「株式投資」は副業ではなく「資産運用」に分類されます。
したがって、自分の資産を使い、長期的な資産形成を目的に行う場合は、禁止されていません。
ただし、いくつか守らなければならない注意点・ルールがあります。
インサイダー取引は禁止
公務員の仕事で得た内部情報(たとえば市町村の大型事業や新規プロジェクトの情報など)を利用して株の売買を行うことは法律で固く禁じられています。
これは民間企業の社員も同じですが、公務員はより厳しい倫理規定が課せられています。職務専念義務・信用失墜行為の禁止
勤務時間中に株の売買や株価チェックを繰り返すのは当然NGです。
また、株式投資で大きな損失を出して生活に支障が出るような場合、本業のパフォーマンス低下や信用失墜につながるリスクがあります。短期売買や「事業的」投資は注意
継続的なデイトレードやFXなど、あまりにも頻繁な売買を行い「投資が事実上の副業・事業」とみなされると、服務規律上の問題となることも。
「長期保有を基本」とし、頻繁な売買での大きな利益を狙うスタイルは控えましょう。自分の自治体や所属ごとの規定も要確認
法律上は問題なくても、自治体や省庁ごとに「独自の倫理規定」や「資産報告義務」が設けられている場合もあります。
念のため、人事や総務など担当窓口で確認しておくと安心です。
【参考:人事院公式リンク】
よくある不安と誤解
Q.「株式投資はバレたら処分される?」
→通常、証券口座や投資利益が職場に直接伝わることはありません。ただし、明らかな規則違反や不正行為があった場合は別です。
Q.「副業禁止なのに大丈夫?」
→株式投資やNISA、投資信託などは“資産運用”に該当し、「副業」扱いにはなりません。
Q.「家族に心配される…」
→投資=ギャンブルと思われがちですが、「資産形成の一環」として、少額からコツコツ積み立てることの意義を伝えると理解も得やすくなります。
Q.「損をしたらどうしよう…」
→リスクはゼロではありませんが、知識をつけて少額・長期分散で始めれば、リスクは十分コントロール可能です。
最初から大きな金額を投じず、「毎月少しずつ」「生活費に影響しない範囲で」を徹底しましょう。
Q.「何から始めたらいいかわからない」
→まずは「株の雑誌」「株の入門書」「公式の無料講座」「YouTubeの初心者向け動画」からスタートするのがおすすめです。
この記事でも“具体的な学び方”を後述します。
迷ったら「少額で実際に始めてみる」ことも重要
投資の勉強を始めたばかりのころは、「もっと知識をつけてから」「失敗が怖いからまだ始めないでおこう」と、ついインプットばかりに時間をかけてしまう方も多いものです。
私自身も次から次へと新しい本を読み漁り、それでも不安が消えないのでなかなか投資に踏み切ることができませんでした。
ですが、実際に“自分のお金”を少しだけ動かしてみることで、初めて分かること・気付くことがたくさんあります。
たとえば、
取引画面や入出金の流れ
注文方法や「思ったよりドキドキする」自分の感情
損益が変動するリアルな数字の感覚
これらは、本やネットだけでは絶対に得られない「実践知」です。
しかも今は、「数百円〜数千円」から取引できる時代。
生活費に影響のない範囲の少額で、“まず一歩”踏み出すことが、学びの効率アップにも大きくつながります。
最初の一歩は、完璧な知識がなくても大丈夫です。
失敗しにくい“超少額”から始めて、動きながら学び続けることをぜひ意識してみてください。
公務員におすすめの具体的な株式投資勉強方法

株式投資の勉強というと、「本やネットでひたすら情報収集」「難しい専門用語に圧倒されて進めなくなる」という方も多いでしょう。
特に公務員の場合、「忙しい」「失敗できない」「誰にも相談できない」と悩みやすく、つい勉強だけに偏りがちです。
ですが、投資は「知識」と「実践」をセットで進めることで、効率よくスキルが身につきます。
ここでは、私自身や多くの公務員受講者が実践して効果を感じた“勉強の7ステップ”を紹介します。
1. 無料&有料ネット教材・動画で基礎を固める
まずは、「株式投資とは何か」「株の仕組み」「基本用語」などを知ることから始めましょう。
書籍も良いですが、証券会社の公式セミナーや金融庁・日本証券業協会のYouTube動画など、信頼できる無料教材が今は充実しています。
特にYouTubeの「初心者向け投資解説」や金融庁の公式コンテンツは、難しい表現が少なく、図解や実例も豊富です。
動画で学ぶと「分かったつもり」が減り、イメージが湧きやすいのもメリットです。
【参考HP】
2. 証券会社の公式セミナー・eラーニングを活用する
ネット証券や大手証券会社では、無料のオンラインセミナーやeラーニング講座が毎月のように開催されています。
会員登録をしなくても「初心者向けNISAセミナー」や「失敗しない株式投資の始め方」などに参加でき、分からないことはその場でプロに質問できるのも魅力です。
3. 四季報や経済ニュースで「実際の情報」を読む習慣
基礎を理解したら、日経新聞や会社四季報、経済ニュースサイトで「実際の企業や相場の情報」に触れる習慣をつけましょう。
最初は「知らない用語だらけ」でつまずきますが、分からない言葉をメモして1つずつ調べるだけでも知識がどんどん増えていきます。
気になる企業を毎日1社ピックアップし、四季報で「売上・利益・事業内容」を読むのもオススメです。
4. 仮想売買・模擬投資でアウトプット学習
「知識だけ詰め込んでも、実際にやってみると分からないことが山ほど出てくる」
これは、株式投資の世界でもよくある現象です。
少額の実践、もしくは株のシミュレーションアプリやサイトで「アウトプット」することが理解への近道です。
たとえば「1株だけ買ってみる」「投資信託を1000円だけ積み立ててみる」といった小さな一歩でもOK。
画面の操作や、売買後の感情の動きを体験してみることで、リスクの実感やお金の動きが“自分ごと”になります。
5. 家計簿やマネーアプリで「投資を生活に組み込む」
投資は「お金の流れを把握する」ことも大切。
家計簿アプリやマネーフォワード、Zaimなどの資産管理ツールで、毎月の収支や貯蓄額を見える化し、「この範囲なら投資しても安心」という予算を決めておくと、投資の不安も減ります。
公務員は収入が安定しているので、まずは「無理のない金額で継続」が何よりも大切です。
6. SNS・コミュニティの賢い使い方と注意点
投資系YouTubeやX(旧Twitter)などで情報収集をする際は、「公式・金融機関・信頼できる専門家」の発信を中心にし、匿名の意見や過度な煽りには注意しましょう。
投資話を職場で広げない、SNSで個人情報や職業を出しすぎないことも、公務員ならではの大切なリスク管理です。
7. FP資格や公式教材を副教材に
「もっと幅広く、お金全体を学びたい」という方は、FP3級・2級の教材や通信講座もおすすめです。
税金や保険、家計設計までトータルで学べるので、投資だけでなく、人生設計にも役立つ知識が身につきます。
8. 株の雑誌や株入門書を数冊読む
私が最もおすすめするのは、やはり「本」を読むことです。
コツとしては、最初の1冊は「とにかく簡単で分かりやすい入門書」を選ぶこと。
かっこつけて分厚い難しい本を買うと挫折してしまいます。
そのため、まずは「株の雑誌→株の入門書」がおすすめです。
【参考記事】
公務員向けおすすめ株式投資本14選|初心者安心!元県職員FPが体験談で厳選
【ワンポイント】「まずはやってみる」が最大の学び
何度もお伝えしますが、「知識→実践→振り返り」のサイクルこそ、投資勉強の王道です。
はじめての一歩は、100点満点でなくても大丈夫。
失敗しにくい超少額から、“実際に始めてみる”ことで理解が一気に深まります。
私の体験談|公務員から投資を学び始めたリアル記録
「投資は自己責任」とよく言われますが、実際に自分の大切なお金を動かすとなると、不安や緊張でいっぱいになるものです。
私が初めて株式投資に興味を持ったのは、「お金持ちになって早くリタイアして家族と幸せな時間を過ごしたい」という気持ちが出てきたことがきっかけでした。
当時は投資=ギャンブルというイメージが強く、周囲に相談できる人もいませんでした。
ですが、資産運用やお金の勉強ができる「株の雑誌」や「株の入門書」、「YouTube動画」に触れるうちに、「きちんと知識を身につけて始めれば、危ない世界ではない」と思えるようになりました。
初めての証券口座開設と“最初の一歩”
最初に取り組んだのは、ネット証券の口座開設です。
最初はネット手続きが面倒そうに感じていましたが、必要書類や本人確認も案外シンプルで、「自分にもできる」と実感しました。
そして、投資デビューは「数万円の個別株を買う」という少額スタート。
初めて自分のお金が「投資商品」として動き、数字が刻々と少しずつ上下する感覚は、とても新鮮でワクワクしました。
大金をいきなり投じていたら、たぶん怖さのほうが勝っていたと思います。
【参考記事】
【2025年最新】公務員向けおすすめ証券会社4選を元公務員FPが比較!実体験で語る選び方と注意点
失敗から得た教訓と、継続のコツ
「知識だけでなく、まずは少額でもやってみる」ことがいかに大切かは、最初に“想定外の失敗”を経験したことで痛感しました。
思っていたより注文ボタンの場所が分かりづらく、焦って誤発注しかけた
株価が下がったとき、「不安」や「損切りしたい気持ち」が強くなり、冷静に判断できなくなりそうになった
SNSやニュースで“流行り銘柄”に流されそうになり、危うく高値掴みしそうになった
これらは、机上の知識だけでは絶対に分からなかったことです。
失敗を減らすためには、
「一度に大きな金額を投じない」
- 「余力資金で投資を行う(生活資金には手をつけない)」
- 「しっかり自分で分析してからこれぞと思う企業に投資をする」
「自分の投資ルール(例:いくらまで、どんなときに売買するか)を事前に決める」
「定期的に振り返りノートをつけて、自分の感情や判断を見直す」
こうした工夫が役立ちました。
投資が「生活の一部」になって感じたこと
投資を始めてしばらく経つと、「経済のこと」「お金の使い方」「家計の見直し」「将来の備え」を自然と考えるようになりました。
特にExcelの家計簿を使い、毎月の投資額や収支をチェックすることで、「投資=特別なこと」ではなく「貯金や保険と同じ、人生の基礎」になったと感じます。
家族にも、最初は反対気味でしたが、「しっかり勉強してリスクを下げている」「余力資金で投資している」と伝えることで、少しずつ理解と協力を得られるようになりました。
まとめ
最初は不安でも、小さく始めて実践を重ねることで、着実に「分かること」「できること」が増えていきます。
「難しい」と感じるのは最初だけ。
小さな成功体験の積み重ねが、あなたの投資の自信につながります。
公務員によくあるQ&A・悩み

公務員が株式投資を始めるとき、多くの方が感じる“よくある疑問や悩み”をQ&A形式で解説します。
法律や規則の観点はもちろん、実際に現場でよく聞く「リアルな心配ごと」まで幅広くカバーします。
Q1. 投資をしていることは職場にバレませんか?
A. 基本的にはバレることはありません。
株式投資や投資信託で得た利益や証券口座の情報が、職場に自動的に通知されることはありません。
ただし、勤務中の取引や情報漏洩、インサイダー取引など明らかな違反があれば、当然ながら調査や処分の対象となります。
<注意点>
確定申告で「住民税の納付方法」を“自分で納付”にしておくと安心です(特に特別徴収の場合)。
職場で不用意に投資の話を広めないほうが無難です。
Q2. 副業禁止なのに大丈夫?
A. 「資産運用」として認められています。
株式投資・NISA・投資信託などは、あくまで「資産運用」であり副業には該当しません。
Q3. 確定申告や税金はどうなる?
A. NISAなら原則非課税、それ以外は利益が20万円を超えた場合、確定申告が必要です。
特定口座(源泉徴収あり)を使えば、確定申告不要の場合も多いです。
詳しくは証券会社のサポートや、国税庁公式サイトで確認しましょう。
Q4. 家族やパートナーの理解が得られません
A. 少額から始めること・“資産運用”としてリスク管理を徹底していることを丁寧に伝えましょう。
投資に悪いイメージを持つご家族も多いですが、「生活費や貯金とは別で、無理なくコツコツ積み立てる」「ギャンブル的な短期投資はしない」ことを繰り返し説明することで、徐々に理解を得られるケースが多いです。
私が株式投資をやっていることが安心材料となり、今では妻、母、兄、親戚、友人も株式投資を始めています。
Q5. 投資のことを誰にも相談できません
A. 無理に周囲に話す必要はありませんが、不安な場合は「証券会社の無料相談」や「FPへの個別相談」を利用しましょう。
また、自治体や金融庁主催のマネーセミナーも公務員の参加OKです。
SNSやネット掲示板での情報収集はリスクもあるので、公式サポートや専門家の窓口を積極的に使うのがおすすめです。
Q6. 投資で大きく損をしたらどうしよう?
A. 最初から「生活に支障のない少額」で始めるのが鉄則です。
また、全財産を一つの銘柄や投資商品に集中させず、必ず分散投資を心がけましょう。
短期の値動きに一喜一憂せず、長い目でコツコツ続けることが最大のリスクヘッジです。
まとめ
公務員ならではの悩みや不安も、正しい知識と工夫で十分カバーできます。
不安を放置せず、「調べる・相談する・少額で始めてみる」のサイクルを大切にしましょう。
独学で成果を出すためのコツ・注意点

株式投資の勉強を始めると、
「情報が多すぎてどれが正しいのか分からない」
「思ったように続かない」
「途中で挫折しそう」
こうした壁に誰もが一度はぶつかります。
ここでは、公務員が独学で着実に成果を出すための実践的なコツと注意点を紹介します。
最短ルートを目指すより、“続ける工夫”と“リスク管理”を重視しましょう。
1. 情報源は「公式」と「信頼できる専門家」に絞る
株式投資の情報はネット上にあふれていますが、初心者が最初に混乱しやすいのが「玉石混交の情報」です。
金融庁・証券会社・日本証券業協会など、公的機関や大手金融機関の教材や解説をまずはベースにし、個人ブロガーやSNSの情報は“参考程度”に留めましょう。
2. 分からない用語や仕組みは「すぐメモ・すぐ調べる」
「知らない単語が出たらノートやスマホにメモ」
「その日のうちに自分の言葉で説明できるまで調べる」
この“反復インプット”が独学成功の近道です。
3. 模擬取引や少額投資で「実践力」を鍛える
インプットだけでは身につきません。
証券会社のデモ口座や仮想売買アプリ、実際に「1000円だけ投資信託を積み立ててみる、1万円で個別株を買ってみる」など、“体感”する機会を増やすことで、「なぜ値動きが起きるのか」「自分はどんなときに不安になるのか」が分かります。
4. 無理な金額・高リスク商品には絶対手を出さない
最初から大きな利益を狙って「高リスクな株」「レバレッジ型ETF」「信用取引」に手を出すのはNG。
あくまで「生活に影響のない金額」「分散投資」が鉄則です。
小さな失敗なら“授業料”で済みますが、大きな損失は長く引きずります。
5. モチベーション維持には「成果の見える化」が効く
「なかなか成果が出ない」ときも、
投資記録に「今日学んだこと」「取引で感じたこと」を毎回記録
積立金額や保有株数の“ちょっとした変化”を毎月グラフで可視化
こうした“進歩の記録”が続ける原動力になります。
6. 失敗したときこそ「冷静に振り返る」
損失や失敗をしたときこそ、「なぜ失敗したのか?」「何が原因だったのか?」を冷静に振り返ることが大事です。
感情的になって「取り返そう」と無理な売買を重ねるのが最大の失敗パターン。
「失敗ノート」をつけて、自分の傾向を分析してみましょう。
7. 「投資の話」を広げる場面・相手は選ぶ
公務員は特に、職場や知人との会話で投資の話を広げることは慎重に。
SNSでも“身バレ”や「投資している=副業」と誤解されるリスクもあります。
公式な場・信頼できる相談先を活用しましょう。
まとめ
独学での株式投資は、「知識→実践→振り返り→継続」のサイクルが一番の成功法則です。
焦らず、地道に、でも着実に――。
「今日から1つでも進歩する」を目標に、あなたらしい投資スタイルを築いてください。
まとめ
株式投資の勉強は、「知識を身につける」ことだけがゴールではありません。
インプットしたことを、実際に“少額から試してみる”――この小さな一歩が、投資リテラシーを本物に変えてくれます。
公務員にとって投資は、将来への備えであり、安心して生活を送るための大切な手段です。
ルールを守り、無理のない範囲で学びながら始めれば、資産運用は決して“危ないもの”ではありません。
このガイドで紹介した通り、
まずは公式や信頼できる教材・動画で「基礎」を固める
わからない言葉や仕組みはその都度メモをし、調べて“自分の言葉”にする
仮想取引や超少額投資で「実践」の経験を積む
家計管理もセットで考え、無理な金額や高リスク投資を避ける
投資ノートや家計簿アプリで「学び」と「成長」を“見える化”する
失敗も冷静に振り返り、焦らず継続する
――この「学び→実践→振り返り」のサイクルを回すことが、着実なステップアップにつながります。
【関連記事】