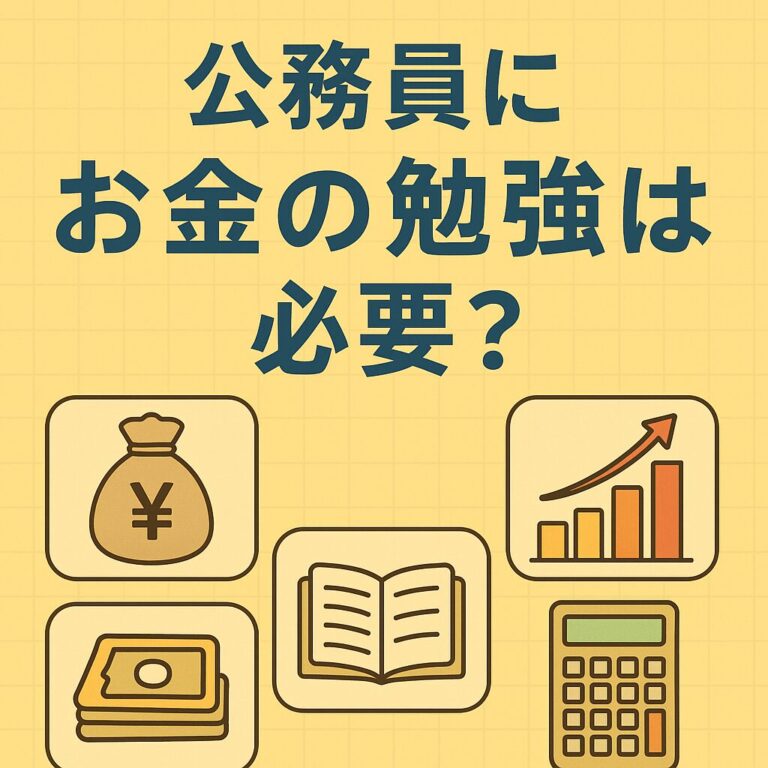「公務員は安定しているから、お金のことは心配いらない」
――そう思っていませんか?
私もかつて県職員として9年間働いていたとき、まさにそう信じていました。
しかし実際には、安定した収入の裏で「お金の知識がないこと」が原因で、知らず知らずのうちに“損をしている公務員”がたくさんいます。
たとえば、
- 共済組合の保障内容を知らずに保険を二重加入している
- NISAやiDeCoを「自分には関係ない」と思って放置している
- 退職金や年金を「なんとなく」でしか把握していない
こうした“お金の無知”は、人生のどこかで必ず影響します。
だからこそ、公務員にこそ「お金の勉強」が欠かせません。
この記事では、元県職員でありFPの私が、なぜ公務員ほどお金の知識が必要なのか、そしてどんな分野から学べば安心できるのかを、わかりやすくお伝えします。
読めば、「勉強する意味」だけでなく、今日から実践できる一歩が見えてくるはずです。
では、順に見ていきましょう。
🏛 第1章:なぜ公務員にこそ「お金の勉強」が必要なのか

「公務員は安定しているから、お金の心配はいらない」――そう思っている方は多いでしょう。
確かに、毎月の給与は保証され、ボーナスも支給されます。
しかし、それが“安心”である一方、お金に対する危機感が薄れやすい構造でもあるのです。
私は県職員として9年間働いていましたが、FP(ファイナンシャルプランナー)の勉強を始めてから、
「公務員ほどお金の知識が必要だったのか」と痛感しました。
その理由を、3つの観点から説明します。
💡 ① 日本人はそもそも「お金の教育」を受けてこなかった
まず前提として、日本では学校でも家庭でも“お金の授業”を受ける機会がほとんどありません。
文部科学省の調査によると、家庭科で学ぶ内容は「家計の管理」程度で、投資・年金・税金といった実生活に直結する知識までは教えられていても、さわりだけです。
結果として、多くの人が「給与天引き」「税金」「社会保険」の仕組みをよく分からないまま社会に出ます。
これは民間だけでなく、公務員も例外ではありません。
だからこそ、「知らないうちに損をしている」ケースが驚くほど多いのです。
公務員は頭が良い人が多く、プライドも高いのでお金の知識不足を認めたくない人が意外と多くいます。
「自分は公務員だから頭がいい、わざわざお金の勉強をしなくても知識はそれなりにある」と思ってしまっている人がいます。
🏦 ② 安定した収入が“お金オンチ”を生む
公務員の強みは「安定」ですが、それが同時に“油断”を生みます。
共済組合があるから安心
給料は減らないし倒産もしない
退職金や年金があるから大丈夫
- ボーナスもしっかりでる
- クビもない
こう思い込み、家計を真剣に見直すきっかけが生まれにくいのです。
私自身も在職中は「お金のことは苦手」と避けてきました。
でも退職して初めて、自分がどれだけ制度や税金を理解していなかったかに気づいたのです。
たとえば、
高い保険に加入していた(比較しないで営業担当のいうままに契約していた)
NISAやiDeCoの存在を知らなかった(投資をしなくても公務員なら老後は大丈夫だと考えていた)
給与天引きの銀行積立を「なんとなく」で続けていた
これらはすべて「知識がないこと」による損失でした。
⚠️ ③ 知らないと“静かに損をする”のが公務員の現実
公務員の給与体系は明確で、昇給・手当・退職金まで制度化されています。
一見すると完璧ですが、その裏では「自分で考えなくても生活できる」環境が整いすぎているのです。
税金が自動で引かれるから、節税を意識しない
共済組合に任せきりで保険の中身を把握していない
老後資金を「退職金と年金だけで足りる」と思ってしまう
つまり、“自動的に守られている”ようで、実は守られていない。
この構造を理解していないと、いざ転職・退職・病気などの変化が起きたときに立ち行かなくなります。
✍️ FPとしての一言
「お金の勉強」は、贅沢のためではなく、“安心のための知識”です。
特に公務員は、安定した収入をどう活かすかで差がつきます。
お金を「ただもらう人」から「運用し、守り、増やす人」へ――。
それが、これからの時代に求められる“新しい公務員の教養”です。
💰 第2章:「お金の勉強」で得られる3つのメリット

お金の勉強というと、「難しそう」「時間がかかりそう」と感じる人が多いかもしれません。
でも実は、お金の知識を少し持つだけで、生活の安心感と選択肢が大きく変わります。
ここでは、公務員が“お金の勉強”を始めることで得られる3つのメリットを紹介します。
🧠 ① 将来の不安が減り、人生設計が立てやすくなる
お金の知識を持つと、「将来、何にいくら必要か」が見えるようになります。
住宅ローン、教育費、老後資金――これらを数字で把握できるだけで、“なんとなくの不安”が“具体的な対策”に変わります。
たとえば、
- 人生のライフプランニング(何歳頃どのくらいの支出があるのか)をあらかじめ想定し、貯金や投資を始める
年金受給額をシミュレーションしてみる
退職金の運用方法を考えておく
教育費を「いつ・いくら」貯めるか逆算する
公務員は計画性のある仕事を得意とする人が多いですが、家計も“人生のプロジェクト”として管理することで、同じように成果が出ます。
💬 「見えない不安」は“数値化”すれば解決できる。
これが、お金の勉強で得られる最大の安心です。
💸 ② 無駄な支出が減り、家計にゆとりが生まれる
お金の知識を持つと、“知らずに払っていたお金”を見直せます。
たとえば、
医療保険を見直して月5,000円カット
通信費を格安SIMに変えて月5,000円カット
税金控除(ふるさと納税・iDeCo)を活用して節税
実際、FPとして相談を受けていても、「お金の勉強をしただけで月1〜2万円浮いた」という方は珍しくありません。
公務員の場合、安定しているがゆえに固定費を疑う機会が少ないのが実情です。
でも、ほんの少し知識を身につけるだけで、年間数十万円単位の差になります。
💬 「お金の勉強」は“稼ぐ力”ではなく“守る力”を高める第一歩です。
🌿 ③ 精神的な安心と自由な選択肢が手に入る
お金の知識を持つことで、日常の小さな不安が減ります。
たとえば、将来の出費を想定できることで「急な支払い」に動じなくなり、資産を育てる仕組みを知ることで、「仕事を続ける理由」も前向きになります。
特に、公務員は「転勤」「出産」「退職」などライフイベントの変化が多い職業。
だからこそ、お金の勉強=人生の安定装置になります。
私自身もFPの勉強を始めてから、「将来の見通しが立つだけで、気持ちが軽くなる」ことを実感しました。
💬 知識は“心の保険”。お金の勉強は、安心して働くための“人生のセーフティネット”です。
💡 第3章:「お金の勉強」は何から始めればいい?初心者向け3ステップ

「お金の勉強をしたい」と思っても、いざ始めようとすると何から手をつけていいか分からない――
これは多くの人がぶつかる壁です。
でも安心してください。お金の勉強は、順序を守って少しずつ進めれば、確実に理解が深まります。
ここでは、公務員がお金の勉強をムリなく進めるための3ステップを紹介します。
🏠 ステップ①:まずは“自分の家計”を知ることから
最初の一歩は、「お金の流れを見える化すること」です。
投資や保険の知識よりも、まずは自分の収支を把握するのが先。
具体的には、
給与明細を確認し、控除内容(共済掛金・税金)を理解する
固定費(通信費・保険・サブスクなど)をリスト化
紙の家計簿や家計簿アプリ(マネーフォワードMEなど)で1ヶ月の支出を記録
これだけで「思っていたより保険料が高い」「食費がかさんでいる」「コンビニでの買い物が多い」といった気づきが得られます。
特に公務員は“給与天引き”で安心してしまい、「いくら使っているのか分からない」状態になりやすい職種。
でも、家計を把握するだけで無駄を減らし、貯蓄のベースが作れます。
📚 ステップ②:本で「正しい知識」を身につけよう
最近はSNSやYouTubeでもお金の情報が手に入りますが、断片的で偏った内容も多く、「何を信じればいいか分からない」と悩む人が後を絶ちません。
だからこそ、最初は“本で学ぶ”ことを強くおすすめします。
理由は3つあります。
情報が体系的で正確(FP監修など信頼性が高い)
知識が線でつながる(税・投資・保険の関係が理解できる)
手元に残るので、何度も復習できる
おすすめの入門書はこちらです👇
| 書名 | 特徴 |
|---|---|
| 『本当の自由を手に入れるお金の大学』(両学長) | 初心者でも非常に読みやすく、生活全般を体系的にカバー |
| 『今さら聞けないお金の超基本』(坂本綾子) | 図解が多く、基礎理解に◎ |
| 『めちゃくちゃ売れてる株の雑誌ザイが作った株入門』(ダイヤモンド・ザイ編集部) | 株式投資の入門書に最適 |
私もこの3冊を軸に学びましたが、どれも「読むほどお金に対する考え方が変わる」良書です。
📘 本は“最もコスパの良い自己投資”。
SNSの断片情報より、1冊を繰り返し読む方が100倍身になります。
💼 ステップ③:実践で「知識を使いながら覚える」
知識は使ってこそ定着します。
完璧に理解してから始める必要はありません。
たとえば:
NISAを月1万円から積み立ててみる
iDeCoを申し込み、税控除を体験する
保険を見直して、不要な特約を削減する
実際に動くことで、「こういう仕組みだったのか」と理解が深まります。
公務員は安定収入があるため、小さく始めてコツコツ積み上げる投資に最も向いた職業です。
💬 “知識→行動→実感”のサイクルこそ、お金の勉強の本質。
🧠 第4章:「お金の勉強=FP試験の内容で十分!」

「お金の勉強」と聞くと、「投資のプロみたいな知識が必要なのでは?」と思う方も多いでしょう。
でも実際には、FP(ファイナンシャルプランナー)の3級レベルで生活に必要な“お金の基礎”はすべて網羅できます。
FPの勉強は、投資や保険だけでなく、税金・年金・住宅ローン・相続までを体系的に学べる仕組み。
つまり、“人生で一度は学んでおくべきお金の教科書”なのです。
📘 FP3級レベルで、生活に必要なお金の基礎知識はすべてカバーできる
FP試験では、次の6分野を学びます👇
ライフプランニングと資金計画
リスク管理(保険)
金融資産運用(投資信託・株式など)
タックスプランニング(税金)
不動産
相続・事業承継
これらはすべて、公務員にとっても必要な知識ばかり。
たとえば「共済組合の医療給付を理解する」「退職金をどう運用する」「ふるさと納税の控除上限を知る」「NISA制度の概要を知る」――
どれもFPの知識そのままです。
つまりFPを学ぶことは、「お金の勉強=生活を守る勉強」なのです。
🧩 試験勉強がそのまま人生に活きる理由
FP試験の勉強は、暗記よりも実生活に置き換えることが重要。
たとえば、
ライフプランの章 → 将来の教育費・老後資金の設計
保険の章 → 自分や家族の保障内容の見直し
金融資産運用 → 投資信託の選び方を理解できる
FP2級の知識を身につけると、「知識が点」から「生活の線」になり、将来設計が一気に明確になります。
🏡 第5章:公務員が「お金の勉強」を始めるときの注意点

お金の勉強は、人生を豊かにしてくれる素晴らしい行動です。
ですが、公務員には特有のルールや落とし穴も存在します。
正しい知識を持っておけば、安全かつ安心して資産形成を進められます。
ここでは、FPとして、公務員が注意すべき3つのポイントをお伝えします。
⚖️ ① 「副業禁止」と「資産運用」は違う
公務員には地方公務員法・国家公務員法で副業禁止規定があります。
ただし、これは“営利を目的とした継続的な事業”を禁じるもので、株式投資や投資信託、NISA・iDeCoでの運用は違法ではありません。
つまり、
株や投資信託での長期積立
不動産の相続・一部賃貸(条件付き)
国債や社債の保有
これらは「資産運用」として認められています。
一方で、
- 株の運用方法を教えてお金を得る
他人資産を管理して手数料を受け取る
企業と関係して副収入を得る
このような行為は副業扱いとなる場合があるため注意が必要です。
🧠 ② SNSやYouTube情報を“鵜呑みにしない”
最近はお金の情報があふれています。
しかし、中には誤った情報や過剰な投資推奨をする発信も多いのが現実です。
特に注意したいのが、「これを買えば月10万円の不労所得!」といった“短期的な儲け話”。
公務員は安定収入がある分、こうした誘惑に巻き込まれやすいです。
あと、「このやり方を実行すれば、必ず10万円が100万円になる」といった、利益が必ずでるという広告も詐欺です。
絶対利益が出るなら人に教えないで自分だけで儲かればいいので。
株式投資に絶対はありません。
💬 本当に信頼できる情報源は、「書籍」「金融庁」「証券会社の公式ページ」など公的なサイト。不安を煽る発信より、“制度を理解する情報”を優先しましょう。
また、SNSで投資成績を公開している人もいますが、「あなたと生活状況が違う」ことを忘れないこと。
お金の表示はいくらでも変えられますし、数字の証拠がありません。
お金の勉強は、“比較”ではなく“自分軸”で進めることが何より大切です。
🪴 ③ コツコツ続けることが、最短ルート
お金の勉強は一夜漬けでは身につきません。
1日10分でも構いません。
毎日「少しずつ」続けることが成果につながります。
とりあえず、
夜寝る前に本を10ページ読む
- 休日に書店に行ってお金の本コーナーに行って立ち読みしてみる
たったこれだけでも、3ヶ月後には「見える世界」が変わります。
🌿 第6章:お金の勉強で“真の安心”を手に入れよう
お金の勉強は、「投資で儲けるため」ではなく、「これからの人生を安心して歩むため」の学びです。
多くの公務員が「安定しているから大丈夫」と思いながらも、本当は「将来への不安」や「お金のモヤモヤ」を抱えています。
でも、お金の知識を少しずつ身につけていくと、その不安は「対策」に変わり、やがて“確信”へと変わっていきます。
🌱 今日からできる小さな一歩
お金の勉強は、いきなり完璧を目指す必要はありません。
まずは次の3つの中から、できることを1つ選んでみましょう。
本を1冊読む(例:『お金の大学』など)
家計簿アプリを入れて、1週間分の支出を見える化する
金融庁の「NISA特設ページ」を読んでみる
この小さな行動が、あなたの将来を大きく変えます。
💡 「知らないまま」を卒業しよう
公務員として誠実に働くあなたは、「お金に無頓着=悪いことではない」と思っているかもしれません。
ですが、本当の誠実さとは、家族・自分の未来をきちんと守る力を持つことです。
お金の勉強を通じて、
無駄な支出を減らす
投資や保険を正しく理解する
将来に向けた安心資産を築く
こうした積み重ねこそが、「真の安定」につながります。
🔗 次に読むおすすめ関連記事
- 公務員の株式投資と家計管理!失敗しない両立のコツを元公務員FPが解説
- 公務員の家計管理と節約術|独身・一人暮らしも貯まるコツ【元公務員FP体験談&解説】
- 公務員が安心して始める株式投資の勉強法|独学のコツと元公務員FP体験談
- 【公務員向け】iDeCoとNISAどっちがおすすめ?元公務員FPが失敗しない選び方を解説
これらの記事も合わせて読むと、実践のステップがより明確になります。
✍️ 最後に
お金の勉強は、誰にでもできる“未来への自己防衛”です。
そして、公務員という安定した立場を持つあなたこそ、知識を行動に変える力をすでに持っています。