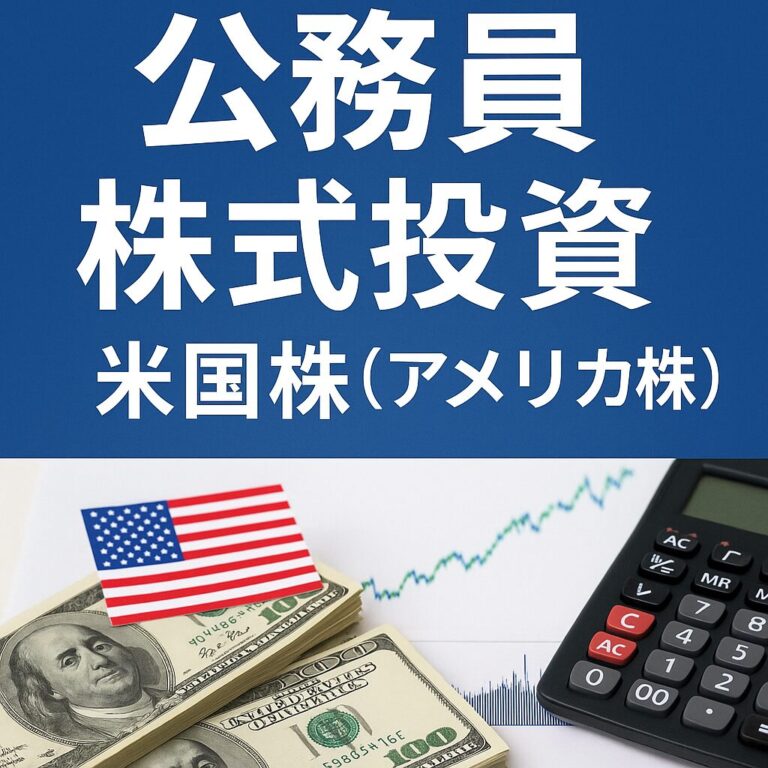公務員として働いていると、安定した収入が得られる一方で、「将来の資産形成」をどうするかという悩みを抱える方は少なくありません。特に年金制度の先行きやインフレ、子どもの教育費や住宅ローンなどを考えると、「給料だけで大丈夫なのか?」と不安を感じる人は多いでしょう。
そんな中で注目を集めているのが 米国株(アメリカ株)への投資です。アップルやマイクロソフト、グーグル(アルファベット)、コカ・コーラといった世界的な企業に直接投資できること、さらに米国市場の成長性や安定した配当文化が魅力とされています。実際、私自身も2024年から全世界株(オルカン)や米国株(S&P500)を投資先に検討し、実際オルカンに投資しています。NISAを活用して少額ですが積み立てていて、現在は10%を超える運用成績となっています。
「でも、公務員って投資しても大丈夫なの?」
「副業禁止規定に引っかからないの?」
「米国株って為替リスクや税金が複雑で難しそう…」
こうした疑問や不安を抱くのは当然です。特に公務員は服務規程や守秘義務が厳しく、金融商品取引に制限があるイメージを持つ人も多いでしょう。ですが実際には、 株式投資は法律や規則で禁止されていません。ただし、内部情報を利用したインサイダー取引や、勤務先の職務と利害関係が生じる投資には注意が必要です。つまりルールを理解し、正しく運用すれば、公務員でも安心して米国株投資を行うことができるのです。
この記事では、
公務員が株式投資をする際の注意点
米国株投資がなぜ人気なのか
証券口座やNISAの選び方
実際にどんな銘柄やETFを選べばいいか
公務員視点でのメリット・デメリット
私の体験談や実例
といったテーマを網羅的に元公務員FPが解説します。さらに、公務員でも安心して始められる「長期積立」「高配当株」「インデックス投資」などのスタイルも紹介しますので、自分に合った方法を見つけていただけるはずです。
また、米国株投資は為替や税制など、日本株とは違う特徴があります。そのため、正しい知識を持って始めることが失敗を避ける第一歩になります。途中で「ドル建てと円建ての違い」「外国税額控除のやり方」なども具体的に触れていきますので、初心者でも理解しやすい構成にしました。
将来のために、コツコツと資産形成を進めていきたい公務員の方へ。この記事を通じて、 「米国株での投資は難しくない」「公務員でもルールを守れば安心してできる」 ということを実感していただければ幸いです。
公務員と株式投資の関係
公務員というと「安定している代わりに副業や投資ができない」と思われがちですが、実際には株式投資は公務員でも認められている資産運用のひとつです。国家公務員法や地方公務員法には「営利企業への従事や兼業の禁止」が規定されていますが、株式投資そのものを禁止する条文は存在しません。
ただし、いくつか注意すべきポイントがあります。
株式投資は副業に当たらない
株式投資はあくまで「資産運用」であり、「労務を提供して対価を得る副業」とは区別されます。つまり、株や投資信託を購入し、配当や売却益を得ることは法律上の「副業」には該当しません。そのため、公務員が証券口座を開き、株式を売買することは基本的に問題ありません。
投資が禁止されるケースもある
ただし、公務員としての職務上の立場を利用して利益を得るような行為は厳禁です。たとえば、勤務先で得た未公開情報をもとに株を購入する「インサイダー取引」は明確に禁止されており、違反すれば懲戒処分や刑事罰の対象となります。これは公務員に限らず一般の会社員でも同じですが、特に公務員は社会的責任が大きいため、より一層の注意が必要です。
また、担当業務が特定の企業や業界に深く関わる場合(例:金融庁や地方自治体の産業課で企業支援を担当しているなど)、利害関係のある企業への投資は「利益相反」とみなされる可能性があります。このようなケースでは、所属部署や人事担当に確認しておくと安心です。
投資規模にも配慮を
さらに、株式投資の規模が極端に大きくなると「営利活動」と誤解されるリスクがあります。たとえば、数千万円単位で頻繁に売買を繰り返していると、周囲から「これは投機的な副業ではないか」と疑われることもあります。公務員としての信頼性を損なわないよう、資産運用はあくまで 長期的・堅実的 に行うのが基本です。
実際の体験談
私の周囲では、勤務時間中にこっそり取引をしている人もいました。これは絶対にNGです。その人は、トイレの中や公用車の中で頻繁に行っていました。バレたら懲戒処分になるので、勤務時間中の取引は止めましょう。ちなみに、私の公務員時代は昼休みを活用して売買しました。昼休みはセーフです。
なぜ公務員に米国株(アメリカ株)が人気なのか
公務員が投資先を考えるとき、多くの方がまず思い浮かべるのは日本株や投資信託かもしれません。ところが、近年は米国株(アメリカ株)に注目する公務員が増えています。その理由はいくつかあります。
世界をリードする企業に直接投資できる
米国市場には、アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル(アルファベット)、テスラといった世界的企業が上場しています。これらの企業は世界中で商品やサービスを提供しており、成長性・競争力が極めて高いのが特徴です。公務員の給料は安定していても爆発的に増えるわけではありません。そこで「世界のトップ企業にお金を働かせる」という発想が人気を集めているのです。
日本株と比べたときの成長力
日本株はバブル崩壊以降、長らく低迷が続きました。日経平均株価がようやくバブル期を超えたのは2024年のことです。一方、米国株はこの30年間で力強く成長を続け、S&P500指数はほぼ右肩上がりの推移を見せています。長期的に資産形成を目指すなら、米国株の成長性は大きな魅力となります。
配当文化の違い
米国企業には「株主還元を重視する文化」が根付いています。特に連続増配企業(数十年間配当を増やし続けている会社)が多数存在するのは米国株の特徴です。例えばコカ・コーラは63年連続で増配を続けています(2025年2月時点)。安定した給与収入に加え、米国株の配当金を得ることで、生活の安心感を高めることができるのです。
公務員との相性が良い「長期積立」
公務員は給与が安定しているため、毎月コツコツと積立投資を継続しやすい立場にあります。米国株ETF(例えばS&P500に連動するVOOやVTI)は、長期積立との相性が抜群です。ドルコスト平均法を活用すれば、相場の上下に左右されにくく、時間を味方に資産を育てることができます。
為替リスクも「分散」の一部に
米国株投資には為替リスクがつきものです。円高になれば円換算の資産は目減りしますが、円安になれば逆に利益が増えることもあります。実はこの為替リスクも「リスク分散」の一環として働きます。日本の経済だけに依存せず、米ドル資産を持つことは、長期的に見てリスクヘッジになるのです。
私の実感
私自身、日本株の個別株と全世界・オルカン(アメリカ株を多く含む)を保有していますが、全世界の方が「安心して持ち続けられる」と感じています。日本株は決算に左右されて株価が下落・停滞しやすく、保有し続けるのに心労が伴っています。一方、全世界は積み立てるだけで市場全体の成長を享受できるため、精神的にも楽でした。「毎月一定額を入れて放置」で成果が出たので、公務員に向いている投資法だと確信しています。
公務員が米国株投資を始める前に知っておくべき基本
米国株投資は魅力的ですが、始める前に必ず理解しておきたい基本があります。ここを押さえておかないと、思わぬ失敗や損失につながる可能性があります。公務員という立場を踏まえて、特に重要なポイントを整理してみましょう。
証券口座の選び方
米国株を購入するには、まず証券口座が必要です。公務員の方がよく利用しているのは以下の3社です。
SBI証券:米国株の取扱銘柄数が豊富で、積立サービスもあり。外国株取引手数料も業界最低水準。
楽天証券 :楽天ポイントが投資に使えるため、普段の生活と連携しやすい。アプリも初心者に使いやすい。
マネックス証券
:米国株の情報提供に強く、決算資料やスクリーニング機能が充実。
どの証券会社もスマホで簡単に口座開設が可能です。まずはメインバンクの引き落とし口座と連携しやすい証券会社を選ぶと、管理がしやすくなります。
NISA・iDeCoとの関係
公務員にとって資産運用を考える際、NISA(少額投資非課税制度) と iDeCo(個人型確定拠出年金) をどう活用するかは大きなテーマです。
NISA:年間一定額までの投資で得られる配当や売却益が非課税になります。米国株ETF(例:VOO、VTIなど)をNISAで積み立てれば、長期的な運用益を効率よく増やせます。
iDeCo:掛金が全額所得控除になり、節税効果が高い制度。ただし運用商品は投資信託が中心で、直接米国株個別銘柄は買えません。米国株インデックスファンドを通じて投資する形になります。
私はNISAで日本の個別株を所有、全世界株・オルカンを積み立て、あとiDeCoも運用中です。
為替リスクを理解する
米国株はドル建てで取引されます。そのため、円ドルの為替レートの影響を避けることはできません。
円高のときに米国株を買えば、将来的に円安になった際に為替差益が期待できます。
逆に円安時に買うと、円高に戻ったときに評価額が下がることもあります。
為替は短期的に予測が難しいため、「タイミングを狙って大金を一度に投入する」のはリスクが高いです。安定収入のある公務員なら、毎月一定額を積み立てるドルコスト平均法※を活用するのが安全策です。
※ドルコスト平均法とは
毎月一定額を決まったタイミングで投資する方法です。株価が高いときは少なく、安いときは多く買えるため、平均購入単価が自然とならされます。相場の上下に振り回されず、長期的に安定した資産形成が可能です。特に忙しい公務員に向いており、NISAや投資信託との相性も抜群です。
税金の基本知識
米国株投資での売ったときにかかる税金は、日本の税(20.315%)だけがかかります。
ただし、米国株投資で得られる配当には、アメリカで10%、日本で20.315%の税金がかかります。つまり、そのままだと二重課税になってしまいます。これを防ぐ方法が外国税額控除です。確定申告を行えば、米国で源泉徴収された税額を日本の税金から差し引くことができます。
公務員でも確定申告は可能であり、むしろ投資をするなら必須の知識です。
参考サイト:SBI証券 外国株式の税制
米国株投資の具体的な方法
米国株投資といっても、選択肢はさまざまです。「どの銘柄を買えばいいのか?」「ETFと個別株の違いは?」と迷う公務員の方も多いでしょう。ここでは、代表的な投資手法を整理しながら、初心者でも始めやすい方法を紹介します。
個別株投資とETF投資と投資信託の違い
米国株投資の王道は、大きく分けて「個別株投資」と「ETF投資」です。
個別株投資
アップルやマイクロソフト、コカ・コーラなど、特定の企業の株を直接購入する方法です。成長企業の株価が上がれば大きなリターンが得られる一方、業績悪化で株価が急落するリスクもあります。情報収集や分析が欠かせません。ETF投資
ETF(上場投資信託)は、複数の銘柄に分散投資できる商品です。たとえば「S&P500」に連動するETF(VOO)は、アメリカを代表する500社にまとめて投資できるため、1社の業績に左右されにくく、初心者でも安心です。- 投資信託
投資信託は、投資家から集めた資金を専門の運用会社がまとめて運用する金融商品です。ETFと同じく分散投資ができますが、証券取引所でリアルタイムに売買するのではなく、1日1回の基準価額で取引されます。たとえば「eMAXIS Slim米国株式(S&P500)」や「楽天・全米株式インデックス・ファンド」などが代表例です。ETFに比べて少額から購入でき、つみたてNISAの対象商品にもなっているため、投資初心者や忙しい公務員にとって始めやすい選択肢といえるでしょう。
公務員は忙しい業務の合間に個別株を頻繁にチェックするのは難しいため、ETFや投資信託を中心に長期投資するスタイルが現実的です。
| 項目 | 個別株投資 | ETF投資 | 投資信託 |
|---|---|---|---|
| 投資対象 | 1社の株式(例:アップル、コカ・コーラ) | 複数銘柄をまとめた上場投資信託(例:VOO、VTI) | 運用会社がまとめて運用する投資信託(例:eMAXIS Slim米国株式) |
| 分散効果 | 低い(1社の業績に左右されやすい) | 高い(数百銘柄に分散) | 高い(ETF同様に分散可能) |
| 売買の方法 | 証券取引所でリアルタイム売買 | 証券取引所でリアルタイム売買 | 1日1回、基準価額で売買 |
| 最低投資額 | 1株単位(数万円~数十万円かかる場合あり) | 数百ドル程度(ETF1口) | 100円~1,000円から可能(少額投資向き) |
| 手数料 | 売買手数料 | 売買手数料+信託報酬(低水準) | 信託報酬(商品により差あり) |
| 情報収集 | 個別企業の決算・ニュースを追う必要あり | 市場全体の動向を追えばよい | 運用はプロに任せられるため手間が少ない |
| 向いている人 | 成長株で大きな利益を狙いたい人 | 分散しつつ長期保有したい人 | 投資初心者や忙しい公務員 |
配当株投資と成長株投資
次に、投資対象を「配当株」にするか「成長株」にするかでスタイルが分かれます。
配当株投資
コカ・コーラやP&Gのように、安定して配当を出し続ける企業への投資です。定期的に配当収入が得られるため、給与+配当という「ダブルの収入源」を作れます。公務員の安定収入との相性が良い投資法です。成長株投資
テスラやアマゾンのように、今後の成長が期待される企業に投資する方法です。将来の株価上昇によるキャピタルゲインを狙うスタイルですが、株価の変動が激しいため注意が必要です。
私の友人は当初、米国の高配当株に投資しましたが、途中からS&P500 ETFに切り替えていました。その理由は、配当収入よりも「市場全体の成長を享受したい」と思ったと言っていました。
ドル建て取引と円貨決済
米国株はドルで取引されますが、証券会社によっては「円貨決済」も可能です。
ドル建て取引:為替手数料を抑えやすい反面、ドルを事前に購入する必要があります。
円貨決済:円でそのまま取引できるため初心者向け。ただし為替スプレッドがやや広め。
長期的に投資を続けるなら、住信SBIネット銀行などでドルを安く買い、SBI証券でドル建て投資をするのがコストを抑えるコツです。
公務員が米国株に投資するメリットとデメリット
米国株投資は魅力的ですが、当然ながらメリットだけではありません。公務員という立場だからこそ得られる強みもあれば、注意すべきリスクもあります。ここでは両面を整理してみましょう。
メリット① 世界経済の成長を取り込める
米国は世界最大の経済大国であり、S&P500やNASDAQに上場する企業は世界をリードする存在です。日本国内だけに投資していると、どうしても経済成長の鈍化に左右されますが、米国株を組み入れることで「グローバルな成長」を自分の資産に反映できます。
メリット② 安定した配当文化
米国企業は株主還元に積極的です。特に「連続増配企業」が多く、数十年間配当を減らさずに増やし続ける企業が多数存在します。公務員は安定収入を得られる職業ですが、そこに米国株の配当収入が加わると、生活の安心感がさらに高まります。
メリット③ 公務員の給与安定性と相性が良い
公務員は毎月安定した給与があるため、相場に振り回されずにコツコツ投資を続けられる立場です。米国株ETFを毎月積立する「ドルコスト平均法」との相性は抜群で、時間を味方にして資産を育てることができます。
メリット④ 円安リスクを資産分散でヘッジできる
資産をすべて円で持っていると、円安が進んだときに購買力が下がります。米国株を通じてドル建て資産を保有すれば、長期的なインフレや円安に対するリスクヘッジになります。
デメリット① 為替変動リスク
米国株はドル建てであるため、為替の影響を受けます。円高になれば、せっかく株価が上昇しても円換算では損失になる場合があります。短期で売買するよりも、長期的な視点で保有することが重要です。
デメリット② 情報収集が難しい
米国株は日本株に比べて情報が英語中心です。企業の決算資料や最新ニュースを追うのはハードルが高いかもしれません。ETFを利用すれば情報収集の負担を減らせますが、個別株に挑戦するなら翻訳ツールや海外メディアを活用する工夫が必要です。
デメリット③ 税制が複雑
米国株の配当にはアメリカで10%課税された後、日本でさらに20.315%課税されます。確定申告で「外国税額控除」を行わないと二重課税のままになり、手取りが減ってしまいます。忙しい公務員にとって、毎年の申告はやや手間に感じるかもしれません。
デメリット④ 取引時間の違い
米国市場は日本時間の夜11時半〜翌朝6時までが開場している時間帯です(SBI証券)。公務員の方が仕事終わりにリアルタイムで取引するのは難しく、どうしても指値注文や自動積立に頼ることになります。短期売買には不向きです。
私の体験談:全世界株(オルカン)投資を始めたきっかけと実感
ここからは、少し私自身の経験を交えてお話しします。私は2017年に株式投資を始めましたが、最初はデイトレや個別株投資に専念していました。ただ、30代後半になり、結婚や子どもの誕生をきっかけに、教育費や住宅ローン、老後資金といった現実的なお金の問題を考えるようになり、資産形成の必要性を強く感じました。そこで、「投資信託」を真剣に検討し始めました。
※今回は全世界株投資について話をしますが、全世界株のなかには米国株も多数含まれているので、ここで取り上げています。
全世界株投資を始めたきっかけ
最初に全世界株や米国株を知ったのは、投資関連の書籍とYouTube「両学長 リベラルアーツ大学」で勉強したときでした。「全世界株やS&P500に長期投資していれば20年で資産が倍以上になっている」というグラフを見て、「リスクを極力低くしつつ、資産を増やせる、こんな方法があるのか」と衝撃を受けたのを覚えています。日本株は将来性に不安を感じていたので「世界に投資した方が合理的なのでは?」と考えるようになったのです。
検討して実際に購入・積み立てているのは投資信託・eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)。NISA口座を使って毎月少額ですが積み立ています。
投資を続けて感じたこと(運用成績)
投資を始めてから最初の1年は、正直あまり成果を実感できませんでした。含み損になる時期もあり、「これで本当にプラスになるの?」と不安になることもありました。しかし、積み立てを続けるうちに運用成績が良くなっていき、現在の運用成績は投資利回り+14.55%とかなり好成績となっています(2025年9月17日現在)。
仕事との両立
投資を続ける中で「本業に支障が出るのでは?」という心配もありましたが、実際には全く影響はありませんでした。なぜなら、全世界株は積立を設定して放置するだけで良かったからです。勤務中に株価を気にする必要もなく、むしろ精神的な安定感を得られました。
よくある質問(Q&A形式)
米国株投資に関心を持つ公務員の方から、よく寄せられる疑問をQ&A形式でまとめました。制度やルールの理解が曖昧なままだと不安が残りますので、ここでしっかり整理しておきましょう。
Q1. 公務員でも株式投資は本当に大丈夫?副業禁止に当たらない?
A. 問題ありません。
株式投資は「資産運用」であり、副業禁止規定で禁止されている「営利企業への従事」には当たりません。ただし、インサイダー取引や勤務先と利害関係のある企業への投資は厳禁です。安心して投資を続けるためにも、勤務先の服務規程を一度確認しておくと良いでしょう。
Q2. 為替リスクが怖いのですが、どう対策すればいいですか?
A. ドルコスト平均法を活用しましょう。
円高・円安を予測するのはプロでも困難です。そこで毎月一定額を積み立てる「ドルコスト平均法」を使えば、購入価格を平準化でき、リスクを抑えられます。また、資産の一部をドル建てで保有することは、円安リスクのヘッジにもなります。
Q3. 米国株はどの証券口座を使えばいい?
A. SBI証券、楽天証券、マネックス証券が3大定番です。
取引手数料や使いやすさに大きな差はありません。初心者は楽天証券の使いやすいアプリから始める方が多く、本格的に積立や為替コストを重視するならSBI証券がおすすめです。
Q4. NISA(つみたて投資枠)で米国株に投資できる?
A. できます。
直接米国株を買うことはできませんが、米国株に連動する投資信託(eMAXIS Slim米国株式、楽天VTIなど)を通じて投資可能です。税制優遇を最大限活用できるため、公務員にもおすすめの方法です。
Q5. 円安が進んでいるけど、今から始めても遅くない?
A. 遅くありません。
円安局面での買付は一見割高に感じますが、長期で見ると為替の動きは読めません。むしろ「時間を味方につけること」が大切です。毎月一定額を積立すれば、買付タイミングを気にせず安心して続けられます。
Q6. 忙しくて米国株の情報収集ができません…
A. ETFや投資信託を利用すれば大丈夫です。
S&P500や全米株式に連動する商品なら、1本で分散投資ができ、企業情報を逐一追う必要はありません。公務員のように忙しい仕事をしている方でも、無理なく投資を続けられます。
米国株投資の始め方・ステップまとめ
ここまで米国株投資の魅力や注意点を解説してきましたが、「実際にどう始めればいいのか?」が一番気になるところだと思います。公務員の方がスムーズに投資を始められるように、ステップを整理しました。
ステップ① 証券口座を開設する
まずは証券会社に口座を開設します。私が実際に利用していて、かつおすすめなのはSBI証券・楽天証券・マネックス証券の3社です。
(再掲)
- SBI証券:米国株の取扱銘柄数が豊富で、積立サービスもあり。外国株取引手数料も業界最低水準。
- 楽天証券 :楽天ポイントが投資に使えるため、普段の生活と連携しやすい。アプリも初心者に使いやすい。
- マネックス証券
:米国株の情報提供に強く、決算資料やスクリーニング機能が充実。
口座開設には本人確認書類などが必要です。スマホで完結できるので、まずは行動に移すのが第一歩です。
ステップ② NISAを設定する
次に、NISA口座 を開設します。NISAを活用すれば、一定額までの投資で得られる配当や売却益が非課税になります。
NISA(つみたて投資枠):毎月積立に適しており、投資信託を中心に米国株へ投資可能
NISA(成長投資枠):年間投資枠が大きく、米国ETFや個別株を直接購入できる
公務員は給与が安定しているため、毎月の積立投資と相性が良く、NISA(つみたて成長枠)での長期投資が特におすすめです。
ステップ③ 初めての銘柄を選ぶ
最初から個別株に挑戦すると難しく感じるため、ETFや投資信託から始めるのが安心です。
ETFなら:S&P500連動(VOO)、全米株式(VTI)
投資信託なら:eMAXIS Slim米国株式(S&P500)
これらの商品は「市場全体」に投資できるため、初心者でも安心して続けられます。
ステップ④ 少額から始める
最初は無理のない範囲で始めることが大切です。毎月1万円でも、20年続ければ大きな資産になります。
例:月1万円 × 年利5% × 20年 = 411万円
(※元本240万円 → 運用益171万円)
給与から天引きするイメージで「生活に影響が出ない額」を積み立てると続けやすいです。
ステップ⑤ 長期保有を徹底する
米国株投資は「短期で儲けよう」とすると失敗しやすいです。数年単位で見れば下落相場もありますが、長期的には右肩上がりで成長してきました。
私自身、含み損が出たときに焦った経験がありますが、結果的に「放置しておくのが正解」でした。公務員の安定収入を生かし、「売らずに積み立て続ける」ことが最大の成功法則だと実感しました。
💡 まとめ
証券口座を開設する
NISAを設定する
ETFや投資信託から始める
毎月少額で積み立てる
長期保有を徹底する
この流れで進めれば、公務員でも安心して米国株投資をスタートできます。
まとめ&次の行動
ここまで「公務員が米国株投資を始める方法」について解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返りながら、次に取るべき行動を整理してみましょう。
記事の振り返り
公務員でも株式投資は合法
副業禁止規定には当たらず、安心して資産運用が可能。ただし、インサイダー取引や利害関係のある企業への投資は絶対に避ける必要があります。なぜ米国株なのか
世界的企業への投資機会、連続増配という文化、日本株よりも高い成長力。長期的な資産形成において米国株は欠かせない選択肢です。始める前の基本知識
証券口座選び、NISAの活用、為替リスクや税制(外国税額控除)の理解が必須。具体的な投資手法
ETFや投資信託による積立が公務員との相性抜群。高配当株投資も副収入を得たい人に向いています。メリットとデメリット
世界経済を取り込むメリットがある一方で、為替変動・税制・情報収集の難しさなどのリスクも存在。体験談から学べること
小さな積立でも長期的に続ければ成果は出る。本業に支障なく資産形成できるのが米国株の強み。
次に取るべき行動
この記事を読んで「米国株を始めてみたい」と思った方は、次の3つのステップを実行してみましょう。
証券口座を開設する
まずはSBI証券や楽天証券に口座を作りましょう。スマホで10分ほどで申込み可能です。NISAの設定を行う
NISAを活用すれば非課税メリットを享受できます。毎月の積立額を決める
生活費や貯金とバランスを取りながら、無理のない範囲で積立を開始しましょう。
注意喚起(公式情報リンク)
米国株投資は制度改正や税制変更の影響を受ける可能性があります。必ず最新情報を以下の公的機関で確認してください。
内部リンク案(関連記事導線)
この記事を読んだ方におすすめの関連記事:
「公務員でも安心して投資できるのかな…?」と不安に思っている方は、まずは少額で試してみてください。小さな一歩が将来の大きな安心につながります。