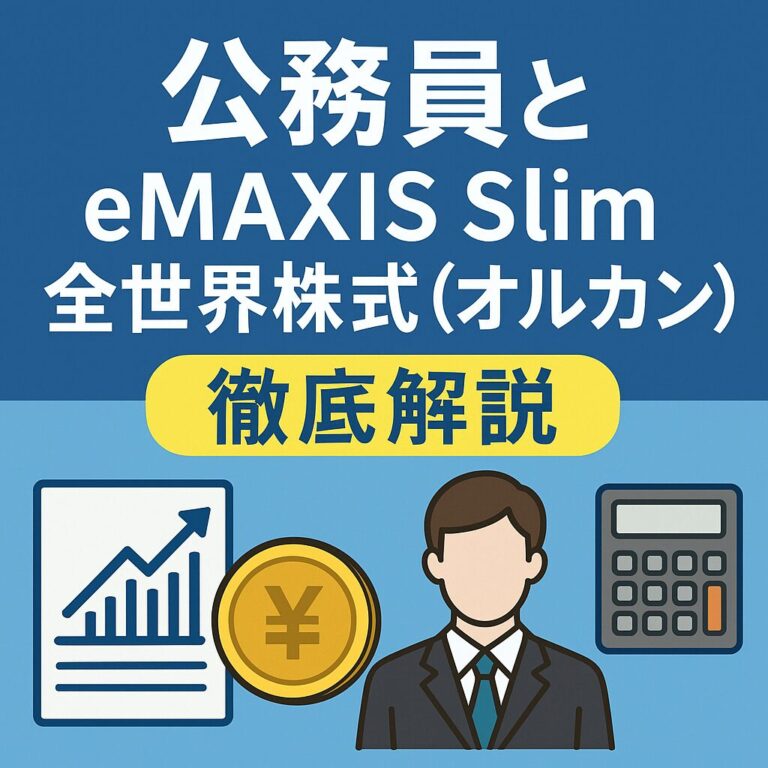「将来の年金は大丈夫だろうか…」
「退職金だけで安心できるのか…」
「貯金が全然増えていかない」
そんな不安から、資産運用に関心を持つ公務員は年々増えています。
そんな中で注目されているのが、投資信託の「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、通称「オルカン」です。
オルカンは1本で世界中の株式に分散投資できるシンプルな投資信託。
特に安定収入のある公務員と相性が良く、給与天引きやNISA・iDeCoとの併用で、ほったらかしの長期投資が可能になります。
私自身も結婚・子供ができたことをきっかけに「将来の備えを始めたい」と思い、色々検討して積み立て始めたのがこのオルカンでした。
最初は月3,000円の少額からのスタートでしたが、時間が経つにつれて「積み立てていてよかった」という安心感が大きくなっています。
この記事では、公務員がオルカンを選ぶメリットやデメリット、実際の運用例、注意すべき点を元公務員FPの視点からわかりやすく解説します。
「これから資産形成を始めたいけど何を買えばいいのか迷っている」
「オルカンについて知りたい」
公務員の方にとって、安心して一歩を踏み出せる内容になるはずです。
eMAXIS Slim 全世界株式(オルカン)とは?
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」、通称オルカンは、三菱UFJ国際投信が運用するインデックス型投資信託です。
名前の通り、世界中の株式に一度に投資できるのが最大の特徴で、個人投資家の間では「投資信託の王道」として人気を集めています。
基本情報と特徴
オルカンは「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)」に連動するよう設計されており、先進国・新興国を含む3,000銘柄程度に分散投資できます。
【内訳・国】
- アメリカ64.5%
- 日本4.9%
- イギリス3.4%
- カナダ2.8%
- 中国3.2%
- インド1.9%
など(2025年3月末現在)
【主要銘柄】
- アップル(アメリカ)
- マイクロソフト(アメリカ)
- エヌビディア(アメリカ)
- アマゾン(アメリカ)
- メタ(アメリカ)
- アルファベット(アメリカ)
- テスラ(アメリカ)
- 台湾セミコンダクター・TSMC(台湾)
など(アメリカの大企業が名を連ねています)
アメリカ、ヨーロッパ、日本、中国など、世界の主要市場をカバーしているため、これ1本で地球全体の成長を取り込める点が大きな魅力です。(アメリカがダントツに多いのには注意)
つまり「どの国の株を買えばいいのか分からない」という悩みを解消し、シンプルかつ合理的な長期投資が可能になります。
なぜ「オルカン」と呼ばれるのか
正式名称が長いため、投資家の間では「オール・カントリー」を略して「オルカン」と呼ばれています。
SNSや書籍、投資系YouTubeなどでも頻繁に登場するため、投資初心者にとっても認知度が高いファンドです。
信託報酬の安さ
投資信託を選ぶ際に最も重要なポイントの一つが「信託報酬(運用コスト)」です。
オルカンの信託報酬は年率0.05775%程度(2025年7月25日時点)と、業界最低水準。
例えば100万円を運用した場合、年間コストはわずか約577円です。
長期運用ではコストの差が複利効果に大きく影響するため、この低コストは非常に大きなメリットです。
運用会社の安心感
オルカンを運用するのは三菱UFJアセットマネジメント。
メガバンクグループに属する大手運用会社であり、信頼性は抜群です。
「怪しい会社の商品ではないか」と不安に思う初心者にとって、安心材料になります。
特に公務員は安定を重視する方が多いため、大手金融機関の運用という実績はプラス要素といえるでしょう。
公務員との相性
オルカンは毎月一定額をコツコツ積み立てるのに適しており、安定収入のある公務員と非常に相性が良い商品です。
「NISAやiDeCoで長期的に積み立てる」ことで、給与や退職金に加えて将来の資産形成を後押ししてくれます。
公務員にオルカンが向いている理由
オルカンは誰にでもおすすめできる投資信託ですが、特に公務員との相性が非常に良いといえます。
その理由は「安定収入」「制度活用」「忙しさとの両立」の3つに集約されます。
ここでは、公務員ならではの観点からオルカンを選ぶメリットを詳しく見ていきましょう。
安定収入とドルコスト平均法の相性
公務員は、
「給与が毎月一定」
「ボーナスも年2回支給」
「完全年功序列で毎年昇給」
「クビには基本的にならない」
と、景気変動や業績に左右せず、非常に安定しているという特徴があります。
そのため、毎月一定額を投資に回す「ドルコスト平均法」※と相性抜群です。
例えば、毎月2万円をオルカンに積み立てた場合、20年間で元本480万円。
仮に年利5%で運用できれば、822万円まで成長する試算になります。
給与が安定しているからこそ、積立投資を無理なく継続でき、長期的な複利の力を最大限に活かせるのです。
【※ドルコスト平均法】
ドルコスト平均法とは、毎月など決まった日に同じ金額で投資する方法です。
株価が高いときは少ししか買えず、安いときは多く買えます。
結果的に平均購入価格がならされて、リスクが減ります。
一度にまとめて買うより、値動きに強い投資方法として初心者にも向いています。
NISA・iDeCoを活用した節税メリット
公務員は副業規制があるため、収入の柱を増やしにくい現実があります。
その代わりに積極的に利用したいのが「NISA」や「iDeCo」といった制度です。
NISAでオルカンを積み立てれば、将来の売却益や分配金が非課税に。
iDeCoを活用すれば、掛金が全額所得控除になり、住民税や所得税が軽減されます。
例えば年収500万円の公務員がiDeCoで月1万円積み立てると、年間で2万4,000円の節税効果が期待できます。
これは実質的に「国が投資を後押ししてくれている」イメージで、公務員にとっては非常に効率的な資産形成手段です。
忙しい公務員に合う「ほったらかし投資」
公務員は残業や研修、異動などで日々忙しく、投資に多くの時間を割くのは難しいのが実情です。
オルカンは1本で全世界に分散投資できるため、他の銘柄を選んだり売買を繰り返したりする必要がありません。
積立設定をしてしまえば、あとは放置で資産が育つ仕組みになっています。
これは時間的余裕が少ない公務員にとって大きなメリットであり、精神的にも「放っておいても大丈夫」という安心感を得られます。
転勤・ライフイベントへの柔軟性
公務員は転勤や異動がつきものです。
株式個別銘柄や不動産投資のように、常に情報収集や管理が必要な投資は続けにくいのが現実。
オルカンであればネット証券の口座を通じて自動積立が可能なので、住居が変わっても投資を中断する必要がありません。
転勤や出産、教育費の出費など人生のイベントがあっても、投資を継続できる柔軟性があります。
メリットとデメリット
オルカンは「投資信託の完成形」と呼ばれることもあるほど評価が高い商品ですが、当然ながらメリットだけではありません。
投資初心者にとって大事なのは、長所と短所を両方理解したうえで自分に合うか判断することです。
ここでは、公務員の立場から見たメリットとデメリットを整理します。
メリット1:世界中に分散投資できる安心感
オルカン最大の強みは、1本で全世界の株式に投資できる点です。
アメリカ・日本・ヨーロッパ・中国・新興国まで広く分散されているため、特定の国や地域に依存せずに資産形成が可能です。
公務員は多忙であり、投資にあまり時間を割けないため、「1本で完結する安心感」は大きな魅力となります。
メリット2:超低コストで長期投資に最適
信託報酬は0.05775%程度と業界最低水準。
以前は同じような全世界株式ファンドで0.5%以上かかるのが当たり前だったため、10分の1以下にまで下がったことになります。
コストは投資成果を直接削る要素なので、長期投資を考える公務員にとって非常に有利です。
メリット3:ほったらかし投資が可能
個別株投資や不動産投資は常に情報収集が必要ですが、オルカンは指数連動型なので市場平均に任せておけばOK。
積立設定をした後は放置しても資産が増えていく可能性があります。
多忙な公務員にとって「手間がかからない」というのは非常に大きなメリットです。
デメリット1:短期では成果が出にくい
オルカンは長期運用前提の商品です。
市場全体に投資しているため、短期間で大きな利益を狙うのは難しいでしょう。
短期間でみると株価が下落し、含み損になることも珍しくありません。
公務員は安定志向が強いため、マイナスが出ると不安になってしまう方も多いですが、「10年、20年の長期で育てる商品」と割り切ることが必要です。
デメリット2:為替リスクがある
オルカンは円だけでなくドルやユーロ、新興国通貨建ての資産にも投資しているため、為替変動の影響を受けます。
例えば円高になると、たとえ株価が上がっても円ベースの評価額は下がることがあります。
これは避けられないリスクですが、長期で見ればプラスに収束しやすいと考えられています。
デメリット3:信託報酬差は小さい
全世界株式ファンドにはオルカン以外にも「SBI・全世界株式(雪だるま)」など競合商品があります。
信託報酬の差はごくわずかで、運用成果に大きな差は出にくいのが実情です。
したがって「絶対にオルカンでないとダメ」というわけではなく、「大手運用会社の安心感」や「商品知名度」で選ばれている部分もあります。
実際の体験談・シミュレーション
投資信託は「長期・積立・分散」が基本だと頭では理解していても、実際にやってみないと実感がわかないものです。
ここでは、私自身の体験談と、数字を使ったシミュレーションを交えて、公務員がオルカンに投資した場合のイメージを紹介します。
公務員時代に月3,000円から始めた体験談
私は常々「貯金がなかなか増えない」「このまま今の貯金だけでは将来が不安だ」と感じていて、結婚を機に、思い切ってオルカンの積立を始めました。
最初は毎月3,000円だけ。
大きな額ではありませんが、「まずは続けること」を優先しました。
当時は投資に対して不安が強く、「本当に増えるのか?」「元本割れしたらどうしよう」と迷いましたが、口座から自動で積み立てられる仕組みにしておいたことで、気づけば習慣になっていました。
運用2年後の実感
積立開始から2年が経った現在、口座残高を確認してみると、運用成績は「+14%」(2025年9月19日時点)となっています。
具体的な金額は避けますが、ざっくりいうと100万円が114万円になっているというイメージです。
もちろん、途中で株価が下落して含み損になった時期もありましたが、放置していたら自然にプラスに戻っていたのです。
これを経験して「やっぱり積立は時間が味方してくれる」と実感しました。
今では投資を始めたことで「将来への不安が少し軽くなった」「お金が増える仕組みを持てた」という精神的な安心感を得られています。
30年シミュレーション(数値例)
では、公務員がオルカンに積立投資を続けた場合、将来どのくらいの資産になるのでしょうか。
以下は毎月2万円を積み立て、年利5%で30年間運用した場合の試算です。
毎月の積立額:2万円
積立期間:30年
元本合計:720万円
想定利回り:年5%
将来の評価額:約1,665万円
元本の約2倍以上に増える試算となり、退職金や年金に加えて大きな資産形成効果が期待できます。
もちろん利回りは保証されるものではありませんが、「長期で続ければこれだけの成果が見込める」という具体的な数字は投資を始めるモチベーションになるはずです。
始め方ガイド
「オルカンが良いのは分かったけれど、どうやって始めればいいの?」という方のために、ここでは公務員が実際にオルカンを購入・積立するための手順を解説します。
初心者でも迷わないように、できるだけシンプルにまとめました。
証券口座を開設する
まず必要なのは証券口座です。
オルカンを購入するなら、ネット証券を利用するのが良いでしょう。
おすすめは以下の3社です。
公務員は副業規制があるため、株の短期売買や信用取引は避けたほうが無難です。
その点、投資信託の積立投資は「資産形成の一環」として問題視されることはありません。
NISA口座を設定する
次に、NISA口座を開設しましょう。
NISAでオルカンを購入すれば、将来の売却益や分配金が完全非課税になります。
たとえば30年間で数百万円の利益が出ても、税金がかからないのは大きなメリットです。
積立額を決める
「いくら積み立てればいいのか?」という悩みは多いですが、最初は無理のない金額で十分です。
公務員であれば、給与の2%~10%程度を目安にすると長続きしやすいです。
例)月収25万円の場合
月5,000円(給与の約2%)
月1万2,000円(給与の約5%)
月2万5,000円(給与の約10%)
重要なのは「金額」よりも「継続」。
少額でも自動積立にしておけば、自然と資産が育っていきます。
【参考記事】
公務員NISAの積立額はいくら?元公務員FPがシミュレーションと体験談で解説
iDeCoを活用する場合
さらに節税効果を得たい方は、iDeCo(個人型確定拠出年金)を検討してもよいでしょう。
公務員は掛金の上限が月20,000円とやや少なめですが、掛金全額が所得控除となり、毎年の税金が安くなります。
「NISAでオルカンを積立 → 余裕があればiDeCoでもオルカンを積立」という流れも良いかと思います。
実際の積立設定方法
証券口座を開設したら、以下のステップで積立設定が可能です。
ログイン後「投資信託」を検索
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を選択
「つみたて設定」をクリック
毎月の積立金額・引き落とし口座を設定
確定して完了(あとは自動で毎月購入される)
設定さえしてしまえば、後は何もする必要がありません。
まさに「放置でOK」の投資スタイルです。
よくある質問Q&A
オルカンは人気の投資信託ですが、いざ始めようとすると「本当にこれで大丈夫なの?」と不安になる方も多いはずです。
ここでは、公務員の方からよく寄せられる質問に答えていきます。
Q1. オルカン1本で大丈夫?
結論から言えば、長期投資においてオルカン1本でも十分です。
なぜなら、世界中の約3,000銘柄に分散投資しているため、すでにポートフォリオが完成しているからです。
ただし、リスクをより分散したい方は、別の投資信託の商品を購入したり、個別株や債券も組み合わせると安心感が増します。
私自身も最初は個別株から始めましたが、今では「個別株(3銘柄)+投資信託(オルカン)+iDeCo」の3本で資産運用しています。
Q2. iDeCoとNISAの両方でオルカンを買ってもいい?
はい、可能です。
NISAは「いつでも引き出せる非課税枠」、iDeCoは「60歳まで引き出せない代わりに節税できる枠」として役割が違います。
たとえば「NISAで毎月2万円」「iDeCoで1万円」という形にすれば、非課税メリットと節税メリットを両取りできます。
公務員の場合、iDeCoの上限は月2万円なので、そこまで無理なく続けられる金額設定が可能です。
Q3. 暴落が来たらどうする?
株式市場は必ず上下を繰り返します。
リーマンショックやコロナショックのように一時的に大幅下落することもありますが、歴史的には10年・20年単位で見れば回復してきました。
暴落時にやってはいけないのは「恐怖で積立をやめてしまうこと」です。
むしろドルコスト平均法により安値で多く買えるチャンスでもあります。
私もコロナショックのときに個別株の評価額が50%程度下がり焦りましたが、積立を続けたことで数年後には大きくプラスに転じました。
Q4. 為替リスクは大丈夫?
オルカンは海外資産が多いため、円高・円安の影響を受けます。
円高になると評価額が下がることもありますが、逆に円安になると資産が増える効果もあります。
為替は長期的には均衡に向かう傾向があるため、長期投資を前提とすれば大きな心配は不要です。
Q5. 公務員でもやっていいの?副業規制に引っかからない?
投資信託の購入・積立は「資産運用」であり、副業には当たりません。
【参考記事】
公務員の株式投資は副業になる?バレるリスク・確定申告・処分事例まで元公務員FPが解説
他ファンドとの比較
オルカンは人気の全世界株式ファンドですが、投資信託には他にも魅力的な選択肢があります。
特に「S&P500連動型」や「全米株式ファンド」と比較されることが多いです。
ここでは、公務員にとってどちらが合うのかを整理してみます。
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と「楽天・プラス・オールカントリー株式インデックスファンド」
「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」と「楽天・プラス・オールカントリー株式インデックスファンド」は、現在では中身がほぼ同じと考えてよいファンドです。
以前の楽天の全世界株式ファンドは、米国ETF「VT」を通じてFTSE Global All Cap Indexに連動しており、銘柄数や仕組みに違いがありました。
そのため「楽天は小型株まで含み、コストがやや高い」といった比較がよく語られてきました。
しかし、2024年以降に登場した「楽天・プラス・オールカントリー」では運用方針が変更され、eMAXIS Slimと同じくMSCI ACWI(除く配当、円換算ベース)に連動する形になっています。
信託報酬も大幅に引き下げられ、現在は両者ともほぼ同水準です。
つまり、投資対象、コスト、運用方針はいずれもほぼ同じであり、長期投資で大きな差が生じる可能性は低いと言えます。
異なるのは運用会社(eMAXISは三菱UFJ、楽天は楽天投信)や純資産規模、設定日の違い程度です。
結論として、現在の両ファンドは「ほぼ同じ中身」であり、どちらを選んでも全世界株式への分散投資効果は変わらず、利用する証券会社や好みに応じて選択すれば十分です。
S&P500 vs オルカン
S&P500はアメリカの代表的な500銘柄に投資する指数で、過去30年で年平均約10%という高い成長率を誇ります。
一方オルカンは全世界に分散しているため、リターンはS&P500よりやや低い傾向があります。
S&P500の特徴
アメリカ市場に集中投資
過去のリターンが高い
成長性は大きいが「アメリカ一本足打法」になるリスク
オルカンの特徴
世界に分散
リターンは平均的だがリスクも分散
「どの国が伸びても恩恵を受けられる」安心感
公務員は安定志向が強い傾向があるため、「大きなリターンよりも安心感を優先したい」という方にはオルカンが合っています。
逆に「多少リスクを取っても高リターンを狙いたい」という方はS&P500を選ぶケースもあります。
全米株式(楽天VTI)との違い
楽天VTI(正式名称:楽天・全米株式インデックス・ファンド)は、アメリカ株式市場全体に投資できる商品です。
実質的には「アメリカ一本」であり、S&P500よりもさらに分散されていますが、やはり米国依存度が高い点は同じです。
楽天VTI:アメリカの約4,000銘柄に分散
オルカン:全世界約3,000銘柄に分散
直近10年で見ると、アメリカ株式は世界を牽引してきたため、楽天VTIのほうがリターンが高いケースが多いです。
しかし「今後30年もアメリカ一強が続くのか?」という点は不透明です。
中国やインドといった新興国の成長も視野に入れるなら、オルカンのほうが安心できる選択肢です。
公務員におすすめなのはどっち?
公務員の場合、給与・ボーナス・退職金といった安定資産があるので、「投資ではリスク分散を意識する」ほうが合理的です。
その観点からは、オルカン=守りを固めた世界分散投資、S&P500や楽天VTI=攻めの米国集中投資という住み分けができます。
私自身も最初は「アメリカ株の方が伸びそう」と思い、S&P500に魅力を感じました。
しかし、とにかく「資産形成でも安定を優先したい」と考え、オルカンを主軸にしました。
その結果、精神的にも安心して積立を継続できています。
制度変更・注意点
オルカンはシンプルでわかりやすい投資信託ですが、制度や市場環境の変化によって思わぬ影響を受ける可能性があります。
特に公務員の方が安心して長期投資を続けるためには、以下の注意点を理解しておくことが重要です。
NISA制度改正の影響
2024年から始まった新NISA制度では、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)が併用でき、非課税投資枠が大幅に拡大しました。
公務員の方がこれから資産形成を始める場合は、まず「つみたて枠」を活用するのが王道です。
ただし、制度は今後の税制改正で変更される可能性があります。
長期投資を前提にする以上、「現行制度は永続するわけではない」と意識しておきましょう。
最新情報は金融庁の公式サイトで確認するのがおすすめです。
為替リスク
オルカンは海外株式が中心のため、円高・円安の影響を強く受けます。
たとえば円高になると、海外株の価値が目減りするため、含み損になることもあります。
ただし、長期的には為替は循環する傾向があるため、10年以上のスパンで投資すれば大きな問題にはなりにくいと考えられています。
公務員のように安定収入がある立場であれば、為替の上下を気にせず積立を続ける姿勢が重要です。
新興国リスク
オルカンは先進国だけでなく中国やインド、ブラジルといった新興国株式も含まれています。
これにより成長の恩恵を受けやすい一方で、政治リスクや景気の急変による下落リスクも抱えています。
特定の新興国の影響で一時的に基準価額が下がることもあり得ますが、全世界に分散しているため、長期的にはリスクを吸収しやすい構造になっています。
まとめと次の行動
ここまで「公務員とオルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)」について詳しく解説してきました。要点を整理すると次の通りです。
オルカンは1本で世界中に分散投資できる投資信託
公務員の「安定収入」と「長期積立」との相性が抜群
NISAやiDeCoを活用すれば、非課税・節税メリットを享受できる
メリットは「低コスト」「放置できる」「分散効果」、デメリットは「短期成果が出にくい」「為替リスク」
実際に月1〜3万円の積立でも、30年後には数百万〜数千万円規模の資産形成が期待できる
私自身もオルカンを選び、積立を続けてきました。
途中で株価が下がり「やめたい」と思った時期もありましたが、続けた結果として「お金が育っている」という実感を得られています。
特に公務員は安定した給与とボーナスがある分、投資では守りを固めてコツコツ積立するのが理にかなっています。
次の行動ステップ
この記事を読んで「やってみようかな」と思った方は、以下のステップをおすすめします。
証券口座を開設(SBI証券や楽天証券が定番)
NISA口座を設定し、つみたて投資枠でオルカンを選択
月5,000円〜1万円程度から積立開始(給与の2%を目安)
余裕があればiDeCoで月5,000円〜2万円を追加して節税効果を得る
あとは積立を止めず、10年・20年と長期で続ける
小さな一歩でも、始めた人と始めない人の差は将来大きく広がります。
関連記事
【注意事項】
本記事は筆者の経験や調査に基づき、公務員の方に向けて一般的な情報提供を行うものです。特定の金融商品や銘柄の購入を推奨するものではありません。
投資には価格変動リスクや元本割れの可能性があり、将来の運用成果を保証するものではありません。
実際の投資判断は、ご自身の責任において行ってください。
最新の制度や商品の詳細については、必ず金融庁・証券会社・運用会社等の公式情報をご確認ください。